概要とは?意味や使い方【書き方の手順も丸わかり】例文あり

「概要」という言葉は、ビジネス文書やレポート、学校の課題、プレゼン資料、さらにはSNSのプロフィール文など、日常のさまざまな場面で使われています。非常に汎用性の高い言葉である一方で、実はその意味や正しい使い方をきちんと理解している人は少ないかもしれません。
「概要を教えてください」と言われて、どの程度まで詳しく書けばよいか悩んだ経験はありませんか? あるいは、「概要と要約って何が違うの?」と感じたことはないでしょうか。
本記事では、「概要」の正確な意味や使い方をわかりやすく解説し、実際の例文を30個紹介します。また、レポートなどで概要を書く際の手順やコツ、類語や英語表現、さらによくある疑問にも答えていきます。
「概要」という言葉の本質を理解し、使いこなせるようになることで、あなたの表現力や伝達力がぐんとアップします。それでは、詳しく見ていきましょう。
目次
- 1 「概要」の意味
- 2 「概要」の正しい使い方
- 3 概要の書き方の手順
- 4 シーン別「概要」の例文【30選】
- 4.1 1. 【セミナー案内】
- 4.2 2. 【売上報告書の概要】
- 4.3 3. 【商品紹介(省エネ家電)】
- 4.4 4. 【ブログ記事紹介】
- 4.5 5. 【アンケート調査報告】
- 4.6 6. 【導入マニュアル】
- 4.7 7. 【イベント告知】
- 4.8 8. 【書籍紹介】
- 4.9 9. 【プロジェクト計画書】
- 4.10 10. 【技術ドキュメント】
- 4.11 11. 【プレスリリース概要】
- 4.12 12. 【オンライン講座案内】
- 4.13 13. 【社内研修資料】
- 4.14 14. 【調査レポート】
- 4.15 15. 【マーケティング資料】
- 4.16 16. 【製品カタログ説明】
- 4.17 17. 【eラーニング案内】
- 4.18 18. 【採用案内】
- 4.19 19. 【CSRレポート概要】
- 4.20 20. 【安全マニュアル】
- 4.21 21. 【学術論文概要】
- 4.22 22. 【ウェブサイト案内文】
- 4.23 23. 【カンファレンス講演要旨】
- 4.24 24. 【求人票の概要】
- 4.25 25. 【製品改善レポート】
- 4.26 26. 【業務改善提案】
- 4.27 27. 【社外ニュースレター】
- 4.28 28. 【動画説明文】
- 4.29 29. 【顧客事例紹介】
- 4.30 30. 【FAQセクションの前文】
- 5 「概要」を使った例文【30選】
- 6 「概要」の類語(言い換え)・英語
- 7 よくある質問
- 8 まとめ
「概要」の意味
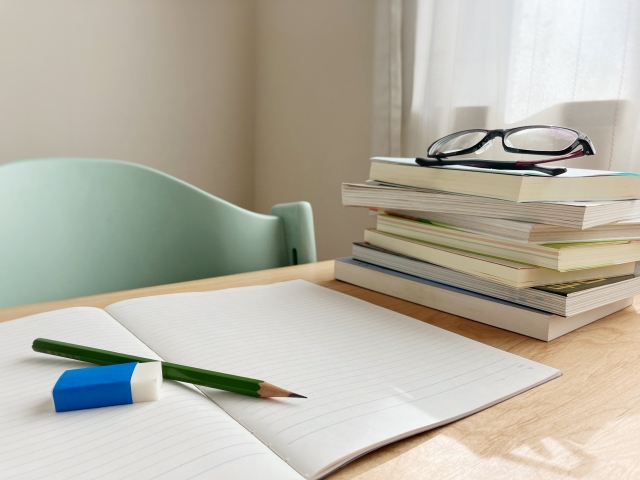
「概要(がいよう)」という言葉は、日常生活やビジネスシーンで非常によく使われる表現ですが、あらためてその意味を確認してみましょう。
辞書における定義
『広辞苑』では、「概要」は次のように定義されています。
物事の大体の内容。おおよそのあらまし。
つまり、「詳細までは説明しないが、要点を簡潔にまとめたもの」が「概要」です。文章や話の全体像を把握するための「導入部分」や「見取り図」としての役割を果たします。
「概要」とは「要点のまとめ」
「概要」は、あらゆる情報の中から本質的な部分や重要なポイントだけを抜き出して、簡潔に整理したものです。そのため、「概要」には次のような特徴があります。
- 詳細ではないが、大筋は把握できる
- 必要なポイントに絞って構成されている
- 読む人に全体像をつかませることが目的
例えば、10ページにわたるレポートの概要は、1ページ程度で構成されるのが一般的です。読み手はこの概要を読むことで、全体を読まなくても内容のおおよそを理解できます。
「概要」が使われる場面
- ビジネス文書:企画書や報告書の冒頭に記載
- レポート・論文:研究内容や分析結果の要点を記載
- プレゼン資料:内容の導入部やまとめとして使用
- イベント紹介:内容や目的を簡単に伝える文
- SNS・動画:投稿やコンテンツの説明文として
このように、「概要」は読む人に内容をわかりやすく伝えるための非常に重要な要素です。
「概要」の正しい使い方

「概要」は便利な言葉ですが、適切な使い方をしなければ相手に正確な情報が伝わらなかったり、誤解を招いたりすることがあります。この章では、「概要」の正しい使い方について、具体的な場面を交えて解説します。
①どんなときに使うべきか
「概要」は、相手に全体の流れや重要な要点をざっくりと伝えたいときに使います。たとえば次のようなケースです:
- ビジネスの企画書:プロジェクトの目的や進行スケジュールを一目で把握してもらう
- 研究レポートや論文:研究の背景、方法、結果、結論を要約して伝える
- プレゼンの冒頭:プレゼン全体の構成やテーマを紹介する
- 動画やSNS投稿:内容を簡潔に説明して閲覧者の興味を引く
②「要約」との違いに注意
「概要」と似た言葉に「要約」がありますが、少しニュアンスが異なります。
| 用語 | 意味 | 違いのポイント |
|---|---|---|
| 概要 | 内容の大筋を簡潔に述べたもの | 構成や目的を含めた全体の説明 |
| 要約 | 内容を短くまとめたもの | 詳細を簡潔にまとめることに重きがある |
たとえば、小説の「要約」は物語の流れを時系列に沿って短くする作業ですが、「概要」はその小説のジャンルやテーマ、特徴など全体像を示すものです。
③「概要」は書き出しで印象を決める
概要を書く際に大切なのは、「最初の一文」で何についての概要かを明確にすることです。読み手にとって、概要はその後の内容を読むかどうかの判断材料になります。
例:
- 「本レポートは、2025年度に実施されたマーケティング施策の効果検証についてのものである。」
- 「本企画の概要は、新商品Xの市場投入に向けた販促戦略の骨子を示すものである。」
④避けたい使い方
- 詳細に立ち入りすぎる:「概要」ではなく「本文」や「詳細説明」となる
- 抽象的すぎる:読んでも内容がわからない
- 箇条書きだけで終わる:伝わりにくくなる可能性がある(補足説明を添えると効果的)
概要の書き方の手順

-レポートの概要の書き方を中心に解説-
概要は、「全体のポイントを簡潔に伝えるための文書」です。しかし、実際に書こうとすると「どこから手を付ければいいのか分からない」と感じることも少なくありません。ここでは、特にレポートにおける概要の書き方をステップごとに解説します。
ステップ1:目的を明確にする
まず、そのレポートが何のために書かれたのかを明確にしましょう。概要は、内容を読まなくても「なぜこの文書が存在するのか」が伝わることが重要です。
例:
- 本レポートは、○○調査の結果をまとめたものである。
- 本稿では、△△に関する研究の成果を報告する。
ステップ2:主な内容・構成をまとめる
レポートの構成に沿って、各セクションの要点を1〜2行で簡潔にまとめます。
例:
- 第1章では、調査の背景と目的を述べた。
- 第2章では、アンケートの方法と対象を説明した。
- 第3章では、得られたデータと分析結果を示した。
ステップ3:結論・考察を簡潔に書く
最も重要なのが結論や考察部分。読み手が「このレポートを読んでどういう結論に至ったのか」を一目で把握できるようにします。
例:
- 結果から、○○が△△に与える影響が確認された。
- 本調査により、今後の□□政策の方向性が示唆された。
ステップ4:文量と読みやすさに配慮する
概要は長くてもA4用紙1ページ以内にまとめるのが一般的です。以下のポイントに注意して構成しましょう。
- 一文は短く、明快に
- 専門用語には簡単な説明を添える
- 段落ごとに話題を整理する
- 箇条書きを適宜使って視認性を高める
概要の構成例
【概要】
本レポートは、○○に関する調査結果をまとめたものである。第1章では背景と目的を示し、第2章で調査方法を述べた。第3章では、得られたデータの分析結果を記載している。最後に考察を行い、○○という傾向が見られることを確認した。本レポートは今後の△△活動の指針となることが期待される。
シーン別「概要」の例文【30選】

以下では、さまざまなビジネス・教育・技術・広報の場面において活用される「概要文」の具体例を30件記しました。それぞれの例文は、対象読者に伝わりやすく、要点を的確に押さえた実用的な文章となっており、目的・内容・考察・結論といった構成要素を反映しています。
1. 【セミナー案内】
本セミナーは、SEOに不慣れな方を対象に、検索エンジンの仕組みからキーワード選定、コンテンツ最適化までを、実例を交えながら丁寧に解説する内容です。参加者が自社サイトに応用しやすい実践的な知識を身につけられるよう設計されています。
2. 【売上報告書の概要】
2025年度上半期の売上データを地域別・商品別に分析し、前年比との比較を行った上で、売上変動の要因と今後の販売戦略の方向性をまとめた報告書です。今後の営業活動の改善と戦略策定の基礎資料として活用できます。
3. 【商品紹介(省エネ家電)】
「エコヒーター」は、従来モデルと比較して電力消費を30%削減し、高い省エネ性能と静音性、耐久性を兼ね備えた次世代型の暖房器具です。家庭やオフィスを問わず快適に使える製品として、幅広い利用シーンに対応します。
4. 【ブログ記事紹介】
本記事では、「順次」「逐次」「随時」「適宜」などの混同しやすい表現を例文とともに分かりやすく解説し、それぞれの意味や使い分けのポイントを明確にしています。正確な日本語表現を身につけたい方に役立つ内容です。
5. 【アンケート調査報告】
全国の20代~40代の男女1,000名を対象に実施した調査では、オンライン学習の利用頻度、満足度、課題意識などを多角的に分析しました。結果をもとに、今後の教育サービス改善やユーザー支援施策の立案に活用可能です。
6. 【導入マニュアル】
本マニュアルは、新しく導入された業務システムについて、初期設定から日常の操作までをステップごとに解説しており、初心者でもスムーズに業務を始められるように配慮されています。図解や注意点も多数掲載しています。
7. 【イベント告知】
本イベントは、地域の魅力発信と観光促進を目的に、地元企業や自治体が協力して開催するもので、特産品販売やワークショップ、ステージイベントなど多彩なプログラムが展開されます。地域活性化への貢献が期待されます。
8. 【書籍紹介】
本書は、働き方改革を成功させた企業の実例をもとに、制度設計から現場運用までの具体的な進め方を紹介しています。企業担当者が改革を推進する際の実践的な参考資料として活用できる内容です。
9. 【プロジェクト計画書】
このプロジェクトは、AI技術を活用して物流のルート最適化と自動仕分けの導入を図り、人手不足とコスト増加に対応するものです。計画は3フェーズに分かれており、段階的に導入と検証を進めていきます。
10. 【技術ドキュメント】
本ドキュメントでは、システムアップデートに伴う画面仕様や機能変更点を詳細に説明し、担当者が正確かつ迅速に対応できるよう構成されています。移行作業に関わるすべての関係者の参考資料として活用されます。
11. 【プレスリリース概要】
新たに開発されたサービスについて、その背景、主要機能、対象ユーザー層、リリース予定日などの要点を簡潔にまとめたプレスリリースです。報道関係者や投資家への情報提供を目的としています。
12. 【オンライン講座案内】
この講座は、ビジネスシーンで使える英語表現を基礎から実践まで体系的に学べる内容で、動画教材やロールプレイを通じて、英会話力の向上を目指します。初学者でも取り組みやすい構成です。
13. 【社内研修資料】
新入社員向けのこの資料では、企業文化、基本マナー、日常業務の流れを順を追って紹介しています。理解度チェックや実践練習問題も盛り込み、即戦力化を目的とした研修教材です。
14. 【調査レポート】
地域住民を対象に実施した生活満足度調査の結果を分析し、住環境・医療・交通・行政サービスなど各分野の満足度と課題を明示しています。今後の地域政策立案に向けた基礎資料となります。
15. 【マーケティング資料】
この資料では、自社サービスの市場分析、ターゲット顧客のペルソナ設定、競合状況の比較、広告施策の効果予測などを整理し、次期キャンペーン戦略の立案に役立つ内容となっています。
16. 【製品カタログ説明】
最新のスマートウォッチについて、健康管理機能、通知連携、長時間バッテリー、耐水性能などの主な特長を分かりやすく紹介し、用途別に最適なモデル選びができるよう構成されています。
17. 【eラーニング案内】
このPython講座は、まったくの初心者でも取り組めるよう、文法の基本から簡単な自動化ツールの開発まで、動画・演習・クイズ形式で学べるオンラインプログラムです。
18. 【採用案内】
本採用案内では、当社の事業内容、求める人物像、具体的な職務内容、福利厚生制度、キャリアパス、選考フローを紹介し、学生・社会人どちらにも分かりやすい内容になっています。
19. 【CSRレポート概要】
本レポートでは、環境保全活動、ボランティア活動、働きやすい職場づくりなど、当社のCSR(企業の社会的責任)への取り組みを年度ごとにまとめ、今後の課題と目標も提示しています。
20. 【安全マニュアル】
このマニュアルでは、製造現場や工事現場で発生し得るリスクの洗い出しと、それに対応する手順や注意点を作業工程別に整理しており、安全意識の向上と事故防止を目的としています。
21. 【学術論文概要】
本研究は、日本国内の主要観光地を対象に観光客の満足度調査を行い、回帰分析を用いて満足度に影響を与える要因を明らかにしました。政策提言や観光戦略の参考資料となり得ます。
22. 【ウェブサイト案内文】
当サイトでは、2025年6月より追加された新機能「マイページ設定」や「カスタム通知」の利用方法をまとめ、よくある質問に対応したガイドページをご用意しています。
23. 【カンファレンス講演要旨】
この講演では、最新のクラウドセキュリティ動向と、企業が直面する脅威に対しての具体的な対応策を、実際の導入事例とともに紹介します。情報システム担当者向けの内容です。
24. 【求人票の概要】
当社では現在、営業職・開発職を中心に中途採用を実施中です。職務内容、応募条件、勤務地、勤務時間、給与レンジなどを明記した求人情報をご案内いたします。
25. 【製品改善レポート】
この報告書では、ユーザーから寄せられたフィードバックと操作ログをもとに、UI改善点・機能追加要望・不具合対応状況を整理し、次回バージョンへの反映計画も提示しています。
26. 【業務改善提案】
本提案書は、現行業務フローを可視化し、非効率な作業工程の削減、RPA導入による自動化、進捗管理のデジタル化による業務効率向上を目的に構成されています。
27. 【社外ニュースレター】
当社では四半期ごとに発行しているニュースレターにて、業績報告、新サービスのご紹介、社員インタビュー、CSR活動などの最新情報をお届けしています。
28. 【動画説明文】
この動画では、Excelのピボットテーブル機能を活用して、売上集計・分析を効率的に行う方法を、実際の操作画面を使って解説しています。ビジネスユーザー必見です。
29. 【顧客事例紹介】
本事例では、当社の製品を導入した企業の業務改善プロセスと成果を、定量データや担当者の声を交えて紹介しています。類似業種への提案資料としても活用できます。
30. 【FAQセクションの前文】
このFAQでは、ユーザーの皆さまから寄せられたよくある質問を「操作方法」「アカウント」「請求」などのカテゴリに分けて掲載し、問題解決の一助となることを目指しています。
「概要」を使った例文【30選】

ここでは、「概要」という言葉の使い方がよくわかるように、ビジネス・日常・SNSなどのシーン別に計30個の例文を紹介します。実際の場面を想定しているので、すぐに応用できます。
ビジネスシーン【10選】
- 本書類は、新規事業に関する概要をまとめたものです。
- 下記に今月の業務進捗の概要をご報告いたします。
- プロジェクト概要をご確認の上、ご質問があればご連絡ください。
- 商品開発の概要をプレゼン資料にまとめました。
- 本会議では、全体の概要説明を5分程度で行います。
- 概要だけでなく、詳細資料もご用意しております。
- 会議資料の最初のページに、企画の概要を記載しています。
- 本レポートは、販売戦略の概要とその成果を示したものです。
- 研修プログラムの概要を社内ポータルに掲載しました。
- 業務内容の概要は、以下の通りです。
よく使われる日常的なシーン【10選】
- イベントの概要をLINEで送っておいたよ。
- 映画の概要を読んで、観るかどうか決めました。
- この本の概要を3行で説明してくれない?
- 今日の授業の概要だけでも教えて。
- 概要を話すと、旅行は中止になったんだ。
- 簡単に概要だけ教えてくれる?
- 先生が講義の概要をメールで送ってくれた。
- このアプリの使い方の概要を知りたい。
- 書類の概要だけ目を通しておいて。
- プロフィール欄には概要だけ載せたよ。
SNSなどその他【10選】
- この動画の概要欄にリンクを貼っています。
- 概要欄をチェックして詳細を確認してください。
- プロフィールに自己紹介の概要を書いています。
- 概要だけでもツイートに書いた方がいいよ。
- インスタのキャプションに概要入れといて。
- 概要をハッシュタグで補足するのが最近のトレンド。
- 投稿の内容が長いから、概要をまとめて別ツイにしてあるよ。
- 概要がないとフォロワーに伝わりづらいかも。
- YouTubeの概要欄をしっかり書くと視聴数が上がる。
- この投稿の概要ってどんな感じ?
実際に使われる言い回しを知っておくことで、さまざまな場面で「概要」を自然に使えるようになります。
「概要」の類語(言い換え)・英語

「概要」と似た意味を持つ言葉はいくつか存在します。適切な言葉を選ぶことで、より正確に、そして文脈に合った表現が可能になります。この章では、「概要」の主な類語と、それに対応する英語表現について紹介します。
「概要」の主な類語(言い換え)
| 類語 | 意味・ニュアンス | 違い・使用シーン |
|---|---|---|
| 要旨(ようし) | 内容のもっとも重要な要点 | 学術的、形式的な文章で使われることが多い |
| 概略(がいりゃく) | 詳細を省いた大まかな内容 | 書類や報告書でよく使われる |
| 概観(がいかん) | 全体をざっと見た印象 | 観察・分析に使われることが多い |
| サマリー | 英語の「summary」のカタカナ表現 | ビジネス、IT分野などで多用される |
| 抜粋(ばっすい) | 重要な部分だけを取り出したもの | 原文の一部を引用するときに使用 |
| 要約(ようやく) | 詳細を削って簡潔にまとめたもの | 「概要」よりも文章の流れに重きを置く |
使用例:
- レポートの要旨を添付しています。
- 仕様書の概略は以下の通りです。
- 今回の研究の概観を発表しました。
「概要」の英語表現
「概要」を英語で表現する場合、状況に応じていくつかの単語を使い分けます。
| 英語 | 意味・使い方 | 使用シーン |
|---|---|---|
| overview | 全体像の説明、概観 | ビジネス資料・会議の導入部分など |
| summary | 要約、主要ポイントの整理 | レポート・論文・記事など |
| outline | 概要、構成案 | プレゼンや企画の構造的な説明 |
| abstract | 学術的な要旨 | 論文や学会発表で使用されることが多い |
使用例:
- This document provides an overview of the project.
- Please refer to the executive summary on page 1.
- The outline shows the basic structure of the proposal.
- The abstract summarizes the main findings of the research.
「概要」という言葉は、日本語でも英語でも使い分けが重要です。文脈に応じて適切な表現を選ぶことで、読み手に正確な印象を与えることができます。
よくある質問

ここでは、「概要」に関して読者からよく寄せられる疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q1:「概要」と「要約」の違いは?
A: 「概要」は全体像や構成を簡潔に伝えるものであり、「要約」は内容の流れや詳細を短く凝縮するものです。
- 「概要」=なぜ・どんな構成・どんな結果かを説明(全体像)
- 「要約」=本文の中身を短く縮めたもの(内容重視)
例:
- 概要:このレポートは◯◯の研究についてまとめたもの。調査方法・結果・結論を簡潔に記述。
- 要約:本研究では◯◯を△△の方法で分析し、□□という結論が得られた。
Q2:「概要」はどのくらいの長さが適切?
A: 一般的には200〜400文字程度、長くてもA4で1ページ以内が目安です。ただし、用途によって異なります。
| 用途 | 適切な長さの目安 |
|---|---|
| レポート・論文 | 300〜400文字 |
| ビジネス文書 | 200〜300文字 |
| SNSや動画の説明文 | 100〜200文字 |
Q3:口頭で「概要を説明して」と言われたらどうする?
A: ポイントは、**「テーマ・構成・結論」**の3点を1分以内で伝えることです。
例:
「この企画は新商品Aの販促戦略を考えるものです。市場調査、競合分析、販売計画の3つの観点から検討しています。結果として、ターゲット層を若年層に絞る戦略を提案しています。」
口頭で概要を述べる場面では、専門用語を避けてわかりやすく話すことが大切です。
Q4:「概要」を書くときにありがちなミスは?
A: よくあるミスとその改善策を以下にまとめます。
| ミス | 改善策 |
|---|---|
| 長すぎて読みにくい | 要点を3〜4点に絞る |
| 抽象的で伝わらない | 「何が・どうなったか」を明確に書く |
| 専門用語ばかり | 説明を加えるか、簡単な言葉に置き換える |
まとめ
「概要」とは、物事の全体像や要点を簡潔に伝えるための大切な表現です。ビジネス文書から日常会話、SNS投稿まで幅広く使われる一方で、「要約」との違いや書き方に戸惑うこともあります。
本記事では、概要の意味や使い方、シーン別の例文、書き方の手順を詳しく紹介しました。正しい使い方と構成を理解することで、相手に伝わる文章が書けるようになります。ぜひ今後の情報発信に役立ててください。




