誤読注意「熱る」の読み方・意味・使い方が丸わかり【例文40】

日本語には、一つの漢字で複数の読み方や意味を持つ言葉が多く存在します。「熱る(いきる・ほてる)」もその一つです。この言葉は、日常会話で頻繁に使われるわけではありませんが、文学作品や詩、あるいは感情表現の一環として使われることがあります。
「熱る」には大きく分けて二つの読み方があり、それぞれ異なる意味を持っています。「いきる」と読む場合は、主に感情の高ぶりや激しさを表し、「ほてる」と読む場合は、体の一部が熱を帯びて赤くなるような状態を指します。読み方や文脈によって解釈が大きく変わるため、正しく理解し、使い分けることが大切です。
本記事では、「熱る」の読み方や意味はもちろん、実際の使い方を豊富な例文とともに紹介します。また、語源や類語、英語表現、よくある質問にも触れることで、「熱る」という言葉の奥深さを丁寧に解説していきます。
目次
「熱る」の読み方

「熱る」という漢字は、日常的に見かける「熱」という文字に「る」という送り仮名がついた形です。しかし、その読み方には複数のバリエーションがあり、それぞれに異なる意味が存在します。主に以下の2通りの読み方があります。
いきる
「熱る」を「いきる」と読む場合は、主に文語的・古語的な用法であり、現代の日常会話ではあまり使われません。しかし、文学作品や詩などでは今でも見られる表現です。
この「いきる」は、「感情や気持ちが強く高まる」「内面が熱くなる」といったニュアンスを含みます。怒り、興奮、情熱などが湧き上がるような状態を表現する際に用いられます。
ほてる
一方、「熱る」を「ほてる」と読む場合は、より現代的で日常会話でも使われる言い方です。「顔がほてる」「体が熱る」といった表現で、主に体が内側から熱くなったり、赤くなったりする状態を意味します。
こちらの読み方は、「火照る」とも書かれますが、「熱る」も同様の意味で用いられることがあります。
「熱る」の意味

「熱る」という言葉は、前章で述べたように「いきる」「ほてる」という二つの読み方があります。そして、読み方が違えば、意味もまったく異なってきます。この章では、それぞれの読み方に対応する意味を詳しく見ていきましょう。
熱る(いきる)の意味
「熱る(いきる)」は、感情や内面の熱が高まる状態を表します。これは古語的な表現であり、現代の口語ではあまり使われませんが、文学作品や詩、または古風な表現を求める場面で用いられることがあります。
主な意味:
- 感情や思いが激しく高ぶること
- 内面的な熱情がこみ上げる様子
使用例のイメージ:
- 「怒りに熱る心を抑えきれなかった」
- 「志に熱って前へ進む」
この用法では、外見ではなく心の動きや精神状態を描写する際に使われることが多いです。やや文学的・詩的な響きを持ち、深い情感を伝えたいときに効果的な表現です。
熱る(ほてる)の意味
「熱る(ほてる)」は、身体が内側から熱くなる、または赤らむような状態を表す言葉です。これは現代でも日常的に使われる表現で、特に顔や手など、感情や環境の変化によって熱を感じる部位に関連しています。
主な意味:
- 体の一部が熱を帯び、赤らむこと
- 発熱や緊張、恥ずかしさなどにより体が熱く感じる状態
使用例のイメージ:
- 「風呂上がりで顔が熱る」
- 「緊張して耳まで熱った」
この用法では、身体的な状態に注目し、感覚的・視覚的な変化を表現します。「顔が赤くなる」「体が熱くなる」といった現象に対応する日本語表現です。
「熱る(いきる)」の使い方【例文20】

「熱る(いきる)」という読み方は、現代の会話ではほとんど使われなくなっていますが、文学作品や詩などでは、感情の激しさや情熱を表現するために効果的に使われています。この章では、「熱る(いきる)」の使い方を理解しやすくするため、例文を20個ご紹介します。
基本的な使い方
- 彼の胸には、正義への思いが熱っていた。
- 戦いの前夜、兵たちは士気に熱って眠れなかった。
- 彼女は信念に熱るあまり、周囲が見えなくなっていた。
- 若者たちは夢に熱り、果敢に挑戦を続けていた。
- 国を思う心が熱り、涙を流した。
感情の高まりを表現する例
- 母の言葉に心が熱り、言い返すこともできなかった。
- 怒りに熱る心を、懸命に抑え込んだ。
- 愛に熱るあまり、彼は無謀な行動に出た。
- 情熱に熱る目が、未来を見据えていた。
- 希望に熱った声が、教室に響き渡った。
文学的な描写・詩的な表現
- 我が心、熱る焔のごとく燃え立つ。
- 夜空を見上げて、熱る想いを星に託した。
- 手紙に込めた想いが、熱るほどの切なさを帯びていた。
- 故郷への恋しさに、胸が熱った。
- 運命に抗う者の魂は、常に熱っている。
古風な文脈や創作向けの使用例
- 志に熱る者に、道は自ずと開ける。
- 幼き日の誓いが、今なお熱っている。
- 戦火を逃れてなお、彼の心は熱っていた。
- 師の教えに熱る日々を思い出した。
- 時代を変えんとする若き力が、熱っていた。
「熱る(ほてる)」の使い方【例文20】

「熱る(ほてる)」は、現代でも日常的に使われる表現です。身体の一部が熱を帯びる、あるいは赤くなるような状態を指し、環境的な要因や感情の変化によって起こる身体的反応を描写します。ここでは、具体的な使用シーンに応じた例文を20個ご紹介します。
身体の状態を表す例
- 長風呂のあとで顔が熱っていた。
- 外を歩いたせいで、手が日差しに熱ってしまった。
- 熱いものを食べた後、頬がほんのり熱った。
- ヒーターの前に座っていたら、足先が熱ってきた。
- 日焼けで背中が熱って、シャツが着られなかった。
感情に起因する身体反応の例
- 恥ずかしさで頬が熱るのを感じた。
- 好きな人に話しかけられ、耳まで熱った。
- 怒りが込み上げて、体全体が熱るようだった。
- 褒められた瞬間、顔がぱっと熱った。
- 緊張して手のひらが熱るのを止められなかった。
医療・健康に関する場面
- 発熱で体が熱っていて、頭もぼんやりしている。
- 火傷をした箇所がじんじんと熱っている。
- アレルギー反応で、肌が赤く熱ってしまった。
- 風邪をひいたのか、喉が熱って痛い。
- 目が疲れて熱る感じがする。
比喩的な・少し詩的な表現
- 夕暮れの光に頬が熱ったような気がした。
- 映画の感動的なラストに、胸が熱る思いだった。
- 緊迫した空気の中、額が熱るのを感じた。
- 幸せな気持ちに包まれて、体全体がぽかぽかと熱った。
- 昔の思い出に触れて、心が熱るようだった。
「熱る」の語源

「熱る(いきる・ほてる)」という言葉の語源を探ることで、この言葉の持つ深い意味や歴史的な背景をよりよく理解することができます。
「熱る(いきる)」の語源
「いきる」と読む「熱る」は、古語の世界で用いられていた表現で、「感情が高ぶる」「気持ちが燃え上がる」といった状態を表します。この「いきる」は、元々は「生きる(いきる)」や「息る(いきる)」などと関係があると考えられています。
- 「息る(いきる)」=息づく・感情が動く
- 「息(いき)」とは「呼吸」や「生命力」を指す言葉であり、そこから派生して「内から湧き上がるもの」という意味合いを持ちました。
- 感情や情熱などが内面から「湧き上がる」様子を「熱る」と表現するようになったのです。
また、古語では「熱し(いき)て止まず」といった表現が使われ、強い思いや気持ちが持続することを指していました。このように、「熱る(いきる)」は、心の奥から湧き出る熱のような感情を表すのに適した語だったのです。
「熱る(ほてる)」の語源
一方、「ほてる」と読む「熱る」は、より身体的な変化を表す言葉であり、語源は「火照る(ほてる)」にあります。
- 「火照る」=火のように照る
- 「照る」は「照らす」「光を放つ」という意味ですが、身体が内側から赤く光るように見えることから「火照る」という表現が生まれました。
- つまり、「顔が熱って赤くなる」=「顔が火照る」という状態を示しています。
「火照る」は古くから和歌や随筆などで使われており、「熱る」もその異表記として、身体がぽかぽかと温まる様子や、恥ずかしさ・感情の高ぶりによる赤面を指して使われるようになったと考えられます。
「熱る」の類語(言い換え)

「熱る(いきる・ほてる)」には、それぞれ異なる意味があるため、類語もまた読み方によって異なります。ここでは、「いきる」と「ほてる」の両方の読み方に対応する言い換え表現を紹介します。
「熱る(いきる)」の類語・言い換え
この読み方では、主に感情の高まりや内面的な熱情を表します。そのため、感情が湧き上がる・盛り上がることを表す言葉が類語になります。
| 類語 | 意味 |
|---|---|
| 興奮する | 強い感情で心が高ぶること |
| 感情が高ぶる | 気持ちが抑えきれずに激しくなる |
| 熱中する | 強く夢中になる、没頭する |
| 燃える | 情熱や闘志などが激しくなる |
| 心を奪われる | 感情が引き込まれて制御できなくなる |
| 心が乱れる | 感情が大きく揺れ動く状態 |
| 情熱を抱く | 強い気持ち・熱意を持つこと |
使用例:
- 「志に燃える若者たち」
- 「彼は音楽に熱中している」
- 「大きな夢に心を奪われた少年」
「熱る(ほてる)」の類語・言い換え
こちらは身体が熱を持つ、赤くなるという状態を表すため、身体の熱感や赤らむ様子を表す言葉が類語になります。
| 類語 | 意味 |
|---|---|
| 火照る | 体が内側から熱を帯びて赤らむこと |
| 赤らむ | 顔や肌が赤くなること(恥ずかしさ・熱など) |
| 熱を持つ | 部分的に熱くなること(病気や刺激など) |
| ぽかぽかする | 体が心地よく温かい状態 |
| ほのぼのする | 穏やかに温かさを感じる様子(比喩的にも) |
| のぼせる | 血の気が上り、顔などが赤くなる状態 |
使用例:
- 「恥ずかしさで顔が赤らんだ」
- 「熱い湯に長く浸かっていたせいでのぼせた」
- 「日差しで腕が火照ってきた」
「熱る」の英語
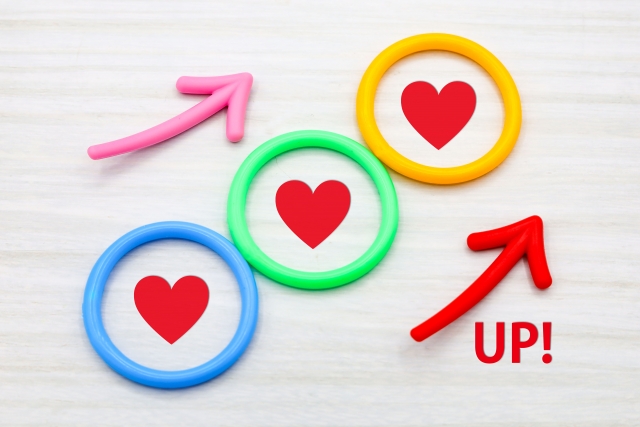
「熱る」は日本語独特の感覚的な表現であり、英語に完全に一致する単語は存在しません。しかし、文脈に応じて適切な英語表現を選ぶことで、ほぼ同じ意味を伝えることが可能です。
ここでは、「熱る(いきる)」と「熱る(ほてる)」それぞれの意味に対応する英訳の例を紹介します。
熱る(いきる)の英語表現
この読み方は、「感情が高ぶる」「情熱が湧き上がる」ような状態を表します。英語では以下のような表現が近い意味を持ちます。
| 英語表現 | 意味・ニュアンス |
|---|---|
| be inflamed with (passion, anger, etc.) | ~に燃え上がる、心が火に包まれるような情熱や怒りを表現 |
| be emotionally stirred | 感情がかき立てられる、動かされる |
| be fired up | やる気や興奮に満ちた状態(口語的) |
| burn with passion | 情熱に燃える(詩的・文学的表現) |
| be overcome with emotion | 感情が抑えきれなくなる |
使用例:
- He was inflamed with anger when he heard the news.
(その知らせを聞いて彼は怒りに熱った) - Her heart burned with passion for justice.
(彼女の心は正義への情熱に熱っていた) - The speech stirred the audience emotionally.
(そのスピーチは聴衆の心を熱くさせた)
熱る(ほてる)の英語表現
「熱る(ほてる)」は、身体が内側から熱くなる、赤くなる状態を表します。英語では以下のような表現が適しています。
| 英語表現 | 意味・ニュアンス |
|---|---|
| feel hot | 熱を感じる(一般的) |
| flush | 顔や皮膚が赤くなる(恥ずかしさ・熱などで) |
| become heated | 熱を帯びる、熱くなる(感情・体温両方に使える) |
| blush | 顔が赤くなる(主に恥ずかしさによる) |
| burn (up) | 熱で体が熱くなる(病気・暑さなど) |
使用例:
- Her cheeks flushed when he complimented her.
(彼に褒められて彼女の頬が熱った) - I’m burning up with a fever.
(熱が出て体が熱っている) - After the hot bath, my skin felt hot.
(熱い風呂の後で肌が熱っていた)
よくある質問

「熱る」という言葉は、現代日本語ではあまり頻繁には使われないため、使い方や意味に関して疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. 「熱る」と「火照る」はどう違うのですか?
A.
基本的には同じ意味で使われることもありますが、細かいニュアンスが異なります。
- 「熱る(ほてる)」は、体が熱を帯びる全般的な状態を指し、やや漢語的で硬い表現。
- 「火照る」は、より感覚的で、顔や肌が赤らむような状態をやわらかく表現します。特に女性の描写や詩的な表現によく使われます。
例:
- 顔が熱る(やや客観的・中性的)
- 頬が火照る(感覚的・詩的)
Q2. 「熱る(いきる)」は今でも使っていいの?
A.
使用は可能ですが、やや文語的・文学的な印象を与えるため、日常会話ではほとんど使われません。詩、短編小説、演劇脚本などで感情の激しさを表現するために使うのが一般的です。
例文として自然な場面:
- 「心が熱った若者の叫びが、夜空にこだました。」(文学的な表現)
Q3. 「熱る」の正しい漢字は「火照る」じゃないの?
A.
「火照る」も正しい表記であり、「熱る(ほてる)」と同義です。ただし、「熱る」は少し硬い印象を与えることがあります。文脈や媒体(小説、説明文、医療文書など)に応じて使い分けましょう。
- 会話・詩的表現 → 火照る
- 医療・説明文 → 熱る
まとめ
「熱る(いきる・ほてる)」という言葉は、一見すると難解で古めかしい印象を受けるかもしれません。しかし、その内には、人の心や体が熱を帯びるような情感や感覚を、豊かに表現できる力が宿っています。
「いきる」と読む場合は、内なる感情や情熱が高まる様子を指し、文学的・詩的な表現として用いられます。一方、「ほてる」と読むときは、身体が熱を持って赤くなる、あるいは熱く感じる状態を意味し、現代の会話や医療、生活の中でも自然に使われる表現です。
それぞれの読み方には異なる意味があり、類語や英語表現も異なります。正しく理解し、文脈に応じて使い分けることで、日本語の表現力がさらに豊かになるでしょう。
例文を通じて具体的な使い方も学んでいただけたと思います。この記事をきっかけに、「熱る」という言葉の魅力や奥深さを、ぜひ日々の表現に取り入れてみてください。




