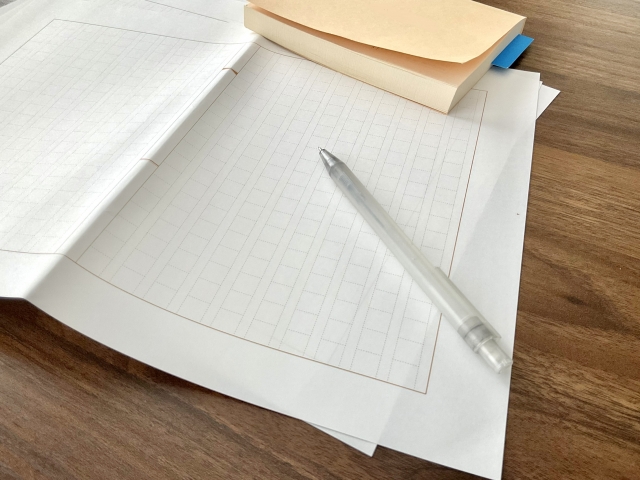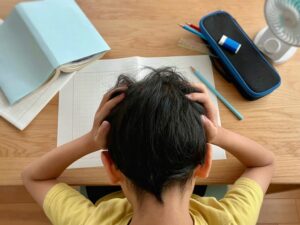読書感想文の書き方「魔法の5ステップ」1時間完成【小学生】
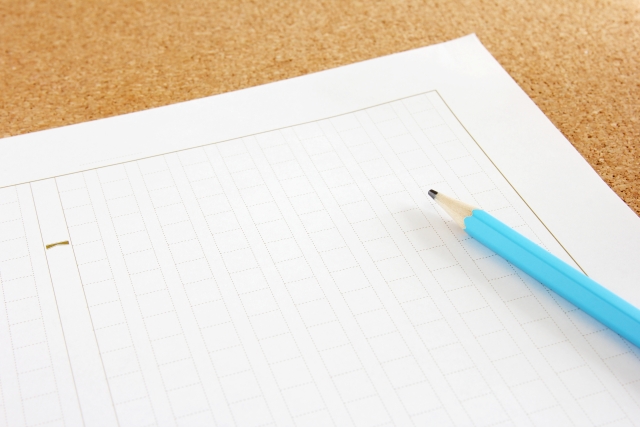
夏休みの宿題の中でも、多くの小学生が「むずかしい!」「どうやって書けばいいの?」と悩むのが読書感想文です。本を読むのは楽しいけれど、いざ書こうと思うと、何を書けばいいのかわからなくなってしまうこともありますよね。
でも、心配はいりません!この記事では、小学生のみなさんが、たった「5つのステップ」で読書感想文を1時間で書き終える方法をわかりやすく紹介します。さらに、全国コンクールで入賞する感想文の特徴や、本の選び方、実際の感想文の例文までたっぷりお届けします。
読書感想文は、「上手に書く」ことよりも、「自分の気持ちを正直に書く」ことが大切です。自分だけの感想を自由に書いて、楽しい作文にしていきましょう!
読書感想文の書き方「魔法の5ステップ」1時間完成【中学生】
読書感想文が苦手な中学生必見!この記事では、1時間で読書感想文が書ける「魔法の5ステップ」をわかりやすく解説。さらに、コンクール入賞作品の共通点やおすすめの本、…
目次
【小学生】読書感想文の書き方「魔法の5ステップ」

読書感想文がむずかしいのは、「どう書けばいいのかわからないから」です。ここでは、小学生でもすぐにできるように、「魔法の5ステップ」をもっとくわしく、1つずつ丁寧に解説していきます。
ステップ1:本を読んだ後、感じたことをメモする(10分)
まず、本を読み終わった直後に、ノートや紙に思ったことを書いてみましょう。これは「下書き」なので、きれいに書こうとしなくても大丈夫です。絵やふきだしを使ってもOK!
ポイント:
- 感情を言葉にする(例:「ドキドキした」「イライラした」「ジーンときた」など)
- 「なぜそう思ったのか?」を少しだけ書いておくと、あとがラクになる
メモの例:
- 最後に○○くんがお父さんと和解したところで、うれしくなった。
- △△ちゃんがいじめられてつらかったと思う。自分もそういう経験がある。
ステップ2:登場人物の気持ちを想像する(10分)
登場人物は、どんな気持ちでその行動をしたのでしょうか?「もし自分だったらどう思うか?」と考えると、感想が深まります。
ポイント:
- 登場人物の行動と言葉に注目しよう
- 「なぜそうしたのか?」を考えると、気持ちが見えてくる
具体例:
- ○○くんは、こわかったけど、友だちを守るためにがんばったんだと思う。
- △△ちゃんはさみしかったのに、家族に言えなくて苦しかったと思う。
ステップ3:心に残った場面を選ぶ(10分)
読んでいて「ドキッとした」「ジーンときた」場面を1つだけ選んで、そのときのようすをくわしく書きましょう。
ポイント:
- 「どんな場面だったか」「誰が何をしたか」を自分の言葉でまとめる
- できれば「セリフ」や「ようす」なども入れて、イメージしやすく書く
例:
△△ちゃんが川に落ちた子を助けたとき、まわりの子はおどろいていました。△△ちゃんは「こわくなかった」と言ったけれど、本当はとてもこわかったんだと思います。
ステップ4:自分が考えたこと・思ったことを書く(10分)
読んで感じたこと、考えたことを自分のことばで書きましょう。このとき、同じような経験があれば、それを紹介するととても良い感想になります。
ポイント:
- 「自分ならどうする?」と考えてみる
- 「似たようなことがあった」「これからこうしたい」など、自分とつなげる
例:
わたしも前に友だちが困っているとき、声をかけられなかったことがある。△△ちゃんのように、もっと勇気を出せばよかったと思った。
ステップ5:自分の日常と結びつけてまとめる(10分)
さいごは、「この本を読んで、自分がどう変わったか」「これからどうしたいか」を書いて終わりにしましょう。
ポイント:
- 「気づいたこと」「学んだこと」「変わったこと」に注目
- 1〜2文でOK!まとめの言葉にしよう
例:
この本を読んで、わたしも家族にちゃんと「ありがとう」を言おうと思いました。毎日があたりまえじゃないことに気づけてよかったです。
これで、あっという間に読書感想文の内容がそろいました!あとは、順番をととのえて清書すれば完成です。
読書感想文全国コンクール入賞作品の傾向
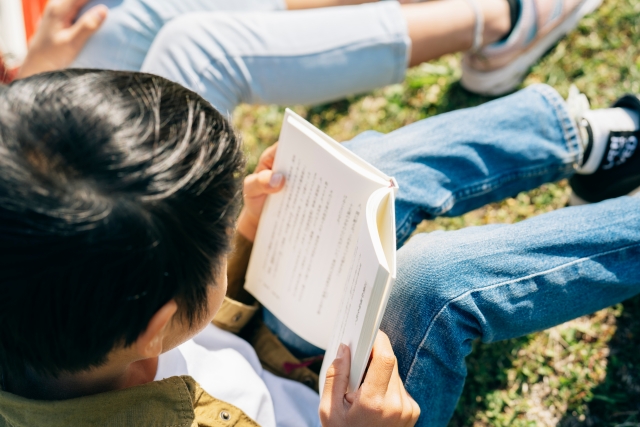
「読書感想文全国コンクール」は、毎年たくさんの小学生が応募する大きな作文コンテストです。実は、入賞する作品にはいくつか共通点(=傾向)があります。どれも特別な才能が必要なわけではなく、「ちょっとした工夫」でできることばかりです。では、どんな感想文が選ばれているのでしょうか?ポイントを5つにまとめて紹介します。
①自分の言葉で書いている
入賞作品は、「ていねいに書かれている」よりも「その子らしい言葉で書かれている」ことが特徴です。辞書にあるようなむずかしい言葉を使うより、自分の気持ちを素直に表す言葉のほうが、読む人の心に伝わります。
例:
- ✕「この書物は私に多くの感動を与えました。」
- ○「この本を読んで、すごく心が動いた。今もドキドキしています。」
②本と自分の体験がつながっている
ただ「おもしろかった」ではなく、「その本を読んで、自分の生活や経験とどう関係があったか」が書かれている感想文が多く選ばれます。これは「自分と本をむすびつける」ということです。
例:
主人公が転校生でドキドキしていたところが、自分の転校のときを思い出して共感した。
③心の動きがくわしく書かれている
「うれしかった」「悲しかった」だけでなく、「なぜそう思ったのか」「そのとき心の中で何が起きたのか」がくわしく書かれている作品が目立ちます。気持ちの変化を書くと、感想文に深みが出ます。
例:
最初は△△くんがきらいだった。でも、がんばっている姿を見て、「なんでそんなにがんばれるの?」と気になってきた。いつのまにか応援していた自分に気づいて、おどろいた。
④オリジナリティがある視点
「みんなが書きそうなこと」よりも、「自分だけが気づいたこと」「ちょっと変わった見方」がある感想文が印象に残ります。小さな発見や、「へぇ!」と思う気づきがあると、読み手に伝わります。
例:
主人公はウソをついたけど、それを見て私は「正直すぎるのもつらい時がある」と思った。
⑤書き出しと終わり方に工夫がある
はじめと終わりが印象的な感想文は、それだけで「読んでみたい!」と思わせます。とくに、書き出しで「本を読む前の自分」や「きっかけ」を書き、終わりで「気づきや変化」をまとめていると、感想文全体がきれいにまとまります。
書き出しの例:
この本は、じつは最初読みたくなかった。でも、読んでみたら気持ちが変わった。
終わり方の例:
本を読み終わって、わたしの心にひとつ、小さな勇気が生まれた気がしました。
読書感想文が楽しくなる!本(テーマ)選びのコツ
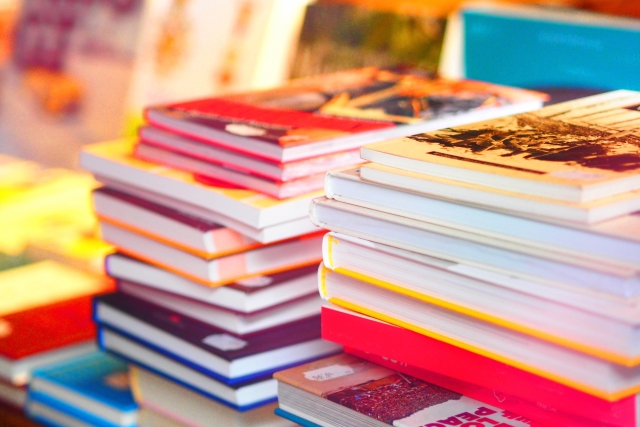
「どの本を読めばいいかわからない」「どれを選んでも感想が書けなさそう…」という声は、小学生の読書感想文あるあるです。でも、実は“本選び”が上手になると、感想文を書くのがグンと楽しくなります!ここでは、本を選ぶときに大切なポイントと、小学生におすすめの本を学年別に紹介します。
①興味のあるテーマを選ぶ
まず大事なのは、「自分が読みたいと思う本を選ぶ」ことです。動物、冒険、家族、スポーツ、ファンタジーなど、自分の好きなジャンルや、気になる話題から選びましょう。
②読みやすい長さの本を選ぶ
分厚すぎる本や、むずかしい漢字ばかりの本を選んでしまうと、途中で読むのがいやになってしまいます。自分の学年に合った本、ページ数が少なめのものから選ぶのがコツです。
目安:
- 低学年:30〜80ページ程度
- 中学年:80〜150ページ程度
- 高学年:100〜200ページ程度
③心が動くストーリーを選ぶ
感想文を書くには、「気持ちが動く」ことが大切です。泣いた、笑った、びっくりした…そんな感情が動く物語なら、自然と感想も出てきます。
こんな本がおすすめ:
- びっくりする展開がある
- 登場人物の成長が描かれている
- 自分と似たような体験が出てくる
④読書感想文におすすめの本【学年別】
小学1〜3年生向け:
- 『おしいれのぼうけん』 ふるたたるひ・たばたせいいち
- 『がまくんとかえるくん』 アーノルド・ローベル
- 『スイミー』 レオ・レオニ
小学4〜6年生向け:
- 『つるばら村のパン屋さん』 茂市久美子
- 『車のいろは空のいろ』 あまんきみこ
- 『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』ブレイディみかこ
⑤図書館や学校の先生に相談しよう
どうしても決められないときは、図書館の司書さんや学校の先生に「読書感想文に合う本を教えてください」と聞いてみましょう。感想を書きやすい本を選んでくれるはずです。
本選びは、感想文を書く前のとても大切なステップです。「自分にぴったりの一冊」を見つければ、読書も作文もずっと楽しくなりますよ!
読書感想文の例文(小学1〜3年生向け)

以下は、小学1~3年生向けの、実際の読書感想文の例です。例文では感情や気持ちを素直に表すポイントを押さえ、まとめています。
例文タイトル:『スイミー』(レオ・レオニ作品)
書き出し
この本を、はじめて見たとき、赤い魚のスイミーがちょっときれいで、なんだかすごそうだなと思いました。魚ばかりの絵がならんでいて、どんなお話かな? ワクワクしてページをめくりました。
本文
スイミーは、みんなが大きな魚にたべられてしまって、ひとりになってしまいます。はじめは、さびしくて、つらかったんだろうなと思いました。もしぼく(わたし)だったら、友だちがいなくて、とてもさびしくて泣くと思います。
でも、スイミーはあきらめませんでした。海の中を黒い魚のおともだちといっしょに泳ぐことで、こわい大きな魚に立ち向かおうとしました。ぼくも、おともだちといっしょなら、こわいこともできるかもしれないと思いました。
また、みんなで集まって「大きな魚のかたち」をつくった場面がいちばん心に残っています。まわりのみんなが協力して、すごくかっこいいなと思いました。わたしも、友だちと協力して何かをやると、もっと楽しくなるんじゃないかな、と思いました。
まとめ
この本を読んで、ひとりぼっちになってもあきらめないで、友だちと助け合ってがんばることが大切だと気づきました。これからは、学校でも友だちに「いっしょにやろう」と声をかけてみたいです。そして、クラスのみんなで楽しいことをたくさんできたらうれしいです。
読書感想文の例文(小学4〜6年生向け)
以下は、小学4〜6年生向けの読書感想文例です。より深く、感情や考えを表現し、約2000文字の構成に近づけています。
例文タイトル:『つるばら村のパン屋さん』(茂市久美子)
書き出し(約300文字)
私は、宿題の読書感想文にぴったりの本を探していて、この『つるばら村のパン屋さん』に出会いました。最初は「パン屋さんのお話かぁ…」と思っていたけれど、読みはじめると、主人公のミカが毎朝早く起きて大切にパンを作る姿が、とてもかっこよく見えてきました。私は朝が苦手だけど、この本を読んで「私も見習いたい」と思いました。
本文
村に住むミカは、おばあちゃんから教わったレシピで、毎日ていねいにパンを焼いています。ある日、お客さんが少なくなって心配すると、「どうすればもっと喜んでもらえるか」と工夫し始めます。私も、部活の試合でミスが多かったとき、どうしたらもっと上手になれるか試行錯誤したことを思い出しました。
ミカは新しいパンの味を考え、村の人に感想を聞いて改良を重ねました。その姿を見て、「人の声をちゃんと聞くことって大事だな」と感じました。私も、友だちの意見を聞いて、グループ活動を上手に進めたいと思いました。
また、ミカがお店を続ける大変さにくじけそうになる場面がありました。特に、大雨でお客さんが来ない日、「今日は売れなかったらどうしよう…」と不安になる様子が心に残りました。私ならきっとあきらめてしまいそうですが、ミカは励まし合える仲間や家族のおかげでまたがんばります。私も、落ち込んだときに、家族や友だちの声に支えられていることに改めて気づきました。
自分の考え・経験とのつながり
私は今年、運動会のリレー練習で全力を出してがんばったけれど、うまくバトンを渡せず悔しい思いをしました。そのとき、監督から「失敗しても、次に生かせばいいんだよ」と言われ、もう一度挑戦できました。ミカのように、失敗をどう生かすかが大切だと感じました。
また、クラスで意見が合わず、仲間とけんかしたこともありました。でも、相手の気持ちを聞くことで、また仲直りできた経験があります。ミカのように、自分の想いを伝えながら相手の声にも耳をかたむけることが、大切だと実感しました。
まとめ
『つるばら村のパン屋さん』から、あきらめずに工夫し続けること、そして誰かと支え合うことの大切さを学びました。私もこれからは、困ったときにはすぐに相談して、みんなで頑張っていきたいです。ミカのように、自分も前向きな気持ちを忘れずにがんばります!
よくある質問(Q&A)

読書感想文に取り組むとき、小学生や保護者の方からよく聞かれる質問をまとめました。困ったときの参考にしてくださいね!
Q1. 本を最後まで読めなかったときはどうすればいい?
A. 最後まで読めなくても、心に残った場面があれば、その部分だけでも感想文は書けます。ただし、「途中までしか読めなかったけれど…」と正直に書いて、自分が感じたことや考えたことに集中すると良いでしょう。あとで続きを読んだら、「読んでよかった」と思えるかもしれません。
Q2. どこまで書けばいいの?(分量の目安)
A. 学校や学年によって異なりますが、だいたいの目安は次の通りです:
- 低学年(1〜3年生):400〜800字
- 中学年(4年生):800〜1200字
- 高学年(5〜6年生):1000〜2000字
書くときは、「書き出し→心に残った場面→自分の気持ち→まとめ」という流れを意識すれば、自然と文字数も増えていきます。
Q3. 書きたいことが浮かばないときはどうする?
A. 無理に書こうとせず、まずは本を読んで「どんな気持ちになったか」をメモに書き出しましょう。好きな場面、イヤだった登場人物、びっくりした出来事など、どんな小さなことでもOKです。そこから少しずつ広げていくと、自然に書く内容が見えてきますよ。
Q4. 書いたけど、うまくまとまらない…
A. まずは、「どんな順番で書いたか」を見直してみましょう。以下のような構成がおすすめです:
- 本を選んだ理由
- 心に残った場面
- 自分の気持ち・考え
- 自分の経験やこれからに結びつけるまとめ
この順に並べ替えるだけでも、感想文はずっと読みやすくなります。
Q5. 家族に手伝ってもらってもいいの?
A. はい、OKです!書く内容は自分の言葉で考えるのが大切ですが、「どういうふうに書けばいいの?」「ここ、変じゃないかな?」と相談するのはとても良いことです。いっしょに読み返したり、アドバイスをもらったりしながら、少しずつ上達していきましょう。
Q6. 原稿用紙の使い方に自信がない!
A. 原稿用紙の使い方にはルールがありますが、慣れれば簡単です。よくあるポイントはこちら:
- 1マスに1文字ずつ書く
- 段落のはじめは1マスあける
- 「。」や「、」は1マスに1つ
- 会話文は「 」も1マスずつ使う
不安な場合は、先生や家族に見てもらって確認しましょう。
まとめ
読書感想文は、「うまく書く」ことよりも、「自分の気持ちを正直に表す」ことが一番大切です。今回紹介した「魔法の5ステップ」を使えば、どんな小学生でも1時間で楽しく感想文が書けます。
本を読んで心が動いたら、それが感想文のはじまりです。登場人物の気持ちに寄りそったり、自分の体験とくらべたりしながら、感じたことを一つずつ書き出してみましょう。
また、読書感想文コンクールの入賞作品には、自分らしい言葉、気持ちの変化、オリジナルの視点など、たくさんのヒントがつまっています。上手にまねして、自分だけの文章を作ってみましょう。
本選びに迷ったときは、図書館や先生に相談したり、この記事のおすすめ本を参考にしてみてくださいね。
読書感想文は、自分のこころの中を見つめるすてきな時間です。今年の夏は、あなたの「思い」を文章にしてみましょう!