「愛でる」の意味【30例文】「まなでる」とは?読み方の正解

「愛でる(めでる)」という言葉を、あなたはどれくらい日常で使っているでしょうか?
最近では、あまり耳にすることのない言葉かもしれません。しかし、文学作品や和の文化に触れると、しばしば登場するこの言葉には、日本語ならではの美しい感性が込められています。
一方で、「愛でる」という漢字を見ると「まなでる」と読んでしまう方もいるかもしれません。読み方を間違えやすく、意味も少し難解に感じられることがあるこの言葉ですが、実はとても奥深く、知っておくと表現の幅が広がる便利な語でもあります。
この記事では、「愛でる」の正しい読み方や意味はもちろん、日常での使い方や30の例文、歴史的背景や英語表現まで、幅広く丁寧に解説していきます。
それでは、まず「愛でる」という言葉の基本から見ていきましょう。
「愛でる」とは

「愛でる」という言葉は、古くから日本語の中で使われてきた、美しさや価値を心から尊ぶときに用いられる表現です。まずはその読み方と意味を詳しく見ていきましょう。
「愛でる」の読み方
「愛でる」は【めでる】と読みます。
「めでる」と平仮名で表記されることもありますが、漢字では「愛でる」と書きます。
一部で「まなでる」と誤読されることがありますが、これは正しい読み方ではありません。「愛」という漢字に「まな」という読みが含まれるため混同しがちですが、「愛でる」に関しては「めでる」が唯一の正解です。
「愛でる」の意味
「愛でる」とは、美しいものや価値あるものを見て、心から感動し、それを大切に思う気持ちを表す言葉です。単に「見る」や「好き」といった感情よりも、もう一歩深い、「尊ぶ」「慈しむ」といったニュアンスを持っています。
たとえば、美しく咲く花を見て「きれいだな」と思うだけでなく、「この一瞬の美しさを心に刻んで大切にしたい」と感じるような、感情の深みがあるときに「愛でる」という言葉がふさわしいのです。
【例】
- 春の桜を愛でる
- 日本庭園の風情を静かに愛でる
- 大切なペットの仕草を優しく愛でる
このように、「愛でる」は心を込めて見つめ、価値を感じ取る繊細な感情を表す日本語です。
「まなでる」と読む?
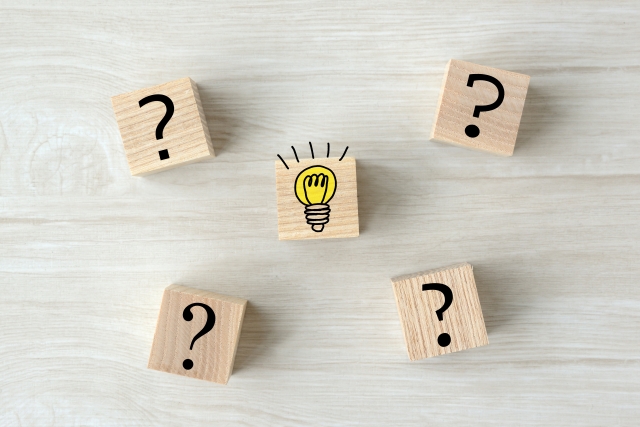
「愛でる」という言葉に接したとき、「まなでる」と読んでしまったことはありませんか?これは比較的よくある誤読のひとつです。この章では、「まなでる」という読み方について詳しく解説します。
「まなでる」は誤読
「愛でる」の正しい読み方は「めでる」であり、「まなでる」と読むのは誤りです。では、なぜ「まなでる」と読んでしまう人がいるのでしょうか?
主な原因は、以下の2点が挙げられます。
①漢字の印象による誤解
「愛」という漢字から、「愛(まな)」という読みを連想してしまうケースです。実際に、「愛(まな)」という読み方は名前(人名)などで使われることもあるため、違和感なく読んでしまうのです。
②読み方に慣れていない
「愛でる」はやや古風で、現代の日常会話ではあまり頻繁に使われないため、読み方を知らずに直感的に読んでしまうこともあります。
辞書や文献でも「めでる」が正解
国語辞典や文献においても、「愛でる」は一貫して「めでる」と記載されています。「まなでる」という読み方は、辞書には存在しません。インターネット上では稀に「まなでる」と書かれている例も見受けられますが、いずれも誤用です。
誤読に注意して、正しく使おう
日本語は美しく奥深い表現が多い分、読み方を間違えやすい漢字も少なくありません。特に「愛でる」のように日常であまり使わない言葉は、誤読が広まりやすい傾向にあります。
正しくは「めでる」と読み、意味も含めて正しく理解して使うことで、表現の豊かさがぐっと広がります。
「愛でる」の使い方【例文30】
「愛でる(めでる)」という言葉は、美しさや価値あるものを心から大切に思い、味わうように見つめるときに使われます。日常会話ではやや文語的な響きがあるものの、詩的・丁寧な表現として非常に魅力的です。
以下では、「愛でる」を使った例文を30個、シチュエーション別に分けてご紹介します。
【1】自然を愛でる

- 春の桜を静かに愛でるひとときが好きだ。
- 雪景色を眺めて、冬の美しさを愛でる。
- 新緑の山々をドライブしながら愛でた。
- 朝日が昇る様子を、窓辺で愛でるのが日課です。
- 秋の紅葉を夫婦で愛でる時間を楽しんだ。
【2】動物や生き物を愛でる

- 子猫の丸まった姿を、つい愛でてしまう。
- 鯉が泳ぐ姿を池のほとりで愛でる老人の姿が印象的だった。
- ペットの小鳥のさえずりを耳で愛でるように聞いていた。
- 小さな虫の繊細な羽を観察しながら愛でる昆虫少年。
- 金魚の優雅な泳ぎを見て、心を愛でるような気持ちになった。
【3】芸術や文化を愛でる

- 日本画の繊細な筆遣いをじっくり愛でる。
- お茶会では茶碗の美しさを愛でる時間がある。
- 書道作品を愛でて、作者の心を読み取る。
- 陶芸の器を手に取り、土のぬくもりを愛でる。
- 能や歌舞伎の所作を愛でる観客の眼差しが真剣だった。
【4】人や人柄を愛でる

- 赤ん坊の笑顔を皆で愛でた。
- 長年連れ添った妻の穏やかな表情を愛でるように見つめた。
- 祖母の優しい語り口を愛でて聞いた。
- 子どもの一生懸命な姿を心から愛でた。
- 年配の方の品ある所作を愛でるように学ぶ。
【5】日常生活の中で愛でる

- 丁寧に淹れた一杯のコーヒーを愛でるように味わう。
- 朝食に出された和食を目でも愛でる。
- 手作りのお弁当の彩りを愛でる。
- 毎日咲くベランダの花を愛でるのが癒しの時間。
- お気に入りの服をクローゼットから出して愛でる瞬間がある。
【6】詩的・文学的な表現で愛でる
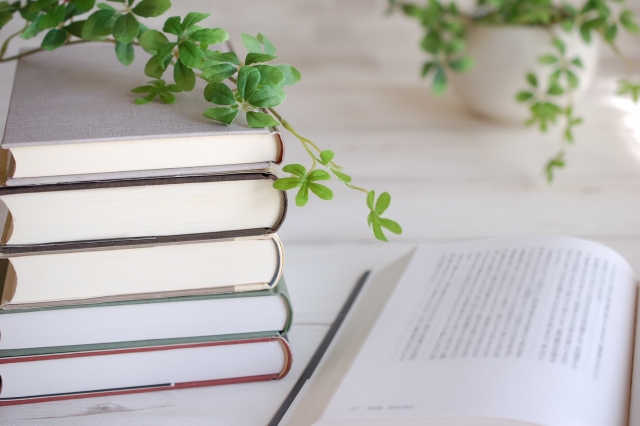
- 月の光を静かに愛でる、そんな夜が好きだ。
- 古典文学の一節を愛でるように何度も読み返す。
- 小さな野草の美しさを見つけて愛でる気持ちを忘れたくない。
- 旅先で出会った風景を心の中で愛でる。
- 日常の中にある美しさを見つけて愛でる心を大切にしたい。
このように、「愛でる」は自然、芸術、人、日常まで、幅広い対象に対して使うことができます。共通しているのは、単なる「観察」や「評価」ではなく、心をこめて「慈しむ」ように見つめる姿勢です。
「愛でる」の歴史

「愛でる(めでる)」という言葉は、現代の日本語においては少し古風な印象を持たれるかもしれません。しかしそのルーツは非常に古く、日本語の美的感覚や感情表現の中核を成す、由緒ある語です。
この章では、「愛でる」という言葉の語源や変遷についてご紹介します。
「愛でる」は古語?
はい、「愛でる」は古語としても長い歴史を持つ言葉です。
語源:「愛づ(めづ)」
「愛でる」の元の形は、平安時代の日本語である「愛づ(めづ)」です。この「愛づ」は、以下のような意味を持っていました。
- 美しいものを賞賛する
- 心を寄せる・慕う
- 感動する・感嘆する
つまり、現在の「愛でる」とほぼ同様の意味で、すでに千年以上前から日本人の感性を表現する重要な言葉として使われていたのです。
古典文学にも頻出
「愛づ」は、『源氏物語』や『枕草子』といった平安時代の古典文学の中でも頻繁に使われています。
たとえば、『源氏物語』では、美しい人や風景に感動した登場人物たちの描写にしばしば「めづ」という言葉が登場し、その感情の深さや繊細さを表しています。
時代とともに形が変化
- 平安時代:「愛づ(めづ)」という動詞が一般的
- 中世以降:「愛でる」という表記に変化し、現代語として定着
- 現代:やや文語的・詩的な語感を持ちながらも、使われ続けている
このように、「愛でる」は長い年月を経て形を変えながらも、常に「美しさへの敬意」や「心からの感動」を表す言葉として受け継がれてきたのです。
「愛でる」の類語

「愛でる(めでる)」という言葉は、美しさや価値あるものを見つめ、心から敬意や愛情をもって接するという深い意味があります。そのため、似たような意味を持つ言葉もいくつか存在しますが、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
この章では、「愛でる」と意味が近い日本語の類語を取り上げ、違いや使い分けも解説します。
主な類語とその違い
| 類語 | 意味・特徴 | 「愛でる」との違い |
|---|---|---|
| 鑑賞する | 芸術作品や自然などを味わいながら見ること | 客観的・分析的な側面がやや強い |
| 賞賛する | 他人や作品をほめること | より言葉にして評価する意味合いが強い |
| 慈しむ | 弱い存在に対する深い愛情や優しさ | 「育てる・守る」意味が含まれる場合がある |
| かわいがる | 親しみを込めて接する | カジュアルで口語的な表現 |
| たしなむ | 趣味などを好み、ほどよく親しむこと | 行動や習慣に対して使われることが多い |
| 味わう | 五感を通じて深く感じ取る | 味覚以外にも、感動や風情に対しても使える |
「愛でる」の独自性
「愛でる」は、これらの類語と比べて、
- 視覚的な感動
- 心の奥底からの尊重や感謝
- 詩的・文化的な美意識
というニュアンスが際立っており、単に「見る」や「好き」といった感覚を超えた、深い情緒を表現できる言葉です。
使い分けの例
- 美術館で絵画を見る → 「鑑賞する」「愛でる」
- 子どもや動物に接する → 「かわいがる」「慈しむ」「愛でる」
- 茶道や俳句を楽しむ → 「たしなむ」「愛でる」
- 美しい風景に見とれる → 「愛でる」「味わう」
「愛でる」は、類語に比べてやや文学的・精神的な深みがある言葉です。日常会話では他の表現でも問題ありませんが、感性や情緒を豊かに伝えたい場面では、「愛でる」を意識的に選んでみるのもおすすめです。
「愛でる」の英語
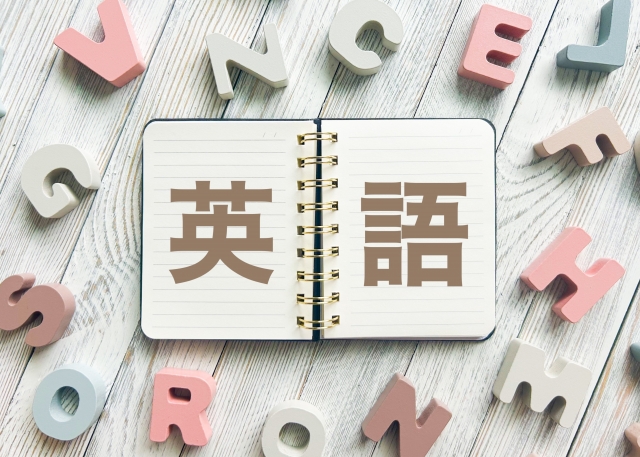
「愛でる(めでる)」という言葉の持つ繊細な感情や情景を、英語でどう表現すればよいか迷うことがあるかもしれません。日本語の「愛でる」には、単に「見る」や「楽しむ」だけではなく、心から大切に想い、深く味わうという意味合いが含まれているため、英語では文脈に応じた言い換えが必要です。
この章では、「愛でる」を英語で表現するための主な単語と使い分けを解説します。
appreciate(鑑賞する、味わう)
「美しさ」や「芸術的価値」に対して、感謝や敬意を持って楽しむという意味で、「愛でる」に最も近い表現のひとつです。
例文
- I took a moment to appreciate the beauty of the cherry blossoms.
(桜の美しさをしばし愛でた。)
admire(賞賛する、うっとり見とれる)
視覚的に見て感心したり、称賛の気持ちを込めて眺めたりする時に使われます。対象に対する感動が強いときに適しています。
例文
- She stood silently, admiring the sunset.
(彼女は静かに夕日を愛でていた。)
cherish(大切に思う、慈しむ)
「心から大切にする」というニュアンスを含み、人や記憶、感情に対して使われます。感情的な深みがある点で「愛でる」と重なる部分があります。
例文
- He cherishes the time he spent with his grandmother.
(彼は祖母と過ごした時間を愛でるように大切にしている。)
enjoy(楽しむ)
よりカジュアルで一般的な表現ですが、日常的な場面では「愛でる」に代わって使うことができます。ただし、「深く味わう」というニュアンスはやや薄くなります。
例文
- They enjoyed the peaceful view from the mountain.
(彼らは山からの穏やかな景色を愛でながら楽しんだ。)
その他の表現
- gaze at(うっとりと見つめる)
- marvel at(驚きや称賛を込めて見る)
- savor(味わう:比喩的に使えば感情・風景にも対応)
例文
- I gazed at the garden, savoring its quiet elegance.
(私は庭を愛でながらその静かな美しさを味わった。)
ポイント
| 英語表現 | ニュアンス | 適した状況 |
|---|---|---|
| appreciate | 美を認めて楽しむ | 芸術・自然・瞬間を味わうとき |
| admire | 感心して見つめる | 見た目の美しさに対して |
| cherish | 感情的に大切にする | 思い出や人に対して |
| enjoy | 楽しむ | カジュアルな場面全般 |
| savor / gaze at | ゆっくり味わう / 見つめる | 比喩的な表現、詩的な場面 |
「愛でる」にピタリと一致する英単語は存在しませんが、文脈に応じてこれらの語を使い分けることで、ニュアンスをしっかり伝えることができます。
よくある質問

「愛でる(めでる)」という言葉は美しい日本語である一方、少し使いづらく感じたり、誤解されたりすることもあります。この章では、読者の方からよく寄せられる疑問にQ&A形式でお答えします。
Q1. 「愛でる」は日常会話で使っても大丈夫?
A. はい、使って問題ありません。ただし、やや文語的・詩的な響きを持つため、フォーマルな場や落ち着いた会話での使用が自然です。親しい人とのカジュアルな会話では「かわいい」「好き」と言った表現の方が馴染みやすい場合もあります。
Q2. ビジネスシーンで「愛でる」は使えますか?
A. 一般的なビジネス会話ではあまり使われません。感性的な表現であり、論理的な会話にはやや不向きです。ただし、文化イベントの企画書や、高級商品のキャッチコピー、手紙などでは上品な印象を与える表現として活用できます。
Q3. 「愛でる」はどういう対象に使う言葉ですか?
A. 美しい風景、芸術作品、動物、植物、人の仕草や所作など、目で見て感じ取れるもの全般に使えます。さらに、記憶や時間、瞬間の美しさを表す詩的な表現としても用いられます。
Q4. 「愛でる」と「かわいがる」は同じ意味ですか?
A. 類似点はありますが、ニュアンスが異なります。「かわいがる」は親しみや愛情を直接的に示す行動(例:子どもを抱きしめる)に対して使うのに対し、「愛でる」はもう少し距離を取り、心で大切に味わうように見守るといった静かな愛情表現です。
Q5. 「めでたい」と「愛でる」は関係ありますか?
A. はい、あります。「めでたい」は「愛でる」の古語「めづ」に由来しています。つまり、「愛でるほどに素晴らしい・祝う価値がある」という意味から派生して「めでたい」となりました。
Q6. 「愛でる」の漢字は必ず使うべきですか?
A. 必須ではありません。文章の雰囲気や媒体に応じて、「めでる」と平仮名で書くこともあります。特に小説や詩などでは、ひらがなのやわらかい印象を優先する場合があります。
このように、「愛でる」は繊細な意味を持つからこそ、使い方に迷う方も多い言葉です。正しく理解し、場面に応じて使えば、表現の幅がぐっと広がります。
まとめ
「愛でる(めでる)」という言葉は、ただ「見る」や「好き」といった単純な意味ではなく、美しさや価値を心で味わい、大切に思うという日本語特有の繊細な感性を表現する言葉です。
平安時代の古語「愛づ(めづ)」を語源とし、千年以上にわたって日本人の美意識や文化の中で生き続けてきました。読み方を「まなでる」と誤解されることもありますが、正しい読みは「めでる」です。
例文や類語との違い、英語表現などを通してわかるように、「愛でる」は多様なシーンで使える上品な表現であり、自然、芸術、人、日常の中にある“静かな感動”を言葉にするのにぴったりです。
現代ではあまり頻繁に使われないかもしれませんが、だからこそ、使いこなせると一目置かれる表現です。大切なものに心を寄せるとき、ぜひ「愛でる」という美しい日本語を使ってみてください。




