「掻ける」の意味と使い方【50例文】ネットスラング用語も解説

「かける」という言葉には、多くの漢字と意味が存在します。たとえば「掛ける」「書ける」「駆ける」など、それぞれ異なる使い方やニュアンスを持っています。しかし、そんな「かける」の中でも、あまり知られていないのが「掻ける」という表現です。
「掻ける」は、「掻く」という動作の可能形、つまり「掻くことができる」という意味を持つ言葉です。日常会話ではなかなか登場する機会は少ないものの、文学作品や詩、または古語表現としては確かな存在感を持っています。
この記事では、「掻ける」の意味や使い方、語源だけでなく、「掻け退ける」「掻け除ける」などの複合語表現、さらには例文50選までを通して、この言葉の魅力をじっくり解説していきます。また、近年使われているネットスラングとしての使い方まで紹介します。
日本語の奥深さや表現の幅広さに触れながら、「掻ける」という言葉を理解し、ぜひ自分の語彙に取り入れてみてください。
「掻ける」の意味

「掻ける」の読みは「かける」です。「掻ける」という言葉は、一般的な辞書や日常会話にはあまり登場しない、ややマイナーな日本語表現です。しかし、きちんと意味を知れば、文章表現に深みを与えることができます。まずは、その基本的な意味から見ていきましょう。
「掻ける」は、動詞「掻く(かく)」に可能の助動詞「~える」が付いた形です。つまり、「掻くことができる」という意味になります。
▼掻けるの主な意味
| 意味 | 説明 | 例文 |
|---|---|---|
| ① かゆいところを指や道具でこする | 皮膚をこすって刺激を与える動作 | 虫に刺された腕を掻いた。 |
| ② 散らしたり、払いのける動作 | 砂やほこりを掻き分ける | 雪を掻いて道を作る。 |
| ③ 水や空気などをかき分けて進む | 泳いだり、進む際の動き | 彼は力強く水を掻いて泳いだ。 |
| ④ 感情や音、汗などを出す | 比喩的な表現 | 恥を掻く、大汗を掻く。 |
他の「かける」との違い
「かける」は同音異義語が非常に多い言葉です。ここでは、よく使われる他の「かける」との違いを簡単に整理しておきます。
| 漢字 | 意味 | 用例 |
|---|---|---|
| 掛ける | 物を引っかける、始める | コートを掛ける、電話を掛ける |
| 書ける | 文章を書くことができる | この漢字は書けない |
| 駆ける | 走るように素早く動く | 馬が野を駆ける |
| 賭ける | 勝負や運に任せる | 命を賭ける |
| 掻ける | 掻くことができる | 背中を掻ける、雪を掻ける |
ネットスラングとしての「掻ける」とは?

近年では、「掻ける」が焦って急いで行動する様子や、テンパって動く様子をネットスラング的に使うこともあります。たとえば、「今から掻けるわ!」というと「急いで行動に移る」という意味合いになります。つまり「掻ける」は、もともとは物理的な動作を表す言葉ですが、日常的な比喩表現やネットスラングとしても使われる多義的な言葉です。
SNSやネットスラングでの使い方の例
ネットスラングにおける「掻ける」は、焦ってバタバタと動き出す・急いで行動する様子を意味します。もともとの「手でかき乱す・かき分ける」という意味から転じて、「状況に慌てて対応し始める」「勢いよく突っ込む・動く」というイメージで使われるようになりました。
- 「やばい、寝坊したから今から掻けるわ!」
→ 慌てて準備して家を出るイメージ - 「イベント始まった瞬間にみんな掻けてて笑った」
→ 一斉に参加者が急いで動き出す様子 - 「締切ギリギリで掻け始める自分が嫌」
→ 焦って取りかかる状態への自虐
若者言葉としてのニュアンス
「掻ける」は、特にSNSやゲーム実況、配信界隈で若者が使うことが多く、「慌ただしく・雑に・必死に動く」といったニュアンスを含みます。
- 丁寧で落ち着いた行動ではなく、
- 勢い任せ・テンパっている感じ
- 必死感・ドタバタ感
これらをユーモラスに、あるいは軽く自虐的に表現したいときに使われます。
言葉の広がりと注意点
「掻ける」は本来、「掻く」の可能形や物理的動作を表す言葉ですが、ネット上では新しい意味を持つ表現として独自に進化しています。ただし、公式な日本語表現ではなく、フォーマルな場面では使わないほうが無難です。
「掻ける」を使った【50例文】
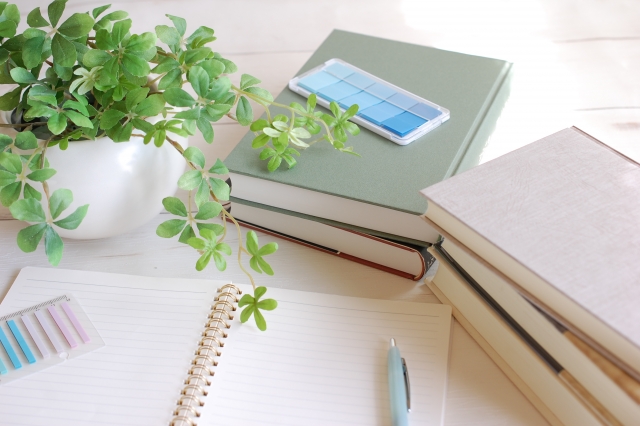
この章では、「掻ける」という言葉をさまざまな文脈で活用した例文を50個紹介します。また、「掻け退ける」「掻け除ける」などの複合語も取り上げて、多様な表現方法に触れていきます。
①身体的な動作としての使い方
- 背中がかゆいけれど、手が届かず自分では掻けなかった。
- 猫は器用に後ろ足で耳の後ろを掻いていた。
- 長い定規を使って、肩甲骨のあたりをなんとか掻いた。
- 子どもが蚊に刺された足をポリポリと掻いている。
- このブラシなら、頭皮の隅々まで気持ちよく掻ける。
- 手を骨折してから、頭のかゆみも自分では掻けず不便だった。
- 冬になると肌が乾燥して、ついあちこち掻いてしまう。
- 痒いところを自分で掻けるのは、当たり前のようでありがたい。
- 緊張のせいか、気づくと首筋を掻いていた。
- 長い孫の手があれば、背中のかゆいところも簡単に掻ける。
②取り除く・払いのける場面での使い方
- 除雪車が通ると、一晩で積もった雪が一気に掻き取られた。
- ほうきを使って、落ち葉を掻き集めた。
- ちりとりに埃を掻き入れてから、ゴミ袋にまとめた。
- 子どもが砂場で砂を掻き分けて、小さなトンネルを作っていた。
- 靴先で水たまりを掻いてみると、中から小さなカエルが跳び出した。
- 表面の泥をシャベルで掻いていくと、固い地面が見えてきた。
- 部屋の隅にたまったゴミを、掃除機では吸いきれず手で掻き寄せた。
- 熊手を使って、庭の落ち葉を広範囲に掻き集めた。
- 草刈りのあと、雑草を一箇所に掻き寄せて燃やした。
- ベンチに座る前に、落ち葉を手でサッと掻き除けた。
③比喩的な表現としての使い方
- 失敗して恥を掻くのが怖くて、何日も準備を重ねた。
- 面接で緊張して、思わず大恥を掻いてしまった。
- プレゼンの最中、冷や汗を掻きながら話し続けた。
- 緊張がピークに達して、背中に汗を掻いた。
- 名前を大声で呼ばれて、思わず顔を掻いてごまかした。
- 冷房の効きすぎで、体が冷えすぎて妙な汗を掻いた。
- 想定外の質問にあたふたして、額に冷や汗を掻いた。
- 退屈な会議が続き、思わず額に変な汗が掻かれた。
- 重要な場面で言葉を噛み、全身に冷や汗を掻いた。
- 結果発表の直前、手のひらにじんわりと汗を掻いていた。
④複合語「掻け退ける」「掻け除ける」などの使い方
- スコップで雪を掻け退けながら、玄関までの道を作った。
- 枯れ枝を手で掻け除けて、小道を進んでいった。
- 前に積もった葉を掻け退けないと、自転車が通れない。
- 落ち葉を一枚ずつ掻け除けると、下から石碑が現れた。
- 古びた棚の埃を掻け除けると、昔のアルバムが出てきた。
- 書類の山を掻け退けながら、目的の資料を探した。
- 重たい雲を掻け退けるようにして、太陽が姿を見せた。
- 心の迷いを掻け除けるようにして、思い切って決断した。
- 地面の泥を掻け退けても、落とした鍵は見つからなかった。
- 林の奥へ進むために、枝葉を手で掻け退けて歩いた。
⑤文語的・情景描写的な使い方
- 老女の手元から落ち葉が静かに掻き集められていた。
- 冷たい風が頬にかかる髪をやさしく掻き分けていった。
- 湖面を渡る舟が、水を静かに掻いて進んでいた。
- 炭火を整えながら、火の粉を掻き立てる音が響いた。
- 指先が滑らかにページを掻きめくっていった。
- 夜の闇を掻け退けるような一筋の光が、窓の外に見えた。
- 水面を掻く音が、静寂の中に響いていた。
- 朝もやを掻き分けるようにして、太陽が顔を出した。
- 記憶の奥底を掻き起こすような懐かしい香りが漂ってきた。
- 夜空に瞬く星が、空を掻くように流れていった。
「掻く」の語源・由来
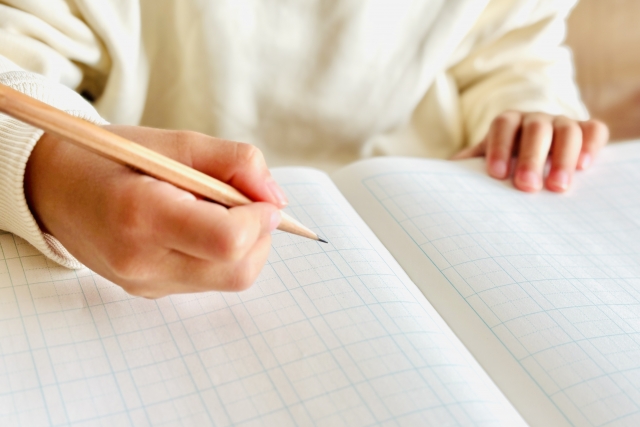
「掻く」は、古くから日本語で使われてきた和語(大和言葉)の一つで、奈良時代からすでに存在した言葉です。その語源は明確に断定されているわけではありませんが、以下のような説が有力です。
擦る・こする動作に由来する説
「掻く」は、もともと手や爪を使って何かをこすったり、払いのけたりする動作を表していました。
これは、「削ぐ(そぐ)」や「刮ぐ(こそぐ)」といった語と同様に、摩擦や除去のイメージが語源となっていると考えられています。
- 「髪を掻く」=櫛でとかす
- 「汗を掻く」=汗を出す(動作の結果)
- 「かゆいところを掻く」=手でこする
これらの使い方すべてに「手を使って何かを動かす・除く・こする」という共通した動作のイメージがあります。
オノマトペ(擬音語)に由来する説
一部の言語学者は、「カカカッ」「カリカリ」といった掻く動作に近い音(擬音)から派生したという説も唱えています。日本語では、こうした動作を音で表した語から動詞が生まれるケースも多いため、掻くもそうした擬音的語源を持つ可能性があると考えられています。
古語・古典における使用
「掻ける」は古語というわけではありませんが、動詞「掻く」自体は平安時代から使用されている非常に歴史ある言葉です。とくに和歌や物語文学の中では、感情や風景描写に多く使われてきました。
たとえば:
- 『枕草子』や『源氏物語』の中には、「涙を掻きぬ」や「草を掻き分け」などの表現が見られます。
- 能や狂言などの古典芸能でも、「掻け退ける」などの動作描写が登場することがあります。
こうした文学的背景を持つ言葉だからこそ、現代でも詩的・情緒的な文脈で使われることがあるのです。
なぜあまり使われなくなったのか?
- 「掻ける」は他の「かける」と比べて意味が限定的であること
- 多くの動作が機械化・道具化され、「掻く」という動作そのものが比喩的に使われる機会が減ったこと
- 現代語では、より平易で具体的な言葉(取る、掃く、取り除くなど)が好まれる傾向にあること
こうした理由から、「掻ける」という表現は徐々に使用頻度が下がり、限られた文脈での登場にとどまっていると考えられます。
まとめ

「掻ける」という言葉は、現代ではあまり耳にする機会がない表現ですが、正しく理解すれば非常に表現力豊かな語であることがわかります。基本的には「掻くことができる」という意味であり、身体のかゆい部分を掻ける、障害物を掻き退けるといった物理的な動作のほか、感情や比喩的な表現にも応用できます。
とくに「掻け退ける」や「掻け除ける」といった複合語は、描写的な文章や文学的な表現に深みを与えることができます。また、語源をたどると「掻く」+「可能の助動詞える」という文法的な構造に基づき、非常に自然な日本語の形であることが分かります。
本記事を通して、「掻ける」という言葉の意味や使い方、由来や例文までを幅広く紹介しました。ふだん使う機会は少なくても、日本語の美しさや奥深さを感じられる表現として、知っておきたい一語と言えるでしょう。




