プロローグ・エピローグ・モノローグ・ダイアローグの違いと日本語訳

私たちが日常的に目にする小説や映画、演劇などの作品には、「プロローグ」や「エピローグ」、「モノローグ」や「ダイアローグ」といった専門用語がよく使われています。英語表記のまま登場することも多く、なんとなく意味を理解していても、正確な違いや日本語での言い換えまでしっかり把握している人は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事では、以下の4つの言葉について、それぞれの意味や使われる場面、日本語での言い換えをわかりやすく解説します。
- プロローグ(Prologue)
- エピローグ(Epilogue)
- モノローグ(Monologue)
- ダイアローグ(Dialogue)
特に創作活動をしている人、脚本や小説を書いている人、またはそれらを深く味わいたい読者・視聴者にとって、これらの用語をしっかり理解することは、作品の構造や演出意図を読み解く手助けになります。それでは、それぞれの用語について詳しく解説していきます。
プロローグとは?
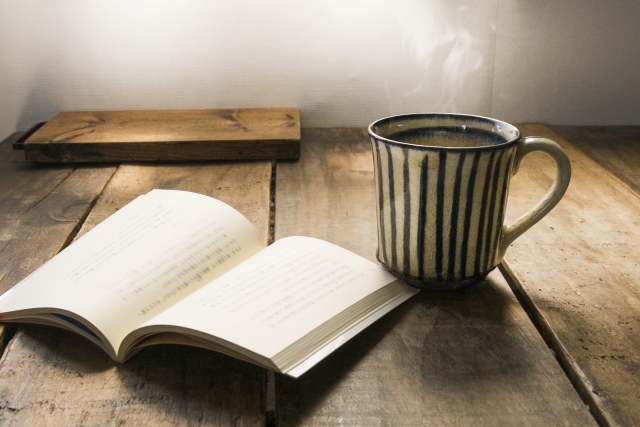
プロローグの定義と語源
「プロローグ(Prologue)」とは、物語や演劇、映画などの作品の冒頭に挿入される導入部のことを指します。
この言葉はギリシャ語の「prologos(プロロゴス)」に由来しており、「pro(前に)」+「logos(言葉)」という意味を持ちます。つまり、「物語の前に語られる言葉」ということです。
どんな場面で使われる?
プロローグは、小説や戯曲、映画などの冒頭に使われ、以下のような役割を果たします:
- 登場人物や世界観の紹介
- 物語の背景説明(時代・場所・状況など)
- 伏線の提示
- 本編とは異なる時間軸(たとえば未来や過去)の出来事を示す
プロローグは「いきなり本編に入る前のウォーミングアップ」として機能します。
読者や観客をスムーズに物語の世界へ引き込むための重要なパートです。
日本語での言い換え
プロローグは日本語では以下のように言い換えることができます:
| 英語 | 日本語の言い換え | 説明 |
|---|---|---|
| プロローグ | 序章 | 物語の第一章の前に置かれる導入的な章 |
| プロローグ | 序文 | 主にエッセイや評論、書籍全般の冒頭に使われる前書き的な内容 |
| プロローグ | 導入部 | 演劇や映画などで、本編が始まる前の部分 |
なお、「序章」と「第1章」は別物です。序章が“導入”なのに対し、第1章は“本編の開始”です。
プロローグの使い方の例
以下に、プロローグが使われている例をいくつかご紹介します:
- 小説の例:
村上春樹の『1Q84』では、冒頭に日常と非日常の境界が描かれ、物語の雰囲気が提示されます。 - 映画の例:
『ロード・オブ・ザ・リング』では、壮大な戦いの歴史(過去)が冒頭で語られ、世界観が一気に明示されます。 - 演劇の例:
シェイクスピア作品では、しばしば“語り手”や“ナレーター”がプロローグとして観客に語りかけ、物語の土台を説明します。
エピローグとは?

エピローグの定義と語源
「エピローグ(Epilogue)」とは、物語や演劇、映画などの本編が終了したあとに挿入される結末のまとめや後日談を指します。
語源はギリシャ語の「epilogos(エピロゴス)」で、「epi(後に)」+「logos(言葉)」という意味を持ちます。つまり、「物語のあとに語られる言葉」——本編のエンディングの“さらにあと”に加えられるパートです。
どんな場面で使われる?
エピローグは、小説や脚本、映画、演劇の終わりに使われ、以下のような役割を果たします:
- 登場人物たちのその後の人生を描く(後日談)
- 物語で提示された伏線の回収
- 読者・観客へのメッセージや教訓の提示
- 続編の布石を打つような内容(次作への橋渡し)
物語が終わった後の“余韻”を残すために、とても重要な構成要素です。
日本語での言い換え
エピローグは、以下のような日本語で言い換えられます:
| 英語 | 日本語の言い換え | 説明 |
|---|---|---|
| エピローグ | 終章 | 本編の終わりに続くまとめの章(本の構成に含まれる) |
| エピローグ | 後書き | 著者が物語の外から語るコメントや補足 |
| エピローグ | 結び | 物語や話の最後を締めくくる部分、終わりの挨拶的な役割 |
| エピローグ | 余話/後日談 | 本編とは異なる時間軸で描かれる“その後”のエピソード |
特に小説や映画では「後日談」がわかりやすい言い換えになります。
エピローグの使い方の例
- 小説の例:
東野圭吾の作品では、事件解決後に描かれる登場人物たちの心情や生活の変化がエピローグとして語られることがあります。 - 映画の例:
映画『ハリー・ポッター』のラストでは、主要キャラクターたちが大人になった後の場面がエピローグとして描かれています。 - 演劇の例:
演劇では、登場人物が観客に直接語りかけながら物語の結末や教訓を伝える“語り”形式のエピローグが使われることもあります。
プロローグとエピローグの違い

プロローグとエピローグはどちらも「物語の本編とは少し離れた部分」に位置していますが、その役割やタイミング、読者への影響は大きく異なります。ここでは、両者の違いを明確にしていきましょう。
時系列における位置の違い
| 用語 | 位置 | 内容の特徴 |
|---|---|---|
| プロローグ | 本編の前 | 物語の導入。世界観、登場人物、背景などを紹介する |
| エピローグ | 本編の後 | 物語の結末やその後の展開、登場人物のその後を描く |
プロローグは、物語が始まる前の出来事や背景を描写するのに対し、エピローグは物語が終わった後の話を語ります。
物語構造における役割の違い
| プロローグ | エピローグ |
|---|---|
| 読者を物語世界に引き込むための“入口” | 読者を現実世界に戻すための“出口” |
| テーマやトーンを提示 | 結末を補足し、余韻やメッセージを強める |
| 謎や伏線をちらつかせることも | 謎の回収や未来への示唆を行う |
たとえるなら、プロローグは「物語の扉を開けるカギ」、エピローグは「その扉を閉じて、読者を送り出す手」です。
読者・観客に与える印象の違い
- プロローグ:
読者の好奇心を刺激し、物語への期待感を高める役割があります。特に序盤の掴みとして重要で、読者が物語を読み進めるかどうかを左右することもあります。 - エピローグ:
物語を振り返り、深い余韻を残す効果があります。登場人物の人生が続いていることを示すことで、読者に“その世界がまだ続いている”という感覚を与えます。
モノローグとは?

モノローグの定義と語源
「モノローグ(Monologue)」とは、登場人物が一人で語るセリフや発言のことを指します。
この言葉はギリシャ語「monos(ひとつ)」+「logos(言葉)」が語源で、直訳すると「一人の語り」となります。つまり、他者との会話ではなく、登場人物が一人で心情や考えを語る場面がモノローグです。
主に使われる分野
モノローグは、以下のようなジャンルでよく使われます:
- 演劇(特に古典・現代演劇)
- 映画やドラマ
- 文学(小説や詩など)
- アニメやゲームのキャラクター語り
とくに舞台では、観客にキャラクターの内面を伝える重要な演出手法として使われています。
モノローグの役割
モノローグには以下のような役割があります:
- 登場人物の内面を明らかにする
- 感情の変化や葛藤を描写する
- 観客(または読者)にだけ明かされる秘密の共有
- 詩的な表現や印象的なセリフによって、作品のテーマを強調する
観客や読者は、モノローグを通じて「登場人物の心の声」に触れることができます。
日本語での言い換え
モノローグの日本語表現としては以下のような言葉が使われます:
| 英語 | 日本語の言い換え | 説明 |
|---|---|---|
| モノローグ | 独白(どくはく) | 舞台や文学で使われる、一人語りの定番訳語 |
| モノローグ | ひとりごと | より日常的で自然な表現(カジュアル) |
| モノローグ | 心の声 | 映像作品でのナレーションなどによく使われる言い換え |
たとえばアニメやドラマでは、登場人物の「心の声」をナレーションとして挿入する形が典型的なモノローグ表現です。
モノローグの使用例
- 演劇の例:
シェイクスピアの『ハムレット』の有名なセリフ「To be, or not to be...」は、主人公の深い葛藤を描くモノローグの代表例です。 - 映画の例:
映画『アメリ』では、主人公アメリの心の声(ナレーション)が多用され、彼女の内面世界を巧みに表現しています。 - 文学の例:
村上春樹の作品では、主人公の内面の独白が長く丁寧に描かれており、読者がその人物に深く共感する仕掛けになっています。
ダイアローグとは?

ダイアローグの定義と語源
「ダイアローグ(Dialogue)」とは、2人以上の人物による対話・会話のことを指します。
語源はギリシャ語「dia(〜を通じて)」+「logos(言葉)」で、「言葉を通じて交流する」という意味があります。つまり、登場人物同士が言葉を交わす場面がダイアローグです。物語における進行やキャラクターの関係性の描写、テーマの展開などに不可欠な要素です。
主に使われる分野
ダイアローグは以下のようなあらゆる表現媒体で使われています:
- 小説や短編小説(セリフ部分)
- 演劇・映画・ドラマ・アニメ
- インタビュー・対談・ラジオ番組
- ゲーム(特にノベルゲームやRPG)
ダイアローグが中心となる作品では、キャラクターの言葉の選び方が性格や背景を表す大事な要素となります。
ダイアローグの役割
- 登場人物同士の関係性や性格を明らかにする
- 物語の進行や状況説明を自然に行う
- 読者や観客に“ライブ感”を与え、臨場感を演出する
- テンポやリズムで読みやすさを調整する役割もある
会話のテンポ、緊張感、ユーモアなどはすべてダイアローグによって生まれます。
日本語での言い換え
| 英語 | 日本語の言い換え | 説明 |
|---|---|---|
| ダイアローグ | 対話 | 正式な場でも使える表現。会話よりやや硬め |
| ダイアローグ | 会話 | 日常的な言い換え。最も一般的 |
| ダイアローグ | セリフのやりとり | 小説や脚本での具体的な形式の言い換え |
| ダイアローグ | 話し合い/やり取り | ビジネスや論文などで使われることもある |
日常では「会話」や「話し合い」、創作の現場では「セリフ」「対話」など文脈に応じた言い換えが使われます。
ダイアローグの使用例
- 小説の例:
村上龍の『限りなく透明に近いブルー』では、リアルで断片的なダイアローグが登場人物の感情の空虚さを表現しています。 - 映画の例:
『ビフォア・サンライズ』シリーズは、登場人物同士の自然なダイアローグが物語の大部分を構成しており、感情の移り変わりを繊細に描いています。 - 演劇の例:
チェーホフの戯曲では、日常的なダイアローグを通して登場人物の無意識の心理がにじみ出る構成が特徴です。
モノローグとダイアローグの違い

モノローグとダイアローグは、どちらも「言葉」を通して物語を構成する重要な要素ですが、話し手の人数・目的・表現効果などに明確な違いがあります。ここでは、その違いを比較しながら詳しく見ていきましょう。
話し手の人数の違い
| 用語 | 話し手 | 対話相手 | 形式 |
|---|---|---|---|
| モノローグ | 1人 | なし(または観客・読者) | 独白・心の声 |
| ダイアローグ | 2人以上 | 相手が存在 | 対話・会話形式 |
モノローグは“自分自身”との対話であり、ダイアローグは“他者”との言葉のやり取りです。
表現の目的の違い
| モノローグ | ダイアローグ |
|---|---|
| 登場人物の内面を深く掘り下げる | 登場人物同士の関係性や状況を描く |
| 感情、葛藤、思想、回想の表現 | 会話を通じた展開、緊張感、リアリティの演出 |
| 観客・読者との間接的な対話(語りかけ) | 登場人物間のやり取りそのものが主軸 |
モノローグは“静的な思考”の描写に向いており、ダイアローグは“動的な状況”を描くために効果的です。
舞台や映像作品での使い方の違い
| モノローグの特徴 | ダイアローグの特徴 |
|---|---|
| カメラが1人の表情をじっくり捉える | カメラが視点を切り替えながらやり取りを追う |
| 照明や音楽と組み合わせて、感情を強調 | セリフのリズムや間合いでリアルな空気感を作る |
| 詩的・象徴的な表現になりやすい | 日常的・リアルな言葉が使われやすい |
特に舞台や映画では、モノローグは印象的な演出の“見せ場”になりやすく、ダイアローグは作品全体の“骨格”を支える会話として構成されます。
例を通して理解する
- モノローグの例(舞台)
「私はなぜここにいるのだろう…。あの時、あの選択をしなければ…」
→ 1人での内省的な語り。観客にだけ心情を打ち明けている。 - ダイアローグの例(小説)
A「昨日のこと、覚えてる?」
B「ええ。でも言いたくないの」
→ 会話の中で緊張や距離感が描かれる。
創作における活用のポイント
- モノローグ:
登場人物の個性や内面を深く描きたいときに有効。詩的な文章表現と相性が良い。 - ダイアローグ:
テンポよく物語を進めたいとき、人間関係の描写や緊張感を演出したいときに不可欠。
どちらもバランスよく使うことで、物語に厚みとリアリティが生まれます。
まとめ

ここまで、以下の4つの言葉について詳しく解説してきました:
- プロローグ(Prologue)
- エピローグ(Epilogue)
- モノローグ(Monologue)
- ダイアローグ(Dialogue)
それぞれの意味、使われる場面、日本語での言い換え、そしてそれらの違いを整理してみましょう。
用語の比較一覧表
| 用語 | 意味 | 日本語での言い換え | 位置・特徴 |
|---|---|---|---|
| プロローグ | 物語の導入 | 序章・序文・導入部 | 本編の前。読者を引き込む |
| エピローグ | 物語の締めくくり | 終章・後書き・結び・後日談 | 本編の後。余韻やまとめ |
| モノローグ | 一人の語り | 独白・ひとりごと・心の声 | 内面の表現・観客への語り |
| ダイアローグ | 複数人の対話 | 会話・対話・やり取り | 登場人物同士のやりとり |
実生活や創作での活かし方
- 創作をしている方へ:
プロローグやエピローグを意識して物語の「入り」と「締め」を整えることで、作品全体の完成度がグッと上がります。
また、モノローグを使って登場人物の心理描写を深めたり、ダイアローグで関係性やテンポを演出することができます。 - 読者・観客として:
これらの要素に注目することで、物語の構造や演出意図をより深く味わえるようになります。
特に「なぜこの作品はこんな始まり・終わり方をするのか?」という視点を持つと、作品への理解が一段と深まります。
さいごに
物語は「語られる内容」だけでなく、「どう語られるか」にも大きな意味があります。
プロローグとエピローグは物語を囲むフレームとして、モノローグとダイアローグはその中身を彩る言葉の手段として、いずれも欠かせない存在です。
ぜひ、これらの用語を正しく理解して、読書や創作、鑑賞の楽しみをさらに深めてみてください。




