「予測」「予想」「推測」の違い【70例文】使い分けガイド

日本語には似たような意味を持つ言葉が多くあり、その中でも「予測」「予想」「推測」は非常に混同されやすい言葉です。いずれも「まだ起きていないこと」「明らかでないこと」を考えるという点で共通していますが、実際にはニュアンスや使い方に明確な違いがあります。
例えば、天気の変化に対しては「天気を予測する」と言いますが、「明日の試合結果」を考えるときは「結果を予想する」となります。また、人の気持ちや話の真意を考えるときには「推測する」という表現を使うことが多いです。
このように、場面ごとに適切な言葉を選ぶことは、自然な日本語表現を身につけるうえでとても重要です。特に、ビジネス文書、学術的な文章、日常会話のいずれにおいても、言葉の選び方一つで伝わり方が大きく変わることがあります。
本記事では、「予測」「予想」「推測」の違いを明確にし、それぞれの使い方を70個の例文とともに詳しく解説していきます。言葉の意味、使い分け、類語との違いまで丁寧に解説するので、日本語の語感を深めたい方、文章表現を磨きたい方にとっても役立つ内容となっています。
目次
「予測」「予想」「推測」の違い

「予測」「予想」「推測」はいずれも「まだ起きていないこと」「はっきりしていないこと」を考える行為ですが、それぞれの意味・使い方・ニュアンスには明確な違いがあります。違いをわかりやすく理解するために、以下の比較表をご覧ください。
| 用語 | 主な対象 | 根拠の性質 | 客観性 | 主な使用場面 | ニュアンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 予測 | 未来 | データ・傾向 | 高い | 天気予報、経済予測など | 数値や事実に基づいた論理的な見通し |
| 予想 | 未来 | 経験・直感 | 中程度 | 試合結果、試験の範囲など | 感覚や印象による見込み |
| 推測 | 過去・現在 | 状況・間接的な手がかり | 低め | 心理状態、原因分析など | 不確かな情報からの仮説的な推定 |
「予測」の意味

「予測(よそく)」とは、過去のデータや現在の状況に基づいて、将来の出来事を見積もることを意味します。多くの場合、客観的な根拠や情報をもとにして、科学的・論理的に未来を見通すことに使われます。
たとえば、気象庁が発表する「天気予報」は、過去の気象データや現在の気象状況をもとに、未来の天気を「予測」しています。また、企業が行う「売上予測」や「需要予測」も、過去の売上データや市場動向に基づいて数値的に将来を見積もる行為です。
このように、「予測」は単なる勘や印象ではなく、ある程度の客観的根拠に基づいた未来予想である点が特徴です。
「予測」は以下のような場面で使われます:
- 天気、災害、交通、株価、経済など、数値や傾向が存在する分野
- データ分析やAI、統計などを使った予想行為
- ビジネスや研究の場面での論理的な将来推定
ポイントとして、「予測」は主に未来のことに対して使われ、かつ比較的客観的な視点が求められる言葉です。
「予想」の意味

「予想(よそう)」とは、これから起こる出来事や結果について、ある程度の根拠や経験をもとに見通しを立てることを意味します。未来のことに対する見込みや推定という点では「予測」と似ていますが、より主観的な印象や感覚が含まれるのが特徴です。
例えば、「明日は雨が降るだろう」というときに、天気予報を根拠にした場合は「予測」となりますが、自分の勘や空模様を見て「たぶん降りそうだな」と考える場合は「予想」です。
また、「彼が勝つと予想していた」や「この映画はヒットすると予想される」のように、スポーツやエンタメ、選挙結果など、結果が未知のものについて自分なりの見通しを立てる場面でよく使われます。
「予想」は次のような場面で使われることが多いです:
- 試験の出題範囲や結果についての見通し
- スポーツの試合結果や競馬、株価の動きに対する読み
- 日常会話での軽い予測(例:「今日は混みそうだね」)
重要なポイントは、「予想」は主に未来を対象としており、主観的・経験的な見解が含まれているということです。
「推測」の意味

「推測(すいそく)」とは、はっきりとした証拠がない状況で、わずかな手がかりや状況から物事を考え出すことを意味します。直感や主観をもとにするという点では「予想」と似ていますが、「推測」はより論理的な思考過程を重視する言葉です。
特徴的なのは、「推測」は過去や現在の出来事について使われることが多い点です。たとえば、次のような場面です:
- 誰が犯人かを推理する場面(例:「現場の状況から犯人を推測する」)
- 誰かの気持ちを考える場面(例:「彼の様子から怒っていると推測した」)
- 原因や背景を考える場面(例:「事故の原因を推測する」)
また、「根拠はないが、おそらくこうだろう」と考えるときにも使われますが、感覚よりも観察・分析・論理的思考に基づく判断を含んでいる点が重要です。
「推測」は次のような場面でよく使われます:
- 誰かの考えや気持ちを読み取るとき
- 起きた出来事の原因を論理的に考えるとき
- 説明の不足を補うために状況から考えるとき
つまり、「推測」は明確な情報が不足している中で、少ない手がかりから考えを導く行為であり、必ずしも未来に限定された表現ではありません。
「予測」「予想」「推測」の使い分け

- 対象の時間軸
- 「予測」「予想」は主に未来を対象としますが、
「推測」は過去や現在の出来事にも使われます。
- 「予測」「予想」は主に未来を対象としますが、
- 根拠の性質と客観性
- 「予測」は客観的データに基づくことが多く、論理性・客観性が高い。
- 「予想」はやや主観的で、経験や印象を元にした予知。
- 「推測」は最も主観的で、不確実な情報からの想像という側面が強いです。
- 使用される場面
- 「予測」:ビジネス、学術、気象、マーケティングなど、分析や計画が必要な分野。
- 「予想」:日常生活、スポーツ、ニュース、試験など、一般的な見込みを立てる場面。
- 「推測」:対人関係や調査、物語理解など、情報が不足している状況で考える場面。
このように、似た意味を持つ3つの言葉でも、文脈や意図に応じて正しく使い分けることが大切です。
「予測」の使い方【例文20】

「予測」は、将来の出来事や状況を、データや傾向に基づいて見積もる場合に使われます。特にビジネス、経済、科学、天気など、客観的な根拠をもとにした見通しを表現する際に非常に重宝される語です。
以下に、さまざまな分野での「予測」の例文を20個紹介します。
ビジネス・経済の文脈での予測
- 来年の売上高は前年比10%増と予測されている。
- インフレ率の上昇が予測されるため、消費者行動に影響が出るだろう。
- 市場の拡大により、競合他社の参入が予測される。
- 為替レートの変動は今後数ヶ月でさらに激しくなると予測される。
- AIの導入が進めば、人件費の削減が予測される。
科学・技術の分野での予測
- 次の火山噴火は数年以内に起こると予測されている。
- 最新の研究により、地球温暖化の影響が今後50年間で深刻になると予測された。
- ウイルスの感染拡大は、今後さらに加速すると予測されている。
- 太陽フレアの影響による通信障害が予測されている。
- ロボット技術の進化により、2030年には自動運転が一般化すると予測されている。
天気・災害の予測
- 明日の午後には激しい雨が予測されています。
- 台風の進路が西にそれると予測されている。
- 地震の発生確率が今後30年で70%と予測された地域がある。
- 大雪による交通機関の乱れが予測されるため、注意が必要です。
- 春の花粉の飛散量は、例年より多くなると予測されています。
日常生活や社会的な場面での予測
- ゴールデンウィーク中は高速道路の渋滞が予測されている。
- 今回の映画は大ヒットが予測されている。
- 少子高齢化が進むことで、労働力不足が深刻化すると予測されている。
- 年末にかけて、オンラインショッピングの需要が増加すると予測されています。
- 今後のエネルギー価格の高騰が生活に与える影響が予測されている。
これらの例文からわかるように、「予測」は事実や傾向に基づいた合理的な見通しを述べるときに使われます。「~と予測される」「~が予測されている」「~が予測された」などの形で、丁寧な文章でも頻繁に用いられます。
「予想」の使い方【例文20】

「予想」は、将来の出来事について、経験や勘、状況判断などを元に見通しを立てることを表します。客観的なデータが必ずしも必要ではなく、日常会話からニュース、エンタメまで幅広く使われる語です。
以下に、「予想」の具体的な使い方を示す例文を20個紹介します。
日常生活・会話での予想
- 今日は雨が降りそうだと予想して、傘を持ってきた。
- 連休明けは道路が混雑すると予想して、早めに出発した。
- 明日のランチは混雑が予想されるから、予約しておいた。
- このアプリはヒットするだろうと予想していた。
- 試験は思ったより難しくなると予想して、しっかり準備した。
スポーツ・イベントに関する予想
- 日本が決勝に進むと予想している人が多い。
- この試合は引き分けになると予想されている。
- 優勝候補のチームが敗退するとは誰も予想していなかった。
- MVPは彼だと多くのメディアが予想している。
- 大会の視聴率は過去最高になると予想されている。
ニュース・社会情勢に関する予想
- 次の選挙では現職が優勢と予想されている。
- 景気回復には時間がかかると予想されている。
- ガソリン価格の高騰はしばらく続くと予想されている。
- 来年度の就職率は改善すると予想されている。
- 人口減少により地方都市の衰退が進むと予想されている。
エンタメ・趣味での予想
- あの映画はアカデミー賞を取ると予想している。
- 次回のストーリー展開は誰もが予想していなかった展開だった。
- このゲームの続編は来年発売されると予想している。
- 人気俳優の結婚が近いと予想する記事が出ている。
- 年末の音楽番組では彼女が大トリになると予想されている。
「予想」は、「~と予想する」「~と予想されている」「予想に反して」など、主観と客観の中間に位置する語です。多くのケースで「~だろう」「~かもしれない」といった推測的な表現と組み合わさって使われることが多いです。
「推測」の使い方【例文20】

「推測」は、不完全な情報や状況から、論理的にある結論を導き出す行為を表す言葉です。確実ではないが、何らかの手がかりを元に「こうだろう」と考えるときに使われます。
特に、過去や現在の状況、人の心理、物事の原因や背景を推し量る場面でよく使われます。
以下に「推測」の使い方を示す具体的な例文を20個紹介します。
人の気持ちや行動に関する推測
- 彼の表情から、かなり疲れていると推測できる。
- 無言だったことから、怒っていたのではないかと推測した。
- メールの返信がないのは、忙しいのだと推測される。
- 彼女の行動から、本当は賛成していなかったと推測できる。
- 子どもの様子から、何か不安を感じていると推測された。
原因や状況の分析としての推測
- 火災の原因は、電気系統のトラブルだと推測されている。
- 故障の理由は過剰な使用によるものと推測される。
- 事故の直前に大きな音がしたと証言されており、タイヤの破裂が原因と推測されている。
- 患者の症状から、新しいウイルスの感染と推測される。
- この遺跡は、1000年以上前に建てられたと推測されている。
不在の事実や背景の補完としての推測
- その言い回しから、彼が本心を隠していると推測した。
- 手紙の内容から、彼はこの街に長く住んでいたと推測される。
- データの欠落部分から、本来の数値はもっと高かったと推測される。
- 声のトーンから、彼女は興奮していたと推測した。
- 書き残されたメモから、犯人の行動が推測される。
学術・研究的な推測
- 地層の状態から、この地域がかつて海だったと推測される。
- 文献の記述から、当時の文化的背景が推測できる。
- 統計の偏りから、調査方法に問題があったと推測された。
- 歴史的記録の断片から、王朝の滅亡時期が推測されている。
- DNAの一致率から、2人は親子関係にあると推測された。
「推測」は、「~と推測する」「~と推測される」「~が推測できる」などの形で使われ、断定ではなく仮定や分析に基づく表現として使われます。特に、根拠はあるが確証がないときに使うのが自然です。
間違えやすい使い方【例文10】
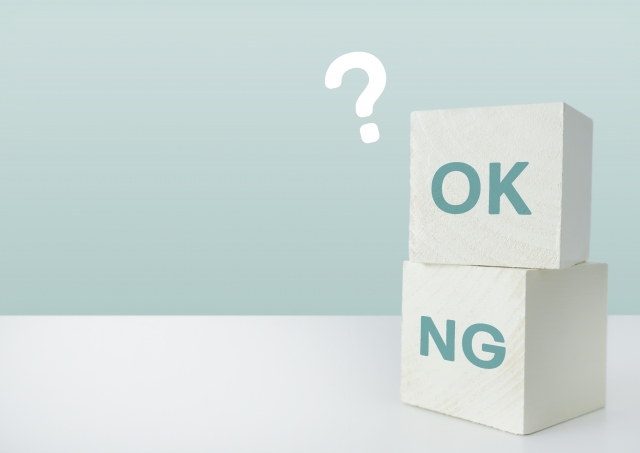
「予測」「予想」「推測」は似た意味を持つため、使い方を混同しやすい言葉です。ここでは、実際にありがちな誤用例を取り上げ、どの言葉を使うのが適切かを、正しい例とセットで紹介します。
①誤:この事故の原因は予測できない。
✅ 正:この事故の原因は推測できない。
解説:原因は過去に起こったことなので、「予測」(未来)ではなく「推測」(過去・現在)を使うのが正しい。
②誤:来年の売上は予想に基づいて決めた。
✅ 正:来年の売上は予測に基づいて決めた。
解説:「予想」は主観的な見込みに近いため、ビジネス文脈では客観性の高い「予測」が適切。
③誤:彼が怒っている理由を予測した。
✅ 正:彼が怒っている理由を推測した。
解説:人の気持ちや背景を考えるときは「推測」を使う。
④誤:午後は雨になると推測しています。
✅ 正:午後は雨になると予測しています。
解説:未来の天候はデータに基づくので「予測」が適切。
⑤誤:この映画はヒットしそうだと推測されている。
✅ 正:この映画はヒットしそうだと予想されている。
解説:ヒットするかどうかは未来のことで、感覚的な見込みを表すには「予想」が適している。
⑥誤:突然の大雨は予想できなかった。
✅ 正:突然の大雨は予測できなかった。
解説:天気は客観的なデータから判断されるため、「予測」が自然。
⑦誤:彼の意図は予想もできなかった。
✅ 正:彼の意図は推測もできなかった。
解説:人の内面や気持ちについて考える場合は「推測」を使用。
⑧誤:将来の景気動向を推測するのは難しい。
✅ 正:将来の景気動向を予測するのは難しい。
解説:経済の未来を考える場合は、客観性のある「予測」が適切。
⑨誤:彼が優勝すると推測していた。
✅ 正:彼が優勝すると予想していた。
解説:未来の結果を考えているので、「予想」が正しい。
⑩誤:会議の内容は予測できますか?
✅ 正:会議の内容は推測できますか?
解説:すでに終わっている会議の内容について話しているなら、「推測」が正解。
このように、「予測」「予想」「推測」は対象(未来/現在/過去)や根拠の性質(客観的/主観的)によって使い分ける必要があります。正しい使い方を身につけることで、より自然で的確な日本語表現が可能になります。
「予測」の類語・英語

「予測」の類語
| 類語 | 意味の違い(簡単に) | 使用例 |
|---|---|---|
| 見通し | 今後の流れや状況の予想、特に全体的な流れに注目 | 経済の見通しは依然として不透明だ。 |
| 展望 | 将来の状態や見込みを広い視野で見ること | 今後の事業展望について説明する。 |
| 予見 | 将来を前もって見抜くこと(やや文学的) | 彼はリスクを予見していた。 |
| 予知 | 災害や現象などを事前に知ること(神秘的な印象) | 地震の予知はまだ難しいとされている。 |
「予測」の英語表現
| 英語 | ニュアンス・使い方 | 使用例(英語) | 使用例(和訳) |
|---|---|---|---|
| prediction | 一般的な予測。感覚的でも科学的でも使える | The prediction for tomorrow is rain. | 明日の予報は雨です。 |
| forecast | 主に天気や経済など、データに基づく予測 | The sales forecast looks positive. | 売上予測は好調だ。 |
| projection | 数値や傾向に基づいた計画的な予測(ビジネス寄り) | Our profit projection shows growth. | 利益予測では成長が見込まれている。 |
「予測」は、文脈によって「prediction」「forecast」「projection」などに言い換えることができます。科学・ビジネス・天気予報などの分野では英語でも語が使い分けられているため、場面に応じた選択が重要です。
「予想」の類語・英語

「予想」の類語
| 類語 | 意味の違い(簡単に) | 使用例 |
|---|---|---|
| 見込み | ある程度の根拠に基づいた予想(実現性が高い) | 来月の完成は見込みが立っている。 |
| 期待 | 良い結果を予想して待つこと | 彼に大きな期待が寄せられている。 |
| 想定 | 仮にこうなると考えること(計画・リスク管理向き) | 最悪のケースを想定して準備を進める。 |
| 推定 | 推測と近く、数値や状況から判断すること | 損害額は数百万円と推定されている。 |
「予想」の英語表現
| 英語 | ニュアンス・使い方 | 使用例(英語) | 使用例(和訳) |
|---|---|---|---|
| expectation | 一般的な期待や予想。希望も含むことが多い | My expectation was that he’d win. | 彼が勝つと予想していた。 |
| guess | 勘や直感による予想。根拠が薄い | My guess is that it will rain tomorrow. | 明日は雨だろうと思う。 |
| assumption | 前提としての予想・想定 | We made the assumption that demand would grow. | 需要が伸びるという前提で計画した。 |
「予想」は、日常会話からビジネス、エンタメまで幅広く使える言葉です。英語では「expectation」が最も近いですが、カジュアルなら「guess」、ビジネスなら「assumption」も使い分けます。
「推測」の類語・英語
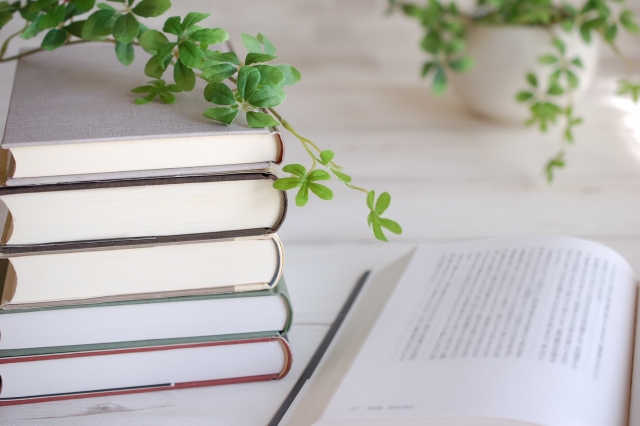
「推測」の類語
| 類語 | 意味の違い(簡単に) | 使用例 |
|---|---|---|
| 推論 | 論理的な根拠に基づいて導く考え | 状況からの推論により、彼が犯人だと判明した。 |
| 憶測 | 根拠が薄く、勝手な想像に近い | 憶測だけで判断するのは危険だ。 |
| 仮定 | 「もし~なら」という前提を置いて考えること | 仮定に基づいて実験を行った。 |
| 判断 | 情報をもとに結論を下す行為 | 状況を総合して判断した。 |
「推測」の英語表現
| 英語 | ニュアンス・使い方 | 使用例(英語) | 使用例(和訳) |
|---|---|---|---|
| assumption | 仮定・前提としての推測 | The assumption was that she knew the plan. | 彼女が計画を知っていたという仮定だった。 |
| inference | 論理的な推論(科学的・分析的な場面で多い) | The inference is based on the available data. | その推論は利用可能なデータに基づいている。 |
| speculation | 十分な根拠のない推測(やや否定的なニュアンス) | His speculation about the result was wrong. | 彼の結果に関する推測は外れていた。 |
「推測」は、確実ではないが何かを推し量る場面で使う言葉です。英語では、根拠の強さに応じて「assumption(仮定)」「inference(推論)」「speculation(憶測)」を使い分けます。
よくある質問(Q&A)

ここでは、「予測」「予想」「推測」に関してよく寄せられる疑問について、簡潔にお答えします。
Q1. 「想定」と「予測」「予想」「推測」の違いは?
A:
「想定(そうてい)」は、起こりうる状況をあらかじめ考えておくことです。
実際に起きるかどうかは別として、「こうなるかもしれない」という前提条件として考えるときに使います。
- 例:災害時を想定して訓練を行う(実際に起きるかどうかはわからない)
- 「予測」:将来の出来事をデータなどから論理的に判断する
- 「予想」:将来の出来事を感覚や経験から見通す
- 「推測」:今起きている、あるいは過去のことを手がかりから考える
Q2. 「仮定」や「推論」と「推測」はどう違うの?
A:
- 仮定:もし~なら、と前提条件を置く考え方。論理的な議論や実験でよく使います。
- 推論:複数の事実や前提を元に論理的に導き出す行為です。科学的、学術的に使われます。
- 推測:必ずしも論理的とは限らず、手がかりや直感で考えることも含みます。
推測は「仮定」や「推論」ほど厳密ではなく、日常的な思考に使われる柔らかい表現です。
Q3. 英語に訳すとき、どう使い分ければいい?
A:
- 「予測」→ forecast / projection / prediction(ビジネス・科学的な見通し)
- 「予想」→ expectation / guess(感覚的、一般的な予見)
- 「推測」→ assumption / inference / speculation(根拠の強さに応じて)
ポイント:
訳語は文脈に応じて変えるのが自然です。例えば、天気なら「forecast」、人の気持ちなら「assumption」が適切です。
Q4. どれを使えばいいか迷ったら?
A:
まずは次の3つのポイントで判断してください:
- 未来のことか?過去・現在のことか?
→ 未来 →「予測」または「予想」/過去・現在 →「推測」 - 根拠は客観的なデータか?主観的な感覚か?
→ データ →「予測」/ 感覚 →「予想」/ 不確かな手がかり →「推測」 - 目的は?(見通し・仮説・前提)
→ 見通し →「予測」「予想」/ 仮説・分析 →「推測」「仮定」「推論」
まとめ
「予測」「予想」「推測」は、いずれもまだ確定していない物事について考える行為を表す言葉ですが、それぞれの意味と使い方には明確な違いがあります。
「予測」は、過去のデータや傾向に基づいて未来を客観的に見通す際に使われ、ビジネスや科学などの分野で頻出します。
「予想」は、経験や勘など主観的な要素から未来を見込みとして考えるときに使われ、日常的な場面でよく登場します。
「推測」は、手がかりや状況から過去や現在の事実を論理的に考えるときに使われ、確実ではない情報から仮定を立てる場面に適しています。
この3語は、場面や文脈によって適切に使い分けることで、言葉の正確性と説得力が高まり、誤解を避けられる表現が可能になります。特に、書き言葉やビジネスの現場では、微妙なニュアンスの違いを理解しておくことが重要です。この記事で紹介した使い方や例文を参考に、ぜひ実践で活かしてみてください。




