「間違いやすい」「間違えやすい」どっちが正しい?【50例文】

日本語には、似たような表現でも微妙な違いがある言葉が多く存在します。その中でも、特によく混同されるのが「間違いやすい」と「間違えやすい」です。
この2つの表現は、どちらも「ミスが起こりやすい」というニュアンスを持っているため、一見すると同じように見えます。しかし、実は文法的な構造やニュアンスに違いがあるため、場面によって使い分ける必要があります。
本記事では、「間違いやすい」と「間違えやすい」の正しい意味と使い方を徹底解説します。また、それぞれの表現を使った例文も50個紹介しますので、読者の皆さんが実際の文章や会話で自信を持って使い分けられるようになることを目指しています。
日本語を正確に、そして自然に使うために、ぜひ最後までお読みください。
目次
「間違いやすい」と「間違えやすい」どっちが正しい?

まず結論からお伝えすると、「間違いやすい」と「間違えやすい」はどちらも文法的に間違いではありません。
- 「間違いやすい」は、『間違い(名詞)』+『やすい(補助形容詞)』で構成されています。
- 「間違えやすい」は、『間違える(動詞)』+『やすい』で構成されています。
どちらも国語辞典に掲載されており、意味としても「ミスしやすい」「誤解しやすい」といった意味で使われています。
「間違いやすい」の意味

「間違いやすい」は、「間違い」という名詞と、「やすい」という補助形容詞が組み合わさった言葉です。文法的には、「名詞+やすい」の形になります。
- 間違い(名詞) + やすい(補助形容詞)
この形は、他にも「誤解しやすい」「混乱しやすい」などの表現と似ていますが、「間違いやすい」は動詞ではなく、名詞を用いている点が特徴です。
意味
「間違いやすい」は、ある対象や状況において、間違いが発生しやすいことを表します。つまり、「誰が」間違えるかに重点を置くのではなく、「どんなことが」間違いの原因になりやすいか、ということに焦点を当てた表現です。
「間違えやすい」の意味

「間違えやすい」は、「間違える」という動詞と、「やすい」という補助形容詞が組み合わさった言葉です。文法的には、「動詞の連用形+やすい」の形になります。
- 間違える(動詞) → 間違え(連用形) + やすい(補助形容詞)
この形は、「食べやすい」「壊れやすい」「信じやすい」などと同じ構造で、日本語では一般的な言い回しです。
意味
「間違えやすい」は、ある人や状況において、動作として“間違える”ことが起こりやすいという意味です。つまり、「誰が」「何を」間違えるのかという主語や対象が明確になる傾向があります。
「間違いやすい」と「間違えやすい」の違い
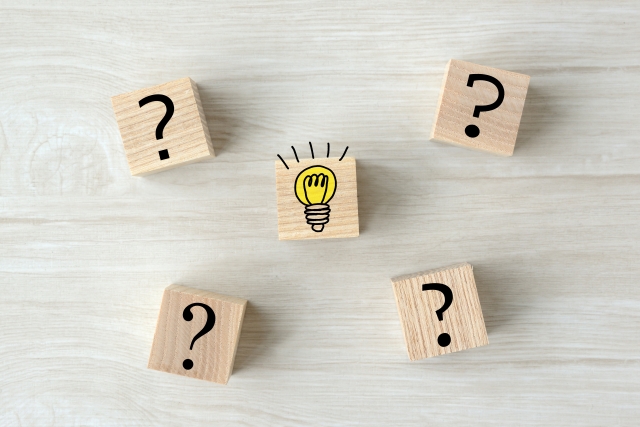
「間違いやすい」と「間違えやすい」は、意味としては非常に近いですが、文法的な構造やニュアンス、使用される文脈に違いがあります。ここでは、その違いを分かりやすく表にまとめて解説します。
| 比較項目 | 間違いやすい | 間違えやすい |
|---|---|---|
| 品詞構成 | 名詞「間違い」+補助形容詞「やすい」 | 動詞「間違える」+補助形容詞「やすい」 |
| 文法的な形 | 名詞+やすい | 動詞連用形+やすい |
| 焦点の置き方 | 状況・内容に焦点 | 動作・行為に焦点 |
| 使用される場面 | 教材・マニュアル・説明書・案内など | 会話・エッセイ・ブログ・日常表現など |
| 主語の必要性 | 不要(一般的な状況を述べる) | 必要(誰が間違えるかが焦点) |
| 例:自然な文 | この単語は間違いやすい。 | 子どもはこの問題を間違えやすい。 |
| フォーマル度 | ややフォーマル | ややカジュアル |
| 使用頻度 | 高い | やや少ない |
「間違いやすい」と「間違えやすい」の使い分け

「間違いやすい」と「間違えやすい」は、どちらも「ミスが起きやすい」という意味合いを持っていますが、使い分けのポイントを押さえることで、より自然で伝わりやすい文章になります。ここでは、具体的な使い分けのコツと判断基準を解説します。
使い分けの基本ルール
| 使いたい内容 | 適した表現 | 解説 |
|---|---|---|
| 状況や内容がミスの原因である場合 | 間違いやすい | 主語なしでも自然。名詞を修飾する表現と相性が良い。 |
| 人が何かをミスする可能性がある場合 | 間違えやすい | 主語が必要。「誰が」「何を」間違えるかを示す。 |
使い分けのコツ①:修飾する語を確認する
✅ 「間違いやすい」が自然な例:
- 間違いやすい漢字
- 間違いやすい表現
- 間違いやすいポイント
上記のように、「何が」間違いの原因になっているのかを表現したい場合は、「間違いやすい」が適切です。
✅ 「間違えやすい」が自然な例:
- 子どもはこの文法を間違えやすい。
- 初心者は操作を間違えやすい。
このように、主語(人)+対象(何を)+「間違えやすい」という構文が基本になります。
使い分けのコツ②:文体・トーンを意識する
- フォーマルな文書やビジネス文書では「間違いやすい」が無難
⇒ 多くの教育機関、官公庁、企業が使っている実績あり。 - カジュアルな文章、口語的な表現では「間違えやすい」も自然
⇒ ブログや会話文、エッセイなどでは違和感が少ない。
使い分けのコツ③:どちらでも通じるが、印象が変わる場合も
たとえば、
- 「この手順は間違いやすい」
→ 手順自体に問題やわかりにくさがある印象。 - 「この手順は間違えやすい」
→ 手順に関わる人の理解や操作に不安がある印象。
どちらも意味は通じますが、焦点の位置が異なるため、伝えたいニュアンスに合わせて選ぶのがポイントです。
判断に迷ったときは?
迷ったときは、以下を基準にしてみてください。
- 「〇〇な表現」や「〇〇な言葉」といった名詞を修飾するなら → 間違いやすい
- 「誰が何を間違える」という動作を表現したいなら → 間違えやすい
「間違いやすい」の使い方【例文20】

「間違いやすい」は、主に「言葉」「表現」「手順」「ルール」など、人が誤解したり、ミスしやすい内容や状況に対して使われる表現です。
ここでは、ビジネス、教育、日常生活など、さまざまなシーンにおける自然な使い方を例文とともに紹介します。
【学習編】
- この漢字は読み方が間違いやすいので注意しましょう。
- 英語の前置詞は意味が似ていて間違いやすい。
- 日本史の年号は数字が近くて間違いやすいですね。
- 数学のこの公式は使い方が間違いやすいです。
- 理科の用語は似た名前が多くて間違いやすい。
【ビジネス編】
- 契約書のこの条文は解釈が間違いやすいため、確認が必要です。
- 入力フォームの順番が複雑で間違いやすいです。
- メールの宛名が複数ある場合、敬称が間違いやすいので気をつけましょう。
- 経費精算書の記入ルールが間違いやすいです。
- 商品の型番が似ているため、発注時に間違いやすいです。
【日常生活編】
- 駅名が似ていて間違いやすいから、路線図で確認しよう。
- アプリの設定画面が複雑で間違いやすい。
- 曜日の並びが祝日と重なると間違いやすいです。
- この薬の用法は、飲むタイミングが間違いやすい。
- 似たような商品名が多くて間違いやすいです。
【その他】
- 敬語の使い方は初めのうちは間違いやすいです。
- ビジネスメールで使う表現は間違いやすいものが多い。
- 似た発音の単語は会話中に間違いやすい。
- 文化や習慣の違いで礼儀作法が間違いやすいこともある。
- 初対面の場では名前の呼び方が間違いやすいです。
このように、「間違いやすい」は内容や状況に焦点を当てた表現で、名詞との組み合わせが非常に自然です。特にフォーマルな文脈では、違和感なく使える万能な言い回しです。
「間違えやすい」の使い方【例文20】
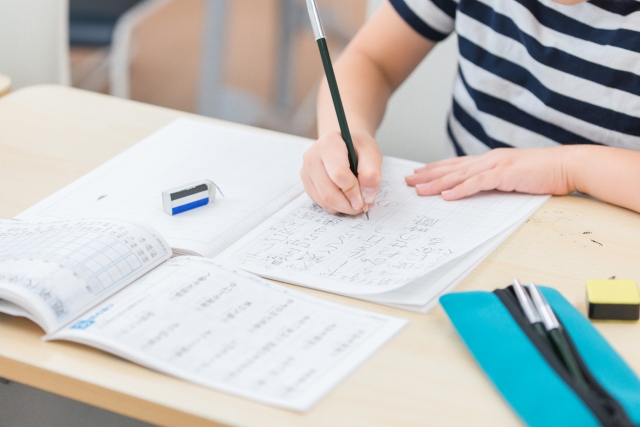
「間違えやすい」は、動詞「間違える」に由来するため、誰が何を間違えるのかという行為・動作に焦点を当てる表現です。主語(人)と目的語(対象)をセットで使うと、自然な文になります。
以下では、ビジネス・学習・日常会話などのシーン別に具体的な例文をご紹介します。
【学習編】
- 学生はこの英文の構文を間違えやすいです。
- 初心者は「than」と「that」を間違えやすい。
- 子どもは漢字の書き順を間違えやすい傾向があります。
- 外国人は日本語の助詞を間違えやすい。
- 初学者は因数分解のステップを間違えやすいですね。
【ビジネス編】
- 新入社員は請求書の提出先を間違えやすいです。
- 部署名の略称を間違えやすいので、正式名称で記入してください。
- 見積書の税率計算は間違えやすいポイントの一つです。
- 社外メールの敬称を間違えやすい社員が多いです。
- 担当者名を間違えやすい案件がいくつかあります。
【日常生活編】
- 子どもは曜日の順番を間違えやすいです。
- 新しいスマホの操作方法を間違えやすいですね。
- 自転車のブレーキ位置を間違えやすい子どももいます。
- 高齢者は服薬のタイミングを間違えやすいため、リマインダーが必要です。
- 同じ建物内の部屋番号を間違えやすいです。
【その他】
- 名前の読み方を間違えやすいので、事前に確認しておくと良いです。
- 結婚式の祝儀袋の書き方を間違えやすい人が多いです。
- 敬語の使い方を間違えやすい新社会人が増えています。
- 電話番号の桁数を間違えやすいので、再確認が大事です。
- 慣れていないと交通系ICカードの使い方を間違えやすいです。
このように、「間違えやすい」は人の行動や動作に重きを置いた表現で、話し手の視点が明確な場面に適しています。主語や対象がはっきりしている場合に自然に使える言い回しです。
迷った時の使い方【例文10】

「間違いやすい」と「間違えやすい」は、どちらを使っても大きな誤解を生むことは少ないですが、文脈によってより自然な表現があります。この章では、どちらの表現がより適切か判断が迷いやすい例文を10個紹介し、それぞれに自然な使い方とその理由を添えて解説します。
【例文1】
このマニュアルは間違えやすい/間違いやすい部分が多い。
推奨:間違いやすい
理由: マニュアルという「物」に焦点があるため、名詞「間違い」に基づく表現が自然です。
【例文2】
新入社員は敬語の使い方を間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違えやすい
理由: 主語(新入社員)が明確で、行動(敬語を使う)に焦点があるため、動詞「間違える」に基づく表現が適しています。
【例文3】
この手順は間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違いやすい
理由: 手順自体が間違いの原因になっているという意味で、名詞ベースの表現が自然です。
【例文4】
初心者はこの設定を間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違えやすい
理由: 「初心者」が主語で、「設定を変更する」という動作を指しているため、動詞に基づいた表現が適切です。
【例文5】
この言い回しは間違えやすい/間違いやすいので、注意してください。
推奨:間違いやすい
理由: 「言い回し」という表現内容自体が誤解の原因であるため、名詞+やすいの形が自然です。
【例文6】
学生はこの問題を間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違えやすい
理由: 主語が学生であり、実際に問題を解く行動に焦点があるので、動詞ベースの「間違えやすい」が合っています。
【例文7】
このFAQは間違えやすい/間違いやすい質問が多い。
推奨:間違いやすい
理由: 内容や構成に焦点を当てているため、「間違いやすい」が自然です。
【例文8】
子どもは曜日の順番を間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違えやすい
理由: 子どもという主語が明確で、「順番を覚える」という行動に注目しているため。
【例文9】
この案内表示は間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違いやすい
理由: 案内表示という「もの」が混乱を引き起こしやすいという状況を表しており、名詞に基づく表現が適切です。
【例文10】
外国人旅行者は乗り換え案内を間違えやすい/間違いやすい。
推奨:間違えやすい
理由: 「外国人旅行者」が主語で、乗り換えという行動に焦点があるため、動詞に基づく表現が適しています。
このように、使い分けに迷うときは「誰が」「何を」という文の構造を意識しながら、対象(名詞)に焦点があるか、行動(動詞)に焦点があるかを判断基準にすることで、より自然な日本語を使い分けることができます。
よくある質問

ここでは、「間違いやすい」と「間違えやすい」に関して、多くの人が疑問に思いやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
Q1. 「間違えやすい」は誤用ではないのですか?
A. 誤用ではありません。
「間違えやすい」は、「間違える(動詞)」+「やすい(補助形容詞)」の正しい文法構造であり、日本語として成立しています。ただし、「間違いやすい」に比べるとやや口語的で、フォーマルな場面では控えられることがあるというだけです。
Q2. ビジネスメールや公式文書ではどちらを使うべき?
A. 一般的には「間違いやすい」が推奨されます。
「間違いやすい」は名詞「間違い」を用いた安定した表現であり、フォーマルな文体に馴染みます。一方の「間違えやすい」はカジュアルな印象を与える場合があるため、公的な文書やビジネスシーンでは避けられる傾向があります。
Q3. 「間違いやすい言葉」と「間違えやすい言葉」の違いは?
A. 焦点の置き方に違いがあります。
- 「間違いやすい言葉」は、その言葉自体が間違いの原因になりやすいことを意味します。
- 「間違えやすい言葉」は、誰かがその言葉を間違えて使ってしまいやすいという「動作」に焦点があります。
とはいえ、どちらも意味が通じるため、大きな誤解が生じることはありません。
Q4. ネイティブの日本人でも混同しますか?
A. はい、混同することがあります。
特に書き言葉に慣れていない場合や、文脈の違いをあまり意識せず使っている人も多くいます。ネイティブであっても、「なんとなく聞いたことがある方」を使ってしまうことは珍しくありません。
まとめ
「間違いやすい」と「間違えやすい」は、どちらも正しい日本語であり、意味も非常に近い表現です。しかし、その文法的構造や文脈に応じた自然さには違いがあります。
「間違いやすい」は、名詞「間違い」に由来する表現で、主に状況や内容がミスの原因になる場合に使われ、ビジネス文書や教育資料などフォーマルな場面で多用される傾向があります。
一方の「間違えやすい」は、動詞「間違える」に由来し、「誰が何を間違えるのか」という行動や動作に焦点を当てた表現です。会話やカジュアルな文章ではよく使われますが、主語や文の構造に注意が必要です。
使い分けに迷ったときは、
- 対象が「物・表現・状況」 → 間違いやすい
- 主語が「人」で動作を強調したい → 間違えやすい
という判断基準を持つことで、より自然で的確な表現が可能になります。
本記事で紹介した50個の例文を参考に、場面に応じた言葉選びができるようになれば、文章の説得力や伝わりやすさもぐっと高まるでしょう。




