一里塚とは?読み方や意味・使い方、知らなかった役割まで解説

日本には、古くから人々の暮らしと旅路を支えてきた独自のインフラがあります。その一つが「一里塚(いちりづか)」です。一里塚とは、かつて主要街道沿いに一定の間隔で築かれた土盛りで、旅人に距離の目安を示すためのランドマークでした。
現代では、自動車や電車、スマートフォンの地図アプリがあれば簡単に現在地や距離がわかりますが、江戸時代にはもちろんそんな便利なツールはありません。そんな中で、一里塚は旅人にとって非常に重要な存在だったのです。
この記事では、「一里塚とは何か?」という基本から、その距離の由来、なぜ約4kmとされているのか、現代に残る一里塚、さらには言葉としての使い方まで、幅広く詳しく解説していきます。
かつての人々の足跡をたどるように、「一里塚」の歴史と意味に触れてみましょう。
目次
一里塚とは?

一里塚(いちりづか)とは、江戸時代に日本各地の主要街道沿いに設けられた「距離の目印」です。一般的には、一里(約4km)ごとに一対(道の両側)で築かれ、旅人がどれくらい進んだか、どこまで行けば目的地に着くのかを知るために使われました。
一里塚の読み方
まず、「一里塚」は「いちりづか」と読みます。「塚(つか)」とは、土を盛り上げて作った小さな丘や土の盛り土を意味し、古墳などにも使われる言葉です。一里塚では、道の両側に高さ1~2メートルほどの塚が築かれ、その上にはエノキや松などの木が植えられることが一般的でした。これは、遠くからでも視認しやすくするための工夫です。
いつ作られたのか?
一里塚が制度として本格的に整備されたのは1604年(慶長9年)、徳川家康の命によるものでした。家康は二代将軍・徳川秀忠に命じ、江戸・日本橋を起点として東海道・東山道・北陸道など主要街道に一里塚の設置を指示。これをきっかけに、全国各地の街道へと一里塚が普及していきました。
当時、幕府は街道整備を進め、交通や物流の円滑化を図る政策を推進していました。一里塚はその一環として設けられ、五街道にはほぼ一里ごとに正確に設置されました。これにより、旅人や参勤交代の大名、飛脚たちは、一里塚を距離の目安としながら移動することができたのです。
現在でも全国各地に、かつての一里塚が史跡として残っている場所があり、当時の街道文化を今に伝えています。
「一里」はどれくらい?
「一里」という単位は、現代で言うと約3.9km〜4kmに相当します。現在のように距離をメートルやキロメートルで測る習慣がなかった時代、人々は「一里ごとに塚がある」という分かりやすい目印で距離を把握していたのです。
旅の途中で一里塚を見かけることで、「あと3つで宿場町だ」「今日はもう5里も歩いた」といった風に、自分の進んだ距離を実感することができました。
一里=約4kmの由来とは?

「一里塚」の「一里」とは、現代の距離に換算するとおよそ3.9km〜4kmとされています。しかし、なぜ「一里」がその距離に相当するのでしょうか?
この章では、一里という単位の成り立ちと、実用的な背景について詳しく解説します。
中国から伝わった距離単位「里」
「里」という単位は、もともと中国から伝わったもので、古代中国ではすでに「里」が距離の基準として使われていました。日本にも漢字文化とともにその概念が伝わり、飛鳥時代から奈良時代にかけて、律令制度の中で採用されるようになります。
ただし、当初の「一里」の距離は一定ではなく、時代や地域によって異なることもありました。江戸時代に入り、幕府が街道を整備するにあたって、「一里=約3.9km」として定めたのが、現在の「一里」の基準となったのです。
徒歩で1時間=約4kmという実用的な基準
もうひとつの重要な視点は、「人が徒歩で1時間に歩ける距離」が一里とされるようになった、という実用的な理由です。当時の人々は、現代人よりもはるかに歩くことに慣れており、1時間でおよそ4km進むのが一般的とされていました。
旅をする上で、「今から1時間歩けば一里塚が見える」「あと2時間で宿場町に着く」といった目安があることで、移動中の計画が立てやすく、安心感にもつながったのです。
実際、一里塚が設置された距離をたどると、ちょうど人が1時間程度で歩けるペースに沿って作られていることが多く、「人間の感覚」に寄り添った距離設計だったことがわかります。
なぜ4km前後に定着したのか?
江戸幕府が一里の長さを全国で統一したことで、「一里=約4km」という基準は街道の整備とともに全国に広まり、定着していきました。この統一があったからこそ、一里塚は全国共通の距離感覚の基準として機能したのです。
一里塚の役割

一里塚は、江戸時代の街道整備の一環として設置された、旅のための「道しるべ」です。しかしその役割は、単なる距離表示だけにとどまらず、当時の社会や交通政策にも深く関わっていました。この章では、一里塚の目的や使われ方について詳しく見ていきます。
①距離を知らせる目印として
一里塚の最も基本的な目的は、「旅人に距離の目安を与える」ことでした。
主要街道では、出発地点から一里(約4km)ごとに一里塚が置かれ、「ここまで一里進んだ」「次の宿場町まであと何里だ」といったことを判断する材料になっていました。
現代で言えば、国道沿いに設置された距離標識やキロポストのような役割と考えるとわかりやすいでしょう。特に、徒歩で移動していた時代において、距離感を把握できることは、心身の疲労を和らげる心理的な支えにもなっていたと言われています。
②幕府による交通管理の手段
一里塚はまた、単に旅人の利便性だけでなく、幕府による街道と交通の管理にも大きな意味を持っていました。
徳川幕府は、参勤交代や物流の円滑化を図るため、全国の街道整備を進めました。その際に、距離が統一され、制度的に管理された「一里塚」は、各地の位置情報を把握するための重要な基準となったのです。
つまり一里塚は、交通インフラの一部であり、統治のツールでもあったのです。
③旅の計画や宿泊のため
江戸時代の旅は、日数や距離を事前に見積もって計画する必要がありました。
一里塚があることで、旅人は「今日は○里歩いて、この宿に泊まろう」といった具体的なプランを立てやすくなります。
例えば、1日に八里(約30km)進めば、ちょうど3つ目の宿場町に泊まれる——そんな計算ができたのも、一里塚という基準があったからこそです。
また、旅の記録や地誌、案内書などにも「○里目に〇〇宿」「〇〇塚から南に二里」などの記述が見られ、一里塚は当時の旅文化に深く根付いていました。
④景観・ランドマークとして
さらに、一里塚は道中の風景の一部としても機能していました。塚の上に植えられたエノキや松の木は、街道を歩く旅人に木陰を提供し、遠くからでも見える目印となっていました。
一部の一里塚では、休憩所のように使われた例もあり、人々の交流の場になったとも言われています。
現存する一里塚

現在でも全国各地に、かつての一里塚が現存しており、地域の歴史を物語る貴重な文化財となっています。Googleマップなどで「一里塚」と検索してみると、意外にも自宅の近くに点在していることに気づくかもしれません。それぞれの一里塚には案内板や石碑が設置されていることも多く、地元の人々によって大切に守られています。
近年では、旧街道をたどる「街道ウォーク」や「歴史ハイキング」が人気を集めており、一里塚を目的地やチェックポイントにして歩く人も増えています。江戸時代の旅人がどんな景色を見ながら、どんな思いでこの道を進んでいたのか――そんな旅人の目線で歴史に触れられる体験は、現代の私たちにとっても貴重な時間となるでしょう。
「一里塚」の使い方
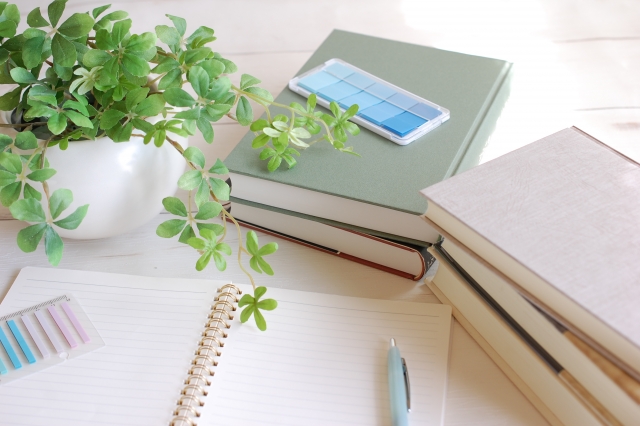
「一里塚(いちりづか)」はもともと、江戸時代の街道における距離の目印でしたが、その「一定間隔で訪れる節目」という性質から、現代日本語では慣用句的にも用いられることがあります。
この章では、「一里塚」の比喩的・象徴的な使い方に焦点を当てて、その意味と使い方を解説します。
一里塚の慣用句的意味とは?
「一里塚」という言葉は、転じて進歩や過程の中の節目、区切り、目印を表す言葉として使われるようになりました。
つまり、何かを達成した際や、物事の進行の中での「通過点」や「記録となる段階」を指すときに使われます。ゴールではなく、そこに至るまでの中間地点やマイルストーンといった意味合いです。
一里塚を使った例文
以下に、「一里塚」を使った代表的な慣用句的表現を紹介します。
①○○の一里塚
ある物事の進行や成長の中での重要な通過点や節目を表す。
例文:
- この作品は彼の作家人生における一里塚と言える。
- 新製品のヒットは、会社の発展の一里塚となった。
②一つの一里塚を越えた
物事が一区切りし、新たな段階へと進んだことを示す表現。
例文:
- 試作品の完成で、プロジェクトは一つの一里塚を越えた。
- 子育てで言えば、小学校入学は一つの一里塚かもしれません。
③一里塚に過ぎない
それ自体は達成ではなく、あくまで通過点にすぎないことを強調する表現。
例文:
- 目標達成まではまだ遠く、今回の成功は一里塚に過ぎない。
- 資格取得は一里塚であり、これからが本番だ。
ビジネスや教育の場でも使われる
このような表現は、ビジネスや教育、スポーツなどの分野でも応用されます。
- ビジネス:「今期の黒字化は、長期的成長への一里塚だ」
- 教育:「中学卒業は学びの一里塚」
- スポーツ:「初勝利はチームにとっての一里塚だった」
このように、何かの到達点・区切りを丁寧に表現したいとき、「一里塚」は日本語らしい奥ゆかしさを持った言い回しとして重宝されます。
ただし、この表現はややフォーマルで、文章語やスピーチでの使用が主です。日常会話ではやや堅苦しく聞こえることもあるため、場面に応じて使い分けましょう。「一里塚」は、ゴールではなく、過程の中にある節目や目印です。この言葉を使うことで、私たちは「いま、どこにいるのか」「これまでどう歩んできたのか」に意識を向けることができます。そんな日本語の美しさと奥深さを、改めて感じさせてくれる表現の一つです。
まとめ

一里塚は、江戸時代に街道の距離目安として設けられた重要なインフラでした。一里(約4km)ごとに塚を築き、旅人に道のりの節目を知らせる役割を果たしました。その距離設定には、「人が1時間に歩く距離」という実用的な基準も関わっており、生活の中に自然と溶け込む存在だったのです。
現在では多くの一里塚が姿を消しましたが、保土ヶ谷や桶川など、一部は史跡として保存され、地域の歴史を語り継ぐ大切な遺産となっています。また、「一里塚」という言葉は、今も節目や通過点を表す慣用句として使われることがあり、文化的にも生き続けています。
一里塚は、単なる土の盛り塚ではなく、当時の社会・旅・人の営みを映し出す象徴です。歴史散策や旧街道歩きの際には、その足元に残る小さな塚に、ぜひ目を向けてみてください。そこには、過去と今とを静かにつなぐ、日本の風景があります。




