老舗は「ろうほ」「しにせ」どっちも正解?正しい読み方【例文30】

「老舗」という言葉、聞いたことはあるけれど、正しく使えているかと聞かれると少し自信がない……そんな方も多いのではないでしょうか?
ビジネスシーンや観光地の紹介記事、テレビのグルメ番組など、さまざまな場面で耳にする「老舗」。しかし、その読み方を「ろうほ」「しにせ」のどちらか分からなかったり、「老舗ってそもそもどういう意味?」と疑問を持ったことがある人も少なくありません。
実際、「老舗」はとても歴史のある言葉であり、正しい読み方・意味・使い方を知っておくことで、表現に深みや敬意を加えることができます。
本記事では、「老舗」の正しい読み方から意味、使い方、語源、類語、英語表現、さらによくある疑問まで、幅広く丁寧に解説していきます。例文も30個ご紹介するので、実際の文章にどう取り入れるかがすぐにイメージできるはずです。
それではさっそく、「老舗」の世界へご案内しましょう。
目次
老舗の読み方は「ろうほ」「しにせ」どっち?

結論から言うと、「ろうほ」も「しにせ」もどちらも正解です。ただし、それぞれの読み方には使われ方や背景に違いがあります。
「ろうほ」は音読みとして正しいが、一般的ではない
「老」は音読みで「ろう」、訓読みで「おいる」や「ふける」と読みます。「舗」も音読みで「ほ」と読むことができます。そのため、「老舗」を音読みの組み合わせで「ろうほ」と読むのは、読み方としては成立します。
実際、一部の古典文学や文語表現では「ろうほ」と読む例もあります。ただ、現代の日本語において「ろうほ」と読むことは非常にまれで、一般的ではありません。
「しにせ」が一般的な読み方
現在、「老舗」は「しにせ」と読むのが最も一般的です。ニュース記事、書籍、テレビ番組など、日常のほとんどの場面では「しにせ」と発音されます。
この「しにせ」という読み方は、漢字の個々の読みとは異なる、熟字訓(じゅくじくん)という特別な読み方に分類されます。
熟字訓とは:複数の漢字が組み合わさった熟語に対して、個々の漢字の読み方にとらわれず、ひとまとまりで特別な訓読みが与えられているもの。
「老」と「舗」はそれぞれ「おいる/ろう」「ほ」と読めるにもかかわらず、「しにせ」と読むのは、この熟字訓が使われているためです。
「しみせ」は誤読
なお、「しにせ」の誤読としてよく見られるのが「しみせ」です。「し」は正しいとしても、「舗」は「みせ」と読むことはないため、「しみせ」は誤った読み方です。会話や文章で使う際には注意しましょう。
「老舗(しにせ)」の意味
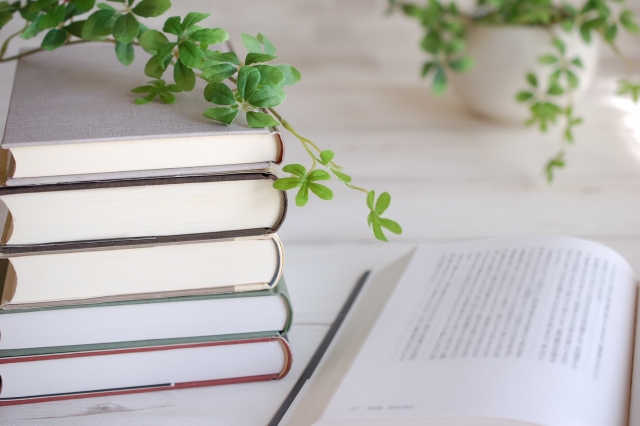
「老舗(しにせ)」という言葉は、長い歴史を持つ企業や商店、あるいは職人の家系などに対して使われます。単なる「古い店」ではなく、代々受け継がれてきた伝統と信用、そして地域や顧客との信頼関係を象徴する存在です。
辞書には、以下のように定義されています。
老舗(しにせ):長い年月にわたって営業を続けてきた店。また、その家系や企業。
たとえば、江戸時代から続いている和菓子屋や、明治時代に創業した呉服店などは「老舗」と呼ばれます。
単に古いだけでは「老舗」とは言えない
ここで注意すべきポイントは、「老舗」と呼ばれるためには単に創業年が古いだけでは不十分だということです。
老舗と認められるには、以下のような要素が求められることが多いです:
- 長期間、同一業種で事業を継続している
- 代替わりしながら経営が継続している
- 地域や顧客からの信頼を築いてきた
- 伝統や文化を大切にしている
つまり、「創業してから古い=老舗」という単純な図式ではなく、「長年にわたり信頼され続けてきたこと」こそが老舗の条件なのです。
「老舗」の使い方【例文30】

「老舗(しにせ)」という言葉は、敬意や信頼、歴史の重みを伝える表現として非常に便利です。ここでは、日常会話・ビジネス・観光・メディア表現など、さまざまな場面での「老舗」の使い方を例文で30個ご紹介します。
飲食店での使い方
- 京都の老舗料亭で、本格的な懐石料理を堪能しました。
- 銀座の老舗寿司店は、予約が数ヶ月待ちです。
- 地元の人に愛される老舗のうなぎ屋があります。
- 明治創業の老舗カフェは、レトロな雰囲気が魅力です。
- テレビで紹介された老舗のラーメン店に行ってきました。
企業・ビジネスでの使い方
- 創業100年を迎える老舗企業として、地域に貢献し続けています。
- 老舗メーカーの技術力は、業界でも一目置かれています。
- 当社は昭和初期から続く老舗の印刷会社です。
- 老舗の酒造メーカーとのコラボ商品を発売しました。
- 老舗企業ならではの信頼と実績を武器に、グローバル展開を進めています。
サービス・観光・文化関連の使い方
- 老舗旅館のもてなしに、心から癒されました。
- 老舗和菓子店の上生菓子は、見た目も味も芸術的です。
- 老舗茶舗で購入した抹茶は、香りが格別でした。
- この街には、明治時代から続く老舗の銭湯があります。
- 老舗の呉服屋で、着物の仕立てをお願いしました。
メディア・マーケティング表現
- 老舗ブランドとしての信頼性が高く評価されています。
- 老舗の名に恥じない品質を守り続けています。
- 新製品にも、老舗らしいこだわりが詰まっています。
- 老舗企業が挑むDX(デジタルトランスフォーメーション)
- 老舗の味を、現代の感覚で再構築した逸品です。
フォーマル・スピーチなどでの表現
- 本日は、老舗企業の皆様と貴重な意見交換の場を設けられ、大変光栄です。
- 老舗としての誇りを胸に、これからも変わらぬ品質を提供してまいります。
- 地域の発展を支えてきた老舗のご尽力に、深く敬意を表します。
- 老舗の知恵と若い力の融合が、次の時代を切り拓く鍵です。
- この業界で、老舗と呼ばれること自体が信頼の証です。
カジュアルな会話・SNS投稿などでの使い方
- あの老舗パン屋、久しぶりに行ったけどやっぱり最高!
- 地元に帰ったら必ず寄る、老舗のラーメン屋さん!
- 老舗の喫茶店でまったり。レトロな空間が落ち着く〜
- 老舗=古臭いって思ってたけど、行ってみたらめちゃくちゃオシャレだった!
- 推しの俳優が老舗ブランドのCMに出てて、うれしい!
「老舗」の語源

「老舗(しにせ)」という言葉には、ただ「古い店」というだけではなく、代々受け継がれてきた商売・伝統・信頼という深い意味が込められています。その背景には、興味深い語源の歴史があります。
「老舗」のもともとの形は「しにす」
現在「老舗」と書いて「しにせ」と読みますが、この「しにせ」は、もともと「しにす(為似す・仕似す)」という動詞が語源だとされています。
「しにす」は、「似せて行う」「誰かの真似をしてやる」といった意味を持つ言葉で、特に先祖の商売や家業を「似せて行う=受け継ぐ」ことを表すものでした。
「しにす」→「しにせる」→「しにせ」へ
この「しにす」が連用形になって「しにせる」となり、そこから名詞化されたものが「しにせ」です。
本来の意味:
- 似せてすること(=先祖のやり方に倣う)
- 代々家業を守り継ぐこと
- 長く商売を続けること
つまり、「しにせ(老舗)」は、単に古いだけでなく、「伝統を引き継ぎながら長年にわたり商売を続けてきた店」という意味がもともと込められていたのです。
当て字としての「老」と「舗」
後に、この「しにせ」という言葉に「老(長い経験)」「舗(店)」という漢字が当てられ、「老舗」という表記が定着しました。
- 老:長い年月・豊富な経験を象徴
- 舗:「店舗」や「商売の場」という意味を持つ漢字
こうした当て字によって、「老舗」=「長年続いている由緒ある店」というイメージが現代にまで引き継がれているのです。
「老舗」という言葉の背景には、単なる古さや年数以上に、歴史の重みや、家業を受け継ぐことへの敬意が込められています。語源を知ることで、「老舗」という言葉をより適切に、そして敬意を持って使えるようになるでしょう。
「老舗」の類語
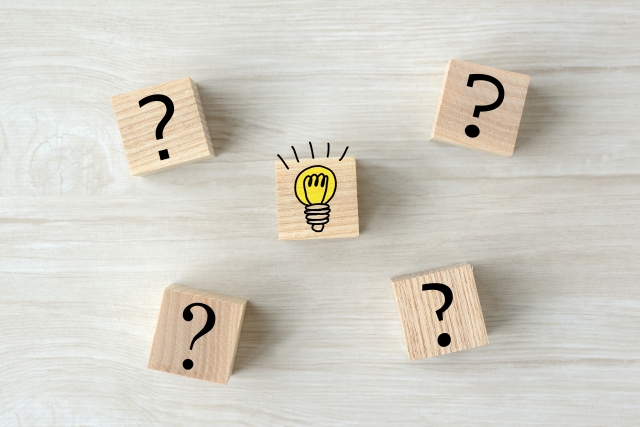
「老舗(しにせ)」には、似た意味の言葉がいくつかあります。ここでは、代表的な類語をわかりやすく紹介します。
①名店
- 意味:評判がよく、有名な店
- 特徴:おいしい料理や良いサービスで知られている
- 例文:この町には多くの名店がある。
②伝統店
- 意味:昔からのやり方を守っている店
- 特徴:伝統的な技術や味を大切にしている
- 例文:伝統店の和菓子は、見た目も美しい。
③由緒ある店
- 意味:歴史や格式がある店
- 特徴:長い歴史があり、由来がはっきりしている
- 例文:この旅館は由緒ある老舗として知られている。
④長寿企業
- 意味:創業してから長いあいだ続いている会社
- 特徴:100年以上続いている企業も多い
- 例文:日本には多くの長寿企業が存在している。
簡単まとめ
| 言葉 | 主なポイント |
|---|---|
| 老舗 | 長い歴史と伝統がある店 |
| 名店 | 有名で評判がいい店 |
| 伝統店 | 昔ながらのやり方を守る店 |
| 由緒ある店 | 歴史や背景が特別な店 |
| 長寿企業 | 長く続いている会社 |
「老舗」の英語

「老舗(しにせ)」を英語で表現するには、歴史の長さや伝統的な背景を伝える言い方が使われます。日本語のように「老舗」という単語が英語にあるわけではないため、文脈に応じて言い換えるのがポイントです。
long-established shop(長く営業している店)
最も一般的で、ビジネスや観光案内などにも使える表現です。
例:a long-established shop in Kyoto
(京都の老舗店)
longstanding business(長年続く事業)
お店だけでなく、企業全体にも使える言い方です。
例:a longstanding business with over 100 years of history
(100年以上の歴史を持つ老舗企業)
traditional store(伝統的な店)
「伝統」という要素を強調したいときに使います。
例:a traditional Japanese confectionery store
(伝統的な和菓子の老舗)
heritage brand / heritage shop(伝統ブランド/伝統的な店)
ブランドとして長い歴史があることを示す場合に使います。
特にファッションや工芸品などにぴったりの表現です。
例:a heritage kimono shop
(伝統ある着物の老舗)
簡単まとめ
| シーン | 英語表現 |
|---|---|
| 一般的な老舗 | long-established shop |
| 長寿企業 | longstanding business |
| 伝統を強調 | traditional store |
| ブランド的表現 | heritage brand / heritage shop |
よくある質問(Q&A)

ここでは、「老舗(しにせ)」に関してよく寄せられる疑問について、簡潔にお答えします。
Q1. 「老舗」と呼ばれるには何年くらい必要?
A:一般的には50年以上、特に100年以上の歴史があると老舗と呼ばれることが多いです。
ただし、明確な基準はありません。大切なのは「長く商売を続けてきたこと」と「信頼を築いてきたこと」です。
Q2. 自分で「老舗」と名乗っていいの?
A:名乗ることはできますが、慎重に使うのが望ましいです。
「老舗」という言葉には重みがあるため、実績や歴史に裏付けがある場合に使う方が信用を得られます。
Q3. 新しい会社でも「老舗」を目指せる?
A:もちろん可能です。
長く続くこと、伝統を築いていく姿勢があれば、将来的に「老舗」と呼ばれる存在になることは十分にあり得ます。
Q4. 「老舗」って飲食店だけに使うの?
A:いいえ、さまざまな業種に使えます。
飲食店のほかにも、和菓子店、呉服店、旅館、工芸品店、時計店など、多くの分野で使われています。
Q5. 「老舗」と「名店」の違いは?
A:「老舗」は歴史と伝統、「名店」は評判や実力に重きを置く言葉です。
老舗が名店であることもありますが、創業が新しくても人気が高ければ名店と呼ばれることがあります。
まとめ
「老舗(しにせ)」とは、長い年月にわたって商売を続け、伝統や信頼を守り抜いてきた店や企業を指す言葉です。読み方には「ろうほ」もありますが、現代では「しにせ」が一般的で、熟字訓という特別な読み方に分類されます。語源は「しにす(為似す・仕似す)」で、先祖の業を受け継ぐという意味があり、「老」と「舗」は当て字として後から加えられました。
「老舗」は、単なる古さではなく、継続性と信頼、そして伝統の継承が評価される存在です。名店や伝統店といった類語と使い分けることで、より的確にその価値を伝えることができます。英語では “long-established shop” や “traditional store” などで表現されます。
老舗に込められた歴史や文化を理解することで、言葉の重みをより深く感じることができるでしょう。正しく使うことで、表現の品格や信頼感も高まります。




