自由研究のまとめ方【誰でもわかる簡単ステップ】例文あり

夏休みや冬休みによく出される「自由研究」。テーマが自由だからこそ、何をどう進めて、どうやってまとめたらいいのか悩む人も多いですよね。特に、研究が終わった後の「まとめ方」がうまくできないと、せっかくの努力が伝わりにくくなってしまいます。
この記事では、小学生と中学生を対象に、誰でもできる簡単なまとめ方のステップをご紹介します。学年別のポイントやコツも紹介するので、自分に合った方法でしっかりまとめましょう!
夏休みの宿題【自由研究アイデア150選】1日で終わるテーマ満載!
夏休みの自由研究で迷っている小学生・中学生必見!本記事では、ジャンル別・学年別に選べる自由研究アイデアを150個ご紹介。1日でできる簡単なものから本格的なものまで…
自由研究のまとめ方【基本的な簡単ステップ】

自由研究のまとめ方は、だれでも使える「5つのステップ」で考えると、とてもスムーズです。このステップをひとつずつ丁寧にやれば、内容がしっかり伝わるレポートになります。
ステップ① テーマと目的を書く
まず一番大切なのは、「なにを調べたか」「なぜそれを選んだか」を書くことです。
ポイント:
- テーマはできるだけ具体的に!
- 自分が興味を持ったきっかけや理由を書くと、見る人が共感しやすい
例:
- テーマ:「身のまわりにある水を調べてみよう」
- 目的:「川の水と水道水の違いを調べて、安心して飲める水について考えたい」
ステップ② 方法を書く
次に、「どんなやり方で調べたか・実験したか」を書きます。ここでは、準備したものや手順を詳しく説明します。
ポイント:
- 使った道具、材料を書く
- 順番を追って、簡単な言葉で書く(箇条書きでもOK)
- 写真やイラストがあるとわかりやすくなる!
例:
- 透明なコップに水を入れる
- 日向・日かげ・冷蔵庫の3か所に置いて、毎時間ごとに水の温度を測る
- 3日間記録をとる
ステップ③ 結果を書く
ここでは、「どんなことがわかったか」「どんな変化があったか」をまとめます。実験や調査の内容によっては、表やグラフを使うと見やすくなります。
ポイント:
- 実際に観察したこと、測った数値などを正確に記録
- 写真をつけるとより具体的になる
- うまくいかなかったことも書いてOK
例:
- 日向の水は朝よりどんどん温度が上がった
- 冷蔵庫の水はずっと同じ温度だった
ステップ④ 考察を書く
考察とは、「どうしてそうなったのか?」を自分なりに考えることです。ここが“自分の考え”をしっかり伝えるチャンスです。
ポイント:
- 結果から「わかったこと」「予想とちがったこと」を書く
- 本やインターネットで調べた情報と比べてみると説得力UP
例:
- 日向の水が温まったのは、太陽の光と気温の影響だと思う
- 冷蔵庫の水の温度が変わらないのは、一定の温度に保たれているから
ステップ⑤ まとめ・感想を書く
最後に、研究を通して感じたことや、学んだことをまとめます。研究全体の「しめくくり」として、しっかり自分の言葉で書きましょう。
ポイント:
- 「この研究で何がわかったか」を一文で書いてみよう
- 「こんどやってみたいこと」「もっと知りたくなったこと」を加えると良い
例:
- 水は置く場所によって温度が大きく変わることがわかった
- 今度は氷を使って、もっと細かく実験してみたい
小学生向け自由研究のまとめ方
小学生の自由研究では、「楽しんで取り組むこと」と「自分の力でまとめること」が最も大切です。ただし、学年によって表現力や理解力に違いがあるため、それぞれのレベルに合った進め方をすることが成功のポイントです。ここでは、低学年・中学年・高学年に分けて、まとめ方のコツを紹介します。
●低学年(小学1年生・小学2年生)向け

低学年の自由研究では、「見るだけでわかる」ような工夫がとても効果的です。まだたくさんの文字を書くのは難しいので、絵や写真を使いながら、短くても自分の言葉でまとめることが大切です。
①テーマを書く
まず、研究のタイトル(テーマ)を書きます。難しい表現にせず、自分が「なにをやったのか」がすぐにわかるようにしましょう。
例:
- 「アリのすみかをさがしたよ」
- 「つよいしゃぼんだまをつくってみた」
②やったことを紹介
どんなことをしたかを、絵や写真といっしょに説明します。短い文章で「〜しました」と書けばOKです。
例:
- 「アリのいるところをさがして、えさをおきました。」
- 「しゃぼんだまにさとうをまぜてふくらませました。」
③わかったことを書く
実験や観察をして「こうなった」「気づいた」ということを書きます。まだ漢字や長文が難しいので、短くても良いです。
例:
- 「アリはさとうにあつまったよ。」
- 「さとうをまぜたしゃぼんだまはこわれにくかった。」
④まとめる紙を用意する
A4の紙1枚でも、模造紙に大きく書いてもOK。順番を意識して貼ると、見やすく伝わります。
ポイント:
- テーマ → やったこと → わかったこと → 感想 の順でまとめよう。
⑤感想を書く
最後に、研究をやってみてどう思ったかを自分の言葉で書きます。楽しさやびっくりしたことを書くだけでも十分です。
例:
- 「アリがいっぱいきてびっくりした!」
- 「しゃぼんだまがつよくなってうれしかった。」
●中学年(小学3年生・小学4年生)向け

この時期になると、文章で説明する力が少しずつ育ってきます。調べたことや実験の方法を、順を追ってわかりやすく書く練習が大切です。表やグラフも少しずつ使えるようになります。
①テーマと目的を書く
研究のテーマと、どうしてそれを選んだかを書きます。
例:
- テーマ:「にんじんのはっぱは水だけでそだつの?」
- 目的:「にんじんを料理したあとにのこったはっぱが育つのか気になったから。」
②調べ方・やり方を説明
どんな方法で調べたか、何日やったか、使った道具などを具体的に書きます。
例:
- 「にんじんのはっぱを切って、コップに水を入れてうかべました。」
- 「毎日水をとりかえて、そだつかどうかをしらべました。」
③結果を書く
観察したことや、調べてわかったことをまとめます。簡単な表や日ごとの記録も使えます。
例:
- 「4日目にははっぱがのびて、7日目には小さなはながさきました。」
④考えたことを書く
なぜそのような結果になったのかを、自分の考えでまとめます。完璧な答えでなくても、自分なりに考えることが大切です。
例:
- 「にんじんのはっぱには、のこっているパワーがあるのかもしれないと思いました。」
⑤まとめ・感想を書く
学んだことや、もっと知りたいこと、やってみた感想を書きます。
例:
- 「水だけでもはっぱがそだつことがわかりました。」
- 「つぎはほかのやさいでもやってみたいです。」
●高学年(小学5年生・小学6年生)向け
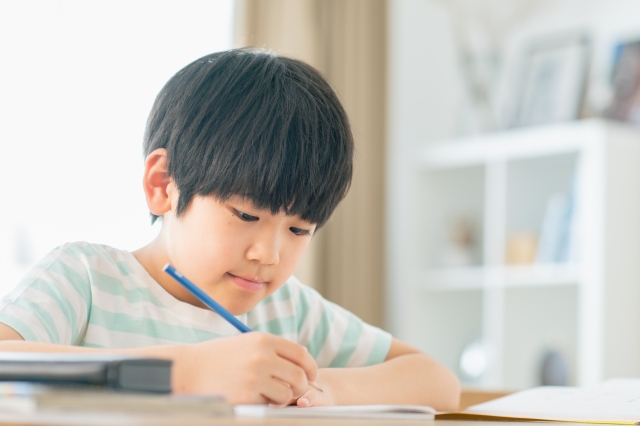
高学年になると、実験や観察の「意味」や「理由」を考える力がついてきます。そのため、仮説(予想)→調査→結果→考察(理由づけ)という流れで書くことが求められます。
①テーマと目的
自分が調べたいと思ったきっかけや、その目的を詳しく書きます。
例:
- テーマ:「氷はどこでいちばん早くとける?」
- 目的:「夏にアイスがすぐとけるのを見て、どんな場所がいちばん早いのかを知りたくなった。」
②仮説を書く(予想)
自分なりに「こうなると思う」と予想を書いておきます。
例:
- 「日なたのほうが一番早くとけると思う。」
③方法を書く
調査・実験の手順を、誰が読んでもわかるように丁寧に書きます。
例:
- 「同じ大きさの氷を3つ用意して、日なた・日かげ・冷蔵庫に置き、10分ごとに記録しました。」
④結果を書く
観察・測定した内容を、数字・表・グラフ・写真などで見やすくまとめます。
例:
- 「日なたの氷は30分で全部とけた。冷蔵庫では90分たっても半分残っていた。」
⑤考察を書く
なぜそうなったか、予想とどう違ったかを説明します。
例:
- 「日なたは気温と太陽の光の両方で早くとけたと思う。冷蔵庫は一定の温度で、温まりにくいからゆっくりだった。」
⑥まとめ・感想を書く
研究を通して何がわかったか、次にやってみたいこと、自分の成長などを書くと良いです。
例:
- 「氷のとけ方に気温と日光が大きく関係していることがわかりました。」
- 「次は風や湿度のちがいでも調べてみたいです。」
中学生向け自由研究のまとめ方
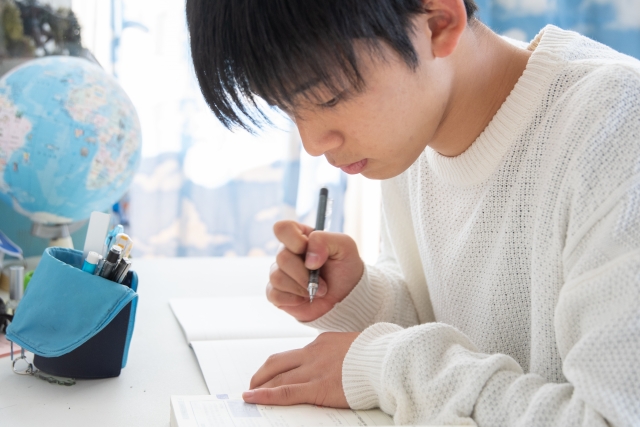
中学生になると、自由研究に求められる内容がぐっと高度になります。単なる観察や調査だけでなく、問題を発見し、自分で仮説を立て、データを集めて考察し、論理的にまとめる力が求められます。
ただし、難しく考えすぎる必要はありません。「自分で考えたことを、順を追って伝える」ことができれば、しっかりとした自由研究になります。
【中学生向けまとめ方の基本構成】
- テーマ(研究課題)
- 目的・背景
- 仮説(予想)
- 方法(実験・調査のやり方)
- 結果(データ・観察)
- 考察(結果からわかったこと・理由)
- まとめ・感想
- 参考文献・資料
①テーマ(研究課題)
まず、研究のテーマを明確にします。「◯◯について調べる」とだけでなく、「何がどうなるか」「なぜそれを調べるのか」までを含めると説得力が出ます。
例:
- 「植物の成長に与える音の影響」
- 「ペットボトルロケットの飛距離に影響を与える要素」
②目的・背景
なぜそのテーマを選んだのか、自分の関心や社会的な背景も含めて説明します。
例:
- 「音楽を聞かせると植物の成長が早くなるという話を聞き、本当かどうかを調べてみたかった。」
- 「学校でロケット作りを体験し、もっと遠くへ飛ばすには何が関係するのか知りたくなった。」
③仮説(予想)
研究を始める前に、「きっとこうなるはず」という予想を書きます。予想が間違っていても問題ありません。
例:
- 「植物にはクラシック音楽を聞かせたほうが、無音よりもよく育つと思う。」
- 「水の量が多いほど、ロケットは遠くに飛ぶはず。」
④方法(実験・調査のやり方)
どんな準備をして、どうやって調べたのか、使った道具や材料、手順を具体的に書きます。だれが読んでも同じことができるように書くのがポイントです。
例:
- 「同じ種類の植物を3つ用意し、それぞれにクラシック音楽、ロック、無音の環境で1日30分ずつ音を聞かせ、2週間育てた。」
- 「ペットボトルに水を100mlずつ増やしながら飛距離を計測し、同じ角度・圧力で飛ばした。」
⑤結果(データ・観察)
実験や観察で得られたデータを、表やグラフ、写真を使って整理します。データは正確に、事実をもとに記録します。
例:
- 「クラシックを聞かせた植物は平均で10cm、ロックは8cm、無音は7cm成長した。」
- 「水の量が200mlのときが最も飛距離が出た(7.5m)」
⑥考察(結果からわかったこと・理由)
結果から、「なぜこうなったのか」を自分なりに考えます。仮説が合っていたかどうかを振り返り、今後の課題も考えます。
例:
- 「クラシック音楽は音のゆらぎが植物の成長に良い影響を与えた可能性がある。リズムや音量も関係するかもしれない。」
- 「水が多すぎると重くなって飛ばなかったため、適度な量が重要だとわかった。」
⑦まとめ・感想
研究を通じて得た知識や経験、学んだこと、今後調べてみたいことなどを書きます。
例:
- 「音と植物の関係について、今後は音の種類や音量による違いも調べたいと思った。」
- 「飛距離をのばすには、空気の圧力やノズルの形状も影響するかもしれない。さらに工夫してみたい。」
⑧参考文献・資料
本やインターネットで調べた情報があれば、最後に記載します。
このように、中学生の自由研究は「問いを立てて、自分で考えて、説明する」力が求められます。難しく見えるかもしれませんが、「順序立てて説明すること」を意識すれば、だれでもしっかりとした研究にまとめることができます。
自由研究まとめ方(例文)

自由研究をどのようにまとめればよいか迷っている人のために、学年別の「まとめ方例文」をご紹介します。自分の学年や理解度に合わせて、書き方や構成の参考にしてください。
【小学生・低学年(小学1生・小学2年生)向け】
テーマ:「アリはどんな食べものがすき?」
テーマ
アリはどんなたべものがすき?
しらべたきっかけ
こうえんでおべんとうをたべていたら、アリがよってきました。パンのくずをもっていったので、ほかのたべものもすきかどうかしりたくなりました。
やりかた
おさらにさとう、ビスケット、パンをのせて、にわにおきました。アリがくるかどうか、10ぷんごとにみました。
けっか
はじめにアリがきたのはさとうでした。そのあとにビスケットにきて、パンにはすこしだけでした。
わかったこと
アリはあまいものがすきだとおもいました。
かんそう
アリがくるのをまつのがたのしかったです。こんどはくだものでもやってみたいです。
【小学生・中学年(小学3年生・小学4年生)向け】
テーマ:「にんじんのはっぱは水だけでそだつのか?」
テーマと目的
にんじんをりょうりにつかったあと、上のはっぱのところがのこったので、水につけたらどうなるのかしらべてみたくなりました。
やりかた
にんじんのはっぱのぶぶんを3つ切って、コップに水をいれて、まいにちおなじ時間にようすをみました。水は2日に1回かえました。しらべたきかんは1しゅうかんです。
けっか
3日めにはあたらしいはっぱが出てきました。5日めにはのびて、色がみどりいろになってきました。7日めには、はっぱのさきがひろがってきれいでした。
かんがえたこと
にんじんのはっぱには、水だけでもそだつちからがのこっているとわかりました。土がなくても、すこしなら育つのがおどろきでした。
まとめと感想
にんじんのあまりのぶぶんでも、そだつことがわかってたのしかったです。こんどはだいこんやかぶでもためしてみたいです。
【小学生・高学年(小学5年生・小学6年生)向け】
テーマ:「氷がとける速さは置く場所で変わるのか?」
テーマと目的
夏にジュースに入れた氷がすぐとけてしまうのを見て、どこに氷を置くと一番早くとけるのか気になりました。そこで、場所によって氷がとける時間に違いがあるのかを調べることにしました。
仮説(よそう)
日なたが一番早くとけると思いました。太陽の光で気温が高くなるからです。
準備と方法
・同じ大きさの氷を3つ用意
・それぞれ「日なた」「日かげ」「冷蔵庫」に置いて観察
・10分ごとにとけた量を見て記録
・氷がなくなるまでの時間を計る
・7月20日午後1時〜2時の間に実験
結果
・日なた:30分で完全にとけた
・日かげ:50分でとけた
・冷蔵庫:2時間たっても半分残っていた
考察
やはり、日なたが一番早くとけました。太陽の熱が直接当たるため、氷の表面がすぐにあたたまり、早くとけたと考えられます。冷蔵庫は温度が一定で低いため、とけるスピードがとても遅くなったと思います。
まとめ・感想
氷のとけ方は気温や日光のあたり方に大きく関係していることがわかりました。次は風のある場所や、湿度の違いでも調べてみたいです。実験はとても楽しく、観察する力がのびたと思います。
【中学生向け】
テーマ:「音楽が植物の成長に与える影響」
研究の背景・目的
テレビ番組で「音楽を聞かせると植物がよく育つ」と紹介されているのを見て、本当に成長に差が出るのかを自分で確かめたいと思いました。環境や刺激が植物にどう影響を与えるのかを調べることを目的としました。
仮説(予想)
クラシック音楽を聞かせた植物が最もよく育つと予想しました。理由は、ゆったりとしたリズムや落ち着いた音が植物にやさしい影響を与えると思ったからです。
方法
・観葉植物(パキラ)を3鉢用意
・3つの環境を用意:「クラシック音楽」「ロック音楽」「無音」
・1日30分、毎日同じ時間に音楽を再生(音量50dB)
・同じ条件の部屋で、光・水の量は統一
・観察期間は2週間、成長の長さ・葉の色・葉の数を記録
結果
・クラシック:成長12cm、葉の数+6枚、色は濃い緑
・ロック:成長10cm、葉の数+4枚、色は少し黄みがかっていた
・無音:成長9cm、葉の数+3枚、色はやや薄めの緑
考察
クラシック音楽のグルーヴや安定したテンポが植物にストレスを与えず、成長を促した可能性があります。ロック音楽では成長はしたものの、葉の色がやや悪く、音の強さや速さが影響していたのかもしれません。無音の環境では、最も成長が遅く、音の刺激がある方が活性化するのではと感じました。
まとめ・感想
音楽によって植物の成長に差が出ることがわかり、おどろきました。科学的な理由はこれからさらに調べたいと思います。次回は音の高さやリズムの違い、また自然音などでも実験してみたいです。
参考文献
・『音と植物の関係』農林水産省資料
・NHK for School「植物のふしぎ」
よくある質問

Q1. 自由研究って、どれくらいの時間をかければいいの?
A.
自由研究にかける時間は、1日〜数日かけてじっくり行うものまでさまざまです。小学生なら 1日〜3日程度、中学生は 1週間〜10日程度を目安にすると良いでしょう。ただし「時間の長さ」よりも、「自分で考えてまとめたかどうか」が重要です。短くても中身がしっかりしていればOKです。
Q2. テーマがなかなか決まりません。どうしたらいいですか?
A.
テーマは「身の回りの気になること」から探すのがコツです。
たとえば:
- 「どうしてお風呂の鏡はくもるの?」
- 「ペットボトルのふたってどれくらいの重さに耐えられる?」
家の中・学校・自然・食べ物・天気など、日常の中で「なぜ?」「どうなる?」と思ったことを書き出してみましょう。
Q3. 実験や観察がうまくいかなかったらどうすればいいの?
A.
うまくいかないことも立派な研究成果です。大切なのは、「なぜうまくいかなかったのか」「次はどうすればうまくいくのか」を自分なりに考えることです。それも考察の一部として書きましょう。
例:「2回目の実験ではうまく泡が出なかった。水の量が多すぎたのかもしれない。」
Q4. 字がきれいじゃないとダメですか?
A.
まったく問題ありません!重要なのは「自分の言葉で一生懸命まとめたこと」です。
きれいに見せたいときは:
- 丁寧な字で書くように心がける
- 見出しや重要な部分を色ペンで強調する
- 模造紙を使うと大きく見せられて効果的
Q5. 家の人が手伝ってもいいの?
A.
低学年のうちは保護者が手伝うこともOKです。ただし、「やるのは子ども、サポートは大人」が基本です。手伝ってもらった部分は、感想や最後に「お父さんにここを手伝ってもらいました」と書いておくと誠実で良い印象になります。
Q6. まとめる時に気をつけるポイントは?
A.
学年を問わず、以下のポイントを意識しましょう:
- 順番を意識する(テーマ→方法→結果→考察→まとめ)
- 見出しや色分けで見やすくする
- 写真・イラスト・図を使うと伝わりやすくなる
- 誤字脱字をチェックする(完成後に声に出して読んでみるのがおすすめ)
まとめ
自由研究は、単なる宿題ではなく、自分の「なぜ?」という気持ちから始まり、「どうして?」を考える学びの場です。
小学生は学年に合った方法で、楽しみながら表現することが大切です。中学生は、自分の考えを論理的に伝える力が求められますが、難しく考えすぎず、丁寧に順序立ててまとめることを意識しましょう。
どの学年でも共通するのは、「自分で考えて行動したこと」が一番の成果になるということです。自分なりの表現で、世界に一つだけの研究を完成させましょう。





