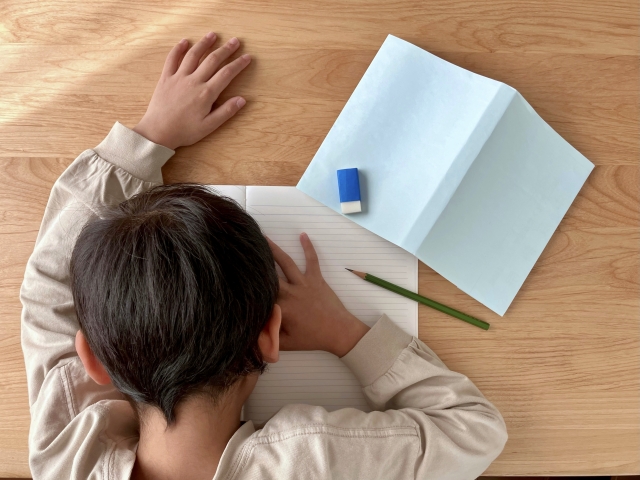【小学生】夏休みの宿題を早く終わらせる方法(30選)
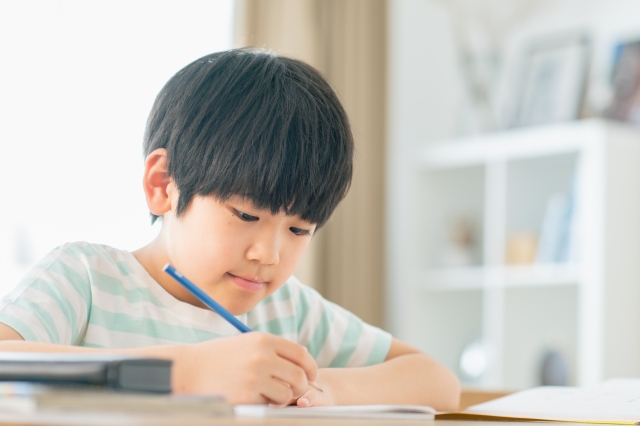
夏休みは小学生にとって、一年の中でも特に楽しみにしている長期休暇です。旅行に行ったり、友達と遊んだり、自由な時間を満喫できる貴重な期間――しかし、その一方で立ちはだかるのが「夏休みの宿題」です。
多くの子どもたちが、夏休みの終盤になって「まだこんなに残ってる…」と焦る経験をしています。また、親としても「早くやりなさい!」と毎日言うのに疲れてしまう…という悩みもよく聞かれます。
そこでこの記事では、「小学生が夏休みの宿題を早く終わらせるための方法」を30個、厳選してご紹介します。ただのテクニックではなく、子どものやる気を引き出し、親子で協力しながら前向きに宿題に取り組めるようになるためのアイデアを盛り込みました。
「やらなきゃ…」から「終わった!自由だ!」へ。そんな気持ちの変化を目指して、この記事を活用してください。
【中学生】夏休みの宿題を早く終わらせる方法(30選)
中学生の夏休みの宿題を早く終わらせるための実践的な方法を30個紹介。スケジュールの立て方、集中力を高める工夫、やる気を引き出す声かけのコツまで、アイデアが満載。…
やる気を上げる5つの考え方

宿題を早く終わらせるために、子どもが「よし、やってみよう!」と思えるようになることがとても大切です。ここでは、子どものやる気を引き出すための、シンプルで実践しやすい5つの考え方をご紹介します。
①子どもに「自分で決めさせる」
宿題を「やりなさい」と言われると、やる気がなくなることがあります。逆に、「今日は何ページやろうか?」「どこから始めたい?」と、子どもに選ばせると、「自分で決めたから、がんばろう」という気持ちが生まれます。小さなことでも、自分で決める経験をさせてあげましょう。
②小さい目標で「できた!」を増やす
「全部終わるまでやって!」ではなく、「今日はドリルを1枚だけ」「この10分間だけ集中しよう」といった小さな目標を立てましょう。そして終わったら、「できたね!すごい!」と声をかけてください。小さな成功の積み重ねが、大きなやる気につながります。
③ごほうびで楽しみをつくる
ごほうびがあると、子どもは「がんばろう!」という気持ちになります。たとえば、「終わったらアイスを食べよう」「3日続けたらゲームの時間を10分増やすね」など、子どもがうれしくなるようなごほうびを用意すると効果的です。紙に書いて見えるところに貼っておくのもおすすめです。
④宿題を「ゲームみたい」にする
ただ机に向かってやるだけだと、つまらなく感じることもあります。そこで「5分以内に終わらせチャレンジ!」「今日のミッション:漢字プリントを全部クリアせよ!」など、ゲームのようにすると楽しくなります。タイマーを使ったり、ポイント制にするのもいい方法です。
⑤宿題が終わった後の楽しみをイメージさせる
「宿題が早く終わったら何しようか?」と聞いて、楽しみを想像させましょう。たとえば、「全部終わったら水族館に行こうね」「自由研究が終わったら好きな遊びをしよう」など、宿題の先にある楽しみを見せることで、「早く終わらせたい!」という気持ちが湧いてきます。
親から子へやる気アップの声掛け

宿題をやらない子どもを見て、「早くやりなさい!」「なんでまだやってないの?」と言ってしまったことはありませんか?しかし、そうした声掛けは、子どものやる気をなくしてしまうことがあります。
ここでは、子どもが「やってみよう」と前向きになれる声のかけ方を、3つのポイントに分けてご紹介します。
①子どもに寄り添う「共感のことば」
まずは、子どもの気持ちをわかってあげることが大切です。「宿題イヤだよね」「今日は暑くて疲れたよね」など、気持ちに寄り添う言葉をかけると、子どもは安心します。そのうえで「じゃあ、ちょっとだけ一緒にがんばろうか」と声をかければ、自然と前向きになれることがあります。
例:
- 「イヤなの、わかるよ。でも少しずつ進めばラクになるよ」
- 「疲れてるよね。じゃあ5分だけ一緒にやってみようか」
②小さな努力を見つけてほめる
子どもは、「がんばったことを見てくれている」と感じると、もっとがんばろうという気持ちになります。全部終わっていなくても、「えらいね」「今のところまでやったの、すごい!」とほめてあげましょう。
ポイントは、「結果」ではなく「過程(がんばり)」をほめることです。
例:
- 「自分で始めたの、えらいね!」
- 「漢字1ページがんばってやったね、すごい!」
③子どもに選ばせて「自分で決めた」と思わせる
「これをやりなさい」と命令するよりも、「どっちからやる?」「何時から始めたい?」と、選ばせることで、自分の意思で動いている感覚が生まれます。これが「やらされ感」を減らし、自主的な行動を促します。
例:
- 「ドリルと日記、どっちからやる?」
- 「夕方までに終わらせたい?それとも今やっちゃう?」
夏休みの宿題を早く終わらせる方法30選
夏休みの宿題は、早く終わらせてしまえば、自由な時間をたっぷり楽しめます。しかし、計画を立てずにいると最後に慌てることも。ここでは、小学生が効率よく宿題を終わらせるための具体的な方法を30個ご紹介します。親子で無理なく実践できるコツばかりです。
スケジュール・計画編

まずは、宿題の全体量を把握し、無理のない計画を立てることが第一歩です。このステップがしっかりしていれば、後半に余裕が生まれます。
① 宿題をすべてリストに書き出す
夏休みの宿題がどれだけあるのか、まずは目に見える形でリスト化しましょう。ドリル、プリント、作文、自由研究などを種類ごとに分けて書き出すことで、全体像が把握しやすくなります。紙やホワイトボードに貼っておくと、進み具合も確認しやすく、達成感も得られます。
② 夏休みの日数と宿題の量を割り算で計画を立てる
宿題の総量を夏休みの残り日数で割って、1日にやる分量を決めましょう。たとえば、30ページのドリルがあるなら「1日1ページ」など、日々のノルマがはっきりすれば取り組みやすくなります。
③ 最初の1週間で多めに進めておく
夏休みの前半は気持ちに余裕があるため、やる気が出やすい時期です。このタイミングで多めに宿題を進めておくと、後半で予定変更があっても安心。残り時間に余裕が生まれます。
④ スケジュール表を作って色分けする
1日ごとに何の宿題をやるかをスケジュール表に書き込み、教科ごとに色分けすると見やすくなります。子ども自身が自分の進み具合を把握しやすくなり、やる気の維持にもつながります。
⑤ 毎日決まった時間に宿題タイムを設定する
「朝ごはんのあと」「おやつの前」など、決まった時間に宿題をする習慣を作ることで、自然と集中しやすくなります。リズムができれば、「やらなきゃ」と思わずに取り組めるようになります。
⑥ 優先順位をつけて進める
宿題には「すぐに終わるもの」と「時間がかかるもの」があります。特に自由研究や読書感想文などは、テーマ決めや準備に時間がかかるため、早めに取りかかるのがおすすめ。先に重い宿題を終わらせておくことで、後半に軽い内容を残し、気持ちにも余裕が生まれます。
⑦ 朝のうちに宿題を終わらせる
朝は頭がスッキリしていて集中力が高く、気温も低いため快適に作業できます。午前中に宿題を終わらせる習慣をつけることで、午後の時間を遊びやお出かけに自由に使えるようになり、生活のリズムも整いやすくなります。
⑧ 「ながら勉強」はやめる
テレビを見ながら、音楽を聞きながらの「ながら勉強」は、集中力が落ちて非効率。短い時間でも、静かな環境でしっかり集中する方が宿題は早く終わります。勉強中は机に向かい、1つのことに集中する習慣をつけましょう。
⑨ 1日の宿題内容を紙に書き出す
その日にやるべき宿題をメモやチェックリストに書き出しておくと、やるべきことが明確になります。終わったらチェックを入れたり、線を引いたりすることで達成感が得られ、「もっと進めよう」という気持ちにもつながります。
⑩ 計画は途中で見直してOK!
初めに立てた計画が完璧に進むとは限りません。日によって気分や体調も変わるため、計画は柔軟に見直して大丈夫です。「遅れた分は明日少し多めにやろう」など、無理のない調整が継続のカギになります。
実行テクニック編

スケジュールを立てたあとは、実際にどう取り組むかが大切です。この章では、集中力を高めたり、宿題の進みを良くするための実践的なテクニックをご紹介します。
⑪ タイマーを使って集中力アップ
「15分だけ集中しよう」とタイマーで時間を区切ることで、子どもは気持ちを切り替えやすくなります。短時間でも集中して取り組む習慣がつくと、宿題も効率的に進められます。時間の見える化は、やる気の維持にもつながります。
⑫ ごほうびシールやスタンプで達成感
宿題が終わったらシールを貼る、スタンプを押すなど、目に見える形で成果を残すことで達成感が得られます。カレンダーや手作りの表に記録するのがおすすめ。努力の積み重ねが見えると、継続する意欲も高まります。
⑬ ゲーム感覚でチャレンジする
「○分以内に終わらせられるかな?」など、宿題をゲームのように工夫してみましょう。ルールを決めて競争するような感覚で取り組むことで、楽しく集中できます。勝ち負けではなく「挑戦する姿勢」がポイントです。
⑭ 親がそばにいるだけで集中力が上がる
子どもは、親がそばにいるだけで安心して勉強に集中できます。一緒に机に向かって読書や家事をしながら見守るだけでOK。過干渉にならず、「見てくれている」と感じさせることが大事です。
⑮ わからないことはすぐ聞ける環境を
難しい問題にぶつかったときにすぐ質問できる環境を作っておきましょう。「あとで聞こう」と思っているうちにやる気が失われることも。つまずいたときの不安を減らすことで、宿題が止まらずに進められます。
⑯ テーマ別に日替わりで取り組む
毎日同じ内容だと飽きてしまいがち。曜日ごとにテーマを決めて、「月曜は算数」「火曜は国語」などと変化をつけると、気分がリフレッシュされ、続けやすくなります。子どもと相談してテーマを決めましょう。
⑰ 宿題が終わったら記録して達成感
「今日はドリル3ページやった!」など、宿題の進み具合を記録すると、「やった感」が強くなります。日記やカレンダーに記録を残すことで、過去の頑張りが目に見えてわかり、自信にもつながります。
⑱ 宿題専用の勉強スペースを用意する
テレビやおもちゃがない静かな場所を「宿題コーナー」にしましょう。場所を決めることで集中力が高まり、気持ちの切り替えもスムーズになります。自分だけの特別なスペースがあると、やる気もアップします。
⑲ 集中できる音楽をBGMにする
リラックスできるピアノ曲や自然音など、集中を妨げない静かな音楽を流すと、勉強しやすい雰囲気を作れます。YouTubeなどで「勉強用BGM」を探して、子どもに合う音を見つけてみましょう。
⑳ 文房具を好きなものでそろえる
お気に入りのキャラクターがついたノートや、好きな色のペンなどを使うことで、「使いたい=やりたい」という気持ちにつながります。自分で選んだ文房具なら、さらにモチベーションが高まります。
モチベーション・工夫編

計画やテクニックがあっても、子どもの「やる気」がなければ宿題は進みません。この章では、やる気を引き出し、楽しく宿題に取り組むための工夫を紹介します。
㉑ 宿題が終わったら遊びの予定を入れる
「終わったら公園に行こう」「アイスを食べに行こう」など、宿題の後に小さなごほうびや楽しみを用意しておくと、子どもは「早く終わらせたい!」という気持ちになります。毎日のちょっとした楽しみが、継続の原動力になります。
㉒ 家族に報告して褒めてもらう
子どもは「見てもらえた」「褒めてもらえた」と感じることで、自信を持ちます。「今日は○ページやったよ!」と自分で報告させる習慣をつけて、しっかり認めてあげることで、次もがんばろうという気持ちが芽生えます。
㉓ 勉強する日と遊ぶ日を分ける
毎日コツコツよりも、「今日は勉強、明日は遊び」と日を分けてメリハリをつけると、やる気が保ちやすくなります。「がんばった分、しっかり遊べる」リズムを作ることで、夏休み全体の充実感もアップします。
㉔ 友達と一緒に宿題タイムを作る
友達と「一緒に宿題やろう」と決めて取り組むと、お互いに刺激になり、集中しやすくなります。図書館や家庭で集まったり、ビデオ通話を使ったりして、楽しみながら進める工夫を取り入れてみましょう。
㉕ 教科書以外の教材や動画を活用する
自由研究や理科の宿題には、図鑑やYouTubeなどの動画も活用しましょう。視覚的に理解でき、興味が持てる内容であれば、自主的に学ぶ姿勢も育ちます。アプリや参考書もおすすめです。
㉖ 自由研究や読書感想文はテーマを早く決める
どちらも時間がかかる宿題なので、まずは「何をやるか」を早めに決めることが成功のカギ。テーマが決まっていれば、調べたり書いたりする作業もスムーズに進み、提出直前に慌てずにすみます。
㉗ 自分の好きな文房具で気分を上げる
お気に入りのキャラノートやカラフルなペンを使うと、宿題への気分が前向きになります。文房具を選ぶところから宿題が始まっていると考え、気持ちよくスタートできる環境を整えましょう。
㉘ 勉強記録をアプリや写真で「見える化」する
「今日は何をやったか」をスマホで写真に残したり、アプリで記録すると、がんばりが目に見えてわかります。視覚化することで子ども自身が達成感を感じやすくなり、やる気の維持にもつながります。
㉙ 親も一緒に目標を立ててチャレンジする
「パパは読書」「ママはウォーキング」など、親も目標を立てて子どもと一緒にがんばる姿を見せると、子どもも「自分もやろう」と思いやすくなります。親子で励まし合いながら取り組むと継続しやすくなります。
㉚ 全部終わったら「がんばった会」を開く
宿題をすべて終わらせたら、家族で「がんばったね会」を開きましょう。特別なおやつを食べたり、好きなご飯をリクエストさせたりして、努力をしっかり認めることで、次のチャレンジへの自信にもなります。
夏休みの宿題やらないとどうなる?知らないと損する5つの問題
夏休みの宿題をやらないとどうなる?学力の差や親子関係まで、実は大きなリスクがあります。本記事では、宿題の本当の目的や、やらないと起こる問題、ラクに終わらせるコ…
よくある質問(Q&A)

夏休みの宿題に関して、親御さんからよく寄せられる疑問や悩みをQ&A形式でまとめました。現実的で無理のない対応法をご紹介します。
Q1. 子どもが全然やる気を出さないとき、どうすればいい?
A. まずは無理にやらせようとせず、「今日はどんな気分?」と声をかけてみてください。やる気が出ない日もあります。そんなときは、少し休憩を入れて、短時間(5〜10分)だけ取り組む方法を試してみましょう。少しでも進めば「やった!」という気持ちが生まれ、次につながります。
Q2. 毎日続かない…途中でダレてしまうのですが?
A. 毎日やろうと意気込むより、「2日やって1日休む」などの“ゆるい計画”が続けやすいです。また、進んだ分が見えるようにカレンダーに色を塗ったり、チェックリストを活用するのも効果的です。目に見える達成感がやる気につながります。
Q3. 宿題を親がどこまで手伝っていいの?
A. 基本は「見守り」が理想です。ドリルや計算などの答えを教えるのではなく、子どもが迷ったときに「どう考えたの?」と一緒に考えてあげるサポート役に回りましょう。自由研究や読書感想文は、テーマ決めや素材集めは手伝ってOK。本番は子どもの言葉を尊重して進めさせると、達成感につながります。
Q4. 自由研究や読書感想文の進め方がわからない…
A. まずはテーマを早めに決めましょう。自由研究なら「身近な不思議」「好きなこと」から選ぶのがおすすめ。読書感想文は、物語の中で印象に残った場面にしぼって「なぜ心に残ったのか」を話し合うと、書き出しやすくなります。構成やまとめ方の例を用意しておくのも安心材料になります。
Q5. 計画通りに進まなかったとき、どう立て直せばいい?
A. 無理に巻き返そうとすると、子どもがストレスを感じます。「今どれくらい進んでる?」「どうしたら間に合いそうかな?」と、子どもと一緒に見直すスタンスが大切です。週単位で目標を決め直すなど、短期で見直す工夫も有効です。
まとめ
夏休みの宿題は、ちょっとした工夫と考え方でグッと取り組みやすくなります。大切なのは「早く終わらせなさい!」と急かすのではなく、子ども自身が「やってみよう」と思えるような仕掛けを作ること。
30のアイデアの中には、どのご家庭でもすぐに始められる工夫がたくさんあります。親子で計画を立てたり、小さな達成を一緒に喜んだりすることで、宿題の時間が“学び”と“成長”の時間に変わります。
早めに宿題を終わらせて、残りの夏休みを思いっきり楽しみましょう!