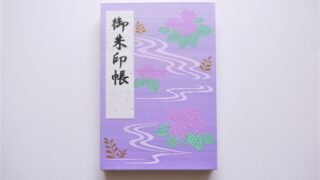暖房は何度からつけるべき?外気温と室温の目安や健康リスクを解説

暖房は何度からつけるべき?
寒さを感じると、「そろそろ暖房をつけようかな?」と考えますが、実際に何度からつけるのが適切なのでしょうか?快適に過ごしつつ、無駄な電気代を抑えるためにも、暖房をつける目安となる温度を知っておくことが大切です。
暖房をつける外気温と時期の目安

暖房をつけるかどうかは、室温だけでなく外気温や季節の変化も重要なポイントになります。一般的に、外気温が15℃を下回ると室温も低下しやすくなり、暖房が必要になることが多いです。
外気温と暖房をつける目安
- 外気温15℃以上:まだ暖房は不要。厚着や日光の活用で快適に過ごせる。
- 外気温10〜15℃:室温が18℃を下回る可能性があり、体感的に寒く感じるため、暖房を検討。
- 外気温5〜10℃:室温が15℃以下になることが多く、健康への影響を考えると暖房を使用するのが望ましい。
- 外気温5℃未満:暖房なしではかなり寒く、低体温症やヒートショックのリスクが高まるため、しっかり暖房を活用する。
暖房を使い始める時期の目安
暖房をつけるタイミングは地域によって異なりますが、一般的には以下のような時期に暖房が必要になります。
- 北海道・東北地方:10月上旬〜4月中旬(朝晩は9月から暖房を使うことも)
- 関東・中部・関西地方:11月上旬〜3月下旬(寒冷地では10月から)
- 九州・四国地方:11月中旬〜3月上旬(比較的温暖なため短期間)
- 沖縄地方:暖房の必要性は低く、真冬でも使用しない家庭が多い
特に朝晩の冷え込みが厳しくなる10月〜11月頃から、暖房を使い始める人が増えてきます。また、4月に入ると暖房を使わなくなる家庭が多いですが、寒冷地ではもう少し長く使う傾向があります。
暖房をつける外気温の目安は10〜15℃以下で、地域や季節によって適切な時期が異なります。室温だけでなく、外気温や体感温度も考慮しながら、無駄なく暖房を活用しましょう。
暖房をつける一般的な基準は「室温18℃以下」

一般的に、室温が18℃を下回ると暖房をつける目安とされています。これは、世界保健機関(WHO)が推奨する最低室温の基準にも基づいています。特に、高齢者や乳幼児がいる家庭では、室温が低すぎると健康リスクが高まるため、最低でも18℃を維持するのが望ましいとされています。
ただし、寒さの感じ方には個人差があるため、すべての人が18℃以下で寒いと感じるわけではありません。服装や湿度によっても体感温度は変わるため、次のポイントを考慮するとよいでしょう。
体感温度は湿度や服装で変わる
同じ気温でも、湿度や服装によって体感温度は異なります。
- 湿度が低いと寒く感じる
- 空気が乾燥すると、体の水分が蒸発しやすくなり、寒さを強く感じます。
- 湿度を40〜60%程度に保つことで、同じ温度でも暖かく感じられます。
- 加湿器を活用するほか、濡れタオルを室内に干すのも効果的です。
- 適切な服装で体感温度を調整
- 室温18℃でも、厚手の靴下やスウェットを着れば十分暖かく感じることがあります。
- 逆に、薄着のままでは室温20℃でも寒く感じることがあります。
- 服を1枚増やすだけで体感温度が約2℃上がると言われています。
暖房器具ごとの適切な温度設定
暖房をつけると決めた場合、使用する暖房器具によって適切な設定温度が異なります。
| 暖房器具 | 推奨温度設定 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| エアコン | 20〜22℃ | 高めに設定すると電気代が増えるため、20℃程度から調整 |
| 石油・ガスファンヒーター | 18〜22℃ | 燃焼による暖房は即効性があるが、換気が必要 |
| こたつ | 低〜中 | 直接体を温めるため、部屋全体を温める必要がない |
| 床暖房 | 25〜28℃ | 部屋全体の暖房には不向きだが、足元からじんわり暖かい |
| 電気毛布 | 35〜45℃ | 部分的に温める用途で節電効果が高い |
エアコンは、設定温度を高くしすぎると電気代がかかるため、20℃前後を目安にし、サーキュレーターや加湿器と併用することで効率よく暖房できます。
暖房をつける適温と健康への影響

暖房の適切な温度設定は、ただ快適に過ごすためだけではなく、健康を守るためにも重要です。室温が低すぎると、風邪をひきやすくなったり、血圧の変動が大きくなったりするため注意が必要です。この章では、暖房をつける適温と、それが健康に与える影響について詳しく解説します。
低すぎる室温が引き起こす健康リスク
暖房を節約しすぎて室温が低くなりすぎると、以下のような健康リスクが発生する可能性があります。
① ヒートショックの危険性(特に高齢者は注意)
室温が10℃以下になると、暖かい部屋との温度差によって血圧が急激に変動し、「ヒートショック」を引き起こすリスクがあります。特にお風呂場やトイレなどは暖房がない場合が多く、寒い部屋から暖かい部屋へ移動する際に血管が急に収縮・拡張し、脳卒中や心筋梗塞のリスクが高まります。
対策:
- 家の中の温度差を少なくする(トイレや脱衣所にも小型暖房を設置)
- 寒い場所に行く前に軽くストレッチをする
② 風邪やインフルエンザにかかりやすくなる
室温が16℃以下になると、体の免疫機能が低下しやすくなります。寒い環境では鼻や喉の粘膜が乾燥しやすくなり、ウイルスに感染しやすくなるため、特に冬場は注意が必要です。
対策:
- 室温を18℃以上に保つ
- 乾燥を防ぐために湿度40〜60%を維持する(加湿器・濡れタオルを活用)
③ 睡眠の質が低下する
寝室の温度が低すぎると、寒くて途中で目が覚めることが増え、睡眠の質が低下する原因になります。特に15℃以下の環境では体が冷えすぎてしまい、リラックスできずに眠りが浅くなる可能性があります。
対策:
- **寝室の温度は16〜19℃**が理想的
- 湯たんぽや電気毛布を活用する
部屋ごとの適切な室温目安
部屋の用途によって、快適に過ごせる適温が異なります。以下の表を参考に、各部屋の暖房設定を調整しましょう。
| 部屋の種類 | 推奨室温 | 補足 |
|---|---|---|
| リビング・ダイニング | 20〜22℃ | 家族が集まる場所なので快適さを優先 |
| 寝室 | 16〜19℃ | 寒すぎると睡眠の質が低下する |
| 子ども部屋 | 18〜20℃ | 風邪予防のため、やや高めが望ましい |
| 浴室・脱衣所 | 18〜20℃ | ヒートショック予防のため、適度に暖める |
| トイレ | 16〜18℃ | ヒートショック対策として、暖房器具を設置するのも有効 |
このように、リビングと寝室では適温が異なるため、同じ設定温度にするのではなく、部屋ごとに調整するのがポイントです。
暖房の適温と省エネのバランス
暖房の温度を上げすぎると、電気代が増えるだけでなく、乾燥しやすくなり健康にも悪影響を及ぼします。そのため、**「快適さ」と「節約」のバランスを取ることが大切」**です。
暖房の温度設定と電気代の関係
エアコンの場合、設定温度を1℃下げるだけで約10%の電気代節約につながると言われています。例えば、エアコンの設定温度を22℃から20℃に下げるだけで、大幅な節約が可能です。
省エネのコツ
- エアコンの温度は20〜22℃に設定し、厚着や加湿で体感温度を上げる
- サーキュレーターや扇風機を使い、暖房の熱を部屋全体に循環させる
- 窓に断熱シートを貼る、カーテンを厚手にするなど、部屋の保温性を高める
暖房を効率よく使う節約術

暖房を使うと、どうしても電気代や燃料代がかかります。しかし、ちょっとした工夫で暖房の効率を上げ、無駄なエネルギー消費を抑えることができます。この章では、暖房を効果的に使うための節約術について詳しく解説します。
窓やドアの断熱対策で暖気を逃がさない
部屋を暖めても、窓やドアの隙間から熱が逃げると暖房の効率が大幅に低下します。特に、室内の熱の約50%は窓から逃げると言われています。以下の対策を行うことで、暖房の効率を大幅に向上させることができます。
① 窓の断熱対策
- 厚手のカーテンを使う
- 冬用の厚手カーテンを使うと、窓からの冷気を遮断できる。
- カーテンの丈は床までしっかり届くものを選ぶとより効果的。
- 断熱シートを貼る
- 窓に貼る透明の断熱シートを使えば、熱の流出を約30〜40%防げる。
- プチプチ(気泡緩衝材)を貼る
- 手軽にできる断熱対策として、窓にプチプチを貼る方法もある。
② ドアや玄関の隙間対策
- すきまテープを貼る
- 玄関や室内ドアの隙間から冷気が入るのを防ぐ。
- 玄関マットを敷く
- 床からの冷気を防ぐため、厚手の玄関マットを使用する。
加湿器を活用して体感温度を上げる
室温が同じでも、湿度を上げると体感温度が高くなり、暖房の設定温度を下げることができます。
湿度と体感温度の関係
- 湿度が20%の場合:体感温度は実際の室温より2〜3℃低く感じる
- 湿度が50%以上の場合:体感温度が上がり、暖房の効率が向上
加湿の方法
- 加湿器を使う(特に超音波式やスチーム式がおすすめ)
- 洗濯物を室内に干す
- 濡れタオルを部屋にかける
- お湯を張った洗面器を部屋に置く
加湿することで乾燥による風邪の予防にもなるため、一石二鳥の節約術です。
エアコンの設定温度とサーキュレーターの併用
① エアコンの設定温度は20℃前後が理想
エアコンの設定温度を22℃以上にすると電気代が増えるため、20℃前後に設定し、他の方法で暖かさを保つのがポイントです。
② サーキュレーターや扇風機で空気を循環させる
暖かい空気は天井にたまりやすいため、サーキュレーターや扇風機を活用すると部屋全体が均一に暖まる。
- サーキュレーターを天井に向けて送風すると、暖気が下に降りてくる
- 扇風機の「弱」モードで部屋の空気をかき混ぜると効果的
- 床付近の寒さを解消できるため、設定温度を下げても快適に過ごせる
省エネ性能の高い暖房器具を選ぶ
暖房器具にはさまざまな種類があり、エネルギー効率の良いものを選ぶことで、電気代を抑えながら快適に過ごせる。
暖房器具別の省エネポイント
| 暖房器具 | 省エネのポイント |
|---|---|
| エアコン | 設定温度を20℃前後にし、サーキュレーターを併用する |
| こたつ | エアコンと併用すると、エアコンの設定温度を下げられる |
| 電気毛布 | 消費電力が非常に少なく、寝室での使用におすすめ |
| オイルヒーター | 断熱対策をしっかりすれば、じんわり暖まるので省エネ効果が高い |
| ガスファンヒーター | 燃費が良く、部屋をすぐに暖められるが、換気が必要 |
電気代を抑えたい場合は、こたつや電気毛布を活用し、エアコンの使用時間を減らすのがポイントです。
暖房費を抑えるための習慣

暖房を効率的に使う工夫をしても、日常の使い方次第で電気代や燃料代は大きく変わります。ここでは、誰でも簡単にできる節約習慣を紹介します。日々のちょっとした工夫を積み重ねることで、暖房費をグッと抑えることができます。
こまめなフィルター掃除で暖房効率アップ
エアコンやファンヒーターのフィルターが汚れていると、暖房効率が低下し、余計な電力を消費してしまいます。
エアコンのフィルター掃除のポイント
- 2週間に1回の掃除が理想的
- 掃除機でホコリを吸い取り、水洗いするだけでOK
- フィルターが汚れていると、電気代が約10%増加すると言われている
ファンヒーターやストーブの掃除
- 吸気口のホコリをこまめに取り除く
- 石油ファンヒーターは定期的にタンクの水抜きをする
- 定期的なメンテナンスで燃費効率を上げる
フィルターを清潔に保つことで、暖房の効率を上げ、余計な電力や燃料の消費を防ぐことができます。
家族全員が同じ部屋で過ごす
暖房費を節約する最も簡単な方法のひとつが、できるだけ家族全員が同じ部屋で過ごすことです。
▼1部屋集中のメリット
- 暖房を使う部屋を1つに絞ると、エネルギー消費が減る
- 家族が集まることで自然な体温上昇が期待できる(人の体温は約37℃あるため、複数人いれば部屋の温度も上がる)
- こたつやホットカーペットを併用すれば、エアコンの設定温度を下げることができる
家族がバラバラに暖房を使うと、各部屋の暖房代が積み重なってしまうため、なるべく1部屋に集まる習慣をつけると暖房費を抑えられるでしょう。
暖房器具を組み合わせて使う
暖房を1種類だけに頼るのではなく、異なる暖房器具を上手に組み合わせることで、省エネと快適さを両立できます。
▼おすすめの暖房器具の組み合わせ
| 組み合わせ | メリット |
|---|---|
| エアコン + こたつ | こたつの熱で下半身を暖めることで、エアコンの設定温度を下げられる |
| ホットカーペット + 電気毛布 | 部屋全体を暖めるのではなく、部分的に暖を取ることで電気代を節約 |
| 石油ストーブ + やかん | 湯を沸かしながら加湿もでき、一石二鳥 |
| こたつ + 湯たんぽ | 極めて省エネで、電気代をほぼかけずに暖まれる |
エアコンだけに頼ると電気代がかさむため、こたつやホットカーペットを併用することで、効率的に暖を取ることができる。
電力会社や契約プランを見直す
最近では、電力自由化によりさまざまな電力会社や料金プランが登場しています。契約内容を見直すだけで、暖房費を削減できる場合があります。
▼電気料金の見直しポイント
- 夜間の電気料金が安いプランを選ぶ(深夜電力プラン)
- 新電力会社に乗り換えることで、年間数千円~数万円の節約になる場合がある
- 「燃料費調整額」や「再エネ賦課金」の影響をチェックし、より安いプランを選択
特にオール電化住宅の場合、夜間の電気料金が安いプランを選ぶことで暖房費を抑えやすくなるため、一度契約内容を確認してみましょう。
ペットがいる家庭での暖房の注意点

寒い季節に暖房を使う際、犬や猫の健康と安全を守るために注意すべきポイントがあります。ペットの適温は18〜22℃、湿度は40〜60%が理想的です。特に乾燥や火傷、低温火傷のリスクに気をつけながら、適切な暖房対策をしましょう。
✅ 室温管理:寒さに弱い犬種や短毛の猫は20〜22℃、寒さに強い犬種や長毛の猫は18〜20℃が目安
✅ 乾燥対策:加湿器を使用し、湿度40〜60%を維持(乾燥は皮膚トラブルや呼吸器への負担に)
✅ 暖房器具の安全対策:ストーブやヒーターは火傷・火事の危険があるため、ガードを設置
✅ ペットが寒がるサイン:震える・丸まる・動きが少なくなる・飼い主の布団に潜るなど
✅ 防寒対策:毛布やペットベッドを用意し、床からの冷気を避ける(犬は防寒服も有効)
✅ 暖房器具の工夫:低温火傷を防ぐため、こたつやペット用ホットマットは適切な温度管理を
ペットが快適に過ごせる環境を整え、暖房を適切に使うことで、健康を守りながら冬を乗り越えましょう。
まとめ
寒い季節に暖房を使う際は、室温18℃以下を目安にしつつ、湿度や服装を工夫して体感温度を上げることが大切です。適切な温度設定として、**リビングは20〜22℃、寝室は16〜19℃**が理想とされています。
また、窓の断熱対策やサーキュレーターの活用で暖房効率を向上させ、エアコンのフィルター掃除や家族全員が同じ部屋で過ごす工夫をすると、暖房費を節約できます。こたつや電気毛布など、省エネ性能の高い暖房器具を組み合わせるのも効果的です。
さらに、電力会社の契約プランを見直すことで、年間の光熱費を抑えることも可能です。これらの工夫を取り入れれば、健康を守りながら快適かつ経済的に冬を乗り越えられます。