「熱り立つ」の意味・読み方や使い方【シーン別30例文】

日々の会話や文章の中で、「怒りがこみ上げてくる」「感情が抑えられない」といった場面に出くわすことはありませんか?そうした感情の高ぶりを表す日本語の中に、「熱り立つ」という表現があります。
この言葉は、日常会話ではあまり聞き慣れないかもしれませんが、文学作品や報道、評論文などでは見かけることがあります。漢字の印象からも強い感情や動きが連想されるこの言葉ですが、実際にはどのような意味や使い方があるのでしょうか?
本記事では、「熱り立つ」の読み方や意味をはじめ、具体的な使い方を30の例文で紹介します。また、語源や類語、英語訳、よくある疑問にも丁寧に答えていきます。読み終えるころには、この表現を自然に使いこなせるようになっていることでしょう。
目次
「熱り立つ」の読み方は「いきりたつ」

「熱り立つ」の読み方は いきりたつ と読みます。
この言葉は比較的珍しい表現であるため、読み方に戸惑う方も多いかもしれません。特に「熱(ねつ)」という漢字の印象から、「ねつりたつ」「あつりたつ」などと誤って読まれることもありますが、正しくは「いきりたつ」です。
「熱り立つ」の意味
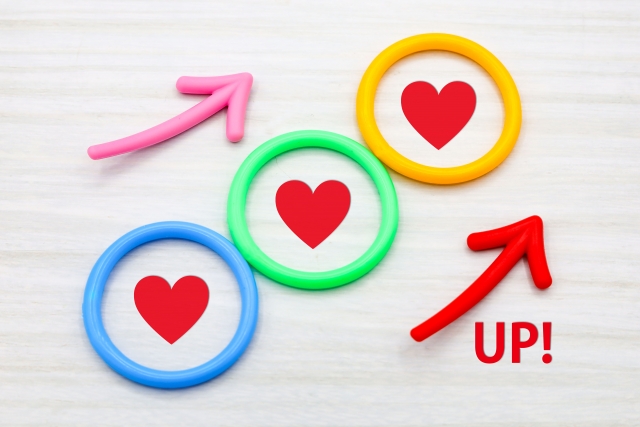
「熱り立つ(いきりたつ)」は、強い感情がこみ上げ、抑えきれずに表に現れてくる状態を表す言葉です。特に「怒り」「苛立ち」「興奮」など、感情が高ぶって精神が昂ぶる様子を表現する際に使われます。
主な意味
- 感情が高ぶること
- 特に怒りや興奮が激しくなり、落ち着いていられない状態。
- 心の内側で感情が“熱を持つ”ように湧き上がってくる様子をイメージすると理解しやすいです。
- 勢い込んで行動すること
- 感情に任せて行動を起こす、気負いすぎてしまう、といったニュアンスも含まれる場合があります。
- たとえば、議論の場で相手の発言に「熱り立って」反論してしまうようなケースです。
どのような感情の時に使う?
「熱り立つ」は、基本的にはネガティブな感情(怒り、苛立ち、緊張など)に使われることが多いですが、文脈によってはポジティブな意味合い(強い熱意、感動、期待など)で使われる場合もあります。
ネガティブな例:
・部下の失敗に熱り立つ上司。
・理不尽な要求に熱り立った彼が、思わず声を荒げた。
ポジティブな例(やや文学的):
・期待に熱り立つ若者の目は輝いていた。
・勝利目前で観客たちが熱り立っている。
「熱り立つ」という言葉には、感情を自分で制御しきれないほど高ぶっている状態というニュアンスが含まれます。そのため、「冷静ではいられない」「感情があふれて抑えがきかない」といった文脈で用いられることが多いです。
シーン別「熱り立つ」の使い方【例文30】

「熱り立つ(いきりたつ)」とは、強い感情や緊張が内側から高まる様子を表す言葉です。職場でのやり取り、会議、日常の人間関係など、現代社会におけるリアルなシーンでの使い方を知っておくと、感情の機微を的確に表現することができます。
①ビジネスシーンでの「熱り立つ」
仕事上での怒りや緊張、議論の白熱など、感情が高ぶる場面です。
| 例文 | 意味 |
|---|---|
| 上司の理不尽な叱責に、思わず熱り立った。 | 怒りの感情がこみ上げてきた。 |
| 会議が紛糾し、出席者たちは次第に熱り立っていった。 | 議論が白熱し感情が高まった。 |
| プレゼン直前、胸が熱り立つのを感じた。 | 緊張と期待で感情が高ぶった。 |
| 商談が難航し、彼の声は徐々に熱り立っていった。 | 焦りと苛立ちが強まった。 |
| 新規プロジェクトに対する熱り立つ思いが、社内を動かした。 | 情熱と意気込みが伝わった。 |
| 競合の成功事例に触れ、チーム全体が熱り立った。 | 負けたくないという闘志が湧いた。 |
②家庭や人間関係シーンでの「熱り立つ」
家庭や友人関係など、感情のぶつかり合いや心の揺れ動きが生じる場面。
| 例文 | 意味 |
|---|---|
| 友人の裏切りに、内心熱り立った。 | 怒りとショックで心が揺れた。 |
| 親子の口論で、父親はすぐに熱り立った。 | 感情が爆発するように高ぶった。 |
| パートナーの一言に、彼女の心は熱り立っていた。 | 傷ついた感情が表に出そうだった。 |
| ご近所トラブルに、住民たちは熱り立った空気に包まれていた。 | 集団の緊張と不満が高まっていた。 |
| 誤解による言い争いで、お互いが熱り立っていた。 | 双方が感情的になっていた。 |
| 兄弟げんかがヒートアップし、二人とも熱り立っていた。 | 感情的な対立が激しくなった。 |
③試験や面接など緊張シーンでの「熱り立つ」
試験、面接、試合など、強いプレッシャーを受ける場面。
| 例文 | 意味 |
|---|---|
| 面接室に入る直前、胸が熱り立った。 | 緊張と不安が混ざった状態。 |
| 試験開始の合図に、頭が熱り立つようだった。 | 緊張で集中しすぎて感覚が高ぶった。 |
| 決勝戦を目前に、選手たちは熱り立っていた。 | 気合と緊張が高まっていた。 |
| 発表会の直前、手が熱り立つほど汗ばんだ。 | 極度の緊張による身体反応。 |
| 面談で想定外の質問をされ、思考が熱り立った。 | 頭が一気に活性化した。 |
| 初舞台に立つ瞬間、体全体が熱り立った。 | 舞台の緊張と高揚感がピークに達した。 |
④スポーツ観戦など集団シーンでの「熱り立つ」
イベント、抗議、試合など、集団が感情で一体化する場面。
| 例文 | 意味 |
|---|---|
| 観客の声援で、スタジアムは熱り立っていた。 | 興奮で一体感が生まれていた。 |
| デモ現場で、群衆が怒りに熱り立っていた。 | 多くの人が強い感情を共有していた。 |
| ライブの開演とともに、会場が熱り立った。 | 興奮と歓声が一気に高まった。 |
| 会議室の緊張が熱り立ち、誰もが沈黙した。 | 空気が張り詰めていた。 |
| 応援合戦が始まり、会場全体が熱り立った。 | 応援熱が高まって盛り上がった。 |
| 授業中の発表に対し、クラスの空気が熱り立った。 | 皆が注目し、緊張感が漂った。 |
⑤身体的な表現シーンでの「熱り立つ」
身体の感覚や心理の内面を比喩的に表現する使い方。
| 例文 | 意味 |
|---|---|
| 恥ずかしさで顔が熱り立った。 | 顔が火照るように赤くなった。 |
| 胸の奥が熱り立つような感情に包まれた。 | 心の中で情熱が湧いた。 |
| 傷口が熱り立ってきた。 | 痛みや熱さを強く感じるようになった。 |
| 緊張で背中が熱り立った。 | 身体が強張るような感覚になった。 |
| 心拍数が上がり、体が熱り立っていた。 | 興奮状態で身体が反応していた。 |
| 驚きのあまり、手のひらが熱り立った。 | 驚きによる生理的反応。 |
「熱り立つ」の語源

「熱り立つ(いきりたつ)」は、日本語の古語表現を基にした複合語で、その語源には深い意味と歴史的背景があります。言葉の成り立ちを理解することで、そのニュアンスや使いどころがより明確になります。
「熱り(いきり)」の語源
「熱り(いきり)」の元となる動詞は、「熱る(いきる)」で、これは古語に由来します。この「いきる」は、以下のような意味を持っていました。
- 気持ちが高ぶる
- 怒る、立腹する
- 感情が盛んになる
この「いきる」は、『源氏物語』や『枕草子』といった古典文学の中にも見られる言葉で、感情の激しさや高まりを表現するのに使われていました。現代語の「怒る」や「興奮する」に相当する意味です。
「立つ」の意味と役割
「立つ」は現代でも使われる言葉ですが、「熱り立つ」の場合は、感情が表に現れる、立ち上がる、外に向かって噴き出すというニュアンスを強調します。
つまり、「熱り(=内にある熱い感情)」が「立つ(=外に現れる)」ことで、「熱り立つ」となり、
抑えていた感情が急激に表に出てきて、高ぶった状態になる
という意味を形成しているのです。
語源のまとめ
- 「熱り」= 古語「いきる」= 怒り・感情の高ぶり
- 「立つ」= 外に立ち現れる、行動に表れる
- 合わせて、「感情がこみ上げてくる様子」や「抑えられない内なる熱情」が表現される。
このように、語源を知ることで、「熱り立つ」が単なる怒りだけでなく、感情の爆発的な高まりを幅広く表す言葉であることがわかります。
「熱り立つ」の類語(言い換え)

「熱り立つ(いきりたつ)」は、感情が高ぶって抑えきれなくなる状態を表す言葉ですが、日本語にはこのような感情の動きを表す表現が数多くあります。この章では、「熱り立つ」と意味が近い類語(言い換え表現)を紹介し、それぞれの微妙なニュアンスの違いや使い分けについても解説します。
怒る(おこる)
- 意味:不快なことに対して腹を立てる。
- 違い:「怒る」は感情の状態を単純に表すのに対し、「熱り立つ」はその感情が急に高まり、表に出てくる様子を強調。
- 使い分け例:
- 「彼は怒った。」(ただ怒っている状態)
- 「彼は熱り立って、机を叩いた。」(感情が抑えきれず爆発した様子)
苛立つ(いらだつ)
- 意味:思い通りにいかず、焦りや不満で落ち着かなくなる。
- 違い:「苛立つ」は比較的静かな不快感や焦燥感に焦点があり、「熱り立つ」はより爆発的で外向的な感情表現。
- 使い分け例:
- 「列に並んでいる間、彼は苛立っていた。」
- 「順番を抜かされて、彼は熱り立った。」
激昂する(げっこうする)
- 意味:感情が高ぶり、非常に怒ること。
- 違い:「熱り立つ」と近い意味だが、「激昂する」はやや文語的・硬い表現で、ニュースや文学的な文脈に向いている。
- 使い分け例:
- 「選手は判定に激昂した。」(強く怒る)
- 「選手は熱り立ち、審判に詰め寄った。」(行動を含んだ感情の爆発)
興奮する(こうふんする)
- 意味:感情が高ぶって落ち着かなくなる。喜び・怒り・緊張など幅広い感情に使える。
- 違い:「興奮する」はポジティブにもネガティブにも使えるが、「熱り立つ」はやや怒り・不満系に寄りがち。
- 使い分け例:
- 「観客は試合に興奮していた。」(中立的・広い感情)
- 「観客は判定に熱り立ち、ブーイングを始めた。」(怒りの感情)
逆上する(ぎゃくじょうする)
- 意味:極度の怒り・動揺によって理性を失うこと。
- 違い:「熱り立つ」は感情が高ぶる過程を描写することが多いが、「逆上」はすでに理性が失われた状態を示す。
- 使い分け例:
- 「犯人は逆上し、手に負えない状態だった。」
- 「彼は熱り立ったが、かろうじて冷静さを保った。」
※日常的な言い換え表現
- 「カッとなる」
- 「ムキになる」
- 「感情が爆発する」
- 「怒りをあらわにする」
これらは口語的・くだけた表現で、会話やSNSなどカジュアルな場面で使いやすい言い換えになります。
「熱り立つ」の英語

「熱り立つ(いきりたつ)」という日本語は、強い感情が高まり、内から外にあふれ出すような状態を表しますが、この感覚をそのまま英語に直訳するのは難しいこともあります。しかし、文脈に応じた適切な英訳を選ぶことで、意味を正確に伝えることが可能です。
以下に、よく使われる英語表現とその使い分けを紹介します。
get worked up(感情的になる)
- 意味:緊張・怒り・興奮などで感情的になる。
- ニュアンス:「熱り立つ」とかなり近い。内面の感情が抑えきれなくなり、言動に出てくる様子。
- 例文:
- He got worked up over a small misunderstanding.
(彼はちょっとした誤解に熱り立った。)
- He got worked up over a small misunderstanding.
get heated(熱くなる/口論になる)
- 意味:議論や感情がヒートアップする。
- ニュアンス:やや中立的。感情の高ぶりを示すが、怒りや情熱、白熱した議論などにも使える。
- 例文:
- The debate got heated quickly.
(議論はすぐに熱り立った/白熱した。)
- The debate got heated quickly.
flare up(感情が爆発する、突然怒る)
- 意味:感情が急に爆発的に表に出る。
- ニュアンス:「突然」「激しく」怒るという点で、「熱り立つ」の一部の用法に近い。
- 例文:
- He flared up when he heard the news.
(その知らせを聞いて彼は熱り立った。)
- He flared up when he heard the news.
fly off the handle(かっとなる、突然怒る)
- 意味:感情がコントロールできなくなり、急に怒り出す。
- ニュアンス:口語的。やや突発的でコミカルな印象もあるため、フォーマルな場にはやや不向き。
- 例文:
- She flew off the handle during the meeting.
(彼女は会議中に熱り立って怒り出した。)
- She flew off the handle during the meeting.
become agitated(動揺する/興奮する)
- 意味:感情的になり、落ち着きを失う。
- ニュアンス:不安や緊張が入り混じった「熱り立つ」に近い状態。
- 例文:
- He became visibly agitated as the argument continued.
(議論が続く中、彼は目に見えて熱り立っていった。)
- He became visibly agitated as the argument continued.
よくある質問

ここでは、「熱り立つ(いきりたつ)」に関して読者の方からよく寄せられる疑問や誤解を、Q&A形式で分かりやすく解説します。
Q1. 「熱り立つ」はポジティブな意味でも使えますか?
A. 基本的にはネガティブな感情に使われることが多いですが、文脈によってはポジティブにも使えます。
例えば、「期待に胸が熱り立つ」「熱り立つような感動」といった表現では、嬉しさや興奮、希望に満ちた気持ちを表すこともできます。ただし、一般的には怒りや苛立ちといった負の感情の高ぶりを示す場面で使われることが多いため、注意が必要です。
Q2. 「熱り立つ」と「怒る」の違いは何ですか?
A. 「怒る」は感情の状態を表す言葉、「熱り立つ」は感情が急激に高まって行動や言動に現れる様子を表します。
つまり、「怒る」は静的な感情の説明に使われるのに対し、「熱り立つ」はその感情が抑えきれず表に現れる動的なプロセスを強調する言葉です。
Q3. ビジネスシーンでも使えますか?
A. 基本的には文章や報告書、スピーチなどの文語的な表現に向いています。口語ではやや堅い印象があります。
会議の議事録やプレゼン資料などで、「担当者が熱り立った様子を見せた」「顧客の反応にチームが熱り立った」といった使い方は可能ですが、会話では「感情的になっていた」「興奮していた」などの表現のほうが自然です。
Q4. 「熱り立つ」の漢字の由来や成り立ちは?
A. 「熱り(いきり)」は、古語「熱る(いきる)」から派生した言葉で、感情が高ぶる様子を表します。「立つ」はそれが表に現れる様子を指します。
このように、漢字の選び方にも意味が込められており、「熱=内なる感情の熱さ」、「立つ=現れる・噴き出す」という組み合わせによって、感情の動きが視覚的にも伝わる表現になっています。
Q5. 「熱り立つ」を使う際の注意点はありますか?
A. 感情的な表現なので、使用する場面や相手に配慮が必要です。
特にビジネスや目上の人に対する言及では、冷静な表現を心がけるのが無難です。また、「熱り立った態度」や「熱り立つような口調」は、相手を非難するような意味合いになることもあるため、慎重に使いましょう。
まとめ
「熱り立つ(いきりたつ)」という言葉は、日常会話ではあまり頻繁に使われるものではありませんが、文学作品や評論、ビジネス文書など、ややフォーマルな文脈では印象的な表現として用いられます。
この言葉の最大の特徴は、感情が内側から激しく高まり、それが外に現れる様子を生き生きと描写できる点にあります。特に怒りや苛立ち、興奮などの強い感情を、単に「怒る」や「イライラする」といった言葉よりも、より動的かつ感情の振れ幅が伝わる形で表現できます。
読み方は「いきりたつ」とやや難解ですが、語源をたどれば「熱る(いきる)」という古語と「立つ」の組み合わせから成り立っており、言葉の成り立ち自体が感情の爆発的な高ぶりをよく表しています。
本記事では、「熱り立つ」の意味や使い方を30の具体例を交えて紹介し、語源、類語、英語訳、さらにはよくある疑問点まで幅広く取り上げてきました。これらを通して、「熱り立つ」という表現の幅広さと奥深さをご理解いただけたのではないでしょうか。
今後、感情の機微を丁寧に伝えたいときや、文章に少し格調を持たせたいときには、「熱り立つ」という言葉を選択肢のひとつとして、ぜひ活用してみてください。使いこなせば、あなたの表現力が一段と豊かになるはずです。




