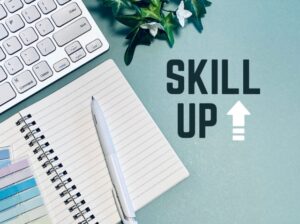「かわいそう」の漢字は「可哀想」「可愛そう」どっち?違いを解説!

「かわいそう」という言葉は、私たちの日常会話の中で頻繁に使われる表現の一つです。友人がつらい目にあっている時、テレビで悲しいニュースを見た時、あるいは動物の保護活動に触れた時など、同情や哀れみの気持ちを込めて「かわいそう」とつぶやくことがあるでしょう。
しかし、この「かわいそう」という言葉を漢字で書こうとしたとき、多くの人が「可哀想」なのか「可愛そう」なのかで迷います。どちらも見かけたことがあるし、意味も似ているように思える。けれど、どちらが正しい表記なのか、そもそもどう違うのか、説明できる人は少ないかもしれません。
本記事では、「かわいそう」の正しい漢字表記について詳しく解説するとともに、その語源や意味の変遷、使い分け方、さらには例文を交えて、より深く理解できるようにご紹介します。迷ったときに役立つ「ひらがな表記」の活用法や、よくある質問にもお答えしますので、最後までお読みいただければ、言葉の使い方に自信が持てるようになるでしょう。
目次
「可哀想」「可愛そう」どっちが正解?

「かわいそう」と漢字で書く場合、一般的に見かけるのは「可哀想」と「可愛そう」の2通りです。どちらも同じ読み方(かわいそう)をしますが、意味や使われ方に違いがあるのでしょうか?この章では、それぞれの表記の特徴と、どちらが「正しい」とされているのかを解説します。
「可哀想」は辞書にも載っている正式な表記
「可哀想」は、現代日本語においてもっとも一般的で標準的な表記とされています。新聞や雑誌、書籍、公的な文書などでは、ほとんどがこの「可哀想」を使用しています。
この表記は以下のように分解できます:
- 「可」:〜することができる
- 「哀」:あわれみ、悲しみ
- 「想」:思う、感じる
つまり「可哀想」は、「哀れに思うことができる=同情できるほど気の毒」という意味合いになります。
「可愛そう」も間違いではない
一方で、「可愛そう」という表記も完全に誤りとは言えません。実際に小説やエッセイなど、やや感情的・文学的な文脈で使われることがあります。「可愛い(かわいい)」という語に由来しているため、対象に対する「愛しさ」や「守ってあげたい気持ち」が強調される印象があります。
ただし、「可愛そう」は辞書にはあまり掲載されておらず、学校教育や公的な文書では推奨されません。あくまで感情的なニュアンスを込めた自由表現として理解されるべき表記です。
どちらを使うべき?
- 公的・標準的な文書や日常の文章では「可哀想」
- 感情を込めたカジュアルな表現や個人の文章では「可愛そう」も可
- 迷ったらひらがな「かわいそう」が無難
このように、「可哀想」と「可愛そう」は使う場面によって選ぶことができますが、原則として「可哀想」が正しい表記であり、「可愛そう」は補助的な感情表現と考えるのが良いでしょう。
「かわいそう」の背景とは

「かわいそう」という言葉は、現代では「気の毒」「不憫(ふびん)」といった意味で使われていますが、その背景には日本語の歴史的な変化と深い感情の流れがあります。この章では、「かわいそう」という言葉がどのように生まれ、意味がどのように変わってきたのかを見ていきましょう。
古語「かはゆし」が語源
「かわいそう」の語源は、古語の「かはゆし(嬰し)」です。「かはゆし」とは、「見ていられないほど気の毒」「つらくて目をそむけたくなるような様子」を意味する言葉でした。中世や古典文学の中でも使われており、人の不幸や弱さに対して抱く同情の気持ちを表していました。
「かはゆし」から「かわいい」へ、そして「かわいそう」へ
「かはゆし」はやがて、「気の毒」という意味だけでなく、「いとおしい」「心が引かれる」といった感情も含むようになります。この感情の変化とともに、「かはゆし」は「かわゆし」→「かわいい」へと音変化を経て、現在の「かわいい」という言葉が生まれました。
現代の「かわいい」は「愛らしい」「見た目が魅力的」「守ってあげたい存在」といったポジティブな意味で使われますが、その根底には「弱さ」や「はかなさ」に対する同情や庇護(ひご)したい感情が存在しています。
このように、「かわいそう」は「かわいい」と深くつながっており、
- かわいい → 愛らしい存在
- かわいそう → 愛らしくて気の毒な存在
という構造が見えてきます。
感情の原点は「気の毒」
つまり、「かわいそう」という言葉には、
- 相手の境遇に対する悲しみや同情
- 弱いものに対して抱く保護本能や愛情
といった、複雑で人間的な感情が込められているのです。「かわいそう」という表現が、単なる「不憫さ」だけでなく、相手に対する思いやりや優しさも含んでいるのは、こうした歴史的な背景があるからです。
「可哀想」と「可愛そう」正しい使い方と使い分け、例文

「可哀想」と「可愛そう」は、いずれも「かわいそう」と読む言葉ですが、前の章で説明したとおり、表記によって微妙なニュアンスや使われる場面に違いがあります。この章では、それぞれの使い方のポイントと、実際の例文を通して、より適切な表現の選び方を解説します。
「可哀想」:もっとも一般的で標準的な表記
「可哀想」は、辞書や公式文書、新聞・書籍など、標準的な日本語表記として広く使われています。「哀(あわれむ)」という漢字が含まれており、相手の不幸やつらい状況に対して同情や憐れみの感情を表す言葉です。
使う場面の例:
- 公的な文章やビジネス文書
- 教科書や新聞など、標準的な日本語が求められる場面
- フォーマルな手紙や説明文
例文:
- 戦争で家族を失った子どもたちは本当に可哀想だ。
- あの事故はとても可哀想な出来事だった。
「可愛そう」:感情的な表現として理解される
「可愛そう」は「可愛い」という感情表現に由来し、辞書にはあまり載っていませんが、完全な誤用というわけではありません。小説やエッセイ、詩などの表現の自由が重視される文章では、あえてこの表記を使うことで、相手に対する「いとおしさ」や「庇護したい気持ち」を強調することがあります。
使う場面の例:
- 感情表現を重視した文章(エッセイ・小説・ブログなど)
- 子どもや動物への感情を込めた言い回し
- SNSや日常会話での柔らかい印象を出したいとき
例文:
- 捨てられた子犬が可愛そうで、見ていられなかった。
- 迷子になって泣いている女の子が、可愛そうで胸が痛くなった。
まとめ:使い分けのポイント
| 表記 | 読み方 | 主な意味 | 推奨される場面 |
|---|---|---|---|
| 可哀想 | かわいそう | 同情・あわれみ | 公式文書、学校、一般文章など |
| 可愛そう | かわいそう | 愛しさ+気の毒な気持ち | 感情表現が重視される文芸など |
| ひらがな表記 | かわいそう | どちらにも使える柔らかい表現 | SNS、会話文、迷ったとき |
迷ったら「かわいそう」とひらがな表記がおすすめ

「可哀想」と「可愛そう」、どちらを使うべきか悩んだ経験はありませんか?
漢字表記にはそれぞれ意味やニュアンスがありますが、どうしても迷ってしまう場合や、どちらが適切か判断がつかないときには、ひらがなで「かわいそう」と書くのが最も無難でおすすめです。
なぜひらがな表記が良いのか?
1. 読みやすく、やわらかい印象になる
ひらがなは視覚的にも柔らかく、読者にやさしい印象を与える表記です。特にウェブ記事やブログ、SNSのようなライトな読み物では、漢字よりも感情的な距離が近く、共感されやすいという特徴があります。
2. 漢字の誤解や誤用を避けられる
「可哀想」と「可愛そう」にはそれぞれ背景や意味の違いがあるため、使い分けに注意が必要です。しかし、誤って漢字表記を選んでしまうと、「間違った表現だ」と受け取られてしまうリスクもあります。ひらがなであれば、そうした誤解を避けることができます。
3. 教育現場や子ども向けの文章でも一般的
子ども向けの絵本や教材、初等教育の現場では、読みやすさを重視して「かわいそう」とひらがなで表記されることが多いです。これは学びやすさと、理解しやすさを優先した結果といえます。
例:ひらがなで書くとこうなる
- 彼の話を聞いて、とてもかわいそうに思った。
- 事故でケガをした猫がかわいそうだったので、すぐに動物病院へ連れて行った。
このように、読み手に寄り添ったやさしい文章にしたいときや、表現のニュアンスにこだわらずスムーズに読み進めてもらいたいときには、「かわいそう」とひらがなで書くのがベストな選択です。
よくある質問

「かわいそう」の表記に関しては、日常の中でふと疑問に思うことがいくつかあります。この章では、特に多く寄せられる質問とその答えをまとめました。
Q1. 「可哀相」と「可哀想」はどちらが正しい?
A:どちらも意味は同じで、使われることがありますが、「可哀想」の方が現在は主流です。
「可哀相(かあいそう)」という表記は、以前は使われていましたが、現代では「想う」の意味を持つ**「想」**を使った「可哀想」がより一般的で、辞書などにもこの表記で掲載されています。
ただし、「可哀相」も古い小説や一部の文芸作品では見かけることがあり、完全に間違いというわけではありません。文体や時代背景によって選ばれることがあります。
Q2. 学校ではどちらを習うの?
A:学校では基本的に「かわいそう」とひらがなで習います。
小学校や中学校の国語の授業では、難読や表記揺れを避けるため、基本的に「かわいそう」とひらがなで教えられます。これは学習指導要領でも、児童が理解しやすい表記を優先するという方針によるものです。
そのため、学生が作文や読書感想文などに「可哀想」と書くことは少なく、教師からも特に推奨されていない場合が多いです。
Q3. 「かわいそう」と言うのは失礼になることがある?
A:使い方によっては、相手にとって不快に感じる場合もあります。
「かわいそう」という言葉は、相手を見下したように受け取られることもあるため、使い方には配慮が必要です。特に、本人が前向きに頑張っているときに「かわいそうだね」と言ってしまうと、同情されていると感じて不快に思うことがあります。
例:避けた方がよい場面
- 病気と闘っている人に「かわいそう」と言う
- 努力して結果を出した人に「そんなに頑張っててかわいそう」と言う
代わりに、
- 「大変だったね」
- 「よく頑張ったね」
といった、相手を尊重する言葉を選ぶと、より丁寧で思いやりのある印象になります。
まとめ

「かわいそう」という言葉は、日常のさまざまな場面で使われる非常に身近な表現ですが、漢字で書こうとすると「可哀想」か「可愛そう」かで迷ってしまうことがあります。
結論から言えば、「可哀想」が辞書にも掲載されている正しい表記であり、公的な文書や一般的な文章ではこちらを使うのが基本です。一方で、「可愛そう」も感情的な表現として用いられることがあり、完全な誤用とは言い切れません。特に、かわいらしさや守ってあげたい気持ちを強調したいときには、文芸的な表現として使用されることもあります。
また、「かわいそう」という言葉は、古語「かはゆし」にルーツがあり、もともとは「気の毒」「見ていられない」といった感情から生まれたものです。その意味の変遷の中で「かわいい」という言葉が派生し、やがて「かわいそう」という表現が形成されていった歴史的背景があります。
迷ったときや、使い分けに悩んだときは、ひらがなで「かわいそう」と表記するのが最も無難で、読み手にもやさしい印象を与えられます。とくにブログ、SNS、会話調の文章では、ひらがなの使用が自然です。
最後に、「かわいそう」は便利な表現である一方、使い方によっては相手を傷つけることもあるため、相手の気持ちに寄り添った適切な言葉選びが大切です。