「継る」の読み方「繋がる」との違い|意味・使い方・例文付き

「継る(つぐ)」と「繋がる(つながる)」──この2つの言葉、一見すると似ているように見えますが、実は意味も使い方もまったく異なります。特に文章を書くときや、話し言葉として使う際に混同してしまうと、文脈が伝わりにくくなることもあるため、正しく理解して使い分けることが重要です。
本記事では、「継る」という言葉は本当に存在するのか、どのように読んでどう使うのか、そして「繋がる」とはどう違うのかを、例文を交えながら丁寧に解説していきます。現代の日本語でよく使われる「繋がる」と、やや古風で見かける機会の少ない「継る」。この2語をしっかりと区別して使いこなせるようになれば、あなたの日本語表現力はぐっとレベルアップします。
「言葉の違いをなんとなくで済ませたくない」「文章表現をもっと正確に、豊かにしたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
目次
「継る」という言葉は存在する?読み方は?

結論から言うと、「継る」という言葉は日本語としては存在しません。正しくは、「継ぐ(つぐ)」です。
「継る」という表記は誤用
「継る(つぐ)」という表記は、時々見かけることがありますが、これは誤表記または誤変換によるものです。パソコンやスマートフォンで「つぐ」と入力して漢字変換をした際に、「継る」が候補として出ることがありますが、これは正しい日本語ではありません。
正式には、「継ぐ(つぐ)」という動詞が正解です。
「継ぐ(つぐ)」が正しい言葉
「継ぐ(つぐ)」は、以下のような意味を持つ日本語の動詞です:
- 後を受けて続ける(例:家業を継ぐ)
- 切れたものをつなぐ(例:言葉を継ぐ)
- 欠けたところを補う(例:布を継ぐ)
文法的には五段活用の動詞で、現代日本語で広く使われています。
つまり、「継る」という表現は誤りであり、正しくは「継ぐ(つぐ)」と書くべきです。
「継る」の意味と使い方

「継る」という言葉はないので、「継ぐ」の意味と使い方を解説します。
「継る(つぐ)」という表記は、一般的な日本語としては存在しません。これは誤変換や誤記として使われることがあるだけで、正式には「継ぐ」と書きます。ここでは、正しい形である「継ぐ」の意味と使い方を紹介します。
「継ぐ」の意味
「継ぐ」は、日本語の基本的な動詞のひとつで、以下のような意味があります:
- 引き継ぐ・受け継ぐ
例:家業を継ぐ、志を継ぐ、伝統を継ぐ
→ 前の人や世代から責任や役目、考えなどを引き受けて続けること。 - つなげる・接ぎ合わせる
例:着物を継ぐ、布を継ぐ、文章を継ぐ
→ 物理的に何かをつなぎ合わせたり、途中で切れたものを再びつなぐこと。 - 補う・修復する
例:破れを継ぐ、欠けた部分を継ぐ
→ 不足している部分を補い、全体として元の形を保つこと。
文法的な使い方
「継ぐ」は五段活用の動詞で、活用例は以下のとおりです:
- 現在形:継ぐ
- 過去形:継いだ
- 連用形:継いで、継ぎます
- 仮定形:継げば
- 命令形:継げ
使い方のコツ
- 「継ぐ」は、形あるものにも、形のないもの(意志・文化など)にも使える便利な動詞です。
- 「繋ぐ」と意味が近いようで、実は「継承」「補修」などのニュアンスが強い点が違いとなります。
「繋がる」の読み方

「繋がる」という言葉は、現代日本語で非常によく使われる表現です。スマートフォン、インターネット、ビジネス、日常会話など、幅広い場面で登場します。
読み方は「つながる」
「繋がる」の読み方は「つながる」です。
この言葉は動詞「繋がる」の基本形であり、自動詞(=動作の対象がない動詞)です。「~が繋がる」というように、主語に対して状態や動きが発生します。
例:
- 電話が繋がる
- 人と人とが繋がる
- インターネットに繋がる
類似語との混同に注意
「つなぐ」という他動詞(~をつなぐ)もよく似た言葉ですが、これは「繋ぐ」と書きます。
- 「繋がる」→ 自動詞:状態が成立する(例:心が繋がる)
- 「繋ぐ」→ 他動詞:何かを結びつける動作(例:手を繋ぐ)
文法的な使い方が異なるので、書く際にはどちらが適切かを注意深く見極める必要があります。
「繋がる」の意味と使い方

「繋がる(つながる)」は、物理的・心理的な「つながり」や「関係性」を表す自動詞です。現代社会では、人間関係からネットワーク通信まで、あらゆる場面で頻繁に使われています。
「繋がる」の主な意味
- 物理的につながっている
- 例:この道は駅まで繋がっている。
- → 道や電線など、実体のあるものが連続している様子。
- 人と人、心と心がつながる
- 例:彼とは深いところで繋がっている気がする。
- → 心理的な関係や信頼感、絆の存在を表す。
- 通信やネットワークが接続される
- 例:Wi-Fiが繋がらない、電話がやっと繋がった。
- → テクノロジー関連でも使われ、通信状態を表す言葉として定着。
- 結果や影響として続いていく
- 例:今回の成功が次のチャンスに繋がる。
- → 原因と結果の関係を表す。抽象的な「つながり」。
使い方の特徴
- 自動詞であるため、主語に対して自然に状態が生じるような表現になります。
- 文語・口語どちらでも使用可能で、フォーマルな文書からカジュアルな会話まで幅広く対応。
- 抽象的な関係性や感情を表現する際に、柔らかく、かつ深い意味を持たせることができる便利な語彙です。
現代的な使われ方
近年では、SNSの普及などにより「人と人とのつながり」が以前にも増して意識されるようになり、以下のような表現も一般化しています:
- 「世界中の人と繋がれる時代」
- 「フォロワーと繋がる」
- 「リアルに繋がる」
こうした用法から、「繋がる」は単なる接続だけでなく、「関係の深さ」や「共感」といった感情的な側面を含む言葉として、広く受け入れられています。
継ると繋がるの違いを超わかりやすく

ここまでで、「継る」という言葉は実際には存在せず、正しくは「継ぐ(つぐ)」であること、そして「繋がる(つながる)」とは別の意味を持つことがわかりました。
この章では、「継ぐ」と「繋がる」の違いを超わかりやすく、ポイントを整理しながら説明していきます。
結論:両者の違いは「関係性」と「動作の目的」にあり!
| 項目 | 継ぐ(つぐ) | 繋がる(つながる) |
|---|---|---|
| 品詞 | 動詞(他動詞) | 動詞(自動詞) |
| 主な意味 | 引き継ぐ・受け継ぐ・補う | 接続される・関係ができる |
| 使い方 | 誰かが何かを「継ぐ」(能動的) | 自然に・状態として「繋がる」(受動的) |
| 使用例 | 事業を継ぐ、伝統を継ぐ | 人と人が繋がる、ネットが繋がる |
| 抽象性 | やや堅め・フォーマル | 幅広く、日常的・抽象的な表現が多い |
| 感情的な意味 | 弱い(論理的・実務的な文脈) | 強い(絆・共感・一体感を含むことが多い) |
わかりやすく言うと…
- 「継ぐ」は、誰かから何かを“引き受ける”動作。主に「責任」「意志」「仕事」など、連続性のある行動に使います。
- 例:祖父の代からの農業を継ぐ。
- 「繋がる」は、自然に“関係や接続が成立する”状態を表します。通信、人間関係、抽象的な感情にもよく使われます。
- 例:遠く離れていても心は繋がっている。
間違えやすいパターンに注意!
- 誤:「父の事業に繋がる」→ 正:「父の事業を継ぐ」
- 誤:「想いを繋がる」→ 正:「想いを継ぐ」または「想いが繋がる」(文脈により)
継ると繋がるの使い分け

「継ぐ(つぐ)」と「繋がる(つながる)」は、語感や印象が似ているため混同しやすい言葉ですが、使い分けのポイントを押さえれば、正しく自然に使えるようになります。
ここでは、よくあるシチュエーション別に、「どちらを使うべきか?」を具体的に解説します。
使い分けポイント①:能動的か、受動的か
- 継ぐは自分の意志で何かを受け継ぐ「能動的な行動」
- 繋がるは自然とつながりができる「状態の変化」や「結果」
✅例:
- 父の跡を継ぐ(→ 自分が意志を持って受け継ぐ)
- 二人の心が繋がる(→ 自然に関係ができていく)
使い分けポイント②:「引き継ぎ」か「関係の成立」か
- 継ぐ=後を受けて続ける、補う、継承する
- 繋がる=物や人が結びつく、関係がつく、通信などが接続される
✅例:
- 会社の経営を継ぐ(← 父や上司から引き継いだもの)
- インターネットが繋がる(← 自然に接続が成立する)
使い分けポイント③:感情・精神面は「繋がる」
- 人との絆、気持ちの共鳴、心の交流といった、感情的・抽象的な「関係」は繋がるを使います。
✅例:
- 離れていても心は繋がっている
- 同じ夢を持つ者同士が繋がる
使い分けに迷ったら?
以下のように考えると判断がしやすくなります:
- 誰かから何かを受け取って引き継ぐ → ✅「継ぐ」
- 人やモノが関係性を持つ、接続する → ✅「繋がる」
「継る」の例文【10選】
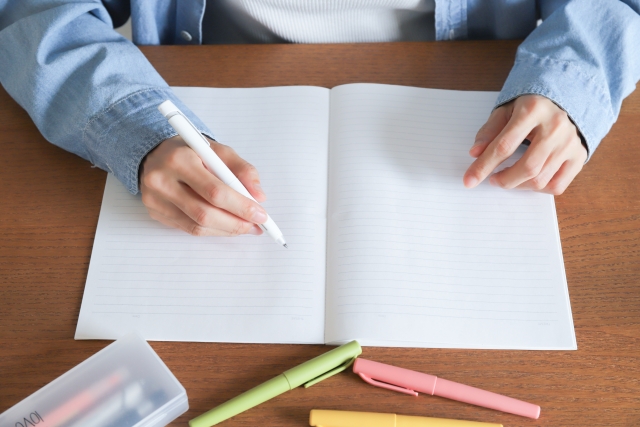
※「継る」という言葉は存在しないため、ここでは正しい表記である「継ぐ(つぐ)」を使った例文を10個紹介します。
「継ぐ」は主に、何かを受け継ぐ・引き継ぐ・補うという意味で使われる他動詞です。ビジネスや家族関係、文化継承など、幅広い文脈で使われます。
- 父の跡を継いで、老舗旅館の女将になった。
- 彼は亡き師匠の技術と精神を継ぐべく、修行を続けている。
- 次期社長として、会社の経営を継ぐことが決まった。
- 代々受け継がれてきた刀を、私が継ぐことになった。
- 地元の祭りを次の世代へ継ぐために、若者たちが集まった。
- 中断された議論を彼がうまく継いだことで、会議が円滑に進んだ。
- 家系図を調べて、誰が血筋を継いでいるのかが明らかになった。
- 古い着物を継いで、新しい服に仕立て直した。
- 彼女は母の意志を継ぎ、看護師の道を選んだ。
- 大切な伝統をただ守るだけでなく、未来へと継いでいくことが重要だ。
「繋がる」の例文【10選】
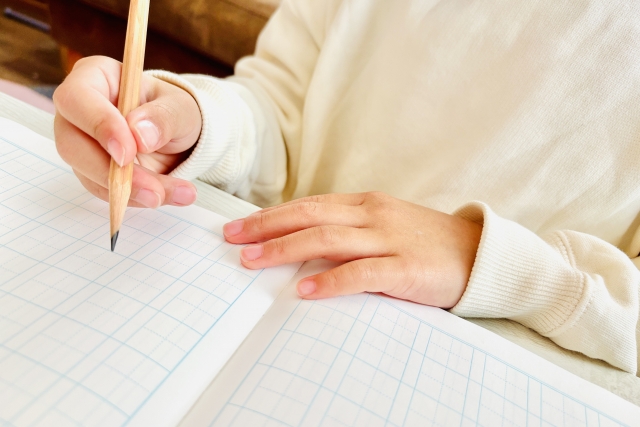
「繋がる(つながる)」は、人・モノ・情報・感情などが関係や連続性を持つことを表す自動詞です。現代の会話や文章では非常に頻繁に登場し、物理的な接続から精神的な絆まで、幅広く使われます。
- 地震の影響で、電話がなかなか繋がらなかった。
- この道は、裏通りを通って商店街に繋がっている。
- 久しぶりに幼なじみとSNSで繋がることができた。
- 彼の言葉が私の心に深く繋がった。
- 国と国が文化を通して繋がる時代になった。
- インターネットがやっと繋がったので、仕事ができるようになった。
- あの経験が、今の仕事に繋がっていると感じる。
- 新しい出会いが、新たな可能性へと繋がることもある。
- 共通の趣味を通じて、多くの人と繋がった。
- どんなに離れていても、心はいつも繋がっているよ。
これらの例文からもわかるように、「繋がる」は接続・関係・影響・共感など、様々な文脈で活用できる柔軟な言葉です。人間関係や情報の流れを表す現代語として、特に重宝されています。
間違えやすい例文【10選】

「継ぐ(つぐ)」と「繋がる(つながる)」は、意味が異なるにもかかわらず、語感やニュアンスが似ているため混同されやすい言葉です。ここでは、「間違えやすい使用例」とその「正しい表現」を対比形式で10例ご紹介し、理解を深めていきます。
| ❌ 間違った表現 | ✅ 正しい表現 | 解説 |
|---|---|---|
| 志を繋ぐ | 志を継ぐ | 「志」は誰かの意志を引き継ぐものなので「継ぐ」が正しい。 |
| 父の跡を繋いだ | 父の跡を継いだ | 家業や役職を受け継ぐときは「継ぐ」を使う。 |
| 意志が代々繋がっている | 意志が代々継がれている | 「継承されている」意味合いなら「継ぐ」が適切。 |
| 電話が継がらない | 電話が繋がらない | 通信・接続の状態は「繋がる」が正しい。 |
| 人との縁を継ぐ | 人との縁が繋がる | 人間関係の自然な成立やつながりには「繋がる」が合う。 |
| 会話を繋いでみた | 会話を継いでみた | 一度途切れた会話を続けるのは「継ぐ」。 |
| 気持ちが継がっている | 気持ちが繋がっている | 心や感情のつながりは「繋がる」を使う。 |
| この問題は未来に継がる可能性がある | この問題は未来に繋がる可能性がある | 原因と結果、影響の関係を表すときは「繋がる」。 |
| 布の端を糸で繋いだ | 布の端を糸で継いだ | 補修・接合する場合は「継ぐ」。 |
| 伝統を若い世代に繋ぐ | 伝統を若い世代に継ぐ | 受け継がせる、伝えるといった意味なら「継ぐ」が自然。 |
曖昧な文脈でも、主体的に行動するなら「継ぐ」/自然に成立するなら「繋がる」と覚えると便利です。
「引き継ぐ・継承する」→ 継ぐ
「接続される・関係が生じる」→ 繋がる
まとめ
「継る」という言葉は日本語には存在せず、正しくは「継ぐ(つぐ)」です。「継ぐ」は何かを引き継いだり、補ったりする能動的な動作を表し、一方で「繋がる(つながる)」は人や物、感情などが自然に結びつく状態を示します。
両者は似た響きを持つため混同されやすいですが、意味や使い方は大きく異なります。例えば、家業や意志を「継ぐ」、人との絆や通信状態は「繋がる」と使い分けるのが正解です。
本記事では、それぞれの意味と使い方、例文、間違いやすいケースなどを通して、違いを明確にしました。言葉の使い分けは、文章の説得力や伝わりやすさを大きく左右します。今回の内容を参考に、「継ぐ」と「繋がる」を場面に応じて正しく使いこなし、より洗練された日本語表現を目指しましょう。




