「愛でる」と「慈しむ」の違い【50例文】意味・使い分け術

日本語には、豊かな感情や繊細なニュアンスを表現する言葉が数多く存在します。その中でも「愛でる(めでる)」と「慈しむ(いつくしむ)」という言葉は、どちらも「愛情」を表す点で共通しているものの、実際の使い方や含まれる感情の方向性には大きな違いがあります。
たとえば、美しい花を見て「愛でる」と感じるのと、赤ちゃんを見て「慈しむ」と感じるのとでは、心の動き方や注がれる感情の種類が異なります。言葉は、適切に使うことでより深く伝わり、誤って使うと意味が通じにくくなることもあります。
本記事では、「愛でる」と「慈しむ」の意味や使い分けを丁寧に解説し、それぞれの言葉を自然に使いこなせるよう、具体的な例文を50個ご紹介します。文語的な表現も含め、日常会話や文章で役立つ内容を意識してまとめました。
言葉の力を正しく、美しく使うために、この2つの言葉の違いをじっくり見ていきましょう。
目次
「愛でる」と「慈しむ」の違い

「愛でる」と「慈しむ」は、どちらも「愛情」を伴う言葉ですが、その感情の向き方や対象、使われる場面にははっきりとした違いがあります。以下の比較表をご覧ください。
比較表:「愛でる」と「慈しむ」の違い
| 項目 | 愛でる(めでる) | 慈しむ(いつくしむ) |
|---|---|---|
| 主な意味 | 美しさや趣を感じて、感心しながら愛情を寄せる | 弱い存在を思いやり、いたわりの気持ちで接する |
| 感情の方向性 | 鑑賞・感心・賞美 | 保護・育成・思いやり |
| 対象 | 花、風景、芸術品、動物などの美しいもの | 子ども、病人、高齢者、小動物などの弱い存在 |
| 主な使用場面 | 詩的・文芸的、自然・芸術の鑑賞 | 家庭的、宗教的、福祉的、人間関係の文脈 |
| 語感・響き | 上品・文語的・趣のある | 温かい・情のある・慈愛深い |
| 行動との関係 | 直接的な行動は伴わず、主に「見る」ことに重きがある | 思いやりをもって接する、行動が伴うことが多い |
| 英語に近い語 | admire, appreciate | cherish, nurture, love |
ポイント
- 「愛でる」は視覚的な感動や感性に訴える言葉であり、美的な対象に対して使われることが多いです。美術館で絵画を鑑賞したり、春の桜を眺めたりする場面に自然と馴染みます。
- 「慈しむ」は相手の立場や状態を思いやる心を含みます。たとえば、赤ちゃんを抱きしめてあやす時や、年老いた親を支えるときなど、相手に寄り添う行動と共に使われます。
このように、両者は単なる言い換えではなく、それぞれに適した使いどころがあります。感情の深さや種類に注目することで、言葉の選び方がより自然になります。
「愛でる」の意味

「愛でる(めでる)」という言葉は、日本語の中でもやや古風で上品な響きを持つ表現です。この言葉は主に、美しいものや可愛らしいものに対して深く心を引かれ、愛情や感動を抱くという意味で使われます。
基本的な意味
「愛でる」は、以下のような意味を持ちます:
- 美しいもの、趣のあるものを鑑賞し、心から感心すること
- 可愛らしさや魅力に対して、愛情をこめて見つめること
つまり、「見る」という行為に感情が伴っている点が大きな特徴です。単に「見る」だけでなく、その対象に愛情や敬意をもって接する行為が「愛でる」です。
「愛でる」は、古典文学や和歌、俳句などでも多く用いられてきました。自然の美しさや季節の移ろい、芸術作品などに心を寄せるときによく使われます。現代でも、丁寧で情緒ある表現として、詩的な文章やナレーションなどに使われることがあります。
読み方と注意点
- 「愛でる」は「めでる」と読みます。
- 誤って「まなでる」や「いでる」と読むのは間違いです。
- 書き言葉としては頻出する一方、話し言葉ではややフォーマルな響きがあります。
このように、「愛でる」は視覚的な魅力を愛情を込めて受け止める言葉であり、鑑賞や賞美の文脈でよく使われます。
「慈しむ」の意味

「慈しむ(いつくしむ)」は、相手に対して深い愛情や思いやりをもって大切にするという意味をもつ日本語です。こちらもやや古風で丁寧な表現ですが、家庭や宗教、教育など幅広い文脈で使われる奥深い言葉です。
基本的な意味
「慈しむ」の意味は、以下のように説明されます:
- 弱いもの、か弱い存在をいたわるように大切に思うこと
- 親が子を思うような、守る気持ちや育てる気持ちを伴う愛情
たとえば、赤ちゃんや年老いた人、病気の人、小さな動物など、「守ってあげたい」「大事に育てていきたい」と思う対象に対して使われます。
「慈しむ」には、単なる「好き」という感情だけではなく、保護・配慮・思いやり・いたわりといった、相手を思って行動する姿勢が含まれています。これは、「愛でる」が視覚的な美しさに心を寄せるのに対し、「慈しむ」は相手の存在全体に心を向けるという違いでもあります。
読み方と注意点
- 「慈しむ」は「いつくしむ」と読みます。
- 誤読されやすいため、特に文章中で使う場合は注意が必要です。
- 「慈」という漢字は「慈悲」「慈愛」などにも使われる通り、仏教的な背景をもつ言葉でもあります。
このように、「慈しむ」は相手を思いやる深い心情を表現する、温かくて奥ゆかしい日本語です。
「愛でる」と「慈しむ」の使い分け
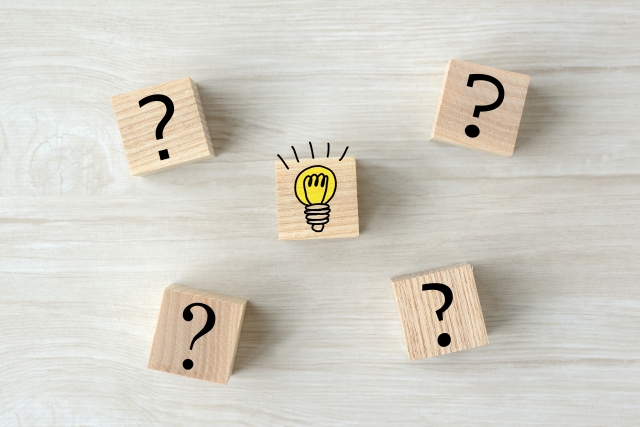
「愛でる」と「慈しむ」は、どちらも愛情を表現する言葉ですが、どのような対象に対して、どんな感情をもって使うのかによって、適切な言葉の選び方が変わってきます。以下では、使い分けのポイントを具体的に説明します。
①感情の性質で使い分ける
- 愛でる:感心・鑑賞・美的な愛情
- 例:風に揺れるコスモスの花を静かに愛でる。
- 慈しむ:いたわり・守りたい気持ち・育てる愛情
- 例:寝つきの悪い赤ん坊を優しく慈しむ。
②対象の特徴で使い分ける
| 対象 | 適した表現 | 理由 |
|---|---|---|
| 花や風景 | 愛でる | 美しさや趣を感じるため |
| 絵画・工芸品 | 愛でる | 視覚的な魅力に対する鑑賞 |
| 赤ん坊・幼児 | 慈しむ | 守る・育てる愛情が含まれる |
| 年老いた親 | 慈しむ | 思いやりや配慮を持って接するため |
| ペット | 両方可能 | 美しさには「愛でる」、世話を含むなら「慈しむ」 |
③行動の有無で使い分ける
- 愛でるは、行動を伴わず「目で楽しむ・心で感じる」ことが多いです。
- 慈しむは、行動(世話・ケア・守ること)を伴う場面で使われることが多くなります。
④文脈による判断
- 文芸的・詩的な文章では「愛でる」がふさわしいことが多いです。
- 家族や宗教的な文脈では「慈しむ」が適していることが多いです。
NG例:使い間違いに注意
- ×「彼は子どもを愛でるように育てた」
→ 不自然。「慈しむように育てた」が適切。 - ×「美しい紅葉を慈しむ」
→ 不自然。「愛でる」が適切。
このように、対象の性質・感情の向き・文脈を意識することで、自然な言葉の使い分けができます。
「愛でる」の使い方【例文20】

「愛でる」は、美しさや趣を感じ取り、それを心から楽しむ・愛しむという行為に使われます。以下に、日常生活・自然・芸術・文芸的表現など、さまざまな場面での使い方を例文でご紹介します。
● 自然・季節の美しさを愛でる
- 春の桜を愛でながら、友人と散歩を楽しんだ。
- 窓辺から見える雪景色をひとり静かに愛でる。
- 秋の紅葉を愛でるために、京都を訪れた。
- 朝露に濡れた花を愛でるその姿に、風情を感じた。
- 月を愛でる風習は、古来より日本人の心に根付いている。
● 動植物や小さな命を愛でる
- 子猫の愛らしいしぐさを微笑みながら愛でた。
- 鯉の泳ぐ様子を愛でる庭園のひとときに癒された。
- 小鳥のさえずりを耳にしながら、姿を愛でる。
- 野に咲く草花を一つひとつ愛でる祖母の姿が印象的だった。
- 植物を育てながら、その成長を日々愛でている。
● 美術・工芸・建築などの芸術を愛でる
- 名画を前に、彼は静かにそれを愛でていた。
- 陶器の肌触りと色合いを愛でるのが趣味だという。
- 書の一文字一文字を愛でるように眺めていた。
- 日本庭園の構図を愛でながら歩くのが好きだ。
- 仏像の穏やかな表情を愛でる時間が、心を落ち着けてくれる。
● 人や情景に対して
- 舞台上の彼女の姿を、観客は愛でるように見つめていた。
- 子どもの寝顔をそっと愛でる母のまなざしが温かい。
- 恋人の笑顔を愛でるように見つめ続けた。
- 老夫婦が互いを愛でるように過ごす様子に感動した。
- 言葉の響きを愛でるように、詩を声に出して読んだ。
「慈しむ」の使い方【例文20】

「慈しむ」は、相手に対して深い思いやりやいたわりの心を持って接するときに使われる言葉です。特に、弱い存在や身近な人への愛情、育てるような関係性の中でよく用いられます。
● 子どもや家族に対して
- 親は我が子を慈しみながら、日々の成長を見守っている。
- 祖母は孫たちを慈しむように優しく接してくれる。
- 赤ん坊を慈しむように抱きかかえる父親の姿が印象的だった。
- 病気の妻を、彼は長年慈しみながら支えてきた。
- 姉は弟を慈しむように面倒を見ていた。
● 高齢者や弱い存在に対して
- 老犬を慈しみ、最期まで世話をし続けた。
- 施設のスタッフは入居者を慈しむ気持ちで対応している。
- 認知症の母を慈しみ、毎日根気よく話しかけている。
- 捨てられた子猫を慈しむように育てた。
- 弱者を慈しむ心は、社会にとって欠かせない。
● 宗教的・精神的な文脈での使用
- 仏のように人々を慈しむ心を持ちたい。
- 教会では、隣人を慈しむことの大切さを学んだ。
- 神が人間を慈しむように、私たちも互いを思いやるべきだ。
- 慈しみの心こそが、人としての基本だと教えられた。
- 彼の説教には、常に人々を慈しむ思いが込められていた。
● 人間関係や日常の場面での使用
- 長年一緒に働いた仲間を慈しむように送り出した。
- 病気の友人に寄り添い、慈しむような言葉をかけ続けた。
- 教師は生徒一人ひとりを慈しむ気持ちで指導している。
- 彼女は植物にも慈しむようなまなざしを向けていた。
- ペットを慈しむことで、命の重みを学んだ。
間違いやすい使い方【例文10】
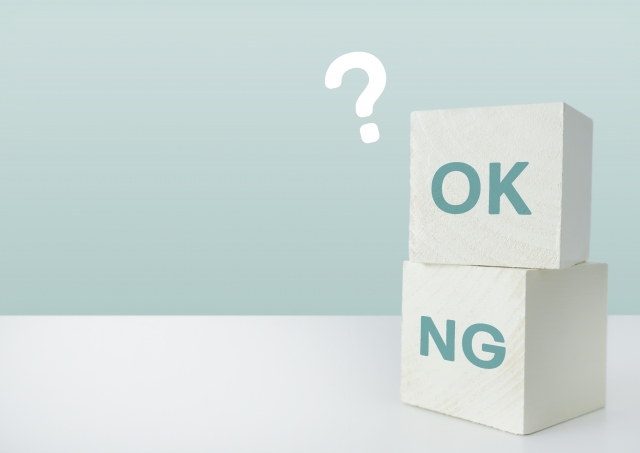
「愛でる」と「慈しむ」はどちらも「愛情」を表す言葉ですが、感情の種類や対象によって使い分ける必要があります。ここでは、意味を混同して使ってしまいがちな例と、適切な表現への言い換えを提示します。
● 誤用と適切な言い換え(例文+解説)
- × 老いた両親を愛でるように介護している。
→ ○ 老いた両親を慈しむように介護している。
※「愛でる」は鑑賞的なニュアンスのため、行動を伴う「慈しむ」が適切です。 - × 美しい風景を慈しんだ。
→ ○ 美しい風景を愛でた。
※自然や美しさに心を寄せる場合は「愛でる」が適切。 - × 飼っている猫を愛でる気持ちで育てている。
→ ○ 飼っている猫を慈しむ気持ちで育てている。
※育てる・世話をするニュアンスが強い場合は「慈しむ」が自然。 - × 彫刻の繊細な表情を慈しむように見つめた。
→ ○ 彫刻の繊細な表情を愛でるように見つめた。
※鑑賞対象には「愛でる」を使う。 - × 孫を愛でるように抱き上げた。
→ ○ 孫を慈しむように抱き上げた。
※抱き上げるという行動が伴うので「慈しむ」が適切。 - × 雪化粧をまとった山々を慈しんだ。
→ ○ 雪化粧をまとった山々を愛でた。
※自然の景色に対する表現では「愛でる」を使用。 - × 弱った鳥を愛でながら看病した。
→ ○ 弱った鳥を慈しみながら看病した。
※「看病」は行動なので「慈しむ」が適切。 - × 書道作品を慈しむように眺めた。
→ ○ 書道作品を愛でるように眺めた。
※芸術作品の鑑賞には「愛でる」がふさわしい。 - × 祖父は亡き妻の写真を慈しむように見ていた。
→ ○ 祖父は亡き妻の写真を愛でるように見ていた。
※視覚的な鑑賞であれば「愛でる」が自然。 - × 芸術家が自作の作品を慈しんで展示していた。
→ ○ 芸術家が自作の作品を愛でて展示していた。
※作品に愛着をもって鑑賞・披露する場合は「愛でる」が適切。
「愛でる」の類語・英語

「愛でる」は、美しいものや趣のあるものに対して愛情や感動をもって接する言葉ですが、同様の意味を持つ表現は他にもいくつか存在します。ここでは、「愛でる」の類語(日本語)と、英語での表現を紹介します。
類語(日本語)
| 類語 | 意味・使い方の違い |
|---|---|
| 鑑賞する | 主に芸術や作品などを味わい、評価すること。やや客観的。例:「絵画を鑑賞する」 |
| 賞美する | 美しさを認め、ほめたたえること。文語的で硬い表現。 |
| 愛しむ(おしむ) | 大切にして惜しむ気持ち。やや文学的、古風な語感。 |
| 見とれる | 美しさに心を奪われてじっと見ること。やや口語的。 |
| 眺める | じっと見つめること。「愛でる」ほどの感情は含まれないが、併用可能。 |
※「愛でる」は、これらの語よりも主観的な愛情や感動を強く含む点が特徴です。
英語表現
「愛でる」にぴったり対応する英語は一語では存在しませんが、文脈に応じて以下のように使い分けられます。
| 英語表現 | ニュアンス・使用例 |
|---|---|
| admire | 敬意をもって美しさや才能をたたえる。例:「I admired the painting.」 |
| appreciate | 美的価値や意味を正しく理解して評価する。例:「She appreciated the scenery.」 |
| gaze lovingly at | 愛情を込めて見つめる。例:「He gazed lovingly at the baby.」 |
| cherish | 愛情をもって大切にする(感情面が中心)。やや「慈しむ」にも近い。 |
| delight in | ~に喜びを感じる。例:「She delighted in the beauty of the garden.」 |
英語に訳す際は、単語の意味だけでなく、状況や感情の深さを反映した表現を選ぶことが重要です。
「慈しむ」の類語・英語

「慈しむ」は、相手に対する深い愛情といたわりの心をもって接することを表す言葉です。このような感情や態度を示す類語や英語表現もいくつか存在します。ここでは、その意味の違いや使い方のポイントを解説します。
類語(日本語)
| 類語 | 意味・使い方の違い |
|---|---|
| 労る(いたわる) | 病気・疲れた人などに対して、体や心を気遣うこと。例:「高齢の母を労る」 |
| 可愛がる | 愛情をもって接するが、少し軽めで日常的な語感。例:「ペットを可愛がる」 |
| 大事にする | もの・人を大切に扱うこと。やや広い意味で使われる。 |
| 愛する | 広く使われる愛情の表現。「慈しむ」よりも情熱的で感情的な場合が多い。 |
| 慈悲をかける | 相手の苦しみに対して同情し、救おうとする行為。仏教的なニュアンスが強い。 |
※「慈しむ」は、これらの語と比べて思いやり・保護・育成の気持ちが特に強いのが特徴です。
英語表現
英語でも「慈しむ」にぴったり一致する単語は存在しませんが、文脈に応じて以下の表現が適しています。
| 英語表現 | ニュアンス・使用例 |
|---|---|
| cherish | 大切に思い、深い愛情を注ぐ。例:「She cherished her children.」 |
| nurture | 育てる・育むという行動を含んだ愛情。例:「They nurtured the child with care.」 |
| care for | 世話をする・気遣うこと。例:「He cared for his elderly father.」 |
| love | 一般的な愛情。文脈により「慈しむ」と同等になることも。 |
| be devoted to | ~に献身する。深い思いやりを伴う。例:「She was devoted to her patients.」 |
「慈しむ」は感情と行動が結びついた言葉なので、英語では動詞と補足語を組み合わせてニュアンスを補うのが一般的です。
よくある質問

ここでは、「愛でる」と「慈しむ」に関して読者からよく寄せられる疑問を取り上げ、分かりやすく回答します。
Q1. 「愛でる」と「慈しむ」は入れ替えても意味は通じますか?
A:部分的には通じることもありますが、基本的には入れ替えない方がよいです。
両者とも「愛情」を示す言葉ですが、感情の種類や対象が異なるため、入れ替えると不自然な文になります。たとえば、「赤ちゃんを愛でる」と言うと、単に見た目が可愛いという意味合いになってしまい、本来の「慈しむ」が持つ思いやりや保護のニュアンスが失われてしまいます。
Q2. ビジネス文書やメールで使ってもよい表現ですか?
A:「愛でる」は基本的にビジネス文書では不適切。「慈しむ」も慎重に使うべきです。
「愛でる」は詩的・感性的な言葉であり、ビジネスシーンでは使われることはほとんどありません。一方「慈しむ」も、宗教的・家庭的なニュアンスが強く、公式文書やメールでは場面を選ぶ必要があります。どうしても使いたい場合は、文脈に注意し、「深く愛情を持って接する」などに言い換えることが一般的です。
Q3. どちらの表現が古風ですか?
A:どちらも古風な語感ですが、「愛でる」の方がより文語的・古典的です。
「愛でる」は和歌や古典文学にも頻出する語で、現代ではやや詩的・芸術的な場面に限定されがちです。「慈しむ」も現代の会話では多用されるわけではありませんが、宗教的・道徳的文脈では今でも自然に用いられます。
Q4. 「愛でる」や「慈しむ」の敬語表現はありますか?
A:どちらも動詞としての敬語は一般的ではありませんが、丁寧な表現に言い換えることは可能です。
例えば、「お子様を慈しんでおられるご様子でした」などのように、「おられる」を使って敬意を表すことはできます。「愛でる」の場合は、「ご鑑賞なさる」や「ご覧になる」に言い換えるのが自然です。
まとめ
「愛でる」と「慈しむ」は、どちらも日本語ならではの繊細な感情表現をもつ美しい言葉ですが、それぞれに異なるニュアンスと使いどころがあります。
「愛でる」は、視覚的な美しさや趣を感じ、感動をもって心を寄せる言葉であり、花や風景、芸術作品などを対象とする場合に自然です。一方で、「慈しむ」は、弱い存在や身近な相手に対して、いたわりや保護の気持ちを込めて接するときに使われる、温かく深い愛情を示す言葉です。
使い方を誤ると、意図した感情が伝わらなかったり、不自然な表現になってしまうことがあります。しかし、それぞれの言葉の持つ背景や適切な場面を理解すれば、より豊かで丁寧な日本語表現ができるようになります。
本記事では、意味の解説から具体的な使い分け、豊富な例文50選、さらには類語・英語表現まで網羅的に紹介しました。言葉選びに迷ったときは、この記事を参考にしながら、シチュエーションに合った言葉を選んでみてください。
正確で美しい日本語を使うことは、相手への敬意や自身の教養を示すことにもつながります。ぜひ、「愛でる」と「慈しむ」を上手に使いこなして、豊かな表現力を磨いていきましょう。




