アドラー心理学を簡単に言うと?特徴や具体例をわかりやすく

近年、自己啓発や教育、ビジネスの現場でも広く注目を集めている「アドラー心理学」。一時期は『嫌われる勇気』という書籍の大ヒットによって、その名を耳にした方も多いのではないでしょうか。
アドラー心理学は、「どうすれば人は前向きに生きられるのか」「人間関係の悩みをどう解決するか」といった、日常生活のあらゆる場面で役立つ考え方が詰まった心理学です。その実践的な内容から、多くの人が実生活に取り入れ、変化を実感しています。
本記事では、アドラー心理学の基本的な考え方から、代表的な理論、実生活への応用例、さらにはメリット・デメリットまでをわかりやすく解説します。初めて学ぶ方でも理解しやすく、すぐに活かせる内容を目指しています。
目次
アドラー心理学とは

アドラー心理学は、オーストリアの精神科医アルフレッド・アドラー(Alfred Adler)によって創始された心理学の理論です。正式には「個人心理学(Individual Psychology)」と呼ばれ、個人の行動や思考はすべて「目的」に向かって動いているという点に大きな特徴があります。
フロイトの精神分析やユングの分析心理学と並び、アドラー心理学は「心理学の三大巨頭」の一つとして位置づけられています。しかし、他の理論と異なり、アドラー心理学は過去の体験よりも「これからどう生きるか」を重視する「未来志向型」の心理学です。
また、アドラー心理学は理論にとどまらず、教育・ビジネス・家庭など、あらゆる場面で実践的に活用されている点も特徴的です。人間関係の悩みを根本から見つめ直し、勇気を持って行動できるよう導く手法として、自己啓発や人材育成の分野でも注目されています。
アドラー心理学を簡単に言うと
「人は変われる。人は自分の意志で未来を選べる心理学」
です。
アドラー心理学は、「過去にとらわれず、未来の目的に向かって行動することができる」という前向きな視点に立っており、「自分の人生は自分で決められる」というメッセージが根本にあります。劣等感も、人間関係の悩みも、自分の考え方と行動次第で乗り越えられる——そのような力強い哲学です。
アドラー心理学の6つの特徴

アドラー心理学には、他の心理学理論とは一線を画す、いくつかの重要な特徴があります。ここではその中でも特に重要な6つのポイントをご紹介します。
①人間の行動には目的がある
アドラー心理学の核心は、「人間の行動はすべて目的を持っている」という考え方です。たとえば「内向的で話さない子ども」は、恥ずかしがり屋だからではなく、「失敗したくない」「批判されたくない」という目的を持って黙っていると解釈されます。
つまり、私たちは過去の経験に縛られるのではなく、自分が選んだ目的に向かって行動しているのです。
②人間の生き方には特有のスタイルがある
アドラーは、人にはそれぞれ「ライフスタイル(生活様式)」があると説きました。これは性格とは少し違い、「人生の中で自分がどうふるまうか」という行動パターンのことです。
このライフスタイルは、幼少期の経験によって形成され、無意識のうちに私たちの判断や行動に影響を与えています。自分のライフスタイルを知ることは、自己理解の第一歩です。
③人生の課題は対人関係に集約される
アドラー心理学では、「人生のすべての悩みは対人関係の悩みである」とされています。仕事、家庭、恋愛、友情——すべての問題は「他者」との関係から生まれるという前提です。
そのため、問題を解決するためには「他者との関わり方」を見直す必要があります。
④人間関係を円滑にするための課題の分離
「課題の分離」とは、自分の課題と他人の課題をきちんと分けて考えるというアドラー心理学の重要な技法です。
たとえば、子どもが勉強しないのは「子どもの課題」であり、親が代わりに悩むことではありません。他人の課題に介入しすぎると、ストレスや衝突の原因になります。
⑤誰かの期待を満たすために生きてはいけない
アドラーは「他人の期待を満たすために生きるのではなく、自分の信じる価値観に従って生きるべきだ」と説きます。これは、他人にどう思われるかよりも、自分がどうありたいかを優先するという考え方です。
もちろん、これは「自己中心的になれ」という意味ではなく、「自立した個人として責任を持って生きる」ということです。
⑥「私」から「私たち」の共同体感覚を持つ
最終的にアドラー心理学が目指すのは、「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」の育成です。これは、自分が社会の一員としてつながりを感じ、他者に貢献しようとする姿勢を意味します。
自立した個人が、他人と協力し、共に生きる感覚を持つことで、より豊かな人間関係と人生が築かれていくのです。
アドラー心理学のシーン別具体例

アドラー心理学は理論だけでなく、実生活での応用にこそ価値があります。ここでは、ビジネス、友人関係、恋愛、子育て、夫婦関係といった日常のシーンごとに、アドラー心理学がどのように役立つかを具体的に見ていきましょう。
ビジネスシーン:部下が言うことを聞かない
部下が自分の指示に従わず、フラストレーションがたまることは多くの上司の悩みです。このとき、「課題の分離」を活用することで、冷静な対応が可能になります。
たとえば、「部下がどう行動するか」は部下の課題であり、上司の役目は「伝えるべきことを適切に伝えること」です。必要以上に感情的になるのではなく、相手の自発性を尊重する姿勢が、信頼関係を築く近道です。
友人とのシーン:価値観の違いでギクシャクする
友人との意見の違いにモヤモヤすることもあるでしょう。アドラー心理学では、「違い」を否定せず、尊重することが大切とされます。
「共同体感覚」に基づけば、「自分とは違うけれど、その人も大切な仲間だ」と捉えることで、対立ではなく相互理解の関係を築くことができます。
恋愛のシーン:相手に尽くしすぎて疲れる
恋愛においても、「他人の期待に応えすぎない」ことが重要です。つい相手に合わせすぎて、自分を犠牲にしてしまう人は少なくありません。
アドラーは「自立した個人」が対等な関係を築くことを重視しています。自分を大切にしながら相手と向き合うことが、健全な恋愛関係への第一歩です。
子育てのシーン:子どもが言うことを聞かない
子どもが指示に従わないとき、叱るよりもまず「その行動にはどんな目的があるのか?」と考えることがアドラー的なアプローチです。
たとえば、反抗的な態度の裏には「注目されたい」「親の関心を引きたい」といった目的があることも。子どもを「勇気づける」関わり方によって、行動が変わっていく可能性があります。
夫婦のシーン:気持ちがすれ違う
夫婦関係では、長年一緒にいるからこその誤解や不満が蓄積しがちです。アドラー心理学では、お互いの課題を切り分け、対等な立場で尊重し合うことが推奨されます。
また、「共同体感覚」を意識することで、「どうすれば二人でよりよい関係を築けるか」という視点が持てるようになり、感情的な対立を避けられます。
アドラー心理学の「劣等感」

「劣等感」という言葉は、日常でもよく使われますが、アドラー心理学ではこの概念が極めて重要な役割を担っています。アドラーは、人間のすべての行動は「劣等感を克服しようとする努力」から始まると考えました。
劣等感とは何か?
劣等感とは、自分が他人より劣っている、価値が低いと感じる心理状態のことです。これは欠点ではなく、誰もが抱える自然な感情です。人は生まれた瞬間から、周囲の大人よりも「無力」な存在であり、そこから成長しようとする過程で劣等感を経験します。
つまり、劣等感は「成長の起点」であり、「向上したい」「認められたい」という前向きなエネルギーを生む原動力でもあるのです。
劣等感の健全な活用 vs. 劣等コンプレックス
アドラーは、劣等感には2種類あるとしています。
- 健全な劣等感:自分の理想像と現実の差を認識し、「もっと頑張ろう」と前向きに行動する動機になる。
- 劣等コンプレックス:劣等感が強すぎて「自分にはできない」「どうせ無理だ」と諦めたり、言い訳をしたりして行動できなくなる状態。
劣等感そのものは悪いものではありませんが、そこにとどまって行動を止めてしまうと、人生を閉ざす原因になってしまいます。
劣等感を克服するには?
アドラー心理学では、劣等感を克服するために大切なのは「勇気づけ」です。自分自身に対しても、他者に対しても「できる」「価値がある」と認めてあげることで、人は前に進む力を取り戻せます。
また、「他者と比べないこと」も大切です。自分の人生の基準は、自分自身にあるべきだというのがアドラーの基本的な立場です。
アドラー心理学の「勇気づけ」

アドラー心理学において、もっとも実践的で重要な概念の一つが「勇気づけ(Encouragement)」です。これは、落ち込んでいる人や困難に直面している人に対して「あなたにはできる力がある」「あなたには価値がある」と信じ、支える姿勢を指します。
勇気づけとは何か?
アドラーにとっての「勇気」とは、「困難を克服する力」「自分らしく生きる力」のこと。そして「勇気づけ」とは、その力を引き出すための関わり方です。
勇気づけは、子どもに対してだけでなく、職場の部下、パートナー、友人、自分自身に対しても活用できる手法です。ポイントは、相手の行動ではなく「存在そのもの」を肯定することにあります。
ほめることと勇気づけの違い
よく混同されるのが「ほめること」と「勇気づけ」です。
- ほめる:結果や能力に注目し、上下関係を前提にした評価(例:「よくできたね。えらいね」)
- 勇気づけ:努力や姿勢、存在そのものに注目し、対等な立場で支える(例:「がんばってたね」「あなたがいてくれて助かったよ」)
ほめることは短期的な効果があるものの、依存を生む可能性があります。一方、勇気づけは相手の「自信」「自立」を促し、長期的な成長につながります。
日常での勇気づけの実践例
- 子どもに対して:「失敗しても挑戦したことがすごいね」
- 部下に対して:「そのやり方、私は信頼してるよ」
- 自分に対して:「今日はうまくいかなかったけど、ちゃんと向き合った自分を認めよう」
勇気づけは、関係性を深め、信頼を築くための強力なツールです。相手の力を信じ、対等な立場で寄り添う姿勢こそが、アドラー心理学の真髄なのです。
アドラー心理学の「課題の分離」

アドラー心理学の実践的な技法の中でも、特に多くの人の心を軽くしてくれるのが「課題の分離(Separation of Tasks)」です。これは、人間関係のストレスや葛藤を大きく減らす考え方であり、「他人の人生を自分が背負いすぎない」ための有効なアプローチです。
課題の分離とは?
「課題の分離」とは、問題に直面したときに、それが「自分の課題」なのか「他人の課題」なのかを明確に区別することです。
たとえば、
- 子どもが勉強しない → それは「子どもの課題」
- 同僚が仕事をサボる → それは「同僚の課題」
- 恋人が自分をどう思うか → それは「恋人の課題」
というふうに、「最終的な結果を引き受けるのが誰か」で判断します。
どのように活用するか?
課題の分離を実践するためには、次のステップを踏みます:
- 課題の主体を見極める
→ 「最終的に困るのは誰か?」と自問する。 - 他人の課題には介入しない
→ 相手を信じて任せる。自分ができるのは、支援や提案まで。 - 自分の課題には責任を持つ
→ 他人のせいにせず、自分の行動を選び直す。
このように考えることで、「相手にどう思われるか」「相手が自分にどう反応するか」といった、自分ではコントロールできないことに悩む必要がなくなります。
課題の分離がもたらすメリット
- 人間関係のストレスが激減する
- 過干渉・依存から自由になれる
- 相手への尊重と信頼が生まれる
- 自分の人生に集中できるようになる
一見冷たく感じるかもしれませんが、これは「責任の明確化」と「相互の尊重」を意味する、非常に人間関係を良くする方法なのです。
アドラー心理学の「共同体感覚」

アドラー心理学の最終的な目標ともいえるのが「共同体感覚(Gemeinschaftsgefühl)」です。これは、単なる対人関係のテクニックではなく、「人間としてどう生きるか」という人生哲学そのものとも言える重要な概念です。
共同体感覚とは?
共同体感覚とは、「自分が社会の一員であるという感覚」と「他者に貢献しようとする意志」の両方を意味します。
アドラーは、人が幸せを感じるためには、「自分がこの世界に居場所を持っている」「自分には他人の役に立つ価値がある」と感じられることが不可欠だと考えました。
3つの要素
アドラー心理学では、共同体感覚を次の3つの視点で構成しています。
- 自己受容:自分の長所も短所も受け入れ、「このままの自分で大丈夫」と感じること。
- 他者信頼:人は信頼できる存在であり、敵ではないという前提で関係を築くこと。
- 他者貢献:自分が他者や社会に役立っているという感覚を持つこと。
この3つがそろったとき、人は孤独から解放され、精神的な安心感と幸福を得ることができます。
なぜ共同体感覚が重要なのか?
現代社会では「個人主義」が重視されがちですが、それだけでは人は満たされません。人は本質的に「社会的な存在」であり、「誰かとつながりたい」「誰かに役立ちたい」という欲求を持っています。
アドラーは、「幸福とは貢献感のある人生である」と明言しています。つまり、他者とのつながりの中で生き、自分の存在が誰かの助けになっていると実感できることが、人生に意味をもたらすのです。
アドラー心理学の5つのメリット
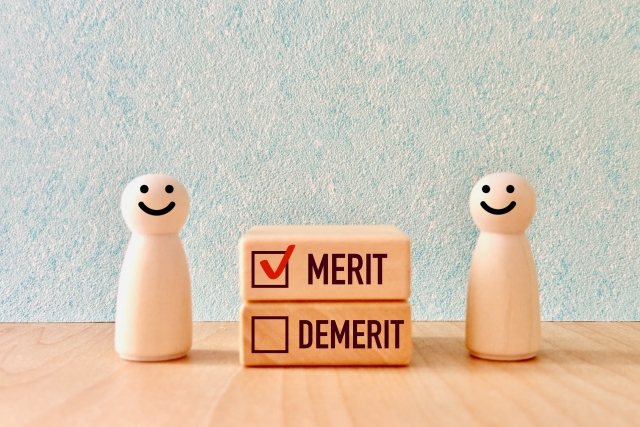
アドラー心理学は、日常のあらゆる人間関係に活用できる「実践の心理学」です。その効果は多くの人が実感しており、心理療法の枠を超えて教育、ビジネス、家庭など様々な分野で活用されています。ここでは、アドラー心理学を学び、実践することによって得られる主なメリットを5つ紹介します。
①対人関係のストレスが減る
「課題の分離」や「共同体感覚」によって、自分と他人との境界がはっきりし、他人の感情や行動に過度に振り回されなくなります。その結果、職場・家庭・恋愛など、あらゆる対人関係が楽になります。
②自分に自信が持てるようになる
「劣等感は成長のきっかけ」と捉えたり、「勇気づけ」によって自己肯定感を高めたりすることで、自分を信じて前に進む力が養われます。「自分には価値がある」と実感できるようになるのです。
③自立した人生を選べるようになる
「他人の期待に応えるために生きてはいけない」という考えは、他人の価値観に縛られない自由な生き方を可能にします。これは、他者との関係を断つという意味ではなく、「自分の軸を持った関係」を築くということです。
④子育てや教育に応用できる
アドラー心理学は、子どもに対する「勇気づけ」や「課題の分離」など、子育てや教育に役立つ考え方が豊富です。「叱る」や「褒める」ではなく、子どもを信頼して対等な関係を築く姿勢は、健全な自立心を育てます。
⑤人生の意味や目的を再発見できる
「人間は目的に向かって行動する存在」という考えに立つことで、自分の人生の方向性や意味を見つけやすくなります。過去にとらわれず、「これからどう生きるか」に焦点を当てる生き方は、多くの人にとって希望となるでしょう。
アドラー心理学の5つのデメリット
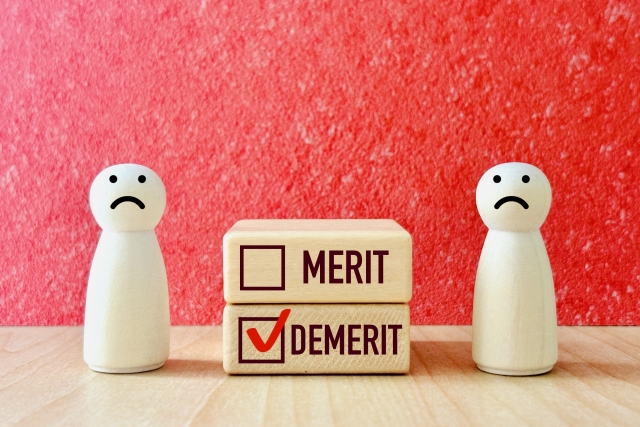
アドラー心理学は非常に実践的で有用な理論ですが、どんな理論にも限界や注意点があります。ここでは、アドラー心理学を実践する際に陥りやすい5つのデメリットについて正直に解説します。
①他者に冷たく見られることがある
「課題の分離」は、他人の問題に踏み込まないという姿勢をとるため、慣れていない人からは「冷たい」「無責任」と誤解されることがあります。実際には相手を尊重している姿勢なのですが、説明や関係性の築き方が必要です。
②自己責任が重く感じられる
アドラー心理学は「自分の人生は自分で選べる」という自由とともに、強い自己責任も求められます。そのため、すべての結果を自分の選択と受け止める覚悟が必要で、人によってはプレッシャーを感じることもあります。
③即効性がないこともある
理論自体はシンプルでわかりやすいのですが、実際に行動を変えるには時間がかかります。特に「ライフスタイル」の変容や「共同体感覚」の獲得は、日々の実践と習慣の積み重ねが必要です。
④他人に押しつけると反発される
アドラー心理学の考え方に感銘を受けた人が、無理に周囲にその価値観を押しつけると、逆に人間関係が悪化することがあります。大切なのは、自分が実践し、結果として他人に影響を与えるという「背中で語る」姿勢です。
⑤感情の扱いが難しい場合がある
「目的論」の視点では、感情すらも自分で選んでいると考えますが、怒りや悲しみといった感情が強い時には、それを「選んでいる」と思うこと自体が苦しく感じられることもあります。そのため、感情の取り扱いには慎重さと柔軟さが求められます。
アドラー心理学のベストセラー
アドラー心理学が日本や世界で広く知られるきっかけとなった本は、自己啓発の分野でも大ヒットを記録しています。その中でも特に注目すべきベストセラーをいくつかご紹介します。
『嫌われる勇気 』

- 著:岸見一郎/古賀史健
- 2013年12月に刊行されて以来、日本国内で約300万部(2024年時点)、世界累計1,000万部を超える驚異の大ヒット作品です 。
- 哲人と青年による対話形式で書かれており、アドラー心理学の核心をわかりやすく、かつ実践的に学べる構成が高く評価されています。
『幸せになる勇気』

嫌われる勇気の続編として話題に。「幸せ」や「共同体感覚」をさらに深く掘り下げ、読者自身の実生活に落とし込む内容として人気です。
『アドラー心理学入門』(岸見一郎)

- 著:岸見一郎
- ベスト新書(KKベストセラーズ)として刊行され、初心者でも取り組みやすいと好評です。
- 理論の背景や日常での活用法を網羅的に紹介しており、セルフヘルプや教育関係者からも支持されています。
その他のおすすめ本
- 『マンガでやさしくわかるアドラー心理学』『まんが!100分de名著 アドラーの教え』など、マンガ形式で学べる入門書も人気です 。
- 原著としては、アドラー自身の著作『The Practice and Theory of Individual Psychology』(1924年刊)など、学術的な内容を知りたい人に向いています。
よくある質問(FAQ)

アドラー心理学に関する理解をさらに深めるために、多くの人が抱きがちな疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1. アドラー心理学と他の心理学の違いは何ですか?
A. フロイトの「原因論」は過去の体験に重きを置くのに対し、アドラー心理学は「目的論」に基づき、未来志向で行動を見つめます。また、ユングが「個人の無意識」を探求したのに対し、アドラーは「他者との関係性」「社会とのつながり」を重視する点が特徴です。
Q2. 「課題の分離」は冷たくないですか?
A. 冷たく見えることもありますが、本質は「相手を信じ、尊重する」という愛ある姿勢です。干渉ではなく、信頼をもとに任せるという考え方で、むしろ人間関係を健全に保つことができます。
Q3. アドラー心理学は誰でも使えるものですか?
A. はい。専門知識がなくても、日常の中で少しずつ実践できます。「他人の期待ではなく、自分の価値観で生きる」「人は変われる」という前向きな姿勢は、すべての人にとって有効です。
Q4. 劣等感を持っているのは悪いことですか?
A. いいえ。アドラーは「劣等感は成長の源」と考えています。問題はその感情に支配されることではなく、それをどう受け止め、行動するかです。劣等感を前向きな力に変えることが重要です。
Q5. 子育てや教育にも本当に効果がありますか?
A. 多くの教育者や保護者がアドラー心理学を実践し、子どもの自己肯定感や自立心の向上を実感しています。「勇気づけ」や「課題の分離」は、子どもとの信頼関係を築くうえで非常に効果的です。
まとめ
アドラー心理学は、「人は過去ではなく、未来の目的に向かって生きる存在である」という前向きな哲学を基にした心理学です。「劣等感」「勇気づけ」「課題の分離」など、現代社会のあらゆる人間関係の課題に応用できる実践的な理論が特徴です。
ビジネスや子育て、恋愛などの場面で活用すれば、自分らしく、そして他人とも調和しながら生きる力が身につきます。アドラー心理学は、自己理解と対人関係の質を高めるための力強い道しるべです。人生に迷いや悩みを抱えるすべての人に、ぜひ知ってほしい学びです。




