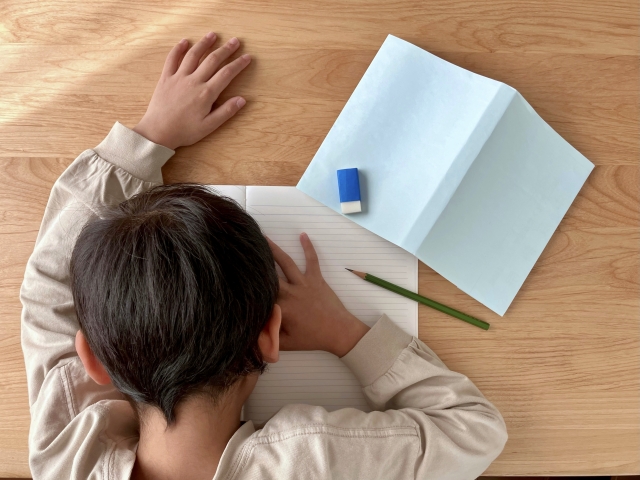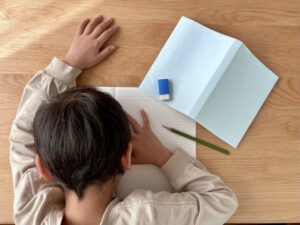夏休みの宿題【自由研究アイデア150選】1日で終わるテーマ満載!

夏休みといえば、子どもたちにとっては楽しみな長期休暇ですが、親にとっては少し頭を悩ませる時期でもあります。その理由の一つが、「宿題」、特に「自由研究」です。
「何をテーマにしたらいいかわからない」「そもそも自由研究って何をすればいいの?」そんな声をよく耳にします。特に低学年のうちは、子どもが自分だけでテーマを決めるのは難しく、親がアドバイスする場面も多いでしょう。
本記事では、そんな悩みを解決するために、小学生から中学生までを対象に、合計150個の自由研究アイデアを厳選して紹介します。簡単に取り組める実験から、本格的な観察・調査テーマ、さらにはSDGsやプログラミングなどの現代的なテーマまで幅広く網羅しました。
お子さまの興味や学年に応じて、きっとぴったりのアイデアが見つかるはずです。自由研究は、学びを深めるだけでなく、自分自身の発見や興味を広げるチャンスでもあります。楽しく、創造的に取り組んでみましょう!
夏休みの宿題やらないとどうなる?知らないと損する5つの問題
夏休みの宿題をやらないとどうなる?学力の差や親子関係まで、実は大きなリスクがあります。本記事では、宿題の本当の目的や、やらないと起こる問題、ラクに終わらせるコ…
目次
夏休みの宿題「自由研究」の選び方のコツ

自由研究は「何をするか」から始まるため、テーマ選びがとても重要です。ここでは、失敗しないテーマの選び方を3つの観点からご紹介します。
① 学年に合った難易度を選ぶ
学年によって、求められるレベルや発表の仕方は変わってきます。
- 低学年(小1〜小3):観察・体験が中心。結果より「やってみた!」が大事。
- 高学年(小4〜小6):比較や分析、まとめ方も重視。仮説を立てて検証する力が問われることも。
- 中学生:より高度な内容が求められ、文献調査やデータ分析も評価対象に。
無理なく達成感を得られる内容を選びましょう。
② 興味や得意なことを活かす
好きなことをテーマにすると、モチベーションが上がり、深く掘り下げることができます。
- 生き物が好き → 飼育・観察・比較実験
- 料理が好き → 食品成分の変化、レシピ比較
- 工作が得意 → 実験装置や模型を作ってみる
「自分の好きなこと」を軸にすると、自然とテーマが見つかります。
③ 期間と準備のしやすさを考える
自由研究には、「1日で終わる簡単なもの」もあれば、「毎日観察して記録する長期的なもの」もあります。
- 忙しい家庭や旅行が多い場合 → 短時間で完結する実験・調査がオススメ
- 時間に余裕がある → 成長記録や天気の変化など長期観察ができるテーマも挑戦可能
また、必要な道具が自宅にあるか、すぐに手に入るかもポイントです。
小学生向け自由研究アイデア(全60選)

小学生には「楽しくて、わかりやすい」が大事!低学年では観察や簡単な実験、高学年では比較や分析にも挑戦できます。学年別に60のテーマを紹介するので、自分にぴったりの研究が見つかります。
自由研究のまとめ方【誰でもわかる簡単ステップ】例文あり
自由研究のまとめ方を小学生(低学年〜高学年)、中学生向けにわかりやすく解説。基本ステップから学年別のまとめ方、よくある質問まで完全網羅。すぐに使える実践的なヒ…
小学生低学年向け(1年生・2年生・3年生)
身近なものを使った観察や簡単な実験が中心のアイデア集です。難しい道具は使わず、1日〜数日で完結するテーマが多いため、自由研究が初めてのお子さまにもおすすめ。楽しみながら学べる内容ばかりです。
- アサガオの花が開く時間を調べる
アサガオが何時ごろに咲くのか、日ごとに記録して比較します。自然のリズムや規則性に気づけるテーマです。 - 野菜を水に入れるとどうなる?浮く?沈む?
じゃがいも、トマト、きゅうりなどを水に入れて、浮くか沈むかを調べて分類。浮く理由を考えるきっかけにも。 - 色水でカラフル花実験(毛細管現象)
白い花を色水にさして色が変わる様子を観察。植物が水を吸い上げる仕組みを実感できます。 - 虫眼鏡で太陽の光を集めると?
太陽光を虫眼鏡で紙に集めて焦点を観察。安全に注意しながら、光の性質を学びます。 - 1日1回だけ咲く花を探してみよう
朝顔や夕顔など、決まった時間に咲く花を毎日観察し、開く時間や気温との関係を記録します。 - 冷凍庫で水を凍らせて観察(氷の形、時間)
ペットボトルや製氷皿など容器を変えて凍らせ、形や時間の違いを記録。水の性質への興味を引き出します。 - 石けんの泡でつくるしゃぼん玉研究
いろいろな石けん液を作り、しゃぼん玉の大きさや飛び方を比べる。配合による違いに注目。 - 植物に水をあげないとどうなる?
同じ植物で水をあげる/あげないを比較し、成長の違いを記録。生命と水の関係を体験的に理解します。 - いろんな葉っぱをこすって模様を写そう(葉っぱアート)
葉の上に紙をのせて鉛筆でこすると、葉脈の模様が浮き出ます。形や種類の違いも観察できます。 - 家の中の磁石がくっつく場所調査
磁石を持ち歩いて、家の中でくっつく素材を調べます。鉄、アルミ、プラスチックなどの違いを発見できます。 - ろ紙を使った色の分解実験(ペーパークロマトグラフィー)
マーカーで描いた点を水につけ、色が分かれる様子を観察。混ざった色の中身を調べる科学実験。 - 水と油が混ざらない理由を調べる
コップに水と油を入れて混ぜてみる。何度混ぜても分離する様子から、性質の違いを感じられます。 - 紙飛行機の飛ぶ距離を比べてみよう
折り方を変えた紙飛行機を飛ばして、飛距離や安定性を比較。飛行の仕組みを遊びながら学べます。 - カブトムシ・クワガタの観察日記
飼育している昆虫の動きや成長を記録。エサの種類や時間帯による行動の変化にも注目できます。 - 毎日の空の色を絵で記録してみよう
毎日決まった時間に空を見て、色を絵にして残します。天気や時間帯による変化を感じられます。 - 雨の日と晴れの日の気温比較
気温計で1日の気温を計り、天気ごとに変化を記録。天候と気温の関係を学ぶ導入にピッタリです。 - 野菜スタンプでアート作品
ピーマン、レンコン、オクラなどの断面をスタンプにして作品を作る。形や構造に注目できる観察活動です。 - 氷が溶けるスピードを比べよう(場所別)
日向・日陰・冷蔵庫などに氷を置き、溶ける速さを記録。温度の影響を実感できます。 - 自分だけのかんたん望遠鏡づくり
虫眼鏡やレンズを使って、簡単な望遠鏡を作ってみる。遠くのものが大きく見える仕組みを理解できます。 - 磁石の力で車を走らせてみよう
紙や段ボールで車を作り、磁石で引っ張って動かす。磁力で物が動く原理を体験できます。
小学生高学年向け(4年生・5年生・6年生)
高学年になると、「比較する」「データをとる」「考察する」といった深い学びが求められます。この章では、やりがいのあるテーマを40個紹介。実験や観察だけでなく、社会的な視点を取り入れたアイデアも満載です。
① 理科・実験系
- 水質の違いを比べよう(川・水道水・雨水)
水の色・におい・透明度を比較し、水質の違いを観察。身近な環境を科学する研究です。 - 発芽実験で条件比較!(日光・暗所・水なし)
豆などの種を、光や水などの条件を変えて育て、成長の違いを調べます。 - 重曹を使った二酸化炭素実験(火山モデル)
重曹と酢で「火山の噴火」を再現。発生する気体を観察し、化学反応を学べます。 - 温度で変わる色の実験(リトマス試験紙)
リトマス紙を使って、温かい・冷たい水の酸性・アルカリ性を調べ、色の変化を記録。 - 太陽光発電を試してみよう(ソーラーパネル)
小型ソーラーパネルで、日陰や厚い雲の日との発電量を比較。再生可能エネルギーを体験。 - 空気で風船を膨らませる実験(重さの影響)
風船に息を吹き込んだとき、顔を近づけたり遠ざけたりして膨らみ方を調べます。 - 結晶を育てよう(塩・砂糖・ホウ砂)
それぞれの溶液からできる結晶の形や成長の様子を比較観察します。 - 音の大きさで音波を観察(グラス振動)
グラスに水を入れ、スプーンで叩く音の大きさや水しぶきで変化を観察。 - 植物の光合成を調査しよう(葉っぱの気泡)
水中に葉をつけて泡の発生を見ることで、光合成の速さを記録。 - 乾燥材で湿度調べ(シリカゲルなど)
湿度計を使い、乾燥材ありとなしの環境での湿度差を比較観察。 - ペットボトルロケットを飛ばそう
空気と水を使ってロケット発射。飛距離や角度を変えて実験可能。 - 油膜で虹色を作ってみよう
水面に油を浮かせ、薄膜干渉で虹色が見える様子を観察します。 - コンクリートの強度実験(砂・セメント比率)
小さなサンプルを作り、強度を比べる。物質の混合比率について学べます。
② 社会・地理系
- 地域の気温の違いを比べよう
市内の複数地点で温度や湿度を測定し、地形や環境の違いを考察。 - 身近な歴史スポットの調査
地元の神社・古墳・史跡などを訪れ、写真や地図と一緒にまとめます。 - 地図記号ビンゴを作ってみよう
地図記号を集め、ビンゴシートやクイズを作成。遊びながら学べます。 - スーパーの価格調査(野菜・パンなど)
異なる店舗で野菜やパンの価格を比べ、物価の地域差をまとめます。 - 交通量調査(車・バイク・歩行者)
決まった時間・場所でカウントを行い、交通量の分析を行います。 - 地元野菜の生産量調査
JAや道の駅などから情報を集め、地元でどの野菜が多く作られているかをまとめます。 - 古地図と現在の地図を比較してみよう
昔の地図と現在の地形や建物の違いを比較し、変化をまとめます。 - ごみのリサイクル率を調べよう
家庭ごみを分類し、リサイクルの割合を調べ、改善案を考察します。 - バリアフリー調査(駅や建物のアクセス)
駅や公共施設のバリアフリー状況を写真でまとめ、改善点も提案。 - 地域のお店のサービス調査
パン屋さんやレストランでサービス内容や価格などを比べてまとめます。 - 豪雨・洪水の仕組み調査
近年の豪雨の原因や対策を調べ、防災について考えます。 - 市役所や図書館の利用状況調査
訪問者数や利用方法などを調査し、利用の活用を提案します。 - 地元伝統文化の調査(祭り・民芸)
伝統行事や工芸をインタビューや見学で調査し、魅力をまとめます。
③ 文系・その他ジャンル
- 読書感想文を分析!ジャンルごとの違いを比べてみよう
冒険小説、歴史もの、ノンフィクションなど、異なるジャンルの感想文を書いて比較。読書の感じ方や表現の違いをまとめます。 - 「ありがとう」は1日何回?家族の会話を調査
家族の1日の会話を記録し、「ありがとう」などポジティブな言葉がどれだけ出るかを数えてまとめます。 - 外国語のあいさつ調査(5か国語くらべ)
英語・中国語・韓国語など、外国語のあいさつや表現の違いを調べ、表やイラストでまとめます。 - 自分新聞を作ろう!1週間の生活を記事にする
毎日の出来事を記者目線で記事にし、自分だけの新聞を作成。観察力や表現力が身に付きます。 - 夢日記をつけて夢の傾向を調べよう
毎朝の夢を記録し、登場人物や場所、気持ちの傾向を分析。自分の心理に興味を持てるきっかけになります。 - 学校の音を記録して音マップを作ってみよう
教室や廊下、図書室などの音を観察・記録し、学校の「音の地図」を作るユニークな取り組みです。 - 「ありがとう」と「ごめんなさい」の気持ちの違い調査
友達や家族に聞き取りをして、それぞれの気持ちの背景やタイミングをまとめてみましょう。 - 図書館で借りられている本のランキング調査
図書館の貸出データを調べて、どの本が人気かを分析。学年別の傾向も面白い発見になります。 - 好きなキャラクターの人気理由をアンケート調査
友達や家族に人気キャラを聞いて、性格やデザインの共通点をまとめます。 - 自作クイズ大会を開催してみよう
オリジナルクイズを作って家族や友達に出題し、反応や正答率を記録して分析します。 - 名探偵になろう!事件をつくって推理ゲーム
小さな「事件」を設定して手がかりを用意。家族や友達に推理してもらい、論理的思考を深めます。 - 1日1つなぞなぞを作る「なぞなぞカレンダー」
毎日オリジナルなぞなぞを考えて、1ヶ月分カレンダーにしてまとめる創造系研究。 - まちのロゴやマークを集めて意味を調べよう
駅、公共施設、会社などのロゴマークを調べて、それぞれのデザインの意味や工夫を研究します。 - 紙の違いを調べてみよう(新聞紙・コピー用紙など)
触感、水を吸う量、強度などを比べて、用途に合った紙の特徴を分析します。
中学生向け自由研究アイデア(全60選)
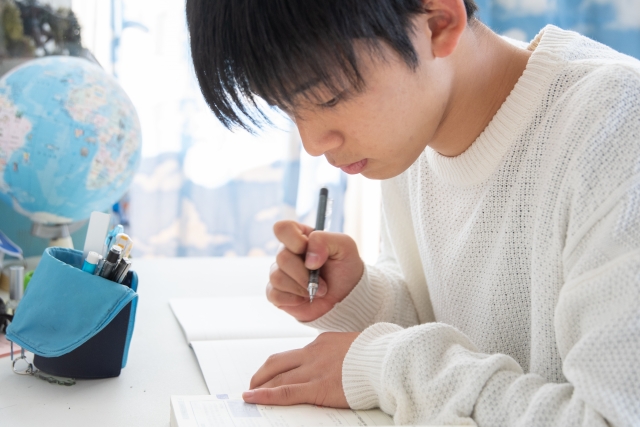
中学生になると、探究の深さやまとめ方も重要になります。理科・社会・文系の3ジャンルに分けて、より本格的に取り組める自由研究アイデアを60個紹介します。理論的に考察したい人にぴったりです。
理科系(20選)
科学的な探究に挑戦したい中学生にぴったりのテーマを紹介。物理、化学、生物、地学のジャンルから、それぞれ実験・観察・比較を通じて「なぜそうなるのか?」を考えながら研究できます。
- 水質調査:河川・水道・雨水の比較
自宅の水道水、庭に置いたバケツに溜まった雨水、近くの川の水などを採取し、pH試験紙や濁度計で調べます。色・におい・透明度の違いも観察し、飲用水としての安全性や自然環境の違いを考察できます。 - 土壌の保水力を調べる
同じ量の水を赤土・黒土・砂などに注ぎ、時間ごとの水の減り具合や重さの変化を記録。作物栽培に適した土の条件を考えるきっかけにもなります。 - 光の強さと光合成速度の関係
水中に沈めた水草(例:アナカリス)に光を当て、出てくる気泡の数を数えて光合成の速さを測定。光源との距離や明るさを変えて実験すると、植物の光合成の最適条件が見えてきます。 - 太陽光パネルの出力比較(色・角度)
同じソーラーパネルを、傾け方や背景の色(白・黒など)で変えて設置し、電圧計で発電量を測定。再生可能エネルギーの利用効率について考えることができます。 - ぬか漬け発酵の観察
同じ野菜(例:キュウリ、ナス)を漬けて、1日、2日、3日…と時間ごとの味、色、においの変化を記録。乳酸菌による発酵の進み具合を観察します。 - 食塩濃度と植物の成長
同じ植物を塩分濃度が異なる水で育て、成長の違いを観察。塩害が農業に与える影響など、社会的テーマにも発展できます。 - アンモニア検出:家庭排水のにおい分析
使用後の雑巾水、トイレの水、キッチンの排水などを比べて、アンモニアのにおいの強さやpHをチェック。清掃や環境衛生の視点から考察できます。 - 金属の酸化実験(鉄・銅などのサビ方)
鉄くぎ・銅線・アルミホイルを水や塩水に浸して数日間観察。どの金属がどんな環境でサビやすいかを調べ、防錆の工夫にも言及できます。 - 風速と音の関係(自作風速計)
自作の風速計(ストローと紙コップで作るタイプ)で風速を計り、笛を吹いたときの音の大きさや高さとの関係を調査。音と空気の関係に踏み込んだ研究です。 - 結晶成長条件の最適化
ミョウバン・食塩・砂糖などを溶かした溶液から結晶を作り、温度や振動、冷やすスピードを変えて結晶の大きさや形を比較。美しい結晶写真も記録に役立ちます。 - 酸性雨を再現して影響を調べる
酢やレモン汁を薄めて酸性の水を作り、植物や金属にかけて影響を観察。酸性雨が自然環境に与える影響を体感できるテーマです。 - 静電気で集めるホコリ実験
風船や下敷きで静電気を発生させ、ティッシュやホコリをどれだけ吸着するかを実験。素材やこすり方による違いも検証できます。 - 音速を測ってみよう(風や温度条件で)
一定距離離れた場所で音を出し、動画やストップウォッチでタイム差を計測。音の速さに影響する要素を体感できます。 - プラスチックの分解実験(家庭ゴミ比較)
使い終わったプラスチック容器を土に埋めて経過観察し、自然環境での分解具合を調べる。環境問題への関心を高めるテーマです。 - 手作りバッテリー:レモン電池の電圧測定
レモンに銅板と亜鉛板を刺して発電し、豆電球が光るかを試します。フルーツごとの電圧比較もできます。 - 紫外線計測と日焼け実験(人体非接触)
UVセンサーを使って時間帯や屋外・室内の紫外線量を測定。日焼け止めや帽子の効果も比較できる安全な研究です。 - 砂の粒子サイズと透水性の関係
ふるいを使って砂を粒の大きさで分け、それぞれに同じ量の水を注いで通過時間を測定。地層や地盤の勉強にもつながります。 - アルコールと砂糖の燃焼実験(安全対策必須)
小さな量でアルコールや砂糖の燃え方を比較。安全な環境下で実施し、火の扱いと燃焼の条件を学べます。 - 植物の葉の染色で光合成部位を観察
ヨウ素液や染色液を使って、光合成を行う葉緑体の部分を染め、顕微鏡やルーペで観察します。 - 磁場の可視化実験(鉄粉やコンパス)
磁石の上に紙を置いて鉄粉をまき、磁場の形を視覚化。方位磁針で周囲の磁場の方向も調べられます。
社会・地理系(20選)
地元のこと、暮らしのこと、社会のしくみなどを深く調べられるテーマです。実地調査やインタビュー、統計分析などを取り入れて、主体的に考察する力が身につきます。
- 地域の防災マップを作ろう
避難所や危険箇所(川沿い、崖など)を地図にまとめ、地域の防災意識を高める研究。ハザードマップとの比較も可能。 - 駅周辺の変化を写真で記録・分析
数年前と現在の駅前の写真を比較し、建物や店の変化から地域の発展や衰退を考察します。 - ごみの分別状況を調べよう(家庭・地域)
家庭や地域のごみ出し状況を記録し、分別のルールや実態とのギャップを探ります。改善案を提案することも可能。 - 市区町村のマスコット調査と人気投票
各自治体のマスコットを調べ、特徴や目的(観光・PR)を比較。人気アンケートを実施してデザインの傾向を分析できます。 - 地元の歴史ある建物を探して記録
神社仏閣、旧家、古民家などを訪ね、写真や資料とともに紹介。地域の歴史を身近に学べます。 - 交通手段の変化を調べてみよう
祖父母や親に昔の交通手段を聞いて、現在と比較。自動車・鉄道・自転車の利用率や移動範囲の違いを考察。 - 道の駅・産直市場で地元産品を調査
地元の農産物や加工品を取材・購入し、どこで作られ、どんな特徴があるのかを調べて紹介します。 - 地域の伝統行事やお祭りの記録
盆踊り、神社の例大祭など、地域に根付いた行事を写真・インタビュー付きでまとめ、文化の継承について考察します。 - 災害時の避難生活をシミュレーション
自宅の防災用品を調べ、何日生き延びられるかを計算。不足するものや改善点を明らかにします。 - 商店街と大型スーパーの違いを調査
取り扱い商品、価格、客層、接客の違いを比較。買い物体験も交えてまとめられます。 - 歴史ある地名の由来を調べよう
地元の町名や通り名の意味を調べ、地理や歴史とのつながりを探ります。 - 市の統計資料から人口変化をグラフ化
市役所や自治体サイトのデータを使って、人口推移や年齢構成をグラフ化。高齢化や少子化の傾向も分析可能です。 - 水源地を探訪して飲み水のルートを調査
自宅の水道がどこから来ているかを調べ、浄水場や川の上流を訪ねて写真や資料をまとめます。 - 公園の使われ方を観察調査(時間帯・利用者)
公園を朝・昼・夕方に観察し、利用者の年齢層や遊具の使われ方を記録。地域との関わりを考察します。 - 方言・なまりの違いを調べてみよう
祖父母や親戚などにインタビューし、世代・地域による言葉の違いや意味を比較。方言の魅力も紹介。 - 学校の制服の変化を調べる
昭和・平成・令和と時代ごとの制服を比較し、ファッションや時代背景の違いを探る社会文化研究。 - コンビニの商品数や価格を比較調査
同じチェーンのコンビニでも立地により価格や品ぞろえが違うのかを調べ、表やグラフでまとめます。 - エネルギーの使い方を家庭内で記録
電気・ガス・水道の使用量を記録し、節約方法や省エネの提案を含めた家庭エネルギー研究。 - 住んでいる町の地形と災害リスクを調査
標高、河川、斜面などを地図や現地調査から読み取り、災害時に危険なエリアを可視化します。 - 外国人観光客向けの観光案内を作成
英語や簡単な日本語で観光スポットを紹介するパンフレットを自作。外国人視点で地域を見直せます。
文系・その他系(20選)
言葉、文化、表現、心理など、理科以外の興味分野に向けたテーマを紹介。アンケート調査や観察記録、自分の思考を言葉で表す研究など、多様な視点から取り組める内容です。
- 身の回りのカタカナ語を分類して調べる
日常にある外来語(例:コンビニ、インスタ、リモートなど)を集めて意味・由来・使い方を調査。言葉の流行や変化を学べます。 - 人気のYouTuberの特徴を分析しよう
登録者数が多いYouTuberをいくつか選び、ジャンル、話し方、編集の工夫などを比較。視聴者の心理分析にも発展します。 - 読書感想文で使われる言葉を分析
過去の自分の感想文や他人の感想文を読み、「よく使う言葉」「表現の特徴」などを統計的に分析。作文のコツも発見できます。 - 1日スマホに触れる時間を記録・分析
自分のスマホ使用時間をアプリで記録し、目的(SNS、動画、ゲームなど)別に時間配分を分析。依存の兆候や改善案を考えます。 - 家族で使う言葉の傾向を観察(感情別)
1日家族の会話を記録し、「うれしい言葉」「注意の言葉」などに分類。家族内コミュニケーションを客観的にとらえます。 - 有名な詩や短歌に出てくる季節語の調査
俳句や短歌の中から季語を集めて、春夏秋冬でどう違うかをまとめる。日本語の美しさを再発見できます。 - 「ありがとう」と言われた回数の記録
学校や家庭で、誰から何回「ありがとう」と言われたかを1週間記録。人間関係をポジティブに見直せるテーマ。 - 学校の授業中に聞いた面白い言い回し調査
先生の話や教科書に出てくる言い回しをメモし、なぜ印象に残ったのかを考える。文章表現力アップにもつながります。 - 自分史を書く「わたしの10年間」
生まれてから現在までの出来事を年表形式でまとめ、写真や家族の話を元に振り返る。将来の夢も書いてもよいテーマです。 - 図書館の人気本ランキングと傾向調査
図書館の貸出ランキングから人気のジャンルや年齢別の好みを分析。本離れや読書習慣について考えるきっかけになります。 - 昔話や童話の構成を比較してみよう
昔話や童話を数作品選び、「登場人物」「結末のパターン」などを比較。物語の構造を理解できます。 - 街中の標識・ピクトグラムを集めて分類
公共施設や駅などにある視覚記号を撮影・スケッチして、意味や形の違いをまとめる。ユニバーサルデザインの研究に発展。 - 広告ポスターのデザイン比較(年代・ジャンル別)
昭和・平成・令和の広告を比較し、配色・フォント・キャッチコピーの違いを分析。デザインに興味のある人向け。 - お小遣い帳を1ヶ月つけてお金の使い方を分析
1ヶ月の出費を記録して、無駄遣い・必要経費・貯金のバランスを確認。お金の計画性について考察します。 - おにぎりの具で人気投票&分析
クラスや家族で人気の具をアンケートし、地域や年齢での好みの違いを分析。データのまとめ方の練習にも。 - なぞなぞを自作してジャンル分けしてみよう
オリジナルのなぞなぞをたくさん作り、「食べ物系」「言葉遊び系」などに分類。創造力と構成力が鍛えられます。 - 占いの内容を比較して信頼度を検証
同じ日の複数の占い(星座・血液型など)を集めて、共通点や矛盾を探る。心理的な信頼感の検証にもつながります。 - 子ども新聞と一般新聞の記事を比較
同じニュースを子ども新聞と一般紙で読み比べ、言葉遣いや情報量の違いを分析。メディアリテラシーを養える研究です。 - 絵文字の使われ方をSNSで観察
SNS投稿を観察して、年齢や性別ごとに使われる絵文字の傾向をまとめる。現代の言語・感情表現の研究にも。 - クラスの笑いのツボを調査しよう
おもしろいと思う話や芸人などをクラスメイトにアンケートし、男女差や個人差の傾向を探ります。ユニークで楽しいテーマ。
テーマ別・ジャンル別アイデア(全30選)

自由研究のテーマは、「興味のある分野」から選ぶのもおすすめです。この章では、「環境問題」「プログラミング」「食べ物」「動物」「アート」といったジャンル別に、特徴的で個性的な研究アイデアを紹介します。学年を問わず取り組める内容ばかりなので、自分の関心に合わせてチャレンジしてみましょう。得意なことや好きなものがそのまま研究テーマになれば、楽しく取り組めて、完成度も高くなります。
環境・SDGs
地球温暖化やごみ問題、水資源の保全など、今注目されている環境・SDGsに関するテーマを紹介。未来を考えるきっかけになる研究がそろっています。
- 地域のプラスチックごみ量を調査しよう
ビーチや公園などでごみを拾い、プラスチックごみの量や種類を分類。環境への影響やリサイクルの意識もまとめられます。 - 家庭のエコ度チェックリストを作成
節電・節水・分別・買い物袋の再利用など、家庭でできるエコ活動をチェックリスト化。効果と意識の変化を記録します。 - 雨水利用の実験(畑・鉢植え比較)
雨水と水道水で植物を育てて成長を比較。節水効果や植物への影響も評価できます。 - 発泡スチロールの分解実験
自然環境下に置いた発泡スチロールがどう劣化・分解するかを周期的に観察。マイクロプラスチック問題への入り口になります。 - 身近な再生可能エネルギーを探る
家や学校で見られる太陽光、風力、地熱などを調査。仕組みやメリット・デメリットをまとめてパンフレット作成も可。 - 家庭から出る食品ロスの量を記録
家族協力のもと、食べ残しや賞味期限切れの食品量を1週間調査し、削減策を提案します。
プログラミング・IT系
デジタル技術に興味のある子どもたち向けに、ゲーム作りやアプリ比較、ITツール活用型の自由研究を提案。21世紀の学びを先取りできます。
- スクラッチでゲームを作って遊び心解析
スクラッチを使い、オリジナルゲームを制作。ユーザーが面白いと感じる要素(難易度、見た目など)を友達に評価してもらい分析。 - スマホアプリのUIを評価する調査
同じジャンルのアプリ(例:天気予報)を比較し、使いやすさやデザイン性を分析。改善案も考えてみましょう。 - IoT花壇でリモート観察
湿度センサーや温度計を使い、ネット経由で植物の成長を観察。遠隔でも育つことの仕組みを学べます。 - Webサイトの読み込み速度を比較実験
異なるデバイス(PC・スマホ・タブレット)で同じWebページを読み込み、速度や表示の違いを記録。 - 人工知能チャットボットを作ってみる
簡単な会話ができるチャットボット(例:Python+ChatterBot)を作成し、どんな質問に答えられるか実験。 - ARアプリで地元観光案内を作成
ARツール(例:CoSpaces等)を使って地元の名所ガイドを作成し、スマホをかざすと情報が浮かぶ仕掛けに挑戦。
食品・料理の研究
身近な「食」をテーマに、科学的に比較・分析できる研究が充実。材料や調理法を変えて観察・記録することで、家庭科×理科のような学びが可能です。
- パンのふくらみを砂糖や塩で比べる
砂糖・塩の量を変えたパン生地を焼いて、膨らみ具合や食感の違いを比較。 - 野菜の色素抽出実験(食品着色)
ほうれん草・ビーツ・にんじんなどの色をお湯・酢・アルコールで抽出し、色の出やすさを観察。 - 冷凍食品の解凍スピード調査
自然解凍・電子レンジ・流水での解凍を比較し、ミクロレベルでの変化(色・食感)も記録。 - 発酵食品の味の変化調査(ぬか漬け・キムチ・甘酒など)
1日ごとの味や香り、酸味の変化を記録し、発酵の進みを分析。 - グルテン含有量と粘りの関係を実験
小麦粉の種類(水稻粉・強力粉・薄力粉)でパンや麺を作り、粘りと食感を比較。 - 手作りアイスの素材比較(牛乳・豆乳・ヨーグルトなど)
異なるベース材料でアイスを作り、味・硬さ・口当たりを比較。
ペット・動物
生き物が好きな子におすすめ。飼っている動物や身近な生物を観察し、その行動や特徴から発見を引き出す自由研究です。命の大切さも実感できます。
- ペットの餌の食いつき調査
異なる市販ペットフードを試し、愛犬・愛猫の食いつきを記録。色・香り・形状の影響も考察。 - セミ・カブトムシの活動時間観察
セミやカブトムシを昼夜問わず観察し、活発な時間帯や気温との関係を記録。 - 鳥のさえずりを録音して種類を分類
スマホで録音し、鳴き声から種類を調べてどの時間帯にどの鳥がいるかまとめます。 - 昆虫の幼虫と成虫の形の変化を記録
幼虫の写真・スケッチ・測定を行い、成虫になるまでの成長を詳しく記録。 - 水生生物観察:池や川の生き物調査
池や川の水草、魚、カエルなどを調べ、生物の種類と生息環境をまとめます。 - ペットボトル製エサ台で鳥を呼ぶ実験
手作りエサ台に入れるエサの種類(種・パンくず)を変えて来る鳥の数を比較。
アート・デザイン研究
創造力や表現力を活かしたい人向けのジャンル。光や色、構成、パッケージデザインなど、アートの中にある「科学」や「心理」を探る研究を提案します。
- 光と影の作品制作と分析
光源とオブジェを使って壁に映る影の形を記録し、時間とともに変化する影の動きをまとめます。 - 温度による色の変化絵画(熱色絵具)
温度で色が変わる絵具や素材を使い、手で触ると色が変わる作品を制作・観察。 - まちの壁画や落書きを写真で記録
地域のストリートアートを撮影し、色使いやテーマ、メッセージ性を分析します。 - パッケージデザイン比較研究(食品や日用品)
同じ商品ジャンルのパッケージを集め、配色・形・キャッチコピーの違いを比較。 - 手作り版画でデザインの深層を探ろう
自分でデザインした版画作品を制作し、彫る・刷る・構図の工夫などを記録。 - 自由な折り紙アート:折り方と見た目の関係
折る回数や形を変えた折り紙で作品を作成し、視覚的な違いをまとめます。
よくある質問(FAQ)

Q1. 1日で終わる自由研究はありますか?
あります。特に低学年や時間が限られている場合には、「紙飛行機の飛ぶ距離比較」「色水で花が変色する実験」などがおすすめです。準備や観察に時間がかからず、その日のうちに観察・記録・まとめまで終わらせることができます。
Q2. 必要な道具はどこでそろえるべき?
ほとんどの材料は、100円ショップやホームセンター、スーパーで入手可能です。実験や観察テーマを選ぶ際には、「特別な機器がいらないもの」「家庭にあるものでできるもの」を優先して選ぶと、準備の負担が減ります。
Q3. インターネットの情報を参考にしても大丈夫?
基本的に問題ありませんが、そのまま丸写しするのはNGです。参考にした情報は、「自分で実験・観察・調査を行った上で補足資料として使う」のが理想的。引用元は明記すると信頼性も高まります。
Q4. 親はどこまで手伝っていいの?
自由研究は「子どもが自分で考え、まとめる」ことが大切ですが、小学生では準備や道具の使い方に親のサポートが必要な場面もあります。あくまで「サポート役」に徹し、「調べ方を教える」「実験時の安全を見守る」といった形が適切です。
Q5. まとめ方のコツはありますか?
自由研究の基本構成は以下のようになります:
- テーマ(研究の目的)
- 準備したもの(材料・道具)
- やり方(方法・手順)
- 結果(観察・記録)
- 考察(わかったこと・気づき)
- 感想
イラストや写真を入れると見やすくなり、先生にも伝わりやすいレポートになります。
まとめ
夏休みの自由研究は、子どもの「好き」や「興味」から始まる学びのチャンスです。本記事では小学生から中学生まで、学年別・ジャンル別に合計150のアイデアを紹介しました。
科学実験から地域調査、プログラミングやアートまで、幅広いテーマから選ぶことで、自分にぴったりの研究テーマが見つかるはずです。大切なのは、楽しみながら「なぜ?」を探究すること。自由研究を通じて、観察力・発想力・表現力を育んでいきましょう。