当該と該当の違い【例文60】決定的な違い丸分かり

「当該」と「該当」。どちらもビジネス文書や報告書、あるいは法律文書などで頻繁に目にする言葉ですが、意味や使い方を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。似たような響きと漢字を使っているため、何となく同じように使ってしまっているケースも多く見受けられます。
しかし、実はこの二つの言葉は「意味」も「使い方」も明確に異なります。使い方を間違えると、文章全体の意味が曖昧になったり、信頼性を損なったりする恐れがあります。
この記事では、まず「当該」と「該当」の意味を整理し、それぞれの使われ方を具体的なシーンと例文を通じて詳しく解説していきます。さらに、両者の決定的な違いを比較表でわかりやすく説明し、実際の文書作成や会話で正しく使えるようになることを目指します。
それでは、一緒に「当該」と「該当」の違いをしっかり理解していきましょう。
目次
「当該」と「該当」の違い
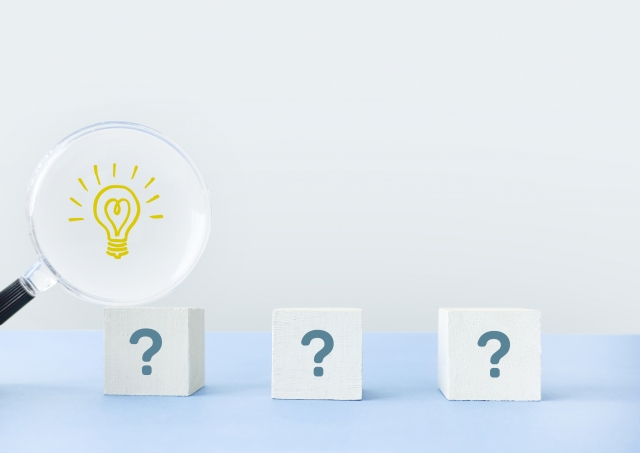
「当該」と「該当」はどちらも「何かを指し示す」働きを持ちますが、意味と用途には明確な違いがあります。以下の表で整理してみましょう。
| 項目 | 当該(とうがい) | 該当(がいとう) |
|---|---|---|
| 意味 | 特定のものや人を指す | 条件・基準に合うものを指す |
| 使う場面 | 法律文書、契約書、報告書、公式通知など | アンケート、調査、報告書、問い合わせなど |
| 使い方 | 名詞の前に置いて、その対象を特定する(例:当該商品) | 条件に合うものを述べる(例:該当する項目) |
| 文の役割 | 指示語の強化・正確な対象の特定 | 一致・適合の有無を表す |
| 否定形との相性 | あまり使わない(例:×当該なし) | よく使う(例:該当なし) |
決定的な違い
- 「当該」は、すでに特定されている対象を再確認・指名する言葉です。
例:報告書で「当該案件は〜」と使うことで、その報告対象を明確にします。 - 「該当」は、条件に一致するかどうかで判断される対象を示す言葉です。
例:「該当者はいません」は、条件に当てはまる人がいないことを意味します。
使い分けのポイント
- 「どれのことかを明確に示したい」→ 当該
- 「条件に当てはまるかどうかで振り分けたい」→ 該当
「当該」の意味
「当該(とうがい)」とは、「今話題にしているその対象」や「特定の物事に関係する」ことを表す言葉です。文脈によっては「その」「この」といった指示語に近い働きを持ちますが、「当該」はよりフォーマルで正確に対象を指し示す役割を担います。
特徴
- 法律やビジネス文書で多用される堅めの表現
- 「この」「その」よりも明確に対象を示すことができる
- 文脈の中で、すでに説明されているものや、これから詳述するものを指す
たとえば、「当該商品」や「当該社員」という表現では、すでに述べられている商品や社員について述べていることがわかります。一般的な会話ではあまり使われない表現ですが、書類やメールでは正確さが求められるため、よく使用されます。
「該当」の意味
「該当(がいとう)」とは、「条件や基準に当てはまること」や「ある事柄に一致すること」を意味します。何らかの条件が与えられている状況で、それに合致する対象がある場合に使われる言葉です。
特徴
- 条件との一致を表す
- アンケート、調査、報告書、法的文書などで使用される
- 否定文(該当しない)との相性が非常に良い
例えば、「該当者なし」「該当項目がありません」といった表現では、「条件に合う人や項目が存在しない」という意味になります。一方で、「該当する場合は以下を記入してください」などの形で、条件に当てはまる場合の対応を促す言い回しとしてもよく使われます。
このように、「該当」は条件・基準との関係性の中で使う言葉であり、対象を明確に指す「当該」とは用途が異なります。
「当該」を使うシーン

「当該」は、特定の対象を正確に示す必要がある場面で使われます。特にビジネスや法律、行政などのフォーマルな文書において、その対象を明示する役割として重宝されています。
① 法律・契約関連文書
法令や契約書では、「この条項がどの対象に関するものか」を明確にする必要があります。そのため、「当該契約書」「当該条項」などが頻出します。
② 行政文書・公的手続き
行政の通達や申請書類などで、「どの申請」「どの資料」に関しての説明かを示すために、「当該申請」「当該資料」などと記述されます。
③ ビジネスメール・社内文書
報告書や依頼文、議事録などの中で、「どの商品」「どの担当者」などを指すために「当該商品」「当該担当者」などの表現が使われます。
④ 報告書・調査資料
特定の調査対象や報告対象を表すのに「当該施設」「当該期間」などの語が使用されます。
※注意点
「当該」は文語的で硬い表現のため、口頭での会話やカジュアルな文脈では「その」「該当の」などの柔らかい表現に置き換えることが適切な場合があります。
シーン別「当該」の使い方【例文20】
ここでは、実際のビジネス・行政・法務などのシーンにおける「当該」の使い方を例文で紹介します。使い方のニュアンスや文脈に注目してご覧ください。
① 法律・契約関連文書
- 当該契約は両者の合意に基づき締結されたものとする。
- 当該条項は、違約時の罰則について定めたものである。
- 当該書類の提出期限は、今月末までです。
- 当該特許は現在申請中である。
- 当該案件は法務部の確認が必要です。
② 行政文書・公的手続き
- 当該申請については、以下の書類を添付してください。
- 当該地区における災害救助は終了しました。
- 当該補助金の対象となる条件を満たしていません。
- 当該自治体の判断により中止されました。
- 当該届出は所定の様式で提出してください。
③ ビジネスメール・社内文書
- 当該商品の仕様について、詳細をご確認ください。
- 当該社員に対する処分は未定です。
- 当該報告書は営業部が作成したものです。
- 当該部署との連携が必要になります。
- 当該ミスに関しては、再発防止策を講じています。
④ 報告書・調査資料
- 当該期間中の売上推移を以下に示します。
- 当該施設では、感染症対策が徹底されています。
- 当該地域の人口動態について調査を行いました。
- 当該プロジェクトは2025年4月に開始されました。
- 当該データは機密情報に該当します。
「該当」を使うシーン

「該当」は、ある条件や基準に合致するかどうかを表現する際に使用されます。調査・アンケート・報告書・エラー対応など、情報の選別や分類が必要な場面で特に多く見られる表現です。
① アンケート・調査結果の記述
対象者や条件に一致する項目を報告する際に「該当」が使われます。例:「該当者なし」「該当する項目は以下の通り」
② 報告書・会議資料
条件に合致するケースを特定する文脈で登場します。例:「該当部門」「該当案件の進捗状況」
③ トラブル対応・FAQ
ユーザーが遭遇している問題がシステム上の既知の条件に当てはまるか確認するために使用されます。例:「該当するエラーが見つかりませんでした」
④ 採用・資格などの審査
応募条件や認定基準に合うかどうかを判断するための表現として使われます。例:「該当者のみ面接対象となります」
※注意点
「該当」は否定文(該当しない、該当者なし)での使用が非常に一般的です。条件に合致しないことを明確に伝えるのに適しています。
シーン別「該当」の使い方【例文20】
「該当」は、条件に合致する対象があるかどうかを判断・表現する際に使われます。以下に、具体的なシーンごとの例文を20個ご紹介します。
① アンケート・調査
- 該当する方は「はい」にチェックを入れてください。
- 今回の調査では、該当者は見つかりませんでした。
- 該当項目にマークを付けてください。
- あなたが該当する職種を選んでください。
- 年齢別に該当する回答を分類しました。
② 報告書・会議資料
- 該当部門の売上が予想を上回りました。
- 該当案件は現在、審査中です。
- 該当データを抽出してグラフ化しました。
- 該当期間中の業績は安定しています。
- 該当顧客に対しては、個別対応を行います。
③ トラブル対応・FAQ
- 該当するエラーコードは「E102」です。
- 入力内容に該当する情報が見つかりません。
- 該当条件に一致するファイルが存在しません。
- お問い合わせ内容に該当するFAQをご確認ください。
- この不具合に該当する修正パッチはリリース済みです。
④ 採用・資格関連
- 応募条件に該当する方のみご連絡いたします。
- 該当者は書類選考を通過しました。
- 該当資格をお持ちの方はご提示ください。
- 該当者なしの場合は、次回募集をご案内します。
- 該当する経験をお持ちの方を優先的に採用します。
「当該」と「該当」間違えやすい使い方【例文20】
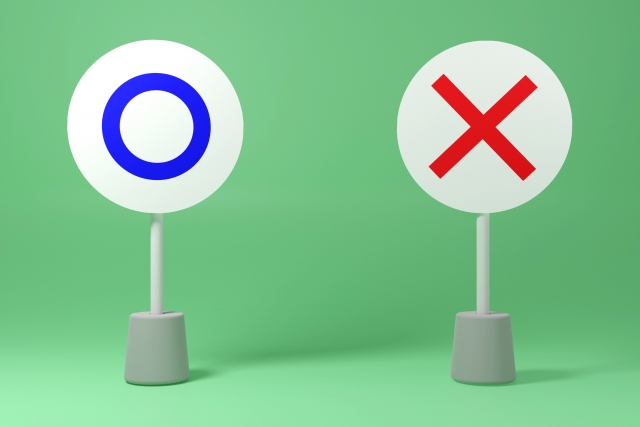
「当該」と「該当」は似ているため、誤って使われることが多くあります。ここでは、誤用例と正しい使用例をセットで紹介し、違いを明確に理解できるようにします。
① ビジネス文書での誤用と正解
- 誤:該当契約書を提出してください。
正:当該契約書を提出してください。 - 誤:当該条件に一致する人を抽出してください。
正:該当条件に一致する人を抽出してください。 - 誤:当該者は面接に進んでください。
正:該当者は面接に進んでください。 - 誤:該当部署の報告書をご確認ください。
正:当該部署の報告書をご確認ください。 - 誤:当該質問に「はい」または「いいえ」でお答えください。
正:該当質問に「はい」または「いいえ」でお答えください。
② 行政・契約関係での誤用と正解
- 誤:該当資料は以下の通りです。
正:当該資料は以下の通りです。 - 誤:当該者なしと判断された。
正:該当者なしと判断された。 - 誤:当該エリアでは支援が終了しました。
正:該当エリアでは支援が終了しました。 - 誤:該当文書の署名欄をご確認ください。
正:当該文書の署名欄をご確認ください。 - 誤:当該資格を取得した者が対象です。
正:該当資格を取得した者が対象です。
③ 書類・申請・調査の誤用と正解
- 誤:該当項目を記入のうえ、ご提出ください。
正:当該項目を記入のうえ、ご提出ください。 - 誤:当該回答を抽出しました。
正:該当回答を抽出しました。 - 誤:当該期間にサービスを利用された方が対象です。
正:該当期間にサービスを利用された方が対象です。 - 誤:該当規約の内容をご確認ください。
正:当該規約の内容をご確認ください。 - 誤:当該条件に従って対応してください。
正:該当条件に従って対応してください。
④ その他よくある誤用
- 誤:該当商品が見つかりませんでした。
正:当該商品が見つかりませんでした。 - 誤:当該項目に該当しません。
正:該当項目に該当しません。 - 誤:当該者に連絡を行ってください。
正:該当者に連絡を行ってください。 - 誤:該当ミスについて報告します。
正:当該ミスについて報告します。 - 誤:該当施設での調査が必要です。
正:当該施設での調査が必要です。
「当該」の言い換え(類語)
「当該」は文語的な表現であり、ビジネスや法律、行政文書などで使われる堅い言葉です。より日常的な表現に言い換えたい場合や、文章をやわらかくしたい場合は以下の類語を使うことができます。
| 類語 | 解説 | 使用例 |
|---|---|---|
| その | カジュアルな指示語 | その商品は現在在庫切れです。 |
| 該当の | 条件を含めた意味で近い | 該当の資料をご確認ください。 |
| 対象の | 形式的かつ使いやすい | 対象の契約書を提出してください。 |
| 指定の | 範囲が限定されている場合に適用 | 指定の時間に集合してください。 |
| 当の | 文芸的・口語的に使われる | 当の本人は知らなかったようだ。 |
「当該」は、意味が明確かつ誤解を避けたい公式文書でよく使われます。やわらかい言い回しは便利ですが、文脈に応じて選ぶことが重要です。
「該当」の言い換え(類語)
「該当」は「条件や基準に当てはまること」を意味する表現で、やや硬い印象を与える言葉です。場面や読み手に応じて、より分かりやすい言い換えを選ぶことで、文章のトーンや理解度を調整できます。
| 類語 | 解説 | 使用例 |
|---|---|---|
| 当てはまる | 条件に合うという意味で最も一般的 | この条件に当てはまる人を教えてください。 |
| 一致する | データや条件との整合性を示す | 入力内容が条件に一致しません。 |
| 合致する | 正式な文書で多く使われる | 該当者は要件に合致しています。 |
| 該当する | 「該当」の動詞形で自然な言い換え | 該当する場合は、こちらに記入してください。 |
| 適用される | 制度や法律が使われる状況で使用 | この法律は外国人にも適用されます。 |
「該当」は正確な判断や分類が必要な場面で使われます。言い換えを使う際は、文脈によって意味がブレないよう注意が必要です。
よくある質問

ここでは、「当該」と「該当」に関して多くの人が抱く疑問をQ&A形式でまとめました。
Q1. 「該当者なし」と「当該者なし」は同じ意味ですか?
A. いいえ、意味が異なります。
「該当者なし」は、「条件に当てはまる人がいない」という意味で正しい表現です。
一方、「当該者なし」という表現は不自然で、意味が曖昧になります。そもそも「当該」はすでに特定されている対象を指すので、「当該者がいない」と言うと、「話題にしていた人がそもそもいなかった」という矛盾を含む可能性があります。
Q2. 「当該」と「その」は同じですか?
A. 似ていますが、ニュアンスが異なります。
「当該」は文語的かつ専門的な言葉で、特定の対象を正確に指し示す必要がある文脈で使います。「その」はより日常的な言い回しで、話し言葉や軽い文書では「当該」の代用として使われることがありますが、正式文書では「当該」が適切です。
Q3. 「該当」はビジネスメールで使っても良いですか?
A. はい、適切に使えば問題ありません。
「該当者なし」「該当項目」「該当する条件」といった表現は、ビジネスメールでも一般的です。ただし、使用する際は条件との一致が明確であることが重要です。
まとめ
「当該」と「該当」は、漢字も響きも似ているため混同されがちですが、その意味と使い方は明確に異なります。「当該」はすでに特定された対象を指し、「該当」は条件に一致するものを表します。
それぞれの適切な使い方を理解することで、文章の正確性と信頼性が格段に向上します。ビジネス文書や報告書、行政文など、フォーマルな場面で正しく使い分けることが求められます。この記事で紹介した例文や言い換え表現を活用し、日々の業務や文書作成に役立ててください。




