「熱る」の読み方は、ねつる?ほてる?火照るとの違いは?

日本語には、日常会話ではあまり使われなくても、深い意味や豊かな表現力を持つ言葉が数多く存在します。「熱る」という言葉もその一つです。この言葉は、身体や感情の高まりを表す場面で使われることが多く、文学作品やニュース記事、演説などで見かけることがあります。しかしながら、正しい読み方や意味、そして使い方まで理解している方は少ないかもしれません。
この記事では、「熱る」という言葉の正しい読み方として「ほてる」と「いきる」の2つを取り上げ、それぞれの意味や使い方を豊富な例文とともに解説します。さらに、「熱る」とよく似た言葉との違いや、派生語・関連語にも触れながら、語彙力と表現力を深められる内容をお届けします。
「聞いたことはあるけど、実際に使ったことがない」「なんとなく意味はわかるけれど自信がない」という方にも、わかりやすく丁寧にご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
「熱る」の正しい読み方

「熱る」という漢字には、主に2つの訓読みが存在します。それぞれの読み方には異なる意味や用法があり、文脈によって使い分けられます。
一つ目は「ほてる」という読み方で、現代において最も一般的に使われるものです。この「ほてる」は、身体が内側から熱を持ったように感じる状態や、緊張や興奮によって顔などが赤くなる様子を表します。たとえば、「風邪を引いて顔が熱る」や「緊張して頬が熱るのを感じた」といった形で用いられます。なお、「火照る」と書くこともあり、意味としてはほぼ同じですが、漢字の選び方は文章のトーンや作者の意図により異なります。
二つ目は「いきる」と読むもので、古語的な表現にあたります。現代では一般的な会話や文章にはあまり登場しませんが、文語体や古典文学などでは見かけることがあります。この「熱る(いきる)」は、「意気込む」「感情が高まる」「気負う」といった意味合いを持ちます。たとえば、「若者たちは勝利を目指して熱り立つ」や「心の内に熱る想いを押さえきれなかった」といった表現が可能です。
このように、「熱る」は一つの漢字表現でありながら、「ほてる」と「いきる」という二つの読み方を持ち、それぞれ異なる意味と文体に対応しています。読解の際には、その語が使われている文脈をよく確認することが大切です。
「熱る(ほてる)」の意味
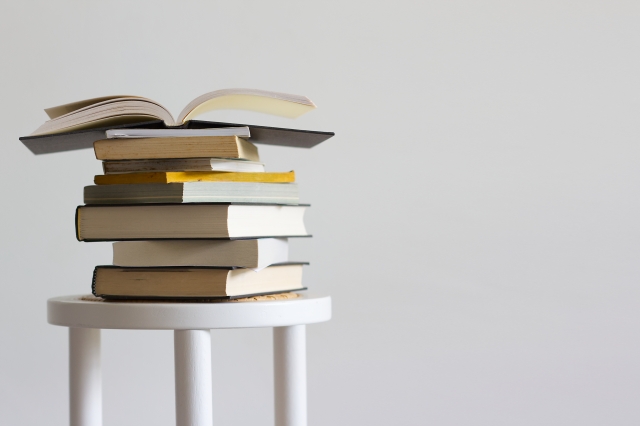
「熱る(ほてる)」という言葉は、身体的な状態や感情の変化を表す日本語表現の一つで、以下のような意味を持ちます。
①身体が熱を帯びる状態
もっとも一般的な意味として、「身体の一部が熱くなる状態」を指します。これは風邪や疲労、運動後などに感じる、体の内側から温まっているような感覚です。また、気温や湿度によるものではなく、体内の反応によって起きる現象を表します。
例:
- 長風呂のせいで顔が熱る。
- 日焼けをして肌が熱っている。
②感情が高まって顔や身体が熱くなる状態
緊張や恥ずかしさ、怒りなどの感情の高まりによって、顔が赤くなる、体が火照るように感じる場合にも「熱る」が使われます。これは精神的な影響が身体に表れたものです。
例:
- 発言を指摘され、思わず顔が熱る。
- 応援しているチームの勝利に心が熱った。
③興奮・高揚の状態
興奮したり、何かに強く心を動かされたりして、感情が高ぶっている状態を表すときにも使われます。文学作品などでは比喩的な表現として用いられることがあります。
例:
- 演奏を聴きながら胸が熱る思いだった。
- かつての情熱がふたたび熱ってきた。
「熱る(ほてる)」という言葉は、単に“熱くなる”というだけでなく、内面からの感情の動きや、自然な身体反応までも繊細に表現できる言葉です。状況に応じて、適切に使い分けることで、表現に深みを持たせることができます。
「熱る(ほてる)」の使い方・例文

「熱る(ほてる)」は、身体的な熱感や感情の高まりを表す際に使われます。以下に、実際の使用シーンを想定した例文を10個ご紹介します。日常会話や文章作成の参考にしていただければ幸いです。
【身体的な熱りを表す例文】
- 長時間歩いたせいで、足が熱ってジンジンする。
- 風邪をひいて熱が出たのか、顔全体が熱っている。
- 夏の強い日差しを浴びて、腕が熱ってきた。
- 湯船に浸かりすぎて体が熱り、なかなか寝つけなかった。
- 日焼けした肩がヒリヒリと熱って痛む。
【感情的な熱りを表す例文】
- 好きな人の前では、いつも顔が熱ってしまう。
- 試験の結果を聞いて、緊張で胸が熱るのを感じた。
- 議論が白熱し、つい感情が熱って声を荒げてしまった。
- 応援していたチームが逆転勝ちし、全身が熱るような興奮を覚えた。
- 初めての発表で、恥ずかしさと緊張が入り混じり、顔が熱った。
これらの例文からわかるように、「熱る」は身体と心の両方に対して使える便利な表現です。特に、直接的に「熱い」「暑い」と言うよりも、内面からの熱を感じさせるニュアンスを持ち、表現に奥行きを与える言葉です。
「熱る」と「火照る」の違い

「熱る(ほてる)」と「火照る(ほてる)」は、どちらも読み方が同じで、意味も似ているため混同されやすい言葉です。しかし、使われる場面やニュアンスには微妙な違いがあります。ここでは、それぞれの違いをわかりやすく比較しながら解説します。
共通点
両者とも、「身体が内側から熱くなる状態」や「感情の高まりによる身体の反応」を表現します。読み方も「ほてる」で共通しています。
違い1:使われる漢字の傾向
- 熱る(熱)
→ 「熱」という字は、物理的・心理的な“熱”全般を表します。
→ 広い意味を持ち、身体や感情の両方に使えます。 - 火照る(火)
→ 「火照る」は主に身体的な状態、特に皮膚が赤くなったり、温かくなる状態を描写します。
→ 肉体的・生理的な反応にフォーカスされる傾向があります。
違い2:使用される場面や文体
- 熱る:
→ 感情の高まり、緊張、怒り、興奮など、心理的な状態を含んだ場面でも使われます。
→ 文語・口語問わず使用可能で、文学的な表現にも登場します。 - 火照る:
→ 主に身体の状態(顔、肌など)に対して用いられることが多いです。
→ 一般的に会話や小説などで肉体的反応を描くときに使われます。
例文比較
| 文例 | 意味 | 適した表現 |
|---|---|---|
| 緊張して顔が赤くなった | 心理的な要因 | 顔が熱った |
| 日焼けして腕が赤くなった | 肉体的な反応 | 腕が火照った |
| 興奮して全身が熱くなった | 感情の高まり | 全身が熱った |
| 長風呂のあとで肌が温かい | 物理的な状態 | 肌が火照った |
- 「熱る」は、感情・身体のどちらにも使える汎用的な表現
- 「火照る」は、身体の状態を中心に描写する際に適している表現
使い分けのポイントは、「原因が心理的か身体的か」、「表現の対象が感情か皮膚か」によって判断することができます。
「熱る(いきる)」の意味
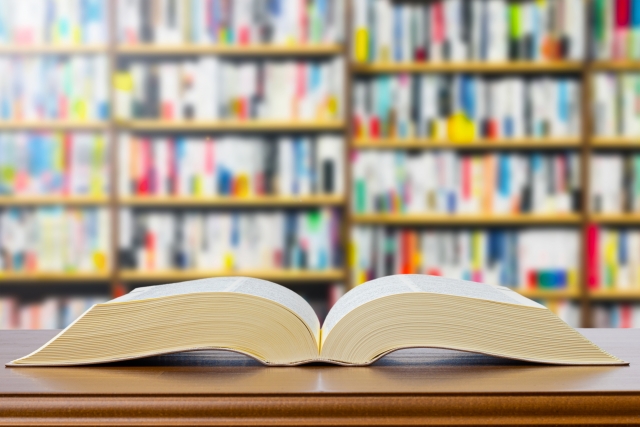
「熱る(いきる)」は、現代ではあまり見かけない読み方ですが、文語的・古典的な日本語表現として確かに存在する言葉です。主に、気持ちが高ぶることや、意気込み、興奮を示す場面で用いられます。
意味
「熱る(いきる)」は、以下のような意味合いを持ちます。
- 意気込む
- 気持ちが高ぶる
- 血気盛んになる
- 興奮して行動を起こそうとする
この言葉は、平安時代や戦国時代の文学・記録・演説などに使われていた歴史があり、現代ではあまり見かけないものの、古典文学や古語辞典ではしばしば登場します。
語源と背景
「熱る(いきる)」の「いき」は、「意気(いき)」や「意気地(いくじ)」といった言葉にも通じ、精神的な高ぶりや活力を意味します。そこに「熱」の文字を当てることで、「内から燃えるような意気込み」というニュアンスが加わっています。
現代での使用
現代の口語ではほとんど使われませんが、以下のような場面で目にすることがあります。
- 歴史小説
- 古典文学やその翻案
- 伝統芸能のセリフ(能・狂言・歌舞伎など)
- 特定の比喩的・詩的な表現としての使用
「熱る(いきる)」の使い方・例文

「熱る(いきる)」は、主に古語や文語体で使われる表現で、「意気込む」「感情が高ぶる」「勢いづく」といった意味を持ちます。現代では少し古風に聞こえる表現ですが、文学的な場面や歴史的背景を描く文章では、効果的に用いられます。
以下に、現代的な言い回しも交えて、「熱る(いきる)」の意味が伝わりやすい例文を10個ご紹介します。
【熱る(いきる) 例文 10選】
- 若武者たちは戦を前にして胸を熱り、士気を高めていた。
- 発言の機会を得た彼は、熱る気持ちを抑えきれず壇上に立った。
- 指導者の言葉に人々は心を熱り、一斉に立ち上がった。
- 初陣を控えた兵たちは、希望と不安に熱っていた。
- 観衆の声援に背中を押され、選手たちは熱ってコートに向かった。
- 熱る想いを筆に託し、彼女は力強い書をしたためた。
- 勝利への執念が彼を熱らせ、誰よりも早く行動に移した。
- 時代の変革を信じる青年たちは、熱る情熱を胸に集まった。
- 長く抑えてきた怒りが、ついに彼を熱らせた。
- 言葉にできぬ感情が胸の奥で熱り、涙となってあふれ出た。
使い方のポイント
- 「熱る(いきる)」は、単なる「熱くなる」ではなく、「内側からわき上がる強い気持ち」を描写する際に用います。
- 主語は人であることが多く、行動や発言の直前に気持ちが高ぶる描写として使うのが自然です。
- 叙情的・詩的な文脈で活躍する表現です。
「熱る」の類語や関連語
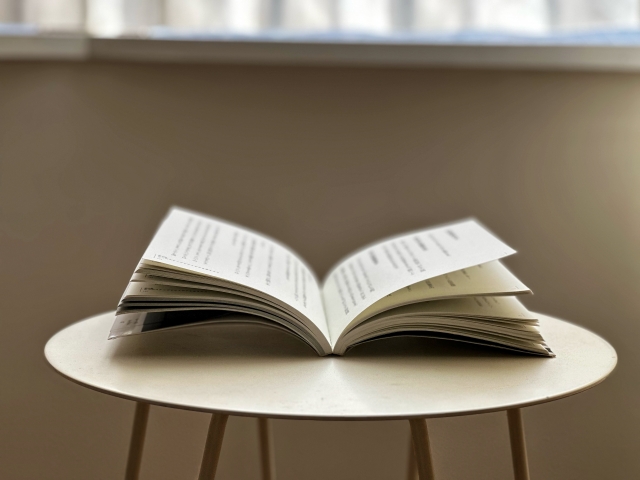
「熱る(ほてる/いきる)」という言葉は、身体的な熱感や感情の高ぶりを表す豊かな表現です。ここでは、その意味に近い「類語」や「関連語」をご紹介し、それぞれの違いや使い分けについても解説します。
火照る(ほてる)
すでに前章で比較した通り、「火照る」は主に身体が熱くなる状態を指します。皮膚の赤みや熱感をともなうような場面に適しています。
- 類似性:どちらも身体の熱感を表す
- 違い:火照るは物理的・生理的な反応に特化
上気する(じょうきする)
興奮や緊張によって顔が赤くなる、またはほてる状態を指します。特に感情の高ぶりに関連して使われる傾向があります。
- 例文:緊張のあまり顔が上気した。
- 「熱る」との違い:ややフォーマルで硬い表現、心理的な要因に限定されがち
紅潮する(こうちょうする)
顔や頬などが赤らむことを表します。血の気が増して赤みを帯びる様子を表現し、医学的な文脈でも使われることがあります。
- 例文:怒りで顔が紅潮した。
- 「熱る」との違い:見た目の変化に焦点を当てた言葉
のぼせる
「熱や興奮で頭がボーッとする」状態を指します。主に身体的な不調や一時的な感情の乱れに使われます。
- 例文:お風呂に長く入りすぎてのぼせた。
- 「熱る」との違い:少しネガティブなニュアンスを含むことがある
興奮する
精神的な高ぶりをストレートに表す現代語です。感情が高まること全般に使用されます。
- 例文:その話を聞いて彼は興奮していた。
- 「熱る(いきる)」に近い意味を持つ
情熱(じょうねつ)
具体的な行動や意志を支える強い感情を指します。やや抽象的な表現で、「熱る(いきる)」の内面描写に近い使い方ができます。
- 例文:彼は教育に対して強い情熱を持っていた。
意気込む(いきごむ)
「熱る(いきる)」と非常に近い言葉で、意欲的に物事に取り組もうとする姿勢を示します。
- 例文:試合に向けて意気込む選手たち。
- 「熱る(いきる)」の言い換えとして適切
「熱り」の読み方と意味、使い方・例文(10選)

「熱り」という言葉は、「熱る」の連用形または名詞形として使われます。読み方は 「ほとぼり」 で、主に比喩的な意味合いで用いられる表現です。特に、「熱りが冷める」という言い回しでよく知られています。
「熱り」の読み方
- 読み:ほとぼり
- 表記:主に仮名(ひらがな)で書かれることが多い(例:「ほとぼりが冷める」)
意味
「熱り(ほとぼり)」には、次のような意味があります。
- 熱気や興奮、感情の高ぶりなどがまだ残っている状態
- 騒動や話題などがまだ世間に強く印象として残っている状態
主に「熱りが冷める」という表現で、時間の経過とともに関心や興奮が静まっていくさまを表現します。
使い方のポイント
- 名詞として使うため、「~の熱り」「熱りが~」といった形で使います。
- 一般的に、「熱りが冷める」「熱りが残る」など、過去の出来事に対する反応の余韻を描く場面で使います。
- 日常会話、ビジネス、報道、文学など幅広い文脈で使用可能です。
例文(10選)
- 事件の熱りが冷めないうちは、慎重な対応が求められる。
- 昨日の喧嘩の熱りがまだ残っていて、話しかけづらい雰囲気だった。
- 勝利の熱りが冷めた後、選手たちは冷静に反省会に臨んだ。
- 彼の大胆な発言の熱りが、SNS上で広まり続けている。
- 初舞台の熱りが心に残り、しばらく眠れなかった。
- 熱りが冷めるのを待ってから、話し合いを再開することにした。
- 話題の熱りが落ち着いた頃に、続編の発表が行われた。
- あの映画の熱りは、公開から数週間経っても消えていない。
- 熱りが再燃し、またもや議論が白熱している。
- トラブルの熱りが冷めたら、きちんと謝罪したいと思っている。
「熱り(ほとぼり)」は、出来事や感情の“余韻”を表現する便利な語句です。特に、冷静さを取り戻す過程や、状況が落ち着くまでの“間”を描く際に、自然に使える日本語表現です。
「熱り立つ」の読み方と意味、使い方・例文(10選)

読み方
「熱り立つ」は 「いきりたつ」 と読みます。
意味
「熱り立つ(いきりたつ)」は、気持ちが高ぶって、抑えきれないほど興奮したり、怒ったりする状態を表します。とくに、怒りや闘志など、強い感情に突き動かされて行動しそうになるような精神状態を表す場面でよく使われます。
使い方のポイント
- 現代の日常会話ではやや文学的・感情の強い表現として使われます。
- 特定の感情(怒り、興奮、闘志)を強調する場面に適しています。
- 感情の「高ぶり」→「行動への衝動」が含まれている点が特徴です。
例文(10選)
- 部下の軽率な行動に、彼は思わず熱り立った。
- 敵の挑発に熱り立つも、冷静さを保とうと努めた。
- 熱り立つ心を押さえつけながら、彼女は口を開いた。
- 試合直前、観客の声援に選手たちは熱り立った。
- 無礼な態度に、父は珍しく熱り立っていた。
- 熱り立つ議論が続き、会議室は一時険悪な雰囲気に包まれた。
- 彼の胸の奥には、まだ熱り立つ思いが残っていた。
- 熱り立つ気持ちを原動力に、彼は立ち上がった。
- 長年の悔しさが熱り立ち、彼の中で再び炎となった。
- 覚悟を決めたとき、熱り立つ心が背中を押した。
類語との違い
「熱り立つ」は「興奮する」「激昂する」「感情が高ぶる」と似た意味ですが、
- 怒りや闘志の感情がメインであること
- 行動に移りそうな衝動を伴うこと
が特徴です。感情のピークに近い状態を描写するときに、より迫力ある表現として使えます。
「人熱れ」の読み方と意味、使い方・例文(10選)

読み方
「人熱れ」は 「ひといきれ」 と読みます。
意味
「人熱れ(ひといきれ)」とは、多くの人が狭い場所に集まったことで発生する熱気や空気のこもった状態を指します。
- 密室や満員電車、教室、イベント会場など、人の集まりによって室温が上がり、空気が重たく感じられる状態
- 湿度・温度・二酸化炭素濃度が上がることによる不快感を含むことが多いです。
使い方のポイント
- 名詞として使用します(例:「人熱れがひどい」)。
- 「人の熱気で暑くなる」という意味で、やや口語的な表現です。
- 実生活の中でのリアルな不快感を描くのに適しています。
例文(10選)
- 満員電車の中は、人熱れで息苦しかった。
- 体育館の扉を開けると、人熱れの熱気が一気に押し寄せた。
- 会場は人熱れで蒸し風呂のようだった。
- クーラーが効かず、部屋中が人熱れでムンとした空気に包まれていた。
- ライブハウスは熱気と人熱れで、立っているだけで汗が噴き出した。
- 密閉された空間で人熱れがひどく、しばらく外に出て涼んだ。
- エレベーター内は人熱れで、誰もが無言になっていた。
- 夏祭りの屋台通りは人熱れがすごく、子どもたちもぐったりしていた。
- 受験会場の教室は、緊張と人熱れで集中しづらかった。
- 人熱れを避けるために、開演前に早めに会場を出た。
補足:漢字と表記について
「人熱れ」は日常的には「人いきれ」「ひといきれ」とひらがな・送り仮名で表記されることが多く、新聞・小説・会話文などでも一般的です。ただし、意味を正確に伝えるために漢字表記「人熱れ」が使われることもあります。
まとめ
「熱る(ほてる/いきる)」という言葉は、一見すると単純な「熱くなる」という意味に思われがちですが、実は身体的・感情的な変化を繊細に表現できる豊かな日本語です。「ほてる」は、体の内側からの熱感や、緊張・恥ずかしさによる反応を描く際に使われ、「いきる」は意気込みや興奮、心の高まりを示す文語的な表現です。
また、「熱り(ほとぼり)」や「熱り立つ(いきりたつ)」「人熱れ(ひといきれ)」などの関連語も存在し、それぞれ異なる文脈で活躍します。似た言葉との違いや使い分けを理解することで、表現力が格段に豊かになります。
本記事を通じて、「熱る」という言葉の持つ多様な意味や魅力を知っていただき、日常の会話や文章の中で、自信を持って使えるようになっていただければ幸いです。




