「ついていく」の漢字は「付」「着」どっち?使い分けと例文60選

日本語には、ひらがなで書かれると一見同じように見えても、漢字にすると意味や使い方が異なる言葉がたくさんあります。その中でも、「ついていく」という言葉は、日常的によく使われるにもかかわらず、「付いていく」と書くべきか、「着いていく」と書くべきか、迷いやすい表現の一つです。
例えば、友達の後ろを歩いていくとき、「友達についていく」はどちらの漢字を使うべきでしょうか?また、時代の流れに「ついていく」場合はどうでしょうか?どちらも自然な日本語に聞こえますが、正確な漢字表記を問われると迷ってしまう方も多いはずです。
本記事では、「ついていく」の正しい漢字表記とその理由を丁寧に解説していきます。また、「付いていく」と「着いていく」の使い分け方、そしてそれぞれの使い方に適した具体的な例文を合計60個ご紹介しながら、感覚的にも理解しやすい内容にまとめています。
言葉の微妙なニュアンスや使い分けに自信がない方、日本語の文章を書く機会が多い方にとって、きっと役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
「ついていく」の漢字の正解

「ついていく」という言葉を正しく漢字で書くと、「付いていく」が基本的な表記となります。
「付いていく」は、次のような意味を持つとされています。
- 誰かの後について進む
- 行動や考えに従って一緒に動く
- 遅れずに物事についていく(例:話についていく、スピードについていく)
このように、「ついていく」は「従う」「伴う」「同行する」といったニュアンスが強く、「付く(つく)」の意味にしっかり合致しているため、漢字で書くときは「付いていく」が正解となるわけです。
【国語辞典の定義を確認】
たとえば、『新明解国語辞典』第八版には、以下のような説明があります。
付く(つく):
① 他の物の表面に密着する
② ある対象と結びつくような状態になる
③ 人や物の後ろに従う、行動を共にする
この③の意味が、「ついていく」の用法にぴったりと当てはまることが分かります。
「着いていく」はどうなの?
一方で、「着いていく」という表記も見かけることがありますが、これは誤用であるケースが多いです。「着く」は「目的地に到着する」ことを意味するため、「一緒に現地に到着する」といった意味で使う場合を除いて、通常は使いません。
この点については、下記で詳しく掘り下げていきます。
なぜ「付いていく」なのか

「ついていく」の正しい漢字表記が「付いていく」である理由は、「付く(つく)」という動詞の意味にあります。ここでは、「付く」の語源や用法を紐解きながら、なぜ「付いていく」が自然な表現になるのかを解説していきます。
「付く」の意味とは?
「付く」にはさまざまな意味がありますが、主に次のような意味があります。
| 意味 | 例文 |
|---|---|
| ① 接触・密着する | 汚れが服に付く、シールが壁に付く |
| ② 仲間になる、従う | あの人に付いて学ぶ、先生に付いて練習する |
| ③ 関連する、影響を受ける | 値段が付く、感情が付く |
この中でも、「ついていく」として使われる場合は②の「従う」「一緒に行動する」といった意味で使われることがほとんどです。
「ついていく」は「従う」「同行する」イメージ
たとえば、以下のような例を見てみましょう。
- 先生に付いていく(=先生の後を追って同行する)
- 話の内容に付いていく(=話の進行に遅れず理解していく)
どちらも、何かや誰かに「従う」「伴う」「寄り添う」といった動きが含まれています。このようなニュアンスを持つのが「付く」であり、だからこそ「ついていく」は「付いていく」が正しいのです。
熟語としても「付」が使われている例
実際、日本語の中には「付く」が使われる熟語が多く存在します。
- 付き添う(つきそう):そばにいて世話をする
- 付属(ふぞく):本体に付いているもの
- 付録(ふろく):おまけで付いてくるもの
これらもすべて、「何かに付随している・同行している」という意味を含んでおり、「付く=従って行く」という感覚が日本語の中で広く定着していることがわかります。
なぜ「着いていく」ではないのか

「ついていく」という表現を「着いていく」と漢字で書いてしまうことがありますが、これは多くの場合誤用です。なぜ「着いていく」では不自然なのかを理解するためには、「着く」という漢字の意味を正確に捉えることが重要です。
「着く」は「目的地に到達する」こと
「着く(つく)」は、「ある場所に到達する」「目的地に至る」という明確な意味を持っています。
【例】
- 電車が駅に着く
- 自宅に着く
- ゴールに着く
このように、「着く」は動作の結果として、どこかに到着することを表します。つまり、「動き」そのものではなく、「その動きの終点」にフォーカスした言葉です。
「着いていく」では意味が合わない理由
「ついていく」という言葉は、基本的に「同行する」「ついて歩く」「ついて理解していく」など、ある対象に合わせて動作をともにする過程を示します。一方、「着く」はゴールに到達することなので、以下のように使うと意味がズレてしまいます。
【不自然な例】
- 先生に着いていく(→「先生と一緒に目的地に到着する」? でも言いたいのは「先生に同行する」)
- 時代に着いていく(→「時代に一緒に到達する」? 不自然)
こうした例では、「着く」という漢字の持つ「到着」の意味が文脈に合わず、結果的に違和感が生じてしまいます。
唯一使える場面:「一緒に目的地に着く」場合
ただし、「着いていく」が絶対に間違いというわけではありません。文脈によっては、意味が通ることもあります。
【自然な例】
- 「一緒に目的地に着いていく」
→ この場合、「Aさんと一緒に目的地に着く」という意味なので、「着いていく」でも意味が通じます。
とはいえ、こうした使い方はかなり限定的で、一般的には「ついていく」は「付いていく」と書くのが適切です。
「付いていく」と「着いていく」の使い分け
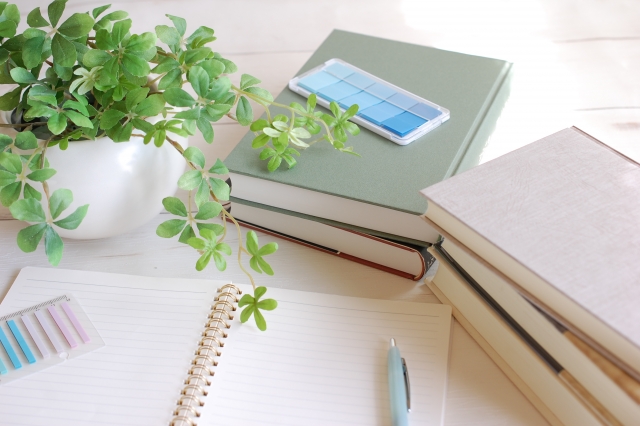
ここまでの解説で、「ついていく」は基本的に「付いていく」と書くのが正解である理由をご理解いただけたかと思います。しかし、文脈によっては「着いていく」もごく限られた状況で使われることがあります。
この章では、よく使われるシチュエーションごとに、どちらの漢字が適切かを具体的に見ていきましょう。
人に「ついていく」:付いていく
✅ 正しい表記
- 先生に付いていく
- 友達に付いていく
- ガイドに付いていく
🔍 解説
この場合、「同行する」「後を追って行動する」という意味なので、「付く」が正解。誰かに従って一緒に行動するニュアンスを含みます。
勉強に「ついていく」:付いていく
✅ 正しい表記
- 勉強に付いていけない
- 授業の内容に付いていくのがやっと
🔍 解説
理解や進度に「追いついている」ことを表す場合は、「従う」「遅れずついていく」という意味になるため、「付く」を使います。
授業に「ついていく」:付いていく
✅ 正しい表記
- 授業についていくのが大変
- 授業に付いていけなくなった
🔍 解説
「内容に遅れないように追従する」という意味なので、「着く」ではなく「付く」が適切です。
時代に「ついていく」:付いていく
✅ 正しい表記
- 時代の流れに付いていく
- 技術の進歩に付いていけない
🔍 解説
時代や流行、変化に対して「遅れないように従っていく」という意味を持つため、「付く」が使われます。
スピードに「ついていく」:付いていく
✅ 正しい表記
- 話すスピードに付いていけない
- チームの練習についていくのがやっと
🔍 解説
速さや変化についていく場合も、「従う」「追いかける」といった意味なので「付く」が正解です。
目的地に「一緒に着く」:着いていく(例外)
✅ 例外的に可能な表記
- 彼と一緒に駅に着いていく
- バスで目的地に着いていく
🔍 解説
この場合、「目的地に一緒に到達する」ことを表しており、「着く」の本来の意味(到着)が当てはまるため、「着いていく」と書いても文脈上は自然です。ただし、使用頻度は非常に低く、ほとんどの場面では「付いていく」を使います。
まとめ:見分け方のコツ
| シーン・文脈 | 正しい表記 | ポイント |
|---|---|---|
| 同行・従う | 付いていく | 人・考え・動きに従うとき |
| 理解・対応 | 付いていく | 勉強・会話・変化など |
| 到着 | 着いていく | 目的地に一緒に到達する場合のみ |
このように、文脈によって正しい漢字は変わってきますが、9割以上のケースでは「付いていく」が正解になります。意味と用途を意識して使い分けることで、より自然で正確な日本語が使えるようになります。
「ついてくる」の漢字の正解

「ついていく」と同じように、日常会話でよく使われる「ついてくる」という表現も、正しい漢字表記に迷いやすい言葉です。「付いてくる」なのか、それとも「着いてくる」なのか――。ここでは、その使い分けを詳しく解説していきます。
基本は「付いてくる」が正解
「ついてくる」も、「ついていく」と同様に、基本的には「付いてくる」と書くのが正解です。
【例】
- 子どもが後ろから付いてくる
- ペットがどこにでも付いてくる
- トレンドの変化がすぐに付いてくる
これらはすべて、後に続いてやって来る、従ってくる、伴ってくるといった意味合いを持っています。つまり「従う」「寄り添う」ニュアンスがあるため、「付く」が適しています。
「着いてくる」は基本的に使わない
一方、「着いてくる」という表現は、文法的に成立しにくく、ほとんど使われません。
「着く」は「目的地に到着する」ことを意味しますので、「着いてくる」と書くと、「目的地に誰かが後から到着してくる」というやや不自然な文脈になってしまいます。
【不自然な例】
- 友達が後から着いてくる
→ 「一緒に目的地に到着する」という意味であれば使えるが、日常的には違和感あり。
「ついてくる」は基本「付いてくる」でOK
| シーン | 正しい表記 | 解説 |
|---|---|---|
| 誰かが後に従ってくる | 付いてくる | 同行・従うという意味合い |
| 一緒に行動する | 付いてくる | 共に動く、付き添うイメージ |
| 後から到着する(まれ) | 着いてくる | 到着に焦点を当てる特定の文脈のみ |
「付いていく」「ついていく」を使った例文【30例】

ここでは、「付いていく」という正しい漢字表記を使った例文を、さまざまなシーン別にご紹介します。日常会話・ビジネス・教育・時代の流れなど、幅広い文脈に対応していますので、使い方のイメージを深める参考にしてください。
①人や物理的な動作に「付いていく」
- 子どもが親のあとを付いていく。
- 山道でガイドに付いていくのがやっとだった。
- ペットがどこへでも付いていくので可愛い。
- 迷子にならないように先頭に付いていく。
- 彼の歩くスピードに付いていくのが大変だ。
- 道がわからなかったので、彼に付いていった。
- 観光地ではツアーガイドに付いていくのが安心。
- 初めての登山で、経験者に付いていった。
- 新入社員が先輩に付いていって現場を回った。
- 知らない道だったけど、車で彼に付いていった。
②理解・学習・情報の進行に「付いていく」
- 授業に付いていけなくなってきた。
- 難しい内容だったが、なんとか付いていけた。
- 話の展開が早くて付いていけない。
- 新しい技術に付いていくには努力が必要だ。
- 最近のスラングにはもう付いていけない。
- 彼の議論についていくには、知識が足りなかった。
- 数学の応用問題に付いていくのが難しい。
- ゲームのアップデートについていくのが大変。
- 彼の発想力についていける人は少ない。
- 話のテンポに付いていくのがやっとだった。
③時代や流れに「付いていく」
- 時代の変化に付いていくのは容易ではない。
- テクノロジーの進化に付いていくには柔軟さが必要。
- 社会の流れに付いていかないと取り残される。
- トレンドに付いていくのが若干疲れるようになった。
- 情報社会に付いていくために毎日ニュースを読む。
④ビジネス・職場での使用例
- 業務のスピードに付いていけず焦っている。
- 上司の判断に付いていくことができなかった。
- プロジェクトの進行についていけるよう、毎日復習している。
- チームの方針に付いていくか悩んでいる。
- 部下が急成長していて、逆に付いていくのが必死だ。
「ついていく」を自然に使いこなすには?
「付いていく」は、「誰かや何かの後に従う」「一緒に動く」「遅れずに追っていく」といった意味で使われる表現です。前の章で解説したように、到達の意味ではなく、動作のプロセスを重視する文脈で使うのがポイントです。
「付」の入った熟語を使った例文【30例】

「付く(つく)」という動詞は、「ついていく」だけでなく、さまざまな意味や場面で使われる非常に多義的な言葉です。この章では、「付」の入った熟語の例文を分類して、合計30個の文を紹介します。
①「付き合い・付き合う」(人間関係)
- 同僚との付き合いも仕事のうちだと思っている。
- 最近、彼女と付き合い始めた。
- 長年の付き合いがあるので、信頼している。
- 忙しくて、友達との付き合いが減ってしまった。
- 初対面でも気さくに付き合える人は貴重だ。
②「付属・付録・添付」など(追加・付帯)
- この製品には充電器が付属しています。
- 雑誌の付録にスマホスタンドがついてきた。
- 申請書に証明書を添付してください。
- メールに資料を添付し忘れました。
- おまけとしてステッカーが付属していました。
③「付着・粘着・密着」など(くっつく・密接)
- シャボン玉が壁に付着した。
- 衣服にホコリが付着しやすい素材だ。
- このラベルは強力に粘着するタイプです。
- 汗が肌に密着するような不快感がある。
- ガラスに虫が付着していて気になった。
④「配付・交付・発付」など(配る・渡す)
- 資料は事前に全員に配付されていた。
- 補助金が正式に交付された。
- 許可証が市役所から発付された。
- 案内文を近隣住民に配付してください。
- 本日、健康保険証の交付を受けました。
⑤「寄付・献付・寄附」など(提供・寄贈)
- 図書館に本を寄付しました。
- 災害支援のために少額ですが寄附しました。
- 個人からの献付により設備が整えられた。
- 年末にはいくつかの団体に寄付をしている。
- 美術品の寄附で展示が充実している。
⑥「付け加える・付き添う・付きまとう」など(動作・態度)
- 会議で重要な意見を付け加えた。
- 入院中の祖母に看護師が付き添っていた。
- 小さな子どもには親が付き添う必要がある。
- 彼の不安には常にプレッシャーが付きまとっている。
- 不審者に付きまとわれて警察に相談した。
「付」は多様な使い方ができる
「付」は単体でも意味の幅が広い漢字ですが、熟語になるとさらに多様な使われ方をします。接着、追加、配布、寄贈、人間関係の動きなど、非常に汎用性の高い漢字です。熟語としての使い方を覚えることで、文章表現にも深みが出てきます。
「ついていく」「付いていく」漢字とひらがなの使い分け

日本語では、同じ言葉でも漢字で書くか、ひらがなで書くかによって、読み手に与える印象や読みやすさが変わることがあります。「ついていく/付いていく」もその代表例のひとつです。この章では、「漢字」と「ひらがな」の使い分けについて、意味だけでなく文体や状況、読みやすさの観点からも解説していきます。
基本は「付いていく」が正解
文法的・意味的に正確に伝えたい場合や、正式な文章では、「付いていく」と漢字表記するのが基本です。
✅ 適した場面
- 論文やレポート、ビジネス文書
- 教育・学術的な文章
- 漢字の意味をしっかり伝えたいとき
✅ 例
- 最新技術の進歩に付いていくには継続的な学習が必要だ。
- 授業についていけるように、毎日予習をしている。
「ついていく」はやわらかく、親しみやすい印象
一方、ひらがな表記の「ついていく」は、柔らかく親しみやすい印象を与えるため、特に会話調の文や、子ども向け、ブログ、広告、感情を重視する文体に向いています。
✅ 適した場面
- 日記・エッセイ・ブログなどのカジュアルな文章
- 会話文やナレーション
- 読みやすさを優先したいとき
- 読者が子どもや高齢者などの場合
✅ 例
- あの子がどこにでもついていくのが、かわいくてしかたない。
- ついていけないスピードで話されて、頭がパンクしそう…。
読みやすさのための工夫としてのひらがな
日本語の文章では、漢字が続きすぎると読みにくいという問題があります。そういったときに、適度にひらがなを混ぜることで文章が視覚的に読みやすくなります。
✅ 例
- 変化の激しい社会のスピードについていくのは簡単ではない。
- 最先端の研究に付いていくには、相当な努力が必要だ。
このように、同じ文章内で使い分けるのもOKです。
漢字とひらがな、どちらを使うべきかの判断基準
| 判断基準 | 表記例 | 解説 |
|---|---|---|
| 意味を正確に伝えたい | 付いていく | 正式・論理的な文脈で使用 |
| やわらかく見せたい | ついていく | 会話・ブログ・感情を重視する文におすすめ |
| 読みやすさを優先 | ついていく | 漢字の連続を避けたいとき |
| 対象が子どもや一般読者 | ついていく | 視覚的負担を減らせる |
- 意味重視 → 漢字(付いていく)
- 印象・雰囲気重視 → ひらがな(ついていく)
- 読みやすさ重視 → 柔軟に使い分け
「正しさ」だけにこだわらず、誰に読んでもらう文章か?どんな印象を与えたいか?を考えて表記を選ぶことが大切です。
「ついていく」の類語や言い換え表現

「ついていく」は非常に汎用性の高い表現で、人に従う・理解についていく・変化に対応するなど、さまざまな意味を持っています。そのため、文脈に応じて適切な類語・言い換え表現を使うことで、文章にバリエーションが出て、より洗練された印象を与えることができます。この章では、「ついていく」の主な意味ごとに、言い換え表現を整理し、具体的な例文とともに紹介していきます。
「人に従って移動・同行する」意味の言い換え
✅ 主な類語
- 従う(したがう)
- 同行する(どうこうする)
- 付き添う(つきそう)
- 後を追う
✅ 例文
- ガイドについていく → ガイドに同行する
- 母についていった → 母の後を追った
- 看護師が患者についていく → 看護師が患者に付き添う
🔍 補足:フォーマルな文では「同行する」、やややさしい言葉では「付き添う」が好まれます。
「物事に対応する・理解する」意味の言い換え
✅ 主な類語
- 理解する
- 対応する
- 追いつく
- 把握する
- 順応する
✅ 例文
- 授業についていけない → 授業が理解できない
- 話のスピードについていけない → 話に追いつけない
- 技術の進化についていく → 技術に順応する
🔍 補足:「ついていけない」を言い換える場合、「理解できない」「把握できない」など、主語をはっきりさせると読みやすい文章になります。
「流れ・時代・流行に乗る」意味の言い換え
✅ 主な類語
- 適応する
- 対応する
- 追従する(ついじゅうする)
- 歩調を合わせる
- 乗る(例:波に乗る)
✅ 例文
- 時代の変化についていくのが大変 → 時代の変化に適応するのが大変
- トレンドについていく → トレンドに乗る
🔍 補足:ビジネスやマーケティングの文脈では「対応する」「適応する」がよく使われます。
「共感・感情的なつながり」の意味を込める場合
✅ 主な類語
- 共感する
- 寄り添う
- 受け入れる
✅ 例文
- 彼の考え方についていけない → 彼の考え方を受け入れられない
- 親の気持ちについていく → 親の気持ちに寄り添う
🔍 補足:「ついていけない」が感情的な距離感や違和感を含む場合、表現を変えることでニュアンスがより繊細に伝わります。
文脈に応じて、自然な言い換えを
| 意味 | 類語(言い換え) |
|---|---|
| 同行する | 従う、同行する、付き添う、後を追う |
| 理解・対応 | 理解する、追いつく、把握する、順応する |
| 時代・変化に乗る | 適応する、対応する、追従する、乗る |
| 感情・共感 | 寄り添う、共感する、受け入れる |
ポイント:言い換えでは「意味が通じるか」だけでなく、「文章のトーンや読み手に合っているか」を考えるのが大切です。
まとめ

「ついていく」という表現は日常でよく使われますが、漢字で表す際には「付いていく」と「着いていく」で迷うことがあります。基本的には「付いていく」が正しく、「従う」「同行する」「遅れずについていく」といった意味を持つためです。一方、「着いていく」は「目的地に一緒に到着する」といった場面に限って使われる非常に限定的な表現です。多くの場面では「着く」では意味が通らず、誤用となるため注意が必要です。
また、「付いていく」は硬い印象のある漢字表記、「ついていく」は柔らかく親しみやすい印象があるため、文体や読者層に応じて使い分けることが重要です。さらに、意味をより明確に伝えるためには「同行する」「順応する」などの類語も場面に応じて活用すると、表現の幅が広がります。正しい漢字と使い方を知ることで、文章力も格段に向上するでしょう。




