濡れた靴を早く乾かす方法【10選】放置は危険!臭いを防ぐ対処法

雨の日や水たまりをうっかり踏んでしまったとき、靴が濡れてしまうのは避けられないことですよね。でも、「そのままにしておけば乾くだろう」と油断して放置していませんか?実は、濡れた靴を放置することで、臭いやカビ、靴そのものの劣化など、さまざまなトラブルを引き起こす可能性があります。
本記事では、「濡れた靴を早く乾かす」ための実用的な方法から、スニーカー以外の靴の乾かし方、乾かすときの注意点まで詳しく解説します。正しい対処法を知っておけば、靴を長持ちさせるだけでなく、清潔で快適な足元環境をキープできますよ。
目次
濡れた靴を放置するとどうなる?5つのリスク

濡れた靴をそのまま放置すると、思わぬトラブルを引き起こすことがあります。ここでは、代表的な5つのリスクを解説します。どれも靴の寿命を縮めたり、健康に悪影響を及ぼすものばかり。濡れた靴はできるだけ早く正しく乾かすことが重要です。
1. 嫌な臭いの原因になる
濡れた靴の内部は高湿度状態になりやすく、特に気温が高いときは雑菌の繁殖が爆発的に進みます。人間の足には汗腺が多く、汗によって湿った環境がさらに悪化。その結果、雑菌やバクテリアが汗や皮脂を分解する際に悪臭のもととなる物質(イソ吉草酸など)を発生させます。
この臭いは一度つくと消えにくく、洗っても繊維に染みついていることが多いため、完全に取り除くのが難しくなります。また、職場や電車の中などで靴を脱ぐ場面があると、周囲にも気を使わなければならなくなります。
2. 足のトラブルを引き起こす
湿った靴の中は、皮膚にとって非常に刺激の強い環境です。靴内に繁殖した雑菌やカビは、水虫(白癬菌)や汗疹、接触性皮膚炎などを引き起こす原因に。特に足の皮膚がふやけているとバリア機能が弱まり、ちょっとした刺激でも傷がつきやすくなり、そこから感染することも。
また、濡れた靴は通気性が著しく悪くなり、足が蒸れてかゆみや赤みを伴うこともあります。スポーツや長時間の外出後は、靴と一緒に足のケアも忘れずに行いましょう。
3. 靴のカビ発生による健康被害
カビは湿気と栄養があれば簡単に発生します。靴についた土やホコリ、皮脂などがカビの栄養源となり、わずか数日でも放置すると白や黒、緑色のカビが靴の中や外に繁殖することがあります。
さらに怖いのは、カビの胞子が空気中に舞い、それを吸い込んでしまうことで起こる被害。特に免疫力の低い人やアレルギー体質の人、小さなお子さんや高齢者は、カビによって喘息やアレルギー性鼻炎を引き起こすリスクが高まります。
4. 靴の型崩れ・素材の劣化
靴は、形状を保つために特定の設計と素材が使われていますが、水分を吸収するとその構造が簡単に崩れてしまいます。革靴であれば水分によって革が伸びたり縮んだりして、履き心地が悪くなるほか、乾く際に表面が硬くなり、ひび割れの原因になります。
布製のスニーカーも、乾燥の際に縮んだりヨレたりすることで型崩れを起こしやすくなります。ソールとアッパー部分の接着が弱まり、靴底が剥がれてしまうこともあります。
5. 使用期間が短くなる
濡れた靴を放置すると、上記のようなさまざまなダメージが重なり、靴そのものの寿命が大幅に縮まります。素材の劣化や形崩れ、臭いやカビの定着などが進むと、見た目も悪くなり、使用感も落ちてしまい、結局は買い替えざるを得ないことに。
特に高価な革靴や、お気に入りのスニーカーなどは一足一足を長く履きたいもの。濡れた後の早めの乾燥と適切なメンテナンスを習慣づければ、靴を長く美しく保つことができ、結果的に出費も抑えることができます。
濡れた靴を早く乾かす方法【10選】
濡れた靴を素早く、かつ安全に乾かすためには、正しい方法を選ぶことが大切です。ここでは、家庭でできる効果的な乾燥方法を10個ご紹介します。靴の素材や状況に合わせて使い分けましょう。
①新聞紙を詰める

濡れた靴を早く乾かすための方法として、最も手軽で効果的なのが「新聞紙を詰める」方法です。この方法は電気を使わず、気軽に実践できる点が大きな魅力です。
新聞紙は木材パルプを原料としており、非常に高い吸水性を持っています。靴の中に新聞紙を入れると、靴内部の湿気や水分を効率的に吸収してくれます。また、新聞紙は柔らかく変形しやすいため、靴の形にフィットしやすく、内部の隅々まで水分を吸い取ることができます。
さらに、新聞紙は水分を吸収するとわずかに膨らむ性質があります。そのため、靴の形が崩れるのをある程度防ぎながら乾かすこともできます。
手順
- 新聞紙を適当な大きさにちぎるか、軽く丸める。
- 靴の中に新聞紙を詰める。奥までしっかりと届くようにする。
- 詰めた新聞紙は、2〜3時間ごとに新しい乾いたものに交換する。
- 必要に応じて、靴の外側にも新聞紙を軽く巻きつけると、全体の乾燥が早くなる。
ここで重要なのは、新聞紙を詰めすぎないことです。ぎゅうぎゅうに詰め込んでしまうと通気性が悪くなり、逆に乾きが遅くなる場合があります。新聞紙はあくまで「ふんわり」と詰めるのが理想です。
また、交換のタイミングを逃さず、濡れた新聞紙をそのままにしないことも大切です。濡れたまま放置すると吸水効果がなくなるだけでなく、カビや臭いの原因になることもあります。
注意点
新聞紙による乾燥方法は、スニーカーやキャンバス素材、合成皮革の靴には非常に適しています。一方で、革靴の場合は外側に新聞紙が直接触れると、インクや湿気でシミになる恐れがあります。そのため、革靴には内部のみに新聞紙を詰め、外装部分には別の方法(乾いたタオルや陰干しなど)を併用するのが望ましいです。
②タオルで水分をしっかりオフ

どのような乾燥方法を選ぶにせよ、最初に必ず行ってほしいのが「タオルでの水分除去」です。靴が濡れた直後は、内部にも外部にも多くの水分が含まれており、そのまま乾かそうとしても時間がかかるだけでなく、靴の劣化を早めてしまうことがあります。
タオルを使って余分な水分をしっかり取っておくことで、その後の乾燥作業の効率が大幅に上がります。靴に含まれる水分は、大きく分けて「表面の水分」と「素材内部に染み込んだ水分」の2つがあります。このうち、表面の水分を放置すると、空気に触れる面積が少ない靴の内側では、蒸発しにくくなります。また、水分が多すぎる状態では、新聞紙や乾燥剤もすぐに飽和してしまい、本来の吸水効果を発揮できません。
そのため、乾かす前の段階で、タオルを使ってしっかり水分を除去することで、後の工程がよりスムーズになります。
手順
- 乾いたタオルを1〜2枚用意する(マイクロファイバー素材のものが理想)。
- 靴の外側全体をタオルで軽く押さえるようにして、水分を吸い取る。
- 靴の中にタオルを手で差し入れ、内部の水分も可能な限り拭き取る。
- 特に濡れがひどい部分(つま先、かかとなど)は、タオルで包んで数分置くと効果的。
このとき、タオルで強くこすったり、叩くようにして水分を取ろうとすると、靴の素材を傷める可能性があります。特にキャンバス地やスエードは摩擦に弱いため、優しく押し当てるようにして水分を吸い取るのがポイントです。
注意点
タオルでの水分除去は、靴を早く乾かすための「準備段階」として非常に重要です。タオルでしっかりと水分を取った後に、新聞紙、扇風機、乾燥剤、浴室乾燥機などを組み合わせることで、乾燥効率が大幅にアップします。
また、靴の素材によって拭き取り方に注意が必要です。布製スニーカーは問題なく拭き取れますが、革靴は柔らかいタオルで軽く押さえる程度にし、スエード素材は毛並みに沿ってそっと吸い取るようにして、摩擦は避けましょう。
③扇風機の風で乾かす

濡れてしまった靴を自然乾燥させると、乾くまでに時間がかかり、イヤなニオイやカビの原因にもなります。そんなときは、扇風機の風を使って効率よく乾かすのがオススメです。電気代も比較的安く、安心して使える方法です。
手順
- 靴の中に新聞紙やキッチンペーパーを詰めて、水分をある程度吸い取らせる(1〜2回交換すると効果的)。
- 靴のひもや中敷きは外しておく(別々に乾かす)。
- 靴を立てかける、または洗濯ばさみなどで吊るして、風が靴の中に入りやすい状態にする。
- 扇風機を靴に向けてスイッチを入れ、風を当てる。風量は中〜強がおすすめ。
- 数時間ごとに向きを変えたり、新聞紙を交換しながら様子を見る。
注意点
靴を直射日光の当たる場所に置くと、色あせや型崩れの原因になるため避けましょう。また、扇風機の風だけでは乾燥に時間がかかることがあるため、部屋の湿度が高い場合は除湿機やエアコンの除湿機能を併用すると、より効果的に乾かすことができます。さらに、革製やデリケートな素材の靴は、強い風を長時間当てることで傷む恐れがあるため、風量や乾かす時間に注意しながら行うことが大切です。
④ドライヤーの風で乾かす

急いで靴を乾かしたいときには、ドライヤーの温風を使う方法が効果的です。ただし、高温になるため、素材によっては注意が必要です。正しい手順で行えば、短時間でしっかり乾かすことができます。
手順
- 靴の中に新聞紙やタオルを詰めて、ある程度水分を吸わせてから取り除く。
- 靴のひもと中敷きを外し、それぞれ別に乾かす。
- ドライヤーを「温風(中〜低温)」に設定し、靴から10〜20cmほど離して風を当てる。
- 靴の中にまんべんなく風が当たるよう、角度を変えながら5〜10分ずつ乾かす。
- 完全に乾くまで途中で新聞紙を再度詰めるなどして、内側の湿気を取り除く。
注意点
ドライヤーで靴を乾かす際は、熱による変形や劣化を防ぐため、靴に近づけすぎず、適度な距離を保ちましょう。長時間連続で温風を当てず、途中で休憩を入れることも大切です。特にゴム製や合皮素材、またお子様の靴など小さいサイズのものは熱に弱いため、低温で慎重に行ってください。
⑤乾燥剤・シリカゲルを利用
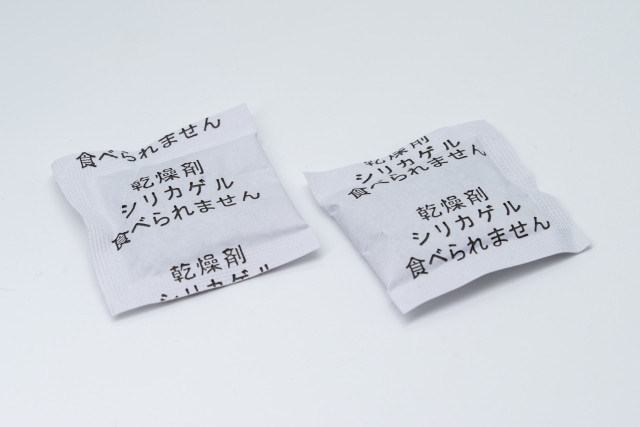
靴の乾燥方法として、意外に見落とされがちなのが「乾燥剤(シリカゲル)」の活用です。お菓子や海苔、靴箱などに入っている小さな袋の乾燥剤ですが、これを再利用することで靴の内部にこもった湿気を安全かつ効果的に除去できます。特に「電気を使いたくない」「放置して乾かしたい」という場面にぴったりの方法です。
シリカゲルは二酸化ケイ素という成分でできた乾燥剤で、空気中の湿気を吸着する性質があります。とても小さな粒子で構成されており、表面積が広いため、見た目以上に多くの水分を吸収できます。また、繰り返し使用できるものも多く、再利用可能という点でも環境にやさしく経済的です。
手順
- 市販や家庭で出た不要なシリカゲルの小袋を数個用意する。
- 靴の中にそのまま入れる、または中敷きの下に挟む。
- 数時間〜一晩放置して、内部の湿気を吸収させる。
靴のサイズや湿り具合にもよりますが、スニーカー1足あたり、シリカゲルの小袋を3〜5個入れると効果が実感できます。また、靴の左右両方に均等に入れることで、全体的にムラなく乾燥が進みます。
注意点
乾燥剤は一度使用しても、天日干しなどで乾燥させれば再利用が可能です。使わないときは密閉袋などに保管すると、効果を長持ちさせることができます。また、乾燥剤がない場合は、重曹やお米をお茶パックに入れて靴の中に入れる簡易的な乾燥パックも、応急処置として有効です。
⑥靴用乾燥機を活用

現代のライフスタイルでは、「濡れた靴を翌日までに乾かしたい」「毎日のように靴を履く必要がある」といった状況が珍しくありません。そんな忙しい人にとって非常に頼れるのが「靴用乾燥機」です。最近では家電量販店やネット通販でも多くの種類が出ており、価格も手頃なものから高機能なものまで幅広くそろっています。
靴用乾燥機とは、靴の内部に風や熱を送ることで短時間で効率よく乾燥させる家電製品です。大きく分けて以下の2タイプがあります。
- 温風式タイプ
内部にヒーターを搭載し、暖かい風を送り込むタイプ。スニーカーや合成皮革の靴に適しており、比較的短時間で乾かすことができます。 - 送風式タイプ
ヒーターを使わず、常温または低温の風を送り込むタイプ。熱に弱い素材の靴や、革靴、スエードなど繊細な素材の靴にも対応しています。
機種によってはタイマー機能や温度設定ができるものもあり、使いやすさや安全性に配慮された設計になっています。
手順
- 靴の中に詰まった水分は、あらかじめタオルなどで軽く拭き取っておく。
- 乾燥機のノズルやアタッチメントを靴の内部に差し込む。
- 素材や濡れ具合に応じて、温度や時間を設定する。
- タイマー終了後、靴の中を手で触って乾き具合を確認する。
スニーカーであれば30分〜1時間程度、革靴やブーツなど厚手の靴であっても2〜3時間以内にしっかりと乾燥させることができます。
注意点
乾燥機は靴を素早く乾かすのに便利ですが、使い方を誤ると傷む恐れがあります。革靴は高温を避け、送風や低温モードを選びましょう。接着剤を使用した靴は高温で接着部分が剥がれる可能性があるため、注意が必要です。
また、スエード素材は熱で風合いが変わることがあるため、慎重に扱ってください。使用前には、取扱説明書で対応素材や温度設定の目安を確認することをおすすめします。
⑦お風呂の乾燥機能で乾かす

最近の住宅には、浴室に「浴室乾燥機」が備わっているケースが増えています。もともとは洗濯物を室内で乾かすための設備ですが、これを靴の乾燥にも活用することで、雨の日でも効率よく靴を乾かすことができます。
特別な道具を買い足す必要もなく、家にある機能を有効活用できるという意味で、非常におすすめの方法です。
手順
靴を浴室で乾燥させる際には、風の通り道を意識することがポイントです。
- 靴に付いた泥や汚れを軽く落とし、タオルなどで外側の水分を取っておく。
- 靴の中に新聞紙や乾燥剤を軽く入れておくと、内側の湿気がより早く取れる。
- 浴室内にある洗濯用の物干しポールなどに、靴のかかと部分を洗濯バサミなどで吊るす。逆さにすることで、靴のつま先側が下になり、重力と風で効率的に水分が抜ける。
- 浴室乾燥機を「乾燥モード(標準または送風)」で運転し、数時間かけて乾かす。
吊るすことで通気性が高まり、靴の内側までしっかりと乾かすことができます。床に直置きすると風が当たりにくくなるため、できるだけ空中に浮かせる工夫が必要です。
注意点
浴室乾燥機を使う際は、高温モードが靴の素材に与える影響に注意が必要です。革靴やスエード、合成皮革など熱に弱い素材は高温を避け、短時間で乾かすようにしましょう。特に3時間を超える使用は接着剤の劣化を招く恐れがあります。
また、靴を吊るす場合は、洗濯バサミの跡がつかないよう靴下や布を挟むと安心です。吊るすのが難しい場合は、浴室内に通気性の良いラックを置き、その上に靴を乗せて乾かす方法も有効です。
⑧中敷きを外して別乾燥

靴の中でも特に湿気がこもりやすいのが「中敷き(インソール)」の部分です。中敷きは足裏と直接触れるため汗や水分を吸収しやすく、濡れた状態のままにしておくと、雑菌やカビ、臭いの原因になってしまいます。乾燥の際には、靴本体と中敷きを必ず別々に乾かすことが重要です。
中敷きは通常、スポンジ状の素材や布・合皮などで作られており、吸湿性が高いものが多く使われています。そのため、一見乾いて見えても中に水分が残っていることが多く、靴全体の乾燥を妨げる原因になります。
また、足から出る汗も中敷きに吸収されやすく、濡れた状態のまま使用すると、雑菌が繁殖し、悪臭や水虫などのリスクが高まります。
手順
以下の手順で、中敷きを安全に取り外し、乾かすことができます。
- 靴の中に手を入れ、中敷きの端を軽く持ち上げてゆっくりと引き抜く。
- 取り外した中敷きは、まず乾いたタオルで軽く押さえて水分を吸い取る。
- 風通しの良い場所に置いて、自然乾燥させる。
- 必要に応じて扇風機や乾燥剤と併用して、乾燥を促進する。
中敷きは薄いため乾きやすく、通常は数時間〜一晩程度でしっかり乾きます。ただし、厚手のクッションタイプやジェル素材の場合は乾燥にやや時間がかかるため、裏返して乾かす、日陰で通気を確保するなどの工夫が必要です。
注意点
中敷きが取り外せない靴の場合は、内部に新聞紙や乾燥剤を詰めて水分を吸収させ、靴口を広げて風通しを良くすると効果的です。また、除湿スプレーや消臭スプレーを使って衛生状態を保つことも大切です。中敷きを外せなくても、部分的な乾燥ケアで湿気対策が可能です。
⑨風通しの良い場所で自然乾燥

濡れた靴を乾かす際、特別な道具や電気を使わずに行える、もっとも自然で安全な方法が「風通しの良い場所での陰干し」です。少し時間はかかりますが、靴の素材を傷めずに乾燥させられるため、特に革靴やスエード素材などデリケートな靴に適しています。
直射日光に当ててしまうと、革が硬くなったり、色落ちしたり、表面がひび割れるなどのトラブルが起こる可能性があります。その点、日陰で風通しの良い場所に干す方法は、温度変化が穏やかで、靴への負担が最小限に抑えられます。
また、自然な空気の流れで乾かすことで、内部の湿気をしっかり取り除き、カビの発生を防ぐ効果もあります。
手順
- 靴の外側と内側の水分をタオルで軽く拭き取っておく。
- 新聞紙や乾燥剤を靴の中に入れて、湿気を吸収させる。
- 靴の底を下にするなど、風が入りやすい状態で設置する。
- ベランダや玄関先など、風通しが良くて雨が当たらない場所に置く。
- 数時間おきに靴の向きを変えることで、全体を均等に乾かす。
特に靴底側は通気性が悪くなりがちなため、靴を立てかけたり、吊るしたりして宙に浮かせるのが理想的です。床に直置きすると、空気が通らず乾きが遅くなるため注意が必要です。
注意点
風通しを良くするには、靴の下に空間ができるようシューズラックやすのこを使ったり、丸めたキッチンペーパーで靴口を開かせたりすると効果的です。ピンチ付きハンガーで吊るす方法や、レンガ・ブロックの上に置くのも有効です。
設置場所としては、直射日光を避けた窓辺、屋根付きのベランダ、玄関先、脱衣所(扇風機併用)などが適しています。湿度の高い日を避け、乾きやすい環境を選びましょう。
⑩重曹で乾燥と脱臭のW効果を得る

濡れた靴を乾かすときにもう一つ気になるのが、「こもったニオイ」ではないでしょうか。特に雨の日に長時間履いた靴や、汗を多くかく季節には、乾かしてもニオイが残ることがあります。そんなときに活躍するのが重曹です。
重曹(炭酸水素ナトリウム)は、掃除や料理に使われる安全な素材でありながら、湿気を吸い取る効果と脱臭効果の両方を持っています。
重曹には以下の2つの特徴があります。
- 吸湿性があるため、靴の中の湿気を取り除く
- 弱アルカリ性の性質で、汗や皮脂の酸性臭を中和する
このため、濡れた靴の乾燥と同時に、嫌なニオイの対策もできるのです。また、重曹は粉末状で扱いやすく、靴の中にそのまま使うのではなく「袋に入れて設置する」ことで、靴を汚すことなく利用できます。
手順
準備するものは家庭にあるもので十分です。
必要なもの:
- 重曹(市販の食品用、掃除用どちらでも可)
- お茶パック、不織布の袋、ガーゼ、ストッキングなど通気性のある素材
- 小さな輪ゴムや糸(袋を閉じる用)
作り方:
- お茶パックなどの袋に、重曹を大さじ1〜2杯ほど入れる。
- 袋の口を輪ゴムや糸でしっかり閉じる。
- 1足につき1〜2個の重曹パックを作り、靴の中に入れる。
使い方:
- 靴の乾燥時に、新聞紙や乾燥剤の代わりとして使う。
- 靴を履かない夜間などに入れておくことで、翌朝には湿気とニオイが軽減されている。
- 乾燥が終わった後も、重曹パックを入れて保管すれば、ニオイ対策として持続的に効果を発揮する。
注意点
重曹パックは靴の中に入れて使うため、靴の外装に触れることがなく、革やスエードといった繊細な素材でも安心して使用できます。加えて、湿気を溜め込みやすい長靴やブーツなどの保管時にも非常に有効です。
スニーカー以外の靴の乾かし方

スニーカーは比較的扱いやすい素材が多いですが、その他の靴──特に革靴・スエード・ブーツ・子ども用の上履きなどは、素材や形状の違いによって乾かし方の工夫が必要です。ここでは、靴の種類別にベストな乾かし方を解説します。
革靴(レザーシューズ)
革靴は水に弱く、乾燥方法を誤るとひび割れや硬化、変形の原因になります。慎重なケアが必要です。
【乾かし方】
- 水分を優しくタオルで拭き取る(ゴシゴシ擦らない)
- 靴の中に新聞紙を詰めて湿気を吸収させる
- 直射日光はNG。風通しの良い日陰で陰干し
- 完全に乾いたら、革専用のクリームで保湿する
💡 革は乾燥しすぎるとひび割れるため、「自然乾燥&保湿」が基本です。
スエード素材の靴
スエードは起毛素材で非常にデリケート。濡れると色ムラや毛羽立ちの原因になります。
【乾かし方】
- 軽く水を拭き取る(タオルでポンポンと押すように)
- 新聞紙を詰めて形を整えつつ吸湿
- 完全に乾いたら、スエードブラシで毛並みを整える
⚠️ スエードはドライヤー・日光NG。乾いた後に防水スプレーをしておくと次回からの防水対策に◎。
ブーツ(革・布製など)
ブーツは形が大きく、中まで乾きにくいのが特徴です。内側の湿気がこもると、臭いやカビの原因に。
【乾かし方】
- まずタオルで表面と中の水分をしっかり拭き取る
- 筒の部分まで新聞紙を入れて湿気を取る
- 逆さに吊るせる場合は、逆さ干しが効果的
- 扇風機をブーツの口に向けて風を当てると中まで乾きやすい
💡 ブーツ用の乾燥スティックや専用乾燥機もおすすめです。
子ども用の上履き・通学靴
子ども用の靴は洗濯頻度が高く、乾燥時間を短くしたいところ。耐久性があり乾かしやすいですが、型崩れや臭いが残りやすいので注意が必要です。
【乾かし方】
- 洗った後はタオルで水気を取る
- 新聞紙を詰めて型崩れを防止
- ピンチハンガーで逆さに吊るし、扇風機や浴室乾燥で時短乾燥
- ニオイ対策には、重曹や靴専用スプレーを活用
🎒 学校が毎日あるお子さんの靴は、予備を1足用意してローテーションすると安心です。
靴を乾かすときの注意点

靴を早く乾かしたい気持ちはわかりますが、間違った方法で乾かすと素材を傷めたり、逆に臭いやカビの原因になってしまうことがあります。ここでは、靴を乾かす際に特に注意すべき5つのポイントをご紹介します。
直射日光はNG!素材を傷める原因に
「日光で早く乾きそう」と思って、靴をベランダに出して直射日光に当てる方も多いかもしれません。しかし、これは革靴やスニーカーの劣化を早める危険な行為です。
- 直射日光で起こるダメージ:
- 革のひび割れ、硬化
- 色あせ・変色
- ゴム部分の劣化や変形
✅ 対処法
日陰で風通しの良い場所に干すのがベスト。屋内なら窓を開けて扇風機を併用しましょう。
ドライヤーは距離と温度に注意
乾かす手段として便利なドライヤーですが、熱風を近づけすぎると靴が変形したり、接着剤が剥がれる原因になります。
- 特にNGな使い方:
- ドライヤーの吹き出し口を靴に直接当てる
- 同じ場所に長時間熱を当てる
✅ 正しい使い方
- 30cm以上離して、低温か送風モードで使用
- 靴の内側に空気が流れるよう、口を少し開ける
カビ対策には“完全乾燥”が重要
「もう乾いたかな?」と思っても、中敷きやつま先部分がまだ湿っていることが多いです。これが原因で靴の中にカビが発生しやすくなります。
- カビは一度発生すると、完全に取り除くのが難しい
- カビ臭はなかなか取れず、不快なニオイの元に
✅ カビを防ぐポイント
- 中敷きやインソールは取り外して別に干す
- 新聞紙や乾燥剤で、靴の奥までしっかり湿気を吸収
乾かす前に汚れを落とす
濡れた状態のまま乾かすと、汚れがそのまま靴に染みついてしまうことがあります。特に泥汚れなどは、そのまま乾くと落としにくくなるので要注意です。
✅ 乾かす前にやるべきこと
- 表面の汚れを軽くブラッシング
- 水で洗える靴は軽くすすいでから乾燥へ
- 革靴など水に弱い素材は、乾いた布や専用クリーナーで拭く
乾燥後のお手入れを忘れずに
「乾いたから終わり!」ではありません。乾燥後のケアが、靴の寿命を大きく左右します。
- 革靴の場合 → レザークリームで保湿し、柔軟性と光沢をキープ
- スエード素材 → 専用ブラシで毛並みを整え、防水スプレーをかける
- スニーカー → 消臭スプレーや重曹パウダーで仕上げると◎
✅ メンテナンスのコツ
- 乾燥後すぐに使わず、半日ほど置いて完全に乾燥させる
- 定期的にケアをしておくと、次回からの乾燥もスムーズになります
乾燥ケアを怠っただけで、数千円~数万円もする靴が使えなくなるのは非常にもったいないこと。日々の正しいケアこそが、靴を長く快適に使う最大のコツです。
濡れた靴の乾かし方:つま先が上(かかとが下)がおすすめ

濡れた靴を乾かす際は、靴を置く向きがとても大切です。おすすめの方法は、靴のつま先を上にして、かかとを下にすることです。これは、靴の中に残った水分を効率よく外に出すために効果的な向きです。
一般的に、靴の中ではつま先の方に水が溜まりやすい構造になっています。そこでつま先を上にしておくことで、重力によって靴の中の水分がかかとの方へ流れ出やすくなり、乾きやすくなるのです。
このとき、靴の中には新聞紙やキッチンペーパーなど、吸水性のある紙を丸めて詰めておくと、さらに水分を吸い取ってくれます。数時間おきに紙を取り替えると、より早く靴を乾かすことができます。
また、扇風機で風を当てたり、ドライヤーの冷風を使ったりするのも効果的です。乾かす際は、なるべく直射日光を避け、風通しのよい日陰で干すようにしましょう。特に革靴の場合は、直射日光や熱風によってひび割れが起きることがあるため注意が必要です。
このように、つま先を上にして、かかとを下にするというシンプルな工夫だけでも、靴を早く、そして型崩れさせずに乾かすことができます。
まとめ
濡れた靴は、そのまま放置しておくと、雑菌の繁殖や悪臭、カビの発生といったさまざまなトラブルの原因になります。また、素材の劣化や足の健康被害にもつながるため、「自然に乾くから大丈夫」と油断せず、正しい方法で早く乾かすことがとても大切です。
本記事では、濡れた靴を早く乾かす10の実践方法を紹介しました。新聞紙や扇風機、乾燥剤など、家庭にあるアイテムでも十分に対応できる手軽な方法ばかりです。また、スニーカー以外の革靴やスエード、ブーツなどは、素材に合わせた乾かし方が必要です。間違った方法で乾かすと、靴が縮んだり変形したりする原因になるため、特に注意が必要です。
乾かす際のポイントとしては、
- 直射日光を避けて陰干しすること
- ドライヤーや熱風の使い方に注意すること
- 靴の中までしっかり乾かすこと
- 汚れを落としてから乾かすこと
- 乾燥後のお手入れを忘れないこと
などがありました。こうした基本を押さえることで、靴の寿命を延ばし、清潔で快適な履き心地を保つことができます。
「ちょっと濡れたくらい」と軽く考えず、日々のケアを習慣にすることで、お気に入りの靴を長く使い続けられるはずです。雨の日や予想外の水濡れに備えて、ぜひ本記事でご紹介した方法を役立ててくださいね。




