「かもしれない」と「かも知れない」正しいのはどっち?をズバリ解説
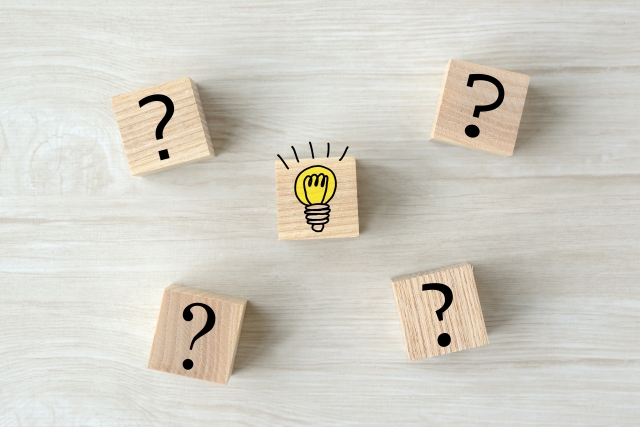
日常の会話や文章の中でよく使われる表現の一つに、「〜かもしれない」という言い回しがあります。たとえば、
「明日は雨が降るかもしれない」
「彼はもう出発したかもしれない」
このように、“推測”や“可能性”を表す便利な言い方として、日本語において広く定着しています。
しかし、SNSやブログ、あるいはメールの中で目にすることがあるのが、もう一つの表記——「かも知れない」。
「行けるかも知れない」
「成功するかも知れない」
この2つの表記、「かもしれない」と「かも知れない」は、どちらが正しいのでしょうか?あるいは、どちらも正しい?使い分けはあるの?——そんな素朴な疑問を抱いたことがある方も多いのではないでしょうか。
本記事では、「かもしれない」と「かも知れない」、それぞれの意味や文法的な背景、そしてどちらが正式・一般的に正しい表記なのかを、分かりやすく解説していきます。言葉は使い方によって印象も変わるもの。正しい知識を持つことで、より伝わる表現ができるようになりますよ。
それぞれの表現の意味と使い方

「かもしれない」と「かも知れない」は、どちらも推量(すいりょう)を表す表現です。つまり、「〜である可能性がある」「〜かも」というような、確定していない情報について話すときに使われます。
共通する意味:〜の可能性がある
たとえば、次のような例文で使われます。
- 例1:
明日は雨が降るかもしれない。
→(雨が降る可能性がある) - 例2:
彼はもう家に着いているかも知れない。
→(家に着いている可能性がある)
どちらの文も、話し手が「そうかもしれない」と思っているだけで、確実ではないというニュアンスを持っています。
どちらも自然な日本語
「かもしれない」「かも知れない」は、どちらも意味的にはまったく同じです。
どちらを使っても、話の内容が変わることはありません。
しかし、表記の仕方に微妙な違いがあり、その背景には文法や漢字表記のルールが関係しています。
次章では、「文法的にどちらが正しいのか?」について詳しく解説していきます。
文法的に正しいのはどちら?

「かもしれない」と「かも知れない」、どちらも意味は同じですが、文法的に正しい表記や、なぜこの2つの表記が存在するのかを見ていくと、面白い背景が見えてきます。
「知れない」は動詞「知る」の活用形
まず、「しれない/知れない」は、動詞「知る」の活用形です。
- 「知る」 → 可能形「知れる」 → 否定形「知れない」
つまり「知れない」は、「知ることができない」「分からない」という意味で使われており、「〜かもしれない」は「そうであるかどうかは分からないけれど、そうかも」という推測の表現になるわけです。
「かも」は助詞の組み合わせ
次に「かも」ですが、これは以下のような構造になっています。
- 「か」:疑問を表す助詞(例:「行くか?」)
- 「も」:範囲を広げる係助詞(例:「彼も来た」)
この2つが合わさることで、「そうである可能性もある」というニュアンスになります。
つまり、文法的には:
「Aか(疑問)」+「も(範囲)」+「知れない(予測できない)」
という構成になっており、どちらの表記も文法的には間違っていません。
「知れない」を漢字で書くのはNG?
文法的に「知れない」と書くのは正しいのですが、実は日本語の表記ルール上では注意が必要です。
- 「知れない」は常用漢字の使い方に抵触することがある
「知る」は常用漢字(国が定めた日常的に使うべき漢字)に含まれていますが、活用語尾が含まれる動詞の活用形(例えば「知れ」「知れない」)は、基本的にひらがなで書くのがルールとされています。
✅ 正しいとされる表記:かもしれない
⚠️ 一般的に避けられる表記:かも知れない
このような背景から、公的文書・ビジネス文書・新聞記事などでは、基本的にひらがな表記の「かもしれない」が採用されています。
「かもしれない」がひらがな表記になる理由

「かもしれない」と「かも知れない」は、文法的にはどちらも問題のない表現ですが、現代の日本語表記では**「かもしれない」=ひらがな表記**が圧倒的に使われています。では、なぜ「知れない」を漢字で書かず、あえてひらがなで書くことが推奨されているのでしょうか?
ここでは、その理由を3つの観点から解説します。
1. 現代仮名遣いのルールによる制限
まず大きな理由のひとつが、「現代仮名遣い」に基づく表記ルールです。
文化庁が定めた「現代仮名遣い」では、次のような方針が示されています:
動詞の活用語尾や補助的に使われる動詞は、基本的にひらがなで書くこと
つまり、「知れない」は動詞「知る」の可能形「知れる」の否定形であり、文の中で補助的に使われていることから、漢字ではなくひらがなで書くのが自然とされるのです。
これは他の表現にも共通していて、
- ✕「出来ない」 → ○「できない」
- ✕「考え得る」 → ○「考えうる」
- ✕「言い切れ無い」 → ○「言い切れない」
のように、可能性や推量などの補助的な意味を持つ語は、ひらがなで表すのが現代の標準的な書き方です。
2. 常用漢字の制限と読みやすさの配慮
日本では、公的な文書や新聞、出版物では「常用漢字表」に基づく表記が基本です。
「知る」は常用漢字に含まれていますが、その活用形(「知れ」「知れない」など)を漢字で書くと、視認性が下がったり、読みづらくなることがあります。
たとえば:
「明日は雨が降るかも知れない。」
と書くと、「かも」と「知れない」の境目がやや分かりにくくなり、読者が一瞬立ち止まることも。そのため、ひらがなで表記することで、文章全体の読みやすさ・スムーズさが保たれるのです。
3. メディア・出版業界の慣習
新聞社や出版社では、表記の統一性を保つために「表記ガイドライン」を設けています。たとえば、
これらでは、「かもしれない」はひらがな表記で統一するよう定められています。したがって、プロの書き手やメディア関係者は基本的に「かもしれない」を使うというスタンスなのです。
実際の使用例を見てみよう

ここまでで、「かもしれない」と「かも知れない」の意味や文法的な背景、そして表記上の違いについて解説してきました。では、実際の世の中ではどちらの表記が使われているのでしょうか?ここでは、新聞、書籍、Web、辞書など、さまざまな媒体における使用例を比較してみます。
新聞や雑誌の記事では?
朝日新聞、読売新聞、毎日新聞などの大手メディア
大手新聞社では、用字用語の統一が厳しく管理されており、「かもしれない」=ひらがな表記が基本です。記者用のガイドライン(例:「朝日新聞の用語の手引」)にも、
「推量や可能性を表す表現(例:かもしれない、できない、しようがないなど)はひらがなで書く」
と明記されています。
NHKのニュースやウェブサイト
NHKでも、「かも知れない」と表記されることはほとんどありません。ニュース原稿や字幕はすべて「かもしれない」で統一されています。
書籍・小説では?
文芸作品やエッセイでは、表記の自由度が比較的高いため、稀に「かも知れない」が使われることもあります。特に古い作品や文語調の文章では、作者の意図や文体に合わせて漢字が選ばれることがあります。
- 例1:昭和初期の文豪の作品
→「…そんな気も、しないではない。あるいは、彼女はもう気づいているかも知れない。」 - 例2:現代小説(若干文語調)
→「この選択が、未来を変えることになるかも知れない。」
ただし、現代の商業出版でも、文庫やビジネス書では「かもしれない」が主流となっています。
Google検索でのヒット数比較(2025年3月時点)
「かもしれない」 → 約8,500,000件
「かも知れない」 → 約420,000件
数字からも明らかなように、「かもしれない」が圧倒的に多く使われています。一方で、「かも知れない」はブログや個人の投稿、創作系の文章などに一定の割合で登場しています。
国語辞典での扱い
✅ 『国語辞典』
- 「かもしれない」の見出しで掲載
- 説明:あることが起こる可能性があるという推量を表す言い方
- 「かも知れない」と漢字で書くこともあるが、現在はひらがなが一般的、と補足あり
✅ Web辞書
- 検索すると「かもしれない」が主見出しになり、「かも知れない」は参照表記として扱われています。
結論とおすすめの使い方

ここまで、「かもしれない」と「かも知れない」の違いについて、意味・文法・表記ルール・実際の使用例を見ながら詳しく解説してきました。この章では、その内容をふまえて、私たちが普段の文章でどちらを使えばよいのか、明確に結論づけていきます。
結論:「かもしれない」が一般的で正しい表記
✅ 「かもしれない」が、文法的にも、表記ルール的にも、実務的にも最も一般的で適切です。とくに以下のようなシーンでは、必ず「かもしれない」を使うのがおすすめです。
- ビジネス文書
- メール、報告書
- 学術論文
- 公的資料
- 新聞・出版原稿
これは、前章でも触れたように「知れない」のような補助的な動詞はひらがなで書くのが標準というルールに基づいています。
「かも知れない」は間違いではないが注意が必要
一方で、「かも知れない」も間違いではありません。
むしろ、文学作品や詩、創作の場面では、漢字の重みや文体との調和を狙って、あえて使われることもあります。
ただし、以下のような注意点があります。
- 表記ゆれ(文章内で「かもしれない」と「かも知れない」が混在すると読みにくい)
- 読み手によっては「古臭い」「違和感がある」と感じる可能性もある
- 校正・編集の現場では修正されることが多い
創作や趣味のブログなどでは使ってもOKですが、公的な文書では避けた方が無難でしょう。
表記を統一することの大切さ
文章を書く上で意外と重要なのが、「表記を統一する」ことです。
「かもしれない」と「かも知れない」を文章内で混在させると、読み手に違和感を与え、読みづらくなる原因になります。
特に:
- ブログ記事
- レポート
- 小説や脚本
など、複数の段落にわたる文章では統一感が非常に大切です。
一度どちらかに決めたら、文全体で揃えるようにしましょう。
| 表記 | 適切な場面 | 備考 |
|---|---|---|
| かもしれない | ✅ ビジネス、公的文書、日常文 | 現代日本語での標準表記 |
| かも知れない | △ 文芸作品、詩、個人ブログなど | 文体に合わせた演出にはOK |
おわりに
言葉には揺れがあり、変化もあります。「かも知れない」という表現も、昔はよく使われていたのかもしれません。でも現代では、より分かりやすく・読みやすく・伝わりやすい表記が求められるようになってきています。
だからこそ、正しい知識を持った上で、シーンに応じた表現を選ぶことが大切ですね。




